 子どもが家から離れ、旅をする。ジュブナイル作品の王道とも言えるシチュエーションです。旅先での出来事を経て子どもが成長していく様子は、文章で読んでも映像で見てもワクワクするものですよね。このジャンルには、スティーブン・キングの『スタンド・バイ・ミー』をはじめ、名作がたくさんあります。
子どもが家から離れ、旅をする。ジュブナイル作品の王道とも言えるシチュエーションです。旅先での出来事を経て子どもが成長していく様子は、文章で読んでも映像で見てもワクワクするものですよね。このジャンルには、スティーブン・キングの『スタンド・バイ・ミー』をはじめ、名作がたくさんあります。
ただ、現代社会で子どもだけの旅を決行するとなると、それなりの理由付けが必要となります。恩田陸さんの『上と外』では主人公兄妹が外国のクーデターに巻き込まれますし、宮部みゆきさん『ブレイブ・ストーリー』の主人公は異世界に行ってしまいました。こういう特殊な設定の物語もとても面白いのですが、今回はもっと現実寄りの作品を取り上げようと思います。朱川湊人さんの『オルゴォル』です。
こんな人におすすめ
子ども目線の旅物語に興味がある人

 現代には、エンターテインメントが溢れています。漫画に小説、ドラマ、映画、ゲームetc。漫画一つ取っても、紙媒体もあれば電子書籍もありと、その数はまさに無数。この分だと、三年後、五年後には、きっとまた新しい娯楽が誕生していることでしょう。
現代には、エンターテインメントが溢れています。漫画に小説、ドラマ、映画、ゲームetc。漫画一つ取っても、紙媒体もあれば電子書籍もありと、その数はまさに無数。この分だと、三年後、五年後には、きっとまた新しい娯楽が誕生していることでしょう。 「昔はよく見聞きしたけど、今はめっきり減ったよなぁ」と思う物事って、色々あります。その中の一つが、ミス・コンテスト。独身女性が優勝を目指して競い合うイベントで、ミス・ユニバースやミス・日本が有名ですね。一時期は様々な自治体や学校がコンテストを開催していましたが、ルッキズムやジェンダーレスといった問題から、昨今はその数も激減したようです。
「昔はよく見聞きしたけど、今はめっきり減ったよなぁ」と思う物事って、色々あります。その中の一つが、ミス・コンテスト。独身女性が優勝を目指して競い合うイベントで、ミス・ユニバースやミス・日本が有名ですね。一時期は様々な自治体や学校がコンテストを開催していましたが、ルッキズムやジェンダーレスといった問題から、昨今はその数も激減したようです。 ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。
ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。 創作の世界において、姉妹というのは良くも悪くも濃密な関係になりがちです。私がイヤミスやホラーが好きだから余計にそう感じるのかもしれませんが、兄弟より複雑な愛憎劇が展開されることもしばしば・・・女同士という性別ゆえに、そういう描写がなされるのでしょうか。
創作の世界において、姉妹というのは良くも悪くも濃密な関係になりがちです。私がイヤミスやホラーが好きだから余計にそう感じるのかもしれませんが、兄弟より複雑な愛憎劇が展開されることもしばしば・・・女同士という性別ゆえに、そういう描写がなされるのでしょうか。 私が子どもの頃、オカルト界隈では<ノストラダムスの大予言>が有名でした。最近は名前が出る機会もめっきり減ったので一応解説しておくと、これはフランスの医師兼占星術師であるノストラダムスが書き残した予言のこと。実物は相当な量の詩集なのですが、日本ではその中の第十巻七十二番『一九九九年七の月、空から恐怖の大王が来るだろう』という一文がやたらと広まり、「一九九九年の七月の世界へ滅亡するんだ!」という騒ぎになったのです。実際のところ、ノストラダムス自身は世界滅亡に関する記述は何一つ残しておらず、そもそも詩の和訳が間違っているという指摘すらあるものの、ホラー好きとしては印象深いブームでした。
私が子どもの頃、オカルト界隈では<ノストラダムスの大予言>が有名でした。最近は名前が出る機会もめっきり減ったので一応解説しておくと、これはフランスの医師兼占星術師であるノストラダムスが書き残した予言のこと。実物は相当な量の詩集なのですが、日本ではその中の第十巻七十二番『一九九九年七の月、空から恐怖の大王が来るだろう』という一文がやたらと広まり、「一九九九年の七月の世界へ滅亡するんだ!」という騒ぎになったのです。実際のところ、ノストラダムス自身は世界滅亡に関する記述は何一つ残しておらず、そもそも詩の和訳が間違っているという指摘すらあるものの、ホラー好きとしては印象深いブームでした。 ホラーやイヤミスの世界において、<子ども>というのは特別な存在になりがちです。子どもは可能性の塊であり、未来の象徴。そのせいか、モンスターや殺人鬼が跋扈し、多数の犠牲者が出る中、子どもだけはなんとか生き残るという展開も多いです。
ホラーやイヤミスの世界において、<子ども>というのは特別な存在になりがちです。子どもは可能性の塊であり、未来の象徴。そのせいか、モンスターや殺人鬼が跋扈し、多数の犠牲者が出る中、子どもだけはなんとか生き残るという展開も多いです。 物語を創る上で、テーマ設定はとても重要です。中には、特にテーマを決めず自由気ままに創作するケースもあるでしょうが、これは恐らく少数派。「身分違いの恋を書こう」とか「サラリーマンの下剋上物語にしよう」とか、最初に設定しておくことの方が多いと思います。
物語を創る上で、テーマ設定はとても重要です。中には、特にテーマを決めず自由気ままに創作するケースもあるでしょうが、これは恐らく少数派。「身分違いの恋を書こう」とか「サラリーマンの下剋上物語にしよう」とか、最初に設定しておくことの方が多いと思います。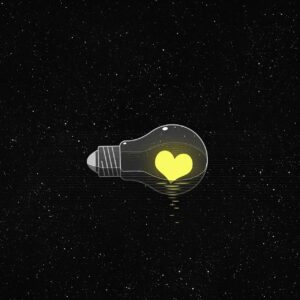 万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・
万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・ 新興宗教。読んで字の如く、伝統宗教(カトリック教会、十三宗五十六派の仏教、イスラム教、ヒンドゥー教etc)と比べ、成立時期が新しい宗教のことです。<時期が新しい>という基準がかなり曖昧な関係上、国内外合わせて相当な数の宗教団体がこれに該当します。
新興宗教。読んで字の如く、伝統宗教(カトリック教会、十三宗五十六派の仏教、イスラム教、ヒンドゥー教etc)と比べ、成立時期が新しい宗教のことです。<時期が新しい>という基準がかなり曖昧な関係上、国内外合わせて相当な数の宗教団体がこれに該当します。