 物語が幸せな結末を迎える<ハッピーエンド>、主要キャラクターが不幸になる<バッドエンド>、傍から見れば不幸だけど当事者は満足している<メリーバッドエンド>、これまでのすべてがリセット・一からやり直しとなる<世界再編成エンド>・・・・・物語には、様々な結末があります。このエンディングが素晴らしいか否かで、作品の評価が決まると言っても過言ではありません。
物語が幸せな結末を迎える<ハッピーエンド>、主要キャラクターが不幸になる<バッドエンド>、傍から見れば不幸だけど当事者は満足している<メリーバッドエンド>、これまでのすべてがリセット・一からやり直しとなる<世界再編成エンド>・・・・・物語には、様々な結末があります。このエンディングが素晴らしいか否かで、作品の評価が決まると言っても過言ではありません。
こうしたエンディングの種類の一つに、<ビターエンド>というものがあります。読んで字のごとく、ほろ苦いエンディングのことで、バッドエンドほど不幸ではないがハッピーエンドとは言い難い・・・という結末を指します。個人的に、一番読者が身近に感じるエンディングはこれではないでしょうか。今日は、ビターエンドの恋愛小説を集めた短編集をご紹介したいと思います。唯川恵さんの『ゆうべ、もう恋なんかしないと誓った』です。
こんな人におすすめ
ほろ苦い読後感の恋愛ショートショートに興味がある人

 死後、死者が一時的に現世に舞い戻り、心残りを晴らす。古今東西、ファンタジーやホラーのジャンルでよくあるシチュエーションです。死の先にも意識や世界がある、あってほしいというのは、人類共通の発想なのでしょうね。
死後、死者が一時的に現世に舞い戻り、心残りを晴らす。古今東西、ファンタジーやホラーのジャンルでよくあるシチュエーションです。死の先にも意識や世界がある、あってほしいというのは、人類共通の発想なのでしょうね。 <毒親>という言葉が作られたのは、一九八〇年代後半のことだそうです。意味は<子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親>。日本でも、二〇一五年頃には<ブーム>と表現してもいいほど有名な概念となり、書籍や映像作品でも頻繁に取り上げられてきました。
<毒親>という言葉が作られたのは、一九八〇年代後半のことだそうです。意味は<子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親>。日本でも、二〇一五年頃には<ブーム>と表現してもいいほど有名な概念となり、書籍や映像作品でも頻繁に取り上げられてきました。 ダブル主人公というのは、手がける際に注意が必要な物語形式だそうです。描き方を間違えると片方だけが目立ってしまったり、最悪、もう片方がただの引き立て役になってしまうことがあり得ることが理由なのだとか。そのため、一時期、特にWeb小説界隈では<ダブル主人公は鬼門>という常識まで存在したらしいです。
ダブル主人公というのは、手がける際に注意が必要な物語形式だそうです。描き方を間違えると片方だけが目立ってしまったり、最悪、もう片方がただの引き立て役になってしまうことがあり得ることが理由なのだとか。そのため、一時期、特にWeb小説界隈では<ダブル主人公は鬼門>という常識まで存在したらしいです。 私は昔から魚介類が大好きです。海が近い地方で育ったせいか、肉より魚の方になじみ深さを感じます。子どもの頃はそれなりに好き嫌いがあったものの、魚に関しては、骨たっぷりの焼き魚だろうと、独特な匂いの青魚だろうと、ぱくぱく食べていたものです。
私は昔から魚介類が大好きです。海が近い地方で育ったせいか、肉より魚の方になじみ深さを感じます。子どもの頃はそれなりに好き嫌いがあったものの、魚に関しては、骨たっぷりの焼き魚だろうと、独特な匂いの青魚だろうと、ぱくぱく食べていたものです。 昔読んだ小説に、こんな台詞がありました。「この世の争いのほとんどは、イロかカネが原因で起こる」。イロ(色)とは性欲や恋愛絡み、カネ(金)とは金銭問題のことで、確かにトラブルのほとんどはそのどちらかが原因だよなと、しみじみ納得したものです。
昔読んだ小説に、こんな台詞がありました。「この世の争いのほとんどは、イロかカネが原因で起こる」。イロ(色)とは性欲や恋愛絡み、カネ(金)とは金銭問題のことで、確かにトラブルのほとんどはそのどちらかが原因だよなと、しみじみ納得したものです。 <その作家さんの著作の中で最初に読んだ本>というのは、強い印象を残しがちです。それが気に入らなければ「この人の本は、もういいかな」となる可能性が高いですし、逆に気に入れば、著作すべてを網羅したくなることだってあり得ます。読書に限った話ではありませんが、最初の一歩って重要なものなんですよね。
<その作家さんの著作の中で最初に読んだ本>というのは、強い印象を残しがちです。それが気に入らなければ「この人の本は、もういいかな」となる可能性が高いですし、逆に気に入れば、著作すべてを網羅したくなることだってあり得ます。読書に限った話ではありませんが、最初の一歩って重要なものなんですよね。 一昔前、悪さをする悪霊や妖怪のことを<物の怪>と呼びました。この<物>とは<人間>の対義語で、超自然的な存在すべてを指すのだとか。ホラーになじみがなくても、ジブリ映画『もののけ姫』で名前を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
一昔前、悪さをする悪霊や妖怪のことを<物の怪>と呼びました。この<物>とは<人間>の対義語で、超自然的な存在すべてを指すのだとか。ホラーになじみがなくても、ジブリ映画『もののけ姫』で名前を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。 単に私の読書傾向の問題なのかもしれませんが、ここ最近読んだ作品の中で物語の鍵を握るのは、母娘ないし姉妹でした。女性同士の場合、掴み合い殴り合いの大乱闘になる可能性が低い(かもしれない)分、水面下でのドロドロを描きやすく、イヤミスやホラーにハマるからかな?と考えています。
単に私の読書傾向の問題なのかもしれませんが、ここ最近読んだ作品の中で物語の鍵を握るのは、母娘ないし姉妹でした。女性同士の場合、掴み合い殴り合いの大乱闘になる可能性が低い(かもしれない)分、水面下でのドロドロを描きやすく、イヤミスやホラーにハマるからかな?と考えています。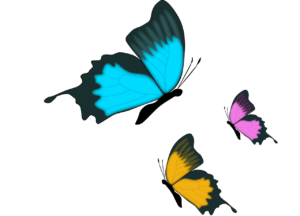 人生において、「趣味は何ですか」と聞かれる機会って意外と多いです。私の場合、そう聞かれた場合の答えは、子どもの頃から「読書です」。その趣味を大人になるまで続けた結果、こういうブログまで始めてしまいました。人間、好きなものについて語ることは楽しいですし、ついつい熱が入ります。
人生において、「趣味は何ですか」と聞かれる機会って意外と多いです。私の場合、そう聞かれた場合の答えは、子どもの頃から「読書です」。その趣味を大人になるまで続けた結果、こういうブログまで始めてしまいました。人間、好きなものについて語ることは楽しいですし、ついつい熱が入ります。