 <呪>。見ただけで不穏な気分になりそうな言葉です。日本という国は、<陰陽師><丑の刻参り>等が様々なカルチャーにさらりと登場することが示す通り、どこか陰気で湿った呪術の宝庫。創作界隈においても、先祖代々伝わる呪いがあったり、登場人物が呪い殺されたりという展開は数えきれないほど存在します。
<呪>。見ただけで不穏な気分になりそうな言葉です。日本という国は、<陰陽師><丑の刻参り>等が様々なカルチャーにさらりと登場することが示す通り、どこか陰気で湿った呪術の宝庫。創作界隈においても、先祖代々伝わる呪いがあったり、登場人物が呪い殺されたりという展開は数えきれないほど存在します。
しかし、成り立ちから考えると、<呪い>というのは必ずしも禍々しいものではありませんでした。そもそも<呪>という漢字自体、<神に仕える年長者(兄)が口にする言葉(口)>から発生しており、むしろ発展的・建設的な意味だったそうです。現代では負の側面ばかり強調されがちですが、かつては呪いで人の幸せや社会の向上を目指すこともあったのかもしれませんね。この作品を読むと、余計にそう思ってしまいます。今回は、藤崎翔さんの『お梅は魔法少女ごと呪いたい』を取り上げたいと思います。
こんな人におすすめ
・伏線たっぷりのホラーコメディが読みたい人
・『お梅シリーズ』のファン
続きを読む
 死後、死者が一時的に現世に舞い戻り、心残りを晴らす。古今東西、ファンタジーやホラーのジャンルでよくあるシチュエーションです。死の先にも意識や世界がある、あってほしいというのは、人類共通の発想なのでしょうね。
死後、死者が一時的に現世に舞い戻り、心残りを晴らす。古今東西、ファンタジーやホラーのジャンルでよくあるシチュエーションです。死の先にも意識や世界がある、あってほしいというのは、人類共通の発想なのでしょうね。
よくあるシチュエーションだからこそ、どう個性的な色付けをするか、作者の技量が問われるテーマです。冷酷な金貸しのもとに仲間の亡霊が現れるチャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』、赤ん坊の体に死んだ夫が乗り移る加納朋子さん『ささらさや』、死者と生者を面会させられる能力者が主役の辻村深月さん『ツナグ』等、どれも魅力たっぷりの名作でした。最近読んだこの本も、とても面白かったですよ。藤崎翔さんの『冥土レンタルサービス』です。
こんな人におすすめ
転生をテーマにしたヒューマンコメディに興味がある人
続きを読む
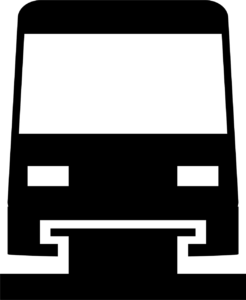 クリエイターに必要な能力は色々あります。その中の一つは発想力。読んで字の如く、物事をクリエイト(創造)するのが仕事なわけですから、アイデアが湧かなくては始まりません。私は先日、童話を創ってみる機会を得たのですが、まあ、全然アイデアが出ないこと出ないこと。頭に浮かぶのは聞いたことがあるストーリーばかりで、たった三十分足らずの時間だったにもかかわらずヘトヘトになってしまいました。一から何かを生み出せる方達って、本当に天才だなと思います。
クリエイターに必要な能力は色々あります。その中の一つは発想力。読んで字の如く、物事をクリエイト(創造)するのが仕事なわけですから、アイデアが湧かなくては始まりません。私は先日、童話を創ってみる機会を得たのですが、まあ、全然アイデアが出ないこと出ないこと。頭に浮かぶのは聞いたことがあるストーリーばかりで、たった三十分足らずの時間だったにもかかわらずヘトヘトになってしまいました。一から何かを生み出せる方達って、本当に天才だなと思います。
当然ながら、このブログで取り上げてきた作家さん達にも、発想力は必要不可欠。その発揮の仕方も十人十色、それぞれ個性があって面白いです。中でも、この方の発想って、ユーモアたっぷりで大好きなんですよ。今日ご紹介するのは、藤崎翔さんの『オリエンド鈍行殺人事件』です。
こんな人におすすめ
どんでん返しのあるユーモア小説短編集が読みたい人
続きを読む
 すべてのジャンルにいえることですが、ホラー作品には定番のシチュエーションというものが存在します。<吹雪の山荘から出られなくなる>とか<ゲーム感覚で呪いの儀式を行ってしまう>とか<真夜中の学校に忘れ物を取りに行く>とかいうやつですね。最後の一つは実際に私も友達と一緒にやったことがあるのですが、怖いというより「おおっ!まさか本当に、こんなホラーお約束の状況に直面できるなんて!」と、妙に感動したものです。
すべてのジャンルにいえることですが、ホラー作品には定番のシチュエーションというものが存在します。<吹雪の山荘から出られなくなる>とか<ゲーム感覚で呪いの儀式を行ってしまう>とか<真夜中の学校に忘れ物を取りに行く>とかいうやつですね。最後の一つは実際に私も友達と一緒にやったことがあるのですが、怖いというより「おおっ!まさか本当に、こんなホラーお約束の状況に直面できるなんて!」と、妙に感動したものです。
お約束は、人気があって面白いからこそお約束たりえるもの。そして、そのお約束のシチュエーションの中でどうオリジナリティを出せるかが、作者の腕の見せ所です。その点、アメリカ映画『キャビン』は、ホラーあるあるネタをふんだんに取り入れつつ、予想の斜め上をいくトンデモ世界を描いていて、とても面白かったです。それからこれも、一ひねりされた展開を楽しむことができました。瀬川ことびさんの『夏合宿』です。
こんな人におすすめ
ユーモラスなホラー短編集を読みたい人
続きを読む
 <ホラーコメディ>というジャンルがあります。文字通り、ホラー(恐怖)とコメディ(喜劇)両方の要素がある作品のことで、不気味なのに妙に笑える展開を迎えるというパターンが多いです。正反対のジャンルのようで、意外と相性がいいんですよ。
<ホラーコメディ>というジャンルがあります。文字通り、ホラー(恐怖)とコメディ(喜劇)両方の要素がある作品のことで、不気味なのに妙に笑える展開を迎えるというパターンが多いです。正反対のジャンルのようで、意外と相性がいいんですよ。
このホラーコメディ、絵的に映えるシチュエーションが多いからか、映像作品でよく見るジャンルなような気がします。私が見たものだと、二〇一〇年の洋画『タッカーとデイル 史上最悪にツイてないヤツら』は日本でも高評価を獲得しました。一〇〇%善人にもかかわらず、風体や振る舞いのせいで殺人鬼と勘違いされてしまう二人組のドタバタが最高に面白かったです。小説だと、ブログでも取り上げた藤崎翔さんの『お梅は呪いたいシリーズ』も、楽しく笑える傑作でした。それからこれも、質の高いホラーコメディです。瀬川ことびさんの『厄落とし』です。
こんな人におすすめ
ユーモラスなホラー短編集を読みたい人
続きを読む
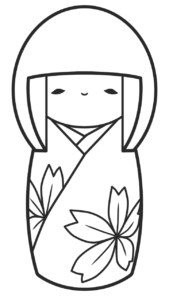 長く続く物語には、時に<転機>というものが訪れます。中には、いわゆる<サザエさん形式>でまったく変わることのない作品もありますが、これは割合としては少数派ではないでしょうか。視聴者や読者を飽きさせないため、何らかの変化が生じることの方が多いと思います。
長く続く物語には、時に<転機>というものが訪れます。中には、いわゆる<サザエさん形式>でまったく変わることのない作品もありますが、これは割合としては少数派ではないでしょうか。視聴者や読者を飽きさせないため、何らかの変化が生じることの方が多いと思います。
この<転機>の形は様々ですが、代表的なものの一つとして挙げられるのが<パワーアップ>。登場人物が修行を積んだり新キャラクターに出会ったりした結果、新たな力を手に入れるというパターンです。漫画『NARUTO』や『ONE PIECE』等でも、主人公チームが修行期間を経てパワーアップするという展開が描かれました。それからこの作品でも、主人公(?)がパワーアップするんですよ。藤崎翔さんの『お梅は次こそ呪いたい』です。
こんな人におすすめ
伏線たっぷりのホラーコメディが読みたい人
続きを読む
 守護霊。文字通り、生者を守護してくれる霊のことです。大抵は、先祖や恋人、可愛がっていたペット等、縁のある存在が守護霊となるケースが多いようですね。困難にぶち当たった時、人知を超えた力で守ってくれる存在がいればいいな・・・そう夢想したことがある人は、決して少なくないと思います。
守護霊。文字通り、生者を守護してくれる霊のことです。大抵は、先祖や恋人、可愛がっていたペット等、縁のある存在が守護霊となるケースが多いようですね。困難にぶち当たった時、人知を超えた力で守ってくれる存在がいればいいな・・・そう夢想したことがある人は、決して少なくないと思います。
小説界で守護霊が活躍する作品といえば、有名どころだと『ハリー・ポッターシリーズ』があります。主要登場人物達が魔法使いということもあり、時に実体を得て敵相手に奮戦する守護霊達の姿は実に格好良かったです。あそこまで目立つ大活躍はしないものの、今回取り上げる作品の守護霊も大したものですよ。藤崎翔さんの『守護霊刑事』です。
こんな人におすすめ
コミカルな刑事ミステリー短編集に興味がある人
続きを読む
 フィクション作品、特にミステリーやサスペンスの世界において、数多くの登場人物達が死体と出くわします。常識的に考えれば、そこで真っ先にすべきことは<救急・警察に通報する>一択なものの、創作の世界となると話は別。主人公がどうにか死体を処分しようと苦悩するところから物語が始まる、という展開も珍しくありません。
フィクション作品、特にミステリーやサスペンスの世界において、数多くの登場人物達が死体と出くわします。常識的に考えれば、そこで真っ先にすべきことは<救急・警察に通報する>一択なものの、創作の世界となると話は別。主人公がどうにか死体を処分しようと苦悩するところから物語が始まる、という展開も珍しくありません。
ここで問題となるのが、死体の処分方法です。燃やす、沈める、バラバラにする等々、様々なやり方がありますが、一番よくあるのは<埋める>ではないでしょうか。土がある場所を掘りさえすればOK!とにかく死体を見えない状態にできる!というお手軽感(?)のせいかもしれませんね。とはいえ、物事はそんなに都合良く進まないのが世の中の常。目先の欲に振り回されたおかげで、とんでもない事態に陥ってしまうこともあり得ます。今回取り上げるのは、そんな修羅場に巻き込まれてしまった人間の悲喜劇、藤崎翔さんの『モノマネ芸人、死体を埋める』です。
こんな人におすすめ
コミカルなクライムサスペンスが読みたい人
続きを読む
 ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。
ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。
ただ、一言で人形といっても、等身大のマネキンから、豪奢な装飾が施されたアンティークドール、子どもが片手で持てる着せ替え人形等々、たくさんの種類があります。その中でジャパニーズホラーにぴったりなのは、満場一致で日本人形でしょう。澤村伊智さんの『ずうのめ人形』や、漫画ですが山岸凉子さんの『わたしの人形は良い人形』には、読者の背筋を凍らせるほど怖い日本人形が登場します。それから、この作品に出てくる人形も、なかなかどうしてインパクト抜群でしたよ。藤崎翔さんの『お梅は呪いたい』です。
こんな人におすすめ
伏線たっぷりのホラーコメディが読みたい人
続きを読む
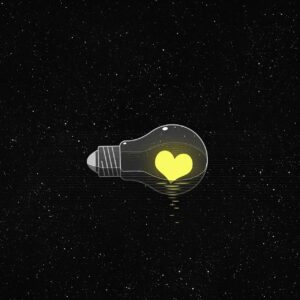 万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・
万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・
とはいえ、事前に内容をチェックしてさえいれば、改題は悪いことではありません。改題後の方がしっくりくるということだってあるでしょう。個人的には、真梨幸子さんの『更年期少女』は、改題後の『みんな邪魔』の方が好みだったりします。それからこの作品も、改題後の題名の方が好きなんですよ。藤崎翔さんの『三十年後の俺』です。
こんな人におすすめ
ブラックユーモアたっぷりの短編集が読みたい人
続きを読む
 <呪>。見ただけで不穏な気分になりそうな言葉です。日本という国は、<陰陽師><丑の刻参り>等が様々なカルチャーにさらりと登場することが示す通り、どこか陰気で湿った呪術の宝庫。創作界隈においても、先祖代々伝わる呪いがあったり、登場人物が呪い殺されたりという展開は数えきれないほど存在します。
<呪>。見ただけで不穏な気分になりそうな言葉です。日本という国は、<陰陽師><丑の刻参り>等が様々なカルチャーにさらりと登場することが示す通り、どこか陰気で湿った呪術の宝庫。創作界隈においても、先祖代々伝わる呪いがあったり、登場人物が呪い殺されたりという展開は数えきれないほど存在します。
 死後、死者が一時的に現世に舞い戻り、心残りを晴らす。古今東西、ファンタジーやホラーのジャンルでよくあるシチュエーションです。死の先にも意識や世界がある、あってほしいというのは、人類共通の発想なのでしょうね。
死後、死者が一時的に現世に舞い戻り、心残りを晴らす。古今東西、ファンタジーやホラーのジャンルでよくあるシチュエーションです。死の先にも意識や世界がある、あってほしいというのは、人類共通の発想なのでしょうね。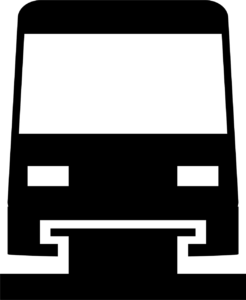 クリエイターに必要な能力は色々あります。その中の一つは発想力。読んで字の如く、物事をクリエイト(創造)するのが仕事なわけですから、アイデアが湧かなくては始まりません。私は先日、童話を創ってみる機会を得たのですが、まあ、全然アイデアが出ないこと出ないこと。頭に浮かぶのは聞いたことがあるストーリーばかりで、たった三十分足らずの時間だったにもかかわらずヘトヘトになってしまいました。一から何かを生み出せる方達って、本当に天才だなと思います。
クリエイターに必要な能力は色々あります。その中の一つは発想力。読んで字の如く、物事をクリエイト(創造)するのが仕事なわけですから、アイデアが湧かなくては始まりません。私は先日、童話を創ってみる機会を得たのですが、まあ、全然アイデアが出ないこと出ないこと。頭に浮かぶのは聞いたことがあるストーリーばかりで、たった三十分足らずの時間だったにもかかわらずヘトヘトになってしまいました。一から何かを生み出せる方達って、本当に天才だなと思います。 すべてのジャンルにいえることですが、ホラー作品には定番のシチュエーションというものが存在します。<吹雪の山荘から出られなくなる>とか<ゲーム感覚で呪いの儀式を行ってしまう>とか<真夜中の学校に忘れ物を取りに行く>とかいうやつですね。最後の一つは実際に私も友達と一緒にやったことがあるのですが、怖いというより「おおっ!まさか本当に、こんなホラーお約束の状況に直面できるなんて!」と、妙に感動したものです。
すべてのジャンルにいえることですが、ホラー作品には定番のシチュエーションというものが存在します。<吹雪の山荘から出られなくなる>とか<ゲーム感覚で呪いの儀式を行ってしまう>とか<真夜中の学校に忘れ物を取りに行く>とかいうやつですね。最後の一つは実際に私も友達と一緒にやったことがあるのですが、怖いというより「おおっ!まさか本当に、こんなホラーお約束の状況に直面できるなんて!」と、妙に感動したものです。 <ホラーコメディ>というジャンルがあります。文字通り、ホラー(恐怖)とコメディ(喜劇)両方の要素がある作品のことで、不気味なのに妙に笑える展開を迎えるというパターンが多いです。正反対のジャンルのようで、意外と相性がいいんですよ。
<ホラーコメディ>というジャンルがあります。文字通り、ホラー(恐怖)とコメディ(喜劇)両方の要素がある作品のことで、不気味なのに妙に笑える展開を迎えるというパターンが多いです。正反対のジャンルのようで、意外と相性がいいんですよ。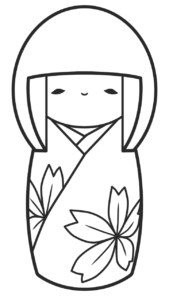 長く続く物語には、時に<転機>というものが訪れます。中には、いわゆる<サザエさん形式>でまったく変わることのない作品もありますが、これは割合としては少数派ではないでしょうか。視聴者や読者を飽きさせないため、何らかの変化が生じることの方が多いと思います。
長く続く物語には、時に<転機>というものが訪れます。中には、いわゆる<サザエさん形式>でまったく変わることのない作品もありますが、これは割合としては少数派ではないでしょうか。視聴者や読者を飽きさせないため、何らかの変化が生じることの方が多いと思います。 守護霊。文字通り、生者を守護してくれる霊のことです。大抵は、先祖や恋人、可愛がっていたペット等、縁のある存在が守護霊となるケースが多いようですね。困難にぶち当たった時、人知を超えた力で守ってくれる存在がいればいいな・・・そう夢想したことがある人は、決して少なくないと思います。
守護霊。文字通り、生者を守護してくれる霊のことです。大抵は、先祖や恋人、可愛がっていたペット等、縁のある存在が守護霊となるケースが多いようですね。困難にぶち当たった時、人知を超えた力で守ってくれる存在がいればいいな・・・そう夢想したことがある人は、決して少なくないと思います。 フィクション作品、特にミステリーやサスペンスの世界において、数多くの登場人物達が死体と出くわします。常識的に考えれば、そこで真っ先にすべきことは<救急・警察に通報する>一択なものの、創作の世界となると話は別。主人公がどうにか死体を処分しようと苦悩するところから物語が始まる、という展開も珍しくありません。
フィクション作品、特にミステリーやサスペンスの世界において、数多くの登場人物達が死体と出くわします。常識的に考えれば、そこで真っ先にすべきことは<救急・警察に通報する>一択なものの、創作の世界となると話は別。主人公がどうにか死体を処分しようと苦悩するところから物語が始まる、という展開も珍しくありません。 ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。
ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。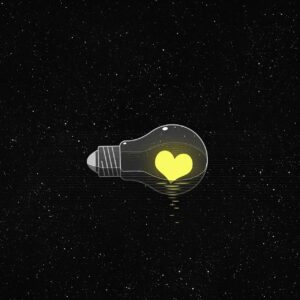 万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・
万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・