 何らかの事件が起こった際、ニュースに以下のフレーズが出てくることがしばしばあります。「精神鑑定の結果を踏まえ、その他の証拠を総合的に考慮した上で・・・」「被告の精神鑑定を行った医師に尋問を行い・・・」。この<精神鑑定>とは、裁判所が被告人等の精神状態・責任能力を判断するため、精神科医といった鑑定人に命じる鑑定の一つ。結果如何によっては裁判所の判断が大きく変わることも有り得る、重要な行為です。
何らかの事件が起こった際、ニュースに以下のフレーズが出てくることがしばしばあります。「精神鑑定の結果を踏まえ、その他の証拠を総合的に考慮した上で・・・」「被告の精神鑑定を行った医師に尋問を行い・・・」。この<精神鑑定>とは、裁判所が被告人等の精神状態・責任能力を判断するため、精神科医といった鑑定人に命じる鑑定の一つ。結果如何によっては裁判所の判断が大きく変わることも有り得る、重要な行為です。
何かと賛否両論を巻き起こしがちなテーマですが、それだけ世間の関心を集めるだけあって、精神鑑定が登場するフィクション作品もたくさんあります。私の場合、強烈に印象に残っているのは日本映画『39 刑法第三十九条』。練られた脚本といい、堤真一さんや鈴木京香さんら俳優陣の熱演といい、何年経っても忘れられない名作です。小説では、山田宗樹さんの『鑑定』も、発想の活かし方が面白かったですよ。先日読んだ小説でも、精神鑑定が大きな役割を果たしていました。知念実希人さんの『閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書』です。
こんな人におすすめ
モキュメンタリ―ホラー小説が好きな人
続きを読む
 フィクションの世界には、<ダークヒーロー>というキャラクターが存在します。読んで字の如く<闇のヒーロー>のことで、正義と相対する立場ながら確固たる信念を持っていたり、悲劇的な過去ゆえに悪側になってしまったり、違法な手段を使いながら人を救ったりするキャラクターを指します。例を挙げると、映画『スターウォーズシリーズ』のダース・ベイダーや、大場つぐみさん原作による漫画『DEATH NOTE』の主人公・夜神月などですね。これらのキャラクターは、どうかすると正義側の主人公より人気を集めることもあったりします。
フィクションの世界には、<ダークヒーロー>というキャラクターが存在します。読んで字の如く<闇のヒーロー>のことで、正義と相対する立場ながら確固たる信念を持っていたり、悲劇的な過去ゆえに悪側になってしまったり、違法な手段を使いながら人を救ったりするキャラクターを指します。例を挙げると、映画『スターウォーズシリーズ』のダース・ベイダーや、大場つぐみさん原作による漫画『DEATH NOTE』の主人公・夜神月などですね。これらのキャラクターは、どうかすると正義側の主人公より人気を集めることもあったりします。
では、ダークヒーローと、ただの悪党の違いは何でしょうか。もちろん、法律上の定義などはありませんが、一般的には、何らかの背景なり美学を持ち、人を救うこともあり得るのが<ダークヒーロー>、目先の利益に溺れるのが<小悪党>という分け方をされている気がします。闇側の存在とはいえ、<ヒーロー>の名を冠するからには、ちんけな小物ではダメということでしょう。それならば、果たして今日ご紹介する作品の登場人物は、ダークヒーローといえるのでしょうか。今回は、櫛木理宇さんの『拷問依存症』を取り上げたいと思います。
<こんな人におすすめ>
・報復をテーマにしたイヤミスに興味がある人
・『依存症シリーズ』が好きな人
続きを読む
 新年あけましておめでとうございます。ブログを解説し、今年で十年目。長く続いたよなと、自分でしみじみしています。今年もミステリーとホラー中心にゆるゆるレビューしていくつもりですので、どうぞよろしくお願いします。
新年あけましておめでとうございます。ブログを解説し、今年で十年目。長く続いたよなと、自分でしみじみしています。今年もミステリーとホラー中心にゆるゆるレビューしていくつもりですので、どうぞよろしくお願いします。
改めてブログ内の記事を振り返ってみると、私が取り上げた作品で一番多いジャンルはミステリー。特に<何かが消える>というシチュエーションが非常に多いことが分かりました。犯人が消え、遺体が消え、凶器が消え、関係者が消え・・・・・<消える>というキーワードは、ミステリーの世界においてとても重要な要素になりがちです。今回は、<消失>にテーマを絞ったミステリー短編集をご紹介したいと思います。北山猛邦さんの『神の光』です。
こんな人におすすめ
消失トリック目白押しのミステリー短編集に興味がある人
続きを読む
 二〇二五年最後の一日となりました。今年も色々あったものの、無事にブログを続けることができて感無量です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
二〇二五年最後の一日となりました。今年も色々あったものの、無事にブログを続けることができて感無量です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
何かと慌ただしいご時世ですが、小説界隈に関していえば、個人的に一番衝撃的だったのは作家・西澤保彦さんが亡くなられたことです。まだ六十代。多作な作家さんだし、てっきり今後も新作がたくさん楽しめると思っていたのに、本当にショックです。心よりご冥福をお祈りするとともに、哀悼の意を表するため、今年の「はいくる」は西澤保彦さんの短編集『パズラー 謎と論理のエンタテイメント』で締めようと思います。
こんな人におすすめ
アクロバティックなミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 今年も残すところあとわずか。世間はすっかりクリスマスおよび年末ムードです。師走、などと言われるほど忙しない時期ですが、こういうバタバタした感じ、結構好きだったりします。
今年も残すところあとわずか。世間はすっかりクリスマスおよび年末ムードです。師走、などと言われるほど忙しない時期ですが、こういうバタバタした感じ、結構好きだったりします。
イルミネーションなどで華やかな季節ですが、私はこの時期に、どこか薄暗く寒々しいものを感じます。気温の低さや、日照時間の短さが原因でしょうか。先日読んだ作品は、そんな気分にぴったりの一冊でした。山口恵以子さんの『見てはいけない』です。
こんな人におすすめ
愛憎絡み合うサスペンス短編集に興味がある人
続きを読む
 どんなジャンルもそうであるように、ミステリー作品はしばしば批判の対象となることがあります。ネタが古い、キャラクターが凡庸、内容がごっちゃになっていて分かりにくい・・・物語に唯一絶対の正解はない以上、ある程度は避けられないことなのかもしれません。
どんなジャンルもそうであるように、ミステリー作品はしばしば批判の対象となることがあります。ネタが古い、キャラクターが凡庸、内容がごっちゃになっていて分かりにくい・・・物語に唯一絶対の正解はない以上、ある程度は避けられないことなのかもしれません。
ミステリーでよくある批判内容として、<謎解きがフェアじゃない>というものがあります。読者に対して正しく情報が提示されておらず、「これで真相を見破るの無理だろ!」という場合に出てくる言葉ですね。ミステリーはホラーと違い、基本的に謎解きを楽しむものですから、それが無理となると批判したくなるのも当然。逆に言えば、ここをクリアしていれば、ミステリーとしての評価はグンと上がる傾向にある気がします。その点、今回取り上げる作品はとても満足度が高かったですよ。歌野晶午さんの『そして名探偵は生まれた』です。
こんな人におすすめ
意外性たっぷりのミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 振り返ってみると、子ども時代の行事は圧倒的に夏が多かった気がします。日が長いこと、日没後も屋外活動がしやすいこと、冬と比べると感染症による体調不良者も出にくいこと等が理由でしょうか。暑すぎて真夏は外出すらままならない現代とは、ずいぶん違ったものだなと思います。
振り返ってみると、子ども時代の行事は圧倒的に夏が多かった気がします。日が長いこと、日没後も屋外活動がしやすいこと、冬と比べると感染症による体調不良者も出にくいこと等が理由でしょうか。暑すぎて真夏は外出すらままならない現代とは、ずいぶん違ったものだなと思います。
創作の世界においても、子どもないし子ども時代が絡んだ作品では、夏の行事が重要な役割を果たすことがしばしばあります。恩田陸さん『蛇行する川のほとり』では演劇祭準備のための夏合宿が、東野圭吾さん『レイクサイド』では避暑地でのお泊り夏期講習が、ミステリーの舞台となりました。夏のきらきらした眩しさと、絡み合う人間模様の生々しさが、いい対比になっていたと思います。今回取り上げる作品では、夏の林間学校での惨劇が描かれていました。櫛木理宇さんの『七月の鋭利な破片』です。
こんな人におすすめ
子どもが絡んだサスペンスミステリーに興味がある人
続きを読む
 SFやホラーのジャンルにおいては、超能力・霊能力・魔力といった異能が頻繁に登場します。と同時に、異能を取り締まったり、サポートしたりする組織や職員が出てくる機会も多いです。日本に限らず海外でも同様なので、万国共通の発想なのかもしれません。
SFやホラーのジャンルにおいては、超能力・霊能力・魔力といった異能が頻繁に登場します。と同時に、異能を取り締まったり、サポートしたりする組織や職員が出てくる機会も多いです。日本に限らず海外でも同様なので、万国共通の発想なのかもしれません。
この手の存在としては、マーベル・シネマスティック・ユニバースに登場する武装組織<S.H.I.E.L.D>、SCP作品世界で暗躍する<SCP財団>などが有名です。タイムリープやタイムトラベルといった能力が登場する作品だと、能力者によって勝手に歴史改変が行われないよう管理する<時空管理局>(名称は違うことも有)なる存在が出てくることも多いですね。「自分もこうした組織の一員だったら・・・」と空想した経験がある方、私を含めて、結構多いのではないでしょうか。今回は、私が大好きな秘密組織・捜査員が登場する作品をご紹介したいと思います。西澤保彦さんの『念力密室!』です。
こんな人におすすめ
SF設定が絡んだミステリーが読みたい人
続きを読む
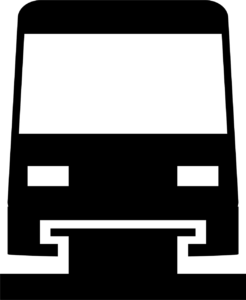 クリエイターに必要な能力は色々あります。その中の一つは発想力。読んで字の如く、物事をクリエイト(創造)するのが仕事なわけですから、アイデアが湧かなくては始まりません。私は先日、童話を創ってみる機会を得たのですが、まあ、全然アイデアが出ないこと出ないこと。頭に浮かぶのは聞いたことがあるストーリーばかりで、たった三十分足らずの時間だったにもかかわらずヘトヘトになってしまいました。一から何かを生み出せる方達って、本当に天才だなと思います。
クリエイターに必要な能力は色々あります。その中の一つは発想力。読んで字の如く、物事をクリエイト(創造)するのが仕事なわけですから、アイデアが湧かなくては始まりません。私は先日、童話を創ってみる機会を得たのですが、まあ、全然アイデアが出ないこと出ないこと。頭に浮かぶのは聞いたことがあるストーリーばかりで、たった三十分足らずの時間だったにもかかわらずヘトヘトになってしまいました。一から何かを生み出せる方達って、本当に天才だなと思います。
当然ながら、このブログで取り上げてきた作家さん達にも、発想力は必要不可欠。その発揮の仕方も十人十色、それぞれ個性があって面白いです。中でも、この方の発想って、ユーモアたっぷりで大好きなんですよ。今日ご紹介するのは、藤崎翔さんの『オリエンド鈍行殺人事件』です。
こんな人におすすめ
どんでん返しのあるユーモア小説短編集が読みたい人
続きを読む
 「嘘ついたら針千本飲ます」「嘘つきは地獄で閻魔様に舌を抜かれるよ」。誰しも人生で一度や二度、こうしたフレーズを見聞きしたことがあると思います。嘘というのは、事実とは異なる言葉を言って他者を騙すことなわけですから、基本的には良くないものとされがちです。昔からある民話にも、嘘つきがひどい目に遭い、正直者が報われるというパターンは山ほどあります。
「嘘ついたら針千本飲ます」「嘘つきは地獄で閻魔様に舌を抜かれるよ」。誰しも人生で一度や二度、こうしたフレーズを見聞きしたことがあると思います。嘘というのは、事実とは異なる言葉を言って他者を騙すことなわけですから、基本的には良くないものとされがちです。昔からある民話にも、嘘つきがひどい目に遭い、正直者が報われるというパターンは山ほどあります。
とはいえ、すべての嘘が悪いものなのか、断罪されるべきものなのかというと、必ずしもそうとは言い切れません。時には誰かのためを思って嘘をつくことだってあるでしょう。一言で<嘘>といっても、そこには無数の背景や事情が存在するのです。今回は、様々な嘘が出てくる作品を取り上げたいと思います。小倉千秋さんの『嘘つきたちへ』です。
こんな人におすすめ
嘘と騙しに満ちたミステリー短編集に興味がある人
続きを読む
 何らかの事件が起こった際、ニュースに以下のフレーズが出てくることがしばしばあります。「精神鑑定の結果を踏まえ、その他の証拠を総合的に考慮した上で・・・」「被告の精神鑑定を行った医師に尋問を行い・・・」。この<精神鑑定>とは、裁判所が被告人等の精神状態・責任能力を判断するため、精神科医といった鑑定人に命じる鑑定の一つ。結果如何によっては裁判所の判断が大きく変わることも有り得る、重要な行為です。
何らかの事件が起こった際、ニュースに以下のフレーズが出てくることがしばしばあります。「精神鑑定の結果を踏まえ、その他の証拠を総合的に考慮した上で・・・」「被告の精神鑑定を行った医師に尋問を行い・・・」。この<精神鑑定>とは、裁判所が被告人等の精神状態・責任能力を判断するため、精神科医といった鑑定人に命じる鑑定の一つ。結果如何によっては裁判所の判断が大きく変わることも有り得る、重要な行為です。
 フィクションの世界には、<ダークヒーロー>というキャラクターが存在します。読んで字の如く<闇のヒーロー>のことで、正義と相対する立場ながら確固たる信念を持っていたり、悲劇的な過去ゆえに悪側になってしまったり、違法な手段を使いながら人を救ったりするキャラクターを指します。例を挙げると、映画『スターウォーズシリーズ』のダース・ベイダーや、大場つぐみさん原作による漫画『DEATH NOTE』の主人公・夜神月などですね。これらのキャラクターは、どうかすると正義側の主人公より人気を集めることもあったりします。
フィクションの世界には、<ダークヒーロー>というキャラクターが存在します。読んで字の如く<闇のヒーロー>のことで、正義と相対する立場ながら確固たる信念を持っていたり、悲劇的な過去ゆえに悪側になってしまったり、違法な手段を使いながら人を救ったりするキャラクターを指します。例を挙げると、映画『スターウォーズシリーズ』のダース・ベイダーや、大場つぐみさん原作による漫画『DEATH NOTE』の主人公・夜神月などですね。これらのキャラクターは、どうかすると正義側の主人公より人気を集めることもあったりします。 新年あけましておめでとうございます。ブログを解説し、今年で十年目。長く続いたよなと、自分でしみじみしています。今年もミステリーとホラー中心にゆるゆるレビューしていくつもりですので、どうぞよろしくお願いします。
新年あけましておめでとうございます。ブログを解説し、今年で十年目。長く続いたよなと、自分でしみじみしています。今年もミステリーとホラー中心にゆるゆるレビューしていくつもりですので、どうぞよろしくお願いします。 二〇二五年最後の一日となりました。今年も色々あったものの、無事にブログを続けることができて感無量です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
二〇二五年最後の一日となりました。今年も色々あったものの、無事にブログを続けることができて感無量です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。 今年も残すところあとわずか。世間はすっかりクリスマスおよび年末ムードです。師走、などと言われるほど忙しない時期ですが、こういうバタバタした感じ、結構好きだったりします。
今年も残すところあとわずか。世間はすっかりクリスマスおよび年末ムードです。師走、などと言われるほど忙しない時期ですが、こういうバタバタした感じ、結構好きだったりします。 どんなジャンルもそうであるように、ミステリー作品はしばしば批判の対象となることがあります。ネタが古い、キャラクターが凡庸、内容がごっちゃになっていて分かりにくい・・・物語に唯一絶対の正解はない以上、ある程度は避けられないことなのかもしれません。
どんなジャンルもそうであるように、ミステリー作品はしばしば批判の対象となることがあります。ネタが古い、キャラクターが凡庸、内容がごっちゃになっていて分かりにくい・・・物語に唯一絶対の正解はない以上、ある程度は避けられないことなのかもしれません。 振り返ってみると、子ども時代の行事は圧倒的に夏が多かった気がします。日が長いこと、日没後も屋外活動がしやすいこと、冬と比べると感染症による体調不良者も出にくいこと等が理由でしょうか。暑すぎて真夏は外出すらままならない現代とは、ずいぶん違ったものだなと思います。
振り返ってみると、子ども時代の行事は圧倒的に夏が多かった気がします。日が長いこと、日没後も屋外活動がしやすいこと、冬と比べると感染症による体調不良者も出にくいこと等が理由でしょうか。暑すぎて真夏は外出すらままならない現代とは、ずいぶん違ったものだなと思います。 SFやホラーのジャンルにおいては、超能力・霊能力・魔力といった異能が頻繁に登場します。と同時に、異能を取り締まったり、サポートしたりする組織や職員が出てくる機会も多いです。日本に限らず海外でも同様なので、万国共通の発想なのかもしれません。
SFやホラーのジャンルにおいては、超能力・霊能力・魔力といった異能が頻繁に登場します。と同時に、異能を取り締まったり、サポートしたりする組織や職員が出てくる機会も多いです。日本に限らず海外でも同様なので、万国共通の発想なのかもしれません。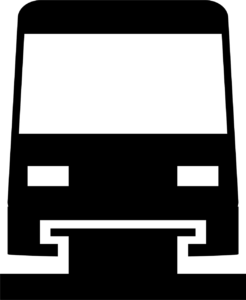 クリエイターに必要な能力は色々あります。その中の一つは発想力。読んで字の如く、物事をクリエイト(創造)するのが仕事なわけですから、アイデアが湧かなくては始まりません。私は先日、童話を創ってみる機会を得たのですが、まあ、全然アイデアが出ないこと出ないこと。頭に浮かぶのは聞いたことがあるストーリーばかりで、たった三十分足らずの時間だったにもかかわらずヘトヘトになってしまいました。一から何かを生み出せる方達って、本当に天才だなと思います。
クリエイターに必要な能力は色々あります。その中の一つは発想力。読んで字の如く、物事をクリエイト(創造)するのが仕事なわけですから、アイデアが湧かなくては始まりません。私は先日、童話を創ってみる機会を得たのですが、まあ、全然アイデアが出ないこと出ないこと。頭に浮かぶのは聞いたことがあるストーリーばかりで、たった三十分足らずの時間だったにもかかわらずヘトヘトになってしまいました。一から何かを生み出せる方達って、本当に天才だなと思います。 「嘘ついたら針千本飲ます」「嘘つきは地獄で閻魔様に舌を抜かれるよ」。誰しも人生で一度や二度、こうしたフレーズを見聞きしたことがあると思います。嘘というのは、事実とは異なる言葉を言って他者を騙すことなわけですから、基本的には良くないものとされがちです。昔からある民話にも、嘘つきがひどい目に遭い、正直者が報われるというパターンは山ほどあります。
「嘘ついたら針千本飲ます」「嘘つきは地獄で閻魔様に舌を抜かれるよ」。誰しも人生で一度や二度、こうしたフレーズを見聞きしたことがあると思います。嘘というのは、事実とは異なる言葉を言って他者を騙すことなわけですから、基本的には良くないものとされがちです。昔からある民話にも、嘘つきがひどい目に遭い、正直者が報われるというパターンは山ほどあります。