 単に私の読書傾向の問題なのかもしれませんが、ここ最近読んだ作品の中で物語の鍵を握るのは、母娘ないし姉妹でした。女性同士の場合、掴み合い殴り合いの大乱闘になる可能性が低い(かもしれない)分、水面下でのドロドロを描きやすく、イヤミスやホラーにハマるからかな?と考えています。
単に私の読書傾向の問題なのかもしれませんが、ここ最近読んだ作品の中で物語の鍵を握るのは、母娘ないし姉妹でした。女性同士の場合、掴み合い殴り合いの大乱闘になる可能性が低い(かもしれない)分、水面下でのドロドロを描きやすく、イヤミスやホラーにハマるからかな?と考えています。
とはいえ、当たり前の話ですが、男性同士だって確執が生まれることは多々あります。真保裕一さんの『お前の罪を自白しろ』では父と息子が、東野圭吾さんの『手紙』では兄と弟が、切っても切れない縁の上で苦悩する人間ドラマを繰り広げました。どちらも映像化された有名作品なので、ご存知の方も多いと思います。それから、知名度という点ではこの二つより低いかもしれませんが、これもお気に入りの作品です。瀬尾まいこさんの『戸村飯店 青春100連発』です。
こんな人におすすめ
兄弟が織りなす青春小説に興味がある人

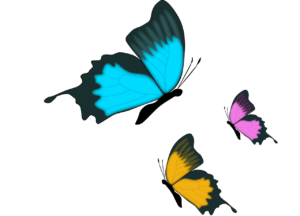 人生において、「趣味は何ですか」と聞かれる機会って意外と多いです。私の場合、そう聞かれた場合の答えは、子どもの頃から「読書です」。その趣味を大人になるまで続けた結果、こういうブログまで始めてしまいました。人間、好きなものについて語ることは楽しいですし、ついつい熱が入ります。
人生において、「趣味は何ですか」と聞かれる機会って意外と多いです。私の場合、そう聞かれた場合の答えは、子どもの頃から「読書です」。その趣味を大人になるまで続けた結果、こういうブログまで始めてしまいました。人間、好きなものについて語ることは楽しいですし、ついつい熱が入ります。 ここ数年で、<ルッキズム>という言葉を聞く機会が激増しました。これは外見を重視する考え方のことで、<外見至上主義><外見重視主義>という言い方もします。一般的に使われるようになったのは最近のような気もしますが、実は日本でも昭和から存在した価値観です。
ここ数年で、<ルッキズム>という言葉を聞く機会が激増しました。これは外見を重視する考え方のことで、<外見至上主義><外見重視主義>という言い方もします。一般的に使われるようになったのは最近のような気もしますが、実は日本でも昭和から存在した価値観です。 <何かを始めようとした時に限って、別のことに目がいってしまう>という経験をお持ちの方、一定数いらっしゃると思います。よく聞くのは、<勉強を始めた途端、部屋の掃除をしたくなった>とかですね。普段は特に気にならないのに、一体どうしてなんでしょう?
<何かを始めようとした時に限って、別のことに目がいってしまう>という経験をお持ちの方、一定数いらっしゃると思います。よく聞くのは、<勉強を始めた途端、部屋の掃除をしたくなった>とかですね。普段は特に気にならないのに、一体どうしてなんでしょう? 電子書籍の台頭が著しいこのご時世。とはいえ、私個人としては、本は紙で読むのが好きです。ちょっとしたコラムやレビューくらいの分量ならいいのですが、単行本一冊分ともなると、画面越しに読むうちに頭と目が疲れてくるんですよ。DVDやCDのレンタルショップはネット配信の勢いに押されているようですが、本屋と図書館は決してなくならないでほしいと切に願います。
電子書籍の台頭が著しいこのご時世。とはいえ、私個人としては、本は紙で読むのが好きです。ちょっとしたコラムやレビューくらいの分量ならいいのですが、単行本一冊分ともなると、画面越しに読むうちに頭と目が疲れてくるんですよ。DVDやCDのレンタルショップはネット配信の勢いに押されているようですが、本屋と図書館は決してなくならないでほしいと切に願います。 家事。読んで字の如く、掃除・洗濯・食事の支度といった<家の仕事>を指す言葉です。今は家電が発達し、資金に余裕があれば外注という手段もあるとはいえ、細々とした家事の数はそれこそ無限大。不器用で要領の悪い私など、やるべき家事が多い時は、しばらくフリーズして現実逃避に走ることさえあります。
家事。読んで字の如く、掃除・洗濯・食事の支度といった<家の仕事>を指す言葉です。今は家電が発達し、資金に余裕があれば外注という手段もあるとはいえ、細々とした家事の数はそれこそ無限大。不器用で要領の悪い私など、やるべき家事が多い時は、しばらくフリーズして現実逃避に走ることさえあります。 「時代は問わないから、海外の作家を一人挙げてみて」と聞かれた時、ウィリアム・シェイクスピアの名前を挙げる人はかなり多いと思います。シェイクスピアは一六世紀後半から一七世紀初頭にかけて活躍したイギリス人作家で、二〇〇二年の<百名の最も偉大な英国人>投票で第五位にランクインするほどの有名人です。それほど有名な偉人にも関わらず、現存する資料が少ないため、<実は作品はシェイクスピアではない別人が書いていた説><複数の作家が共同ペンネームでシェイクスピアを名乗っていた説>等々、面白い噂が色々ある人物でもあります。
「時代は問わないから、海外の作家を一人挙げてみて」と聞かれた時、ウィリアム・シェイクスピアの名前を挙げる人はかなり多いと思います。シェイクスピアは一六世紀後半から一七世紀初頭にかけて活躍したイギリス人作家で、二〇〇二年の<百名の最も偉大な英国人>投票で第五位にランクインするほどの有名人です。それほど有名な偉人にも関わらず、現存する資料が少ないため、<実は作品はシェイクスピアではない別人が書いていた説><複数の作家が共同ペンネームでシェイクスピアを名乗っていた説>等々、面白い噂が色々ある人物でもあります。 「こんな結末は読んだことがない」「予想を遥かに超えた奇想天外なストーリー」。物語を評する上で、これらの文言はしばしば誉め言葉として使われます。私自身、事前の予想を裏切られるビックリ展開は大好物。この話は一体どう落着するのだろうと、手に汗握りながらページをめくったことも一度や二度ではありません。
「こんな結末は読んだことがない」「予想を遥かに超えた奇想天外なストーリー」。物語を評する上で、これらの文言はしばしば誉め言葉として使われます。私自身、事前の予想を裏切られるビックリ展開は大好物。この話は一体どう落着するのだろうと、手に汗握りながらページをめくったことも一度や二度ではありません。 もともとは、飲食店などを一人で利用する客を指す言葉<おひとり様>。それが二〇〇〇年代に入った頃から<一人で生きている自立した大人><同居人がおらず、一人で暮らす人>といった意味で使われるようになりました。流行語大賞にノミネートされたり、ベストセラー書籍のタイトルに使われたりしたこともあり、すっかり世の中に定着した感がありますね。
もともとは、飲食店などを一人で利用する客を指す言葉<おひとり様>。それが二〇〇〇年代に入った頃から<一人で生きている自立した大人><同居人がおらず、一人で暮らす人>といった意味で使われるようになりました。流行語大賞にノミネートされたり、ベストセラー書籍のタイトルに使われたりしたこともあり、すっかり世の中に定着した感がありますね。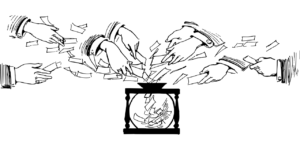 明けましておめでとうございます。毎週水曜更新を基本としている当ブログ、今年は偶然にも一月一日が更新日でした。だからどうというわけではないものの、たまたまこういう記念日に当たると、なんとなく嬉しいものですね。今年も変わらず偏った趣味丸出しの読書レビューを投稿し続けるつもりなので、どうぞよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。毎週水曜更新を基本としている当ブログ、今年は偶然にも一月一日が更新日でした。だからどうというわけではないものの、たまたまこういう記念日に当たると、なんとなく嬉しいものですね。今年も変わらず偏った趣味丸出しの読書レビューを投稿し続けるつもりなので、どうぞよろしくお願いします。