 私は根が小心者ということもあり、体に異変を感じたらさっさと病院に行きます。「実は深刻な病気だったらどうしよう」「様子見している内に手遅れになったら・・・」等々、つい悪い想像を巡らせてしまうんです。そのため、昔から病院はけっこう馴染みのある場所でした。
私は根が小心者ということもあり、体に異変を感じたらさっさと病院に行きます。「実は深刻な病気だったらどうしよう」「様子見している内に手遅れになったら・・・」等々、つい悪い想像を巡らせてしまうんです。そのため、昔から病院はけっこう馴染みのある場所でした。
一つの建物内に生と死が同時に存在する病院は、フィクションの世界においても様々なドラマの舞台とされてきました。ヒューマンストーリーなら垣谷美雨さんの『後悔病棟』、サスペンスなら海堂尊さんの『チーム・バチスタの栄光』、ホラーなら五十嵐貴久さんの『リメンバー』etcetc。いずれも病院という場所の特性を活かした名作ばかりです。先日読んだ小説も、病院とそこに関わる人々の人間模様をテーマにしていました。久坂部羊さんの『怖い患者』です。
こんな人におすすめ
医療の世界を舞台にしたイヤミス短編集が読みたい人

 私は九州人ということもあり、子どもの頃から方言が身近に存在していました。成長後、地元を離れた時、標準語だと思っていた言葉が実は方言だと知って驚いたり、話し言葉から同郷出身者が分かって何となく嬉しかったりと、方言にまつわる思い出も結構あります。そう言えば、メダカは理科教育が広がるまで<メダカ>という統一名がなく、方言による呼び名が日本全国に五百個近くあると知った時は衝撃だったなぁ。
私は九州人ということもあり、子どもの頃から方言が身近に存在していました。成長後、地元を離れた時、標準語だと思っていた言葉が実は方言だと知って驚いたり、話し言葉から同郷出身者が分かって何となく嬉しかったりと、方言にまつわる思い出も結構あります。そう言えば、メダカは理科教育が広がるまで<メダカ>という統一名がなく、方言による呼び名が日本全国に五百個近くあると知った時は衝撃だったなぁ。 暦の上では秋になり、店先に並ぶファッションアイテムも秋を意識したものが増えました。とはいえ、気候はまだまだ夏そのもの。半袖シャツも、帽子も、キンキンに冷えた飲み物も、当分手放せそうにありません。
暦の上では秋になり、店先に並ぶファッションアイテムも秋を意識したものが増えました。とはいえ、気候はまだまだ夏そのもの。半袖シャツも、帽子も、キンキンに冷えた飲み物も、当分手放せそうにありません。 人間の三代欲求は、<食欲><睡眠欲><性欲>と言われています。これを緊急度合という基準で考えると、強いのは睡眠欲、食欲、性欲の順なのだとか。人は睡眠欲や食欲が満たされないと、いずれ体力が尽きて死んでしまいますが、性欲は満たされなくてもすぐ死ぬことはありません。子孫繁栄にしたって、人工的な手段を使えば、欲求云々を抜きにしても可能と言えば可能です。そう考えると、これは確かに正しい順位なのでしょう。
人間の三代欲求は、<食欲><睡眠欲><性欲>と言われています。これを緊急度合という基準で考えると、強いのは睡眠欲、食欲、性欲の順なのだとか。人は睡眠欲や食欲が満たされないと、いずれ体力が尽きて死んでしまいますが、性欲は満たされなくてもすぐ死ぬことはありません。子孫繁栄にしたって、人工的な手段を使えば、欲求云々を抜きにしても可能と言えば可能です。そう考えると、これは確かに正しい順位なのでしょう。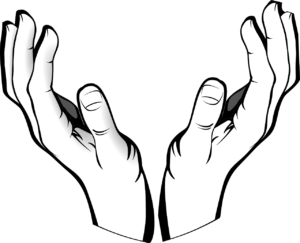 小説を読むことの一体何がそんなに楽しいのか。人によって答えは様々でしょうが、ラストの面白さを堪能したいから、と答える人は多い気がします。感動的なフィナーレだったり、衝撃的などんでん返しがあったり、終わったはずの恐怖が再び甦ってきたり・・・現実世界にはそんなにはっきりしたオチがない分、小説で味わいたいと思うのも当然です。
小説を読むことの一体何がそんなに楽しいのか。人によって答えは様々でしょうが、ラストの面白さを堪能したいから、と答える人は多い気がします。感動的なフィナーレだったり、衝撃的などんでん返しがあったり、終わったはずの恐怖が再び甦ってきたり・・・現実世界にはそんなにはっきりしたオチがない分、小説で味わいたいと思うのも当然です。 バラエティ番組、大好きです。時に悲惨な出来事を映さざるを得ないニュースや、一度見逃すとストーリーが分からなくなる可能性があるドラマと違い、適度に陽気で、適度に気軽。その日の気分次第でチャンネルを合わせれば、難しいことを考えずさらっと楽しめるところが魅力です。
バラエティ番組、大好きです。時に悲惨な出来事を映さざるを得ないニュースや、一度見逃すとストーリーが分からなくなる可能性があるドラマと違い、適度に陽気で、適度に気軽。その日の気分次第でチャンネルを合わせれば、難しいことを考えずさらっと楽しめるところが魅力です。 クローズド・サークルものの定番シチュエーションといえば、洋館、辺鄙な場所にある村、孤島の三つだと思います(すべて交通網・連絡ツールが遮断されていることが前提)。この三つの内、一番行き来するのに労力が要るのは、孤島ではないでしょうか。洋館や僻地の村の場合、死ぬ気で頑張れば自分の足で移動可能ですが、孤島の場合、どうにかして船等の移動手段を確保しなければなりません。となると、操縦は誰がするのか、エンジンは無事なのか等の問題が生じ、物語がよりスリリングなものになります。
クローズド・サークルものの定番シチュエーションといえば、洋館、辺鄙な場所にある村、孤島の三つだと思います(すべて交通網・連絡ツールが遮断されていることが前提)。この三つの内、一番行き来するのに労力が要るのは、孤島ではないでしょうか。洋館や僻地の村の場合、死ぬ気で頑張れば自分の足で移動可能ですが、孤島の場合、どうにかして船等の移動手段を確保しなければなりません。となると、操縦は誰がするのか、エンジンは無事なのか等の問題が生じ、物語がよりスリリングなものになります。 季節は夏真っ盛り。毎年思うことですが、なんだか年々夏の暑さが増している気がします。コロナの影響でマスク着用が一般的になったことも、息苦しさを増加させているのかもしれません。
季節は夏真っ盛り。毎年思うことですが、なんだか年々夏の暑さが増している気がします。コロナの影響でマスク着用が一般的になったことも、息苦しさを増加させているのかもしれません。 デスゲームもの、というジャンルがあります。これは、逃亡不可能な状況に置かれた登場人物達が、生死を賭けたゲームに参加する様子を描いたもの。生還者は一人だけと決められていたり、進行次第では全員生還も可能だったり、敗者は命ではなく社会的生命を奪われたりと、個性的な設定がなされていることが多いです。
デスゲームもの、というジャンルがあります。これは、逃亡不可能な状況に置かれた登場人物達が、生死を賭けたゲームに参加する様子を描いたもの。生還者は一人だけと決められていたり、進行次第では全員生還も可能だったり、敗者は命ではなく社会的生命を奪われたりと、個性的な設定がなされていることが多いです。 人は時に<恐らく絶対実現不可能だろうけど、願わずにはいられない夢>を見てしまうことがあります。世界中の富をすべて手中に収めてしまいたい、かもしれない。片思いの相手が一夜にして自分に夢中になればいいのに、かもしれない。人によって願う夢も様々でしょうが、<亡くなった人が甦ればいいのに><死んでもまた生き返りたい>と思う人は相当数いそうな気がします。
人は時に<恐らく絶対実現不可能だろうけど、願わずにはいられない夢>を見てしまうことがあります。世界中の富をすべて手中に収めてしまいたい、かもしれない。片思いの相手が一夜にして自分に夢中になればいいのに、かもしれない。人によって願う夢も様々でしょうが、<亡くなった人が甦ればいいのに><死んでもまた生き返りたい>と思う人は相当数いそうな気がします。