 「あなたは罪を償わなければなりません」「自分の罪と向き合い、償おうと思います」・・・ミステリーやサスペンス作品で、しばしば登場するフレーズです。罪を犯したなら、必ず償いをしなければならない。これを否定できる人間はどこにもいないでしょう。
「あなたは罪を償わなければなりません」「自分の罪と向き合い、償おうと思います」・・・ミステリーやサスペンス作品で、しばしば登場するフレーズです。罪を犯したなら、必ず償いをしなければならない。これを否定できる人間はどこにもいないでしょう。
では、この<罪を償う>とは一体何でしょうか。刑務所で服役すること?被害者もしくはその遺族に賠償金を払うこと?かつてハンムラビ法典が定めていたように、与えた被害同様の傷をその身に受けること?この答えは人によって千差万別であり、明確な答えを決めることは難しそうです。今回ご紹介する作品にも、罪の償いとは何なのか、煩悶する登場人物達が出てきます。湊かなえさんの『贖罪』です。
こんな人におすすめ
独白形式で進むサスペンスが読みたい人

 地球温暖化が叫ばれて久しい昨今、夏の暑さの到来もどんどん早くなっている気がします。今年で言えば、五月半ばの時点ですでに三十度を超える地方があったとのこと。これから夏本番ですし、暑さ対策をしっかり行い、元気に過ごしたいものですね。
地球温暖化が叫ばれて久しい昨今、夏の暑さの到来もどんどん早くなっている気がします。今年で言えば、五月半ばの時点ですでに三十度を超える地方があったとのこと。これから夏本番ですし、暑さ対策をしっかり行い、元気に過ごしたいものですね。 この世には、是非が簡単に決められないものがたくさんあります。<復讐>もその一つ。聖書に<復讐するは我にあり>と書いてあるように、個人が勝手に復讐することは許されないという考え方は、社会に根強く浸透しています。現実問題、一人一人が自由気ままに憎い相手に復讐していけば秩序は崩壊してしまうわけですから、それもやむをえないと言えるでしょう。
この世には、是非が簡単に決められないものがたくさんあります。<復讐>もその一つ。聖書に<復讐するは我にあり>と書いてあるように、個人が勝手に復讐することは許されないという考え方は、社会に根強く浸透しています。現実問題、一人一人が自由気ままに憎い相手に復讐していけば秩序は崩壊してしまうわけですから、それもやむをえないと言えるでしょう。 ものすごく有名な割に、日本の創作物で主要キャラになることが意外と少ない存在、それが<天使>と<悪魔>だと思います。どちらも外国の宗教に由来する存在だからでしょうか。海外作品の場合、主人公のピンチを天使が救ってくれたり悪魔がラスボスだったりすることがしばしばありますが、日本ではこれらの役割を<神仏><守護霊><怨霊><妖怪>等が担うことが多い気がします。
ものすごく有名な割に、日本の創作物で主要キャラになることが意外と少ない存在、それが<天使>と<悪魔>だと思います。どちらも外国の宗教に由来する存在だからでしょうか。海外作品の場合、主人公のピンチを天使が救ってくれたり悪魔がラスボスだったりすることがしばしばありますが、日本ではこれらの役割を<神仏><守護霊><怨霊><妖怪>等が担うことが多い気がします。 「さあ、今日は一杯やるぞ!」となった時、まずどんなお酒に手を出すでしょうか。缶チューハイ、カクテル、ワイン、日本酒・・・それこそ無限に出てきそうですが、割合で言うなら、「まずビールで」となる人が多い気がします。家にしろ飲食店にしろ準備するのに時間がかからず、アルコール度数もさほどではないビールは、多くの人に好まれています。
「さあ、今日は一杯やるぞ!」となった時、まずどんなお酒に手を出すでしょうか。缶チューハイ、カクテル、ワイン、日本酒・・・それこそ無限に出てきそうですが、割合で言うなら、「まずビールで」となる人が多い気がします。家にしろ飲食店にしろ準備するのに時間がかからず、アルコール度数もさほどではないビールは、多くの人に好まれています。 『必殺シリーズ』『怨み屋本舗』『善悪の屑』・・・ドラマや漫画として人気を博したこれらの作品には、一つの共通項があります。それは、何らかの事情で法の裁きを逃れた、あるいは裁かれたものの罪に不釣り合いな軽い刑罰だった標的を密かに裁く存在が出てくるということ。悲しいかな、罪を犯しておきながらのうのうとのさばる人間は、いつの世にも存在します。「誰かがあいつらに罰を与えてくれたらいいのに・・・」。法的な是非はともかく、そういう感情は誰しもあるでしょう。だからこそ、例に挙げたような作品が人気を集めるのかもしれません。
『必殺シリーズ』『怨み屋本舗』『善悪の屑』・・・ドラマや漫画として人気を博したこれらの作品には、一つの共通項があります。それは、何らかの事情で法の裁きを逃れた、あるいは裁かれたものの罪に不釣り合いな軽い刑罰だった標的を密かに裁く存在が出てくるということ。悲しいかな、罪を犯しておきながらのうのうとのさばる人間は、いつの世にも存在します。「誰かがあいつらに罰を与えてくれたらいいのに・・・」。法的な是非はともかく、そういう感情は誰しもあるでしょう。だからこそ、例に挙げたような作品が人気を集めるのかもしれません。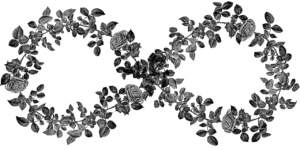 愛とは決して後悔しないこと、最後に愛は勝つ、愛は地球を救う・・・愛に関する有名な台詞や歌詞、格言は数えきれないほど存在します。愛はキリスト教で最大のテーマとされていますし、日本においても、年齢や性別の枠を超えた深く広い慈しみの感情として捉えられることが多いです。お金や権力を求めるのは何となく卑しい気もしますが、<愛のため>というお題目があると、気高く誠実なもののような気がしますよね。
愛とは決して後悔しないこと、最後に愛は勝つ、愛は地球を救う・・・愛に関する有名な台詞や歌詞、格言は数えきれないほど存在します。愛はキリスト教で最大のテーマとされていますし、日本においても、年齢や性別の枠を超えた深く広い慈しみの感情として捉えられることが多いです。お金や権力を求めるのは何となく卑しい気もしますが、<愛のため>というお題目があると、気高く誠実なもののような気がしますよね。 一説によると、人間の三代欲求(食欲、睡眠欲、性欲)の中で一番緊急度が高いのは<睡眠欲>だそうです。「あれ、食欲じゃないの?」と思う向きもありそうですが、なかなかどうして、睡眠を侮ることはできません。食欲の場合、<断食>が一部の宗教や健康法に取り入れられていることからも分かる通り、適切な条件下での制限なら、心身を害することはありません。対して睡眠欲の場合、満たされない場合の肉体的・精神的なダメージは計り知れないものがあります。眠らせないという拷問が存在することが、その証と言えるでしょう。
一説によると、人間の三代欲求(食欲、睡眠欲、性欲)の中で一番緊急度が高いのは<睡眠欲>だそうです。「あれ、食欲じゃないの?」と思う向きもありそうですが、なかなかどうして、睡眠を侮ることはできません。食欲の場合、<断食>が一部の宗教や健康法に取り入れられていることからも分かる通り、適切な条件下での制限なら、心身を害することはありません。対して睡眠欲の場合、満たされない場合の肉体的・精神的なダメージは計り知れないものがあります。眠らせないという拷問が存在することが、その証と言えるでしょう。 ミステリーやホラーのジャンルが好きで、<クローズド・サークル>を知らない方は、恐らくいないでしょう。単語を聞いたことがなくても、「外界と往来不可能な状況で事件が起こる様子を描いた作品のことだよ」と説明されれば、きっとピンとくると思います。嵐の孤島や吹雪の山荘、難破中の船・・・脱出困難な状況で怪事件が起き、「誰が犯人なのか」「次は自分が殺されるのか」と疑心暗鬼に駆られる登場人物達の姿は、多くのミステリーファンをハラハラドキドキさせてくれます。
ミステリーやホラーのジャンルが好きで、<クローズド・サークル>を知らない方は、恐らくいないでしょう。単語を聞いたことがなくても、「外界と往来不可能な状況で事件が起こる様子を描いた作品のことだよ」と説明されれば、きっとピンとくると思います。嵐の孤島や吹雪の山荘、難破中の船・・・脱出困難な状況で怪事件が起き、「誰が犯人なのか」「次は自分が殺されるのか」と疑心暗鬼に駆られる登場人物達の姿は、多くのミステリーファンをハラハラドキドキさせてくれます。 皆さんは文集を作った経験があるでしょうか。私の場合、小学校と中学校で、最低でも年に一回は文集を作った記憶があります。私は作文を書くことが好きだったのでそれほど苦ではありませんでしたが、苦手な子にとっては苦行でしかなかった様子。そんな生徒達のモチベーションを上げ、文集の体裁を整えられるだけの作文を集め、冊子としてまとめなくてはならないのですから、先生達もさぞ大変だったろうなと思います。
皆さんは文集を作った経験があるでしょうか。私の場合、小学校と中学校で、最低でも年に一回は文集を作った記憶があります。私は作文を書くことが好きだったのでそれほど苦ではありませんでしたが、苦手な子にとっては苦行でしかなかった様子。そんな生徒達のモチベーションを上げ、文集の体裁を整えられるだけの作文を集め、冊子としてまとめなくてはならないのですから、先生達もさぞ大変だったろうなと思います。