 創作の世界には、<群像劇>というストーリー手法があります。これは、特定の主人公を設けるのではなく、複数の主要登場人物がそれぞれ別の物語を紡ぎ、最終的に一つの結末に辿り着くスタイルのこと。グランドホテル形式、アンサンブル・キャストなどの呼び方をされることもあるようです。大ヒットを記録したラブコメディ映画『ラブ・アクチュアリー』形式のこと、と言えば、分かりやすいかもしれません。
創作の世界には、<群像劇>というストーリー手法があります。これは、特定の主人公を設けるのではなく、複数の主要登場人物がそれぞれ別の物語を紡ぎ、最終的に一つの結末に辿り着くスタイルのこと。グランドホテル形式、アンサンブル・キャストなどの呼び方をされることもあるようです。大ヒットを記録したラブコメディ映画『ラブ・アクチュアリー』形式のこと、と言えば、分かりやすいかもしれません。
勢いがあって視覚的に映えるからか、群像劇は映画やドラマで使われることが多いです。とはいえ、面白い群像劇小説もたくさんありますよ。恩田陸さんの『ドミノ』や辻村深月さんの『本日は大安なり』は、どちらもわざわざハードカバー版を買ったくらい好きな作品です。上記の二作品より登場人物数は少ないですが、これも上質な群像劇でした。小池真理子さんの『蠍のいる森』です。
こんな人におすすめ
男女の愛憎が絡んだサイコサスペンスが読みたい人

 <猟奇的>というのは、本来、<奇怪・異常なものを強く求める様子>を指す言葉です。現代では、もともとの意味から少し離れ、<残酷な><グロテスクな>という意味で使われることが多いですね。特に、遺体が激しく損壊されていたり連続殺人だったりする事件を<猟奇殺人>と表現するケースが多いと思います。
<猟奇的>というのは、本来、<奇怪・異常なものを強く求める様子>を指す言葉です。現代では、もともとの意味から少し離れ、<残酷な><グロテスクな>という意味で使われることが多いですね。特に、遺体が激しく損壊されていたり連続殺人だったりする事件を<猟奇殺人>と表現するケースが多いと思います。 病院・廃屋と並ぶホラー作品の定番スポット、それが学校です。一説によると、平日の昼は大勢の子どもが出入りして賑やかなのに対し、夜や休日はほぼ無人状態になるギャップが恐怖心をかき立てるのだとか。確かに、無人島で物音がしなくても何とも思わないでしょうが、日中ワイワイと騒がしい学校がしんと静まり返っていると、不安や恐怖がより増す気がします。
病院・廃屋と並ぶホラー作品の定番スポット、それが学校です。一説によると、平日の昼は大勢の子どもが出入りして賑やかなのに対し、夜や休日はほぼ無人状態になるギャップが恐怖心をかき立てるのだとか。確かに、無人島で物音がしなくても何とも思わないでしょうが、日中ワイワイと騒がしい学校がしんと静まり返っていると、不安や恐怖がより増す気がします。 どんな物語にも、必ず主人公ないし主人公格の登場人物が出てきます。となると、膨大な数の主要登場人物が存在するわけで、必然的に彼らのキャラクターも多種多様なものになります。読者の共感を集め、感情移入され、エールを受けながら自分の人生を生きる主人公もいるでしょう。私の場合、これまで読んだ小説で一番応援した主人公は、小野不由美さん『十二国記シリーズ』の陽子。人目を気にするいい子ちゃんだった陽子が、異世界で心身ともにズタボロになりつつ、必死で足掻く姿に感情移入しまくりました。
どんな物語にも、必ず主人公ないし主人公格の登場人物が出てきます。となると、膨大な数の主要登場人物が存在するわけで、必然的に彼らのキャラクターも多種多様なものになります。読者の共感を集め、感情移入され、エールを受けながら自分の人生を生きる主人公もいるでしょう。私の場合、これまで読んだ小説で一番応援した主人公は、小野不由美さん『十二国記シリーズ』の陽子。人目を気にするいい子ちゃんだった陽子が、異世界で心身ともにズタボロになりつつ、必死で足掻く姿に感情移入しまくりました。 ホラー作品には、登場人物達を恐怖のどん底に突き落とすモンスターがしばしば出てきます。このモンスターの種類は、大きく分けて二種類です。一つ目は、<誰が><なぜ><どのように>モンスターになってしまったか、はっきり分かるタイプ。映画『13日の金曜日』シリーズに登場するジェイソンや、鈴木光司さんによる『リング』の貞子がこれに当たります。モンスターの正体やそうなった理由が明確に存在するため、登場人物達の謎解きを見るのも楽しみの一つです。
ホラー作品には、登場人物達を恐怖のどん底に突き落とすモンスターがしばしば出てきます。このモンスターの種類は、大きく分けて二種類です。一つ目は、<誰が><なぜ><どのように>モンスターになってしまったか、はっきり分かるタイプ。映画『13日の金曜日』シリーズに登場するジェイソンや、鈴木光司さんによる『リング』の貞子がこれに当たります。モンスターの正体やそうなった理由が明確に存在するため、登場人物達の謎解きを見るのも楽しみの一つです。 私はこの十年ほど日記をつけ続けています。日付、天気、その日の出来事と食事のメニューを書いた数行程度のものですが、後日、過去の記憶が曖昧な時に振り返ることができて便利ですよ。たまに昔の日記を読み直してみると、「あ、そういえばこんなことがあったっけ」「私、五年前と同じことしてるじゃん」等々、色々と思うところがって面白いです。
私はこの十年ほど日記をつけ続けています。日付、天気、その日の出来事と食事のメニューを書いた数行程度のものですが、後日、過去の記憶が曖昧な時に振り返ることができて便利ですよ。たまに昔の日記を読み直してみると、「あ、そういえばこんなことがあったっけ」「私、五年前と同じことしてるじゃん」等々、色々と思うところがって面白いです。 先日、<ジェントルゴースト・ストーリー>という言葉を知りました。意味は<優しい幽霊の物語>といったところでしょうか。人を祟ったり呪ったりしない、心優しい幽霊が出てくるほのぼのストーリーを指すそうです。こういう幽霊のことを、怪談研究家の東雅夫さんは<優霊>と訳したそうですが、実に名訳だと思います。
先日、<ジェントルゴースト・ストーリー>という言葉を知りました。意味は<優しい幽霊の物語>といったところでしょうか。人を祟ったり呪ったりしない、心優しい幽霊が出てくるほのぼのストーリーを指すそうです。こういう幽霊のことを、怪談研究家の東雅夫さんは<優霊>と訳したそうですが、実に名訳だと思います。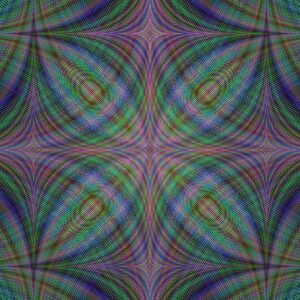 現実に起きた出来事とフィクションとをいかに上手く絡めるか。それは、面白い物語を作る上で重要な要素です。イエス・キリストがキリスト教の始祖であること、徳川家康が江戸幕府を開いたこと、ドイツにアドルフ・ヒトラーという独裁者が存在したこと。すべて歴史的事実であり、なかったことにすることはできません。
現実に起きた出来事とフィクションとをいかに上手く絡めるか。それは、面白い物語を作る上で重要な要素です。イエス・キリストがキリスト教の始祖であること、徳川家康が江戸幕府を開いたこと、ドイツにアドルフ・ヒトラーという独裁者が存在したこと。すべて歴史的事実であり、なかったことにすることはできません。 道徳に反したやり方で相手を精神的に追い詰めるモラルハラスメント、性的な言動で相手に苦痛を与えるセクシャルハラスメント、職場内で権利や立場を利用した嫌がらせを行うパワーハラスメント、妊娠・出産・育児に関することで心身に不快な思いをさせられるマタニティハラスメント、教育現場において教職員がその権限を使って他者の修学や教育の邪魔をするアカデミックハラスメント・・・・・悲しいかな、この世にはたくさんのハラスメント、すなわち人権侵害が溢れています。もちろん、こうした嫌がらせ行為は大昔から存在したのでしょうが、今はインターネット文化が発展した分、より複雑かつ陰湿になってきた気がします。
道徳に反したやり方で相手を精神的に追い詰めるモラルハラスメント、性的な言動で相手に苦痛を与えるセクシャルハラスメント、職場内で権利や立場を利用した嫌がらせを行うパワーハラスメント、妊娠・出産・育児に関することで心身に不快な思いをさせられるマタニティハラスメント、教育現場において教職員がその権限を使って他者の修学や教育の邪魔をするアカデミックハラスメント・・・・・悲しいかな、この世にはたくさんのハラスメント、すなわち人権侵害が溢れています。もちろん、こうした嫌がらせ行為は大昔から存在したのでしょうが、今はインターネット文化が発展した分、より複雑かつ陰湿になってきた気がします。 人あるところにドラマあり。一人の人間が存在すれば、そこには必ず悲喜こもごもが生まれます。それは創作物の世界においても同じこと。だからこそ、多くの人間達が集う場所は、様々なフィクション作品の舞台となってきました。
人あるところにドラマあり。一人の人間が存在すれば、そこには必ず悲喜こもごもが生まれます。それは創作物の世界においても同じこと。だからこそ、多くの人間達が集う場所は、様々なフィクション作品の舞台となってきました。