 本好きなら誰しも一度は憧れるであろう職場、それは<図書館>と<書店>だと思います。この二つの内、図書館は自治体運営であることが多く、採用枠がとても少ないですが、書店は多いとは言えないまでもそれなりに求人があります。周囲を本で囲まれ、手を伸ばせばすぐそこに大量の本がある生活。本好きにとっては夢のような場所でしょう。
本好きなら誰しも一度は憧れるであろう職場、それは<図書館>と<書店>だと思います。この二つの内、図書館は自治体運営であることが多く、採用枠がとても少ないですが、書店は多いとは言えないまでもそれなりに求人があります。周囲を本で囲まれ、手を伸ばせばすぐそこに大量の本がある生活。本好きにとっては夢のような場所でしょう。
ですが、どの職業もそうであるように、書店という仕事は楽しいことだけではありません。実際、求人情報の口コミ掲示板などを見れば、書店稼業の過酷さの一端を垣間見ることができます。とはいえ、玉石混交のネット情報じゃイマイチ大変さが伝わってこないな・・・という方は、これを読んでみてはどうでしょうか。宮西真冬さんの『彼女の背中を押したのは』です。
こんな人におすすめ
家庭や仕事に悩む女性を描いたヒューマンミステリーが読みたい人

 コロナが流行る前、<シェア>という言葉を頻繁に見聞きする時期がありました。大皿料理やスイーツを頼んで同席者同士でシェア、ステーションに停めてある車をみんなで利用するカーシェアリング、各自の能力を必要に応じて共有・マッチングさせるスキルシェア・・・中でも、一つの家に複数人で住むシェアハウスは、人気リアリティショーの設定となったこともあり、爆発的に知名度を伸ばしました。気の合う仲間同士と楽しく、しかし家族ほどべったり干渉することなく暮らせたら、さぞ快適なことでしょう。
コロナが流行る前、<シェア>という言葉を頻繁に見聞きする時期がありました。大皿料理やスイーツを頼んで同席者同士でシェア、ステーションに停めてある車をみんなで利用するカーシェアリング、各自の能力を必要に応じて共有・マッチングさせるスキルシェア・・・中でも、一つの家に複数人で住むシェアハウスは、人気リアリティショーの設定となったこともあり、爆発的に知名度を伸ばしました。気の合う仲間同士と楽しく、しかし家族ほどべったり干渉することなく暮らせたら、さぞ快適なことでしょう。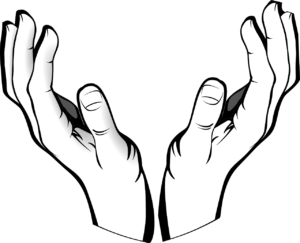 小説を読むことの一体何がそんなに楽しいのか。人によって答えは様々でしょうが、ラストの面白さを堪能したいから、と答える人は多い気がします。感動的なフィナーレだったり、衝撃的などんでん返しがあったり、終わったはずの恐怖が再び甦ってきたり・・・現実世界にはそんなにはっきりしたオチがない分、小説で味わいたいと思うのも当然です。
小説を読むことの一体何がそんなに楽しいのか。人によって答えは様々でしょうが、ラストの面白さを堪能したいから、と答える人は多い気がします。感動的なフィナーレだったり、衝撃的などんでん返しがあったり、終わったはずの恐怖が再び甦ってきたり・・・現実世界にはそんなにはっきりしたオチがない分、小説で味わいたいと思うのも当然です。 バラエティ番組、大好きです。時に悲惨な出来事を映さざるを得ないニュースや、一度見逃すとストーリーが分からなくなる可能性があるドラマと違い、適度に陽気で、適度に気軽。その日の気分次第でチャンネルを合わせれば、難しいことを考えずさらっと楽しめるところが魅力です。
バラエティ番組、大好きです。時に悲惨な出来事を映さざるを得ないニュースや、一度見逃すとストーリーが分からなくなる可能性があるドラマと違い、適度に陽気で、適度に気軽。その日の気分次第でチャンネルを合わせれば、難しいことを考えずさらっと楽しめるところが魅力です。 病院・廃屋と並ぶホラー作品の定番スポット、それが学校です。一説によると、平日の昼は大勢の子どもが出入りして賑やかなのに対し、夜や休日はほぼ無人状態になるギャップが恐怖心をかき立てるのだとか。確かに、無人島で物音がしなくても何とも思わないでしょうが、日中ワイワイと騒がしい学校がしんと静まり返っていると、不安や恐怖がより増す気がします。
病院・廃屋と並ぶホラー作品の定番スポット、それが学校です。一説によると、平日の昼は大勢の子どもが出入りして賑やかなのに対し、夜や休日はほぼ無人状態になるギャップが恐怖心をかき立てるのだとか。確かに、無人島で物音がしなくても何とも思わないでしょうが、日中ワイワイと騒がしい学校がしんと静まり返っていると、不安や恐怖がより増す気がします。 物事には何でも<王道パターン>というものがあります。小説もまた然り。困窮した女性が王子様と巡り会うシンデレラストーリーや、正義のヒーローが巨悪を倒す勧善懲悪ものは、古今東西、数多く存在します。こうした王道物語は、結末が読者の期待を裏切らないこともあり、多くの人々に支持されてきました。
物事には何でも<王道パターン>というものがあります。小説もまた然り。困窮した女性が王子様と巡り会うシンデレラストーリーや、正義のヒーローが巨悪を倒す勧善懲悪ものは、古今東西、数多く存在します。こうした王道物語は、結末が読者の期待を裏切らないこともあり、多くの人々に支持されてきました。 小説や漫画がシリーズ化するための条件は色々ありますが、まず第一は<一冊目が面白かったこと>だと思います。最初の一歩の出来が良く、人気を集めたからこそ続編が出るというのは自明の理。シリーズ作品の中で、一番好きなものとして第一作目を挙げる人が多いのは当然と言えるでしょう。
小説や漫画がシリーズ化するための条件は色々ありますが、まず第一は<一冊目が面白かったこと>だと思います。最初の一歩の出来が良く、人気を集めたからこそ続編が出るというのは自明の理。シリーズ作品の中で、一番好きなものとして第一作目を挙げる人が多いのは当然と言えるでしょう。 世界には何冊の本が存在するのでしょうか。現在の数は調べても分かりませんでしたが、二〇一〇年末のGoogleの調査によると、一億二九八六万四八八〇冊だそうです。それから十年以上の月日が流れているので、今はもっと数が増えているでしょう。では、その中で、私の大好きなフィクション小説の割合は?正確な数は不明なものの、相当数あることは間違いありません。
世界には何冊の本が存在するのでしょうか。現在の数は調べても分かりませんでしたが、二〇一〇年末のGoogleの調査によると、一億二九八六万四八八〇冊だそうです。それから十年以上の月日が流れているので、今はもっと数が増えているでしょう。では、その中で、私の大好きなフィクション小説の割合は?正確な数は不明なものの、相当数あることは間違いありません。 コロナが流行り出してからめっきり足が遠のきましたが、以前は古本屋が大好きでした。本屋と違って購入前に中身を確認することができますし、大型店なら在庫も豊富。世間的な認知度の低い作家さんの著作や、かなり昔に出版された本が置いてあることもあり、時にはとんでもない掘り出し物を見つけることもあります。
コロナが流行り出してからめっきり足が遠のきましたが、以前は古本屋が大好きでした。本屋と違って購入前に中身を確認することができますし、大型店なら在庫も豊富。世間的な認知度の低い作家さんの著作や、かなり昔に出版された本が置いてあることもあり、時にはとんでもない掘り出し物を見つけることもあります。 ペットを飼うことは、ここで書ききれないほどの幸せをもたらしてくれます。毎日同じ屋根の下で寝起きし、食事をし、一緒に遊んだり、気まぐれに振り回されたり、甘えておねだりされたり・・・・・こんな風に家族として過ごしていれば、ペットの死により心を病む人がいるというのも頷けます。
ペットを飼うことは、ここで書ききれないほどの幸せをもたらしてくれます。毎日同じ屋根の下で寝起きし、食事をし、一緒に遊んだり、気まぐれに振り回されたり、甘えておねだりされたり・・・・・こんな風に家族として過ごしていれば、ペットの死により心を病む人がいるというのも頷けます。