 私が子どもの頃、オカルト界隈では<ノストラダムスの大予言>が有名でした。最近は名前が出る機会もめっきり減ったので一応解説しておくと、これはフランスの医師兼占星術師であるノストラダムスが書き残した予言のこと。実物は相当な量の詩集なのですが、日本ではその中の第十巻七十二番『一九九九年七の月、空から恐怖の大王が来るだろう』という一文がやたらと広まり、「一九九九年の七月の世界へ滅亡するんだ!」という騒ぎになったのです。実際のところ、ノストラダムス自身は世界滅亡に関する記述は何一つ残しておらず、そもそも詩の和訳が間違っているという指摘すらあるものの、ホラー好きとしては印象深いブームでした。
私が子どもの頃、オカルト界隈では<ノストラダムスの大予言>が有名でした。最近は名前が出る機会もめっきり減ったので一応解説しておくと、これはフランスの医師兼占星術師であるノストラダムスが書き残した予言のこと。実物は相当な量の詩集なのですが、日本ではその中の第十巻七十二番『一九九九年七の月、空から恐怖の大王が来るだろう』という一文がやたらと広まり、「一九九九年の七月の世界へ滅亡するんだ!」という騒ぎになったのです。実際のところ、ノストラダムス自身は世界滅亡に関する記述は何一つ残しておらず、そもそも詩の和訳が間違っているという指摘すらあるものの、ホラー好きとしては印象深いブームでした。
一時期はテレビで大真面目に特番が組まれるほど人気を集めただけあって、ノストラダムスやその予言が登場するフィクション作品も多いです。ものすごく記憶に残っているのは、さくらももこさんの漫画『ちびまる子ちゃん』の中の一話「まる子ノストラダムスの予言を気にする」。主人公達がノストラダムスの予言を信じ、怯え、「どうせ世界滅亡するのなら勉強なんてしなくていいや」と遊び惚けるようになるが・・・というエピソードで、予言を知った登場人物達のうろたえっぷりや、その後の現実的なオチのつけ方の描写がお見事でした。では、小説では何が印象に残っているかというと、『ちびまる子ちゃん』とは一八〇度違う作風ですが、これを挙げます。森絵都さんの『つきのふね』です。
こんなひとにおすすめ
思春期の少年少女の戦いを描いた青春物語に興味がある人

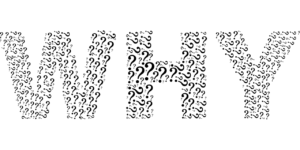 これまでミステリーやホラー小説のレビューで散々「仰天しました」「まんまと騙されました」「驚きでひっくり返りそうでした」と書いてきたことからも分かるように、私は物事の裏を読むのが苦手です。小説にしろ映画にしろ、どんでん返し系の作品はほぼ一〇〇パーセント引っかかり、ラストで絶句するのがいつものパターン。なんならティーンエイジャー向けに書かれたヤングアダルト小説にすら、しっかり騙されてしまいます。
これまでミステリーやホラー小説のレビューで散々「仰天しました」「まんまと騙されました」「驚きでひっくり返りそうでした」と書いてきたことからも分かるように、私は物事の裏を読むのが苦手です。小説にしろ映画にしろ、どんでん返し系の作品はほぼ一〇〇パーセント引っかかり、ラストで絶句するのがいつものパターン。なんならティーンエイジャー向けに書かれたヤングアダルト小説にすら、しっかり騙されてしまいます。 厚生労働省の調査によると、一番自殺が多い年代は六十代、次に五十代、四十代と続くそうです。百歳超えが珍しくない現代において、これくらいの年代はまだまだ働き盛り。公私共にエネルギッシュな年頃と言っても過言ではありません。とはいえ、二十代、三十代と比べれば、体力気力が衰えてくる世代であることもまた事実。だからこそ、苦境に立たされた時、「こんな苦しいことがまだ何十年も続くのか」と弱気になり、自殺に走ってしまうのかもしれませんね。
厚生労働省の調査によると、一番自殺が多い年代は六十代、次に五十代、四十代と続くそうです。百歳超えが珍しくない現代において、これくらいの年代はまだまだ働き盛り。公私共にエネルギッシュな年頃と言っても過言ではありません。とはいえ、二十代、三十代と比べれば、体力気力が衰えてくる世代であることもまた事実。だからこそ、苦境に立たされた時、「こんな苦しいことがまだ何十年も続くのか」と弱気になり、自殺に走ってしまうのかもしれませんね。 昔読んだ小説の中で、こんなエピソードが紹介されていました。『チャレンジャー号爆発事故の発生後、阿鼻叫喚に陥る観客達を写した写真が話題となった。ところが後日、その写真は事故発生後ではなく、打ち上げ直後に撮られたものだと判明した。当初、恐怖と混乱の真っ只中と思われていた観客達の表情は、実は期待と興奮に沸いていたのだ』。その後同様のエピソードを見聞きしたことはないため、もしかしたら単なる噂なのかもしれませんが、十分あり得る話だと思います。物の見え方というものは、受け取る側の価値観や状況によって簡単に変化するものです。
昔読んだ小説の中で、こんなエピソードが紹介されていました。『チャレンジャー号爆発事故の発生後、阿鼻叫喚に陥る観客達を写した写真が話題となった。ところが後日、その写真は事故発生後ではなく、打ち上げ直後に撮られたものだと判明した。当初、恐怖と混乱の真っ只中と思われていた観客達の表情は、実は期待と興奮に沸いていたのだ』。その後同様のエピソードを見聞きしたことはないため、もしかしたら単なる噂なのかもしれませんが、十分あり得る話だと思います。物の見え方というものは、受け取る側の価値観や状況によって簡単に変化するものです。 俳句というのは、とても奥の深い芸術です。たった十七文字という、詩の世界の中でも異例の短さで、風景や作者の心情を表現する。文字数が少ない分、一見簡単だと思えるかもしれませんが、十七文字という縛りの中で世界観を作り上げるのは至難の業です。日本での認知度の高さは言うに及ばず、近年では海外にまで俳句文化が進出し、英語で俳句を詠むこともあるのだとか。日本の伝統文化が世界に広まるのは、日本人として嬉しいことですね。
俳句というのは、とても奥の深い芸術です。たった十七文字という、詩の世界の中でも異例の短さで、風景や作者の心情を表現する。文字数が少ない分、一見簡単だと思えるかもしれませんが、十七文字という縛りの中で世界観を作り上げるのは至難の業です。日本での認知度の高さは言うに及ばず、近年では海外にまで俳句文化が進出し、英語で俳句を詠むこともあるのだとか。日本の伝統文化が世界に広まるのは、日本人として嬉しいことですね。 新興住宅地。読んで字の如く、今まで宅地でなかった土地を新たに興した住宅地のことです。インフラ関係が新しく丈夫なこと、周囲に子育て世界が多く育児に向いていること、古参の住民がいないためゼロから人間関係をスタートさせられることなど、住む上でたくさんのメリットがあります。
新興住宅地。読んで字の如く、今まで宅地でなかった土地を新たに興した住宅地のことです。インフラ関係が新しく丈夫なこと、周囲に子育て世界が多く育児に向いていること、古参の住民がいないためゼロから人間関係をスタートさせられることなど、住む上でたくさんのメリットがあります。 「あなたは罪を償わなければなりません」「自分の罪と向き合い、償おうと思います」・・・ミステリーやサスペンス作品で、しばしば登場するフレーズです。罪を犯したなら、必ず償いをしなければならない。これを否定できる人間はどこにもいないでしょう。
「あなたは罪を償わなければなりません」「自分の罪と向き合い、償おうと思います」・・・ミステリーやサスペンス作品で、しばしば登場するフレーズです。罪を犯したなら、必ず償いをしなければならない。これを否定できる人間はどこにもいないでしょう。 鏡にだけ映る人影、無人の部屋から聞こえるすすり泣き、捨てたはずなのに戻ってくる人形・・・ホラー作品の定番といえる設定ですが、これらには共通点があります。それは<ないはずのものが在る>ということ。自分以外誰もいないはずなのに鏡に人影が映ったり、空室から人の声が聞こえたりしたとすれば、その恐ろしさは想像を絶するものがあります。
鏡にだけ映る人影、無人の部屋から聞こえるすすり泣き、捨てたはずなのに戻ってくる人形・・・ホラー作品の定番といえる設定ですが、これらには共通点があります。それは<ないはずのものが在る>ということ。自分以外誰もいないはずなのに鏡に人影が映ったり、空室から人の声が聞こえたりしたとすれば、その恐ろしさは想像を絶するものがあります。 あけましておめでとうございます。2023年が始まりました。2022年を振り返ってみると、収束の気配が見えないコロナ、ロシアのウクライナ侵攻、安倍元首相の銃殺事件と、気持ちが塞ぐニュースが多かったです。今年こそは明るい兆しが見えますように。それはきっと、全人類共通の願いでしょう。私にできることは少ないかもしれませんが、自分と家族の健やかな生活を守るよう心掛けつつ、読書も楽しんでいきたいです。
あけましておめでとうございます。2023年が始まりました。2022年を振り返ってみると、収束の気配が見えないコロナ、ロシアのウクライナ侵攻、安倍元首相の銃殺事件と、気持ちが塞ぐニュースが多かったです。今年こそは明るい兆しが見えますように。それはきっと、全人類共通の願いでしょう。私にできることは少ないかもしれませんが、自分と家族の健やかな生活を守るよう心掛けつつ、読書も楽しんでいきたいです。 今まで知らなかった作家さんの存在を認知し、その面白さを知る。本好きにとっては無上の喜びの一つです。この<はいくる>のような読書ブログやレビューサイトの存在意義は、そうした喜びのために在るといっても過言ではありません。
今まで知らなかった作家さんの存在を認知し、その面白さを知る。本好きにとっては無上の喜びの一つです。この<はいくる>のような読書ブログやレビューサイトの存在意義は、そうした喜びのために在るといっても過言ではありません。