 世界には何冊の本が存在するのでしょうか。現在の数は調べても分かりませんでしたが、二〇一〇年末のGoogleの調査によると、一億二九八六万四八八〇冊だそうです。それから十年以上の月日が流れているので、今はもっと数が増えているでしょう。では、その中で、私の大好きなフィクション小説の割合は?正確な数は不明なものの、相当数あることは間違いありません。
世界には何冊の本が存在するのでしょうか。現在の数は調べても分かりませんでしたが、二〇一〇年末のGoogleの調査によると、一億二九八六万四八八〇冊だそうです。それから十年以上の月日が流れているので、今はもっと数が増えているでしょう。では、その中で、私の大好きなフィクション小説の割合は?正確な数は不明なものの、相当数あることは間違いありません。
ただ、数が増えるとなると、当然、複数の小説でテーマがかぶるというケースが出てきます。この場合、同じテーマをどうやって上手く料理するかが作家の腕の見せ所。高見広春さんの『バトル・ロワイアル』と、スーザン・コリンズの『ハンガー・ゲーム』は、<公権力主宰のデスゲームに巻き込まれた少年少女達>という設定が共通しているものの、物語の展開やキャラクター設定はまるで別物です。この小説も、違う作家さんの作品とテーマは同じながら、まったく違う面白さを味わえました。森村誠一さんの『ファミリー』です。
こんな人におすすめ
家庭内サイコホラーが読みたい人

 宗教とは本来、人を救い、拠り所となるための存在です。苦しいことがあれば乗り越えられるよう神に祈り、善行を積めば死後に天国に行けると信じる。そんな信仰心は、時に人に大きな力を与えました。「神様の加護があるのだから大丈夫」。そう確信し、自信を持って物事に臨めば、不安も緊張もなく一〇〇パーセント能力を発揮することも可能でしょう。
宗教とは本来、人を救い、拠り所となるための存在です。苦しいことがあれば乗り越えられるよう神に祈り、善行を積めば死後に天国に行けると信じる。そんな信仰心は、時に人に大きな力を与えました。「神様の加護があるのだから大丈夫」。そう確信し、自信を持って物事に臨めば、不安も緊張もなく一〇〇パーセント能力を発揮することも可能でしょう。 私は本をジャケ買い(内容を知らないCDや本などを、パッケージのみで選ぶ購入方法)することがあります。この時、「内容が想像と違う!」と驚かされることもしばしばです。特にハードカバーの場合、文庫本のように裏表紙にあらすじが書いてあるわけではないので、このパターンが多いですね。
私は本をジャケ買い(内容を知らないCDや本などを、パッケージのみで選ぶ購入方法)することがあります。この時、「内容が想像と違う!」と驚かされることもしばしばです。特にハードカバーの場合、文庫本のように裏表紙にあらすじが書いてあるわけではないので、このパターンが多いですね。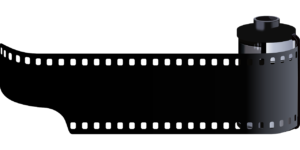 写真が発明されたのは、一九世紀前半のことです。この当時、産業革命によりいわゆる中産階級が多数出現し、彼らの間で肖像画が流行したことで、一気に写真の需要も高まったのだとか。そんな写真は一八四三年、長崎に入港したオランダ船により日本に入ってきました。当初は一枚撮るのにも特殊な技術や設備が必要だったようですが、インスタントカメラや携帯電話、スマートフォン等の普及により、今やその気になれば幼児だって写真を撮ることができます。
写真が発明されたのは、一九世紀前半のことです。この当時、産業革命によりいわゆる中産階級が多数出現し、彼らの間で肖像画が流行したことで、一気に写真の需要も高まったのだとか。そんな写真は一八四三年、長崎に入港したオランダ船により日本に入ってきました。当初は一枚撮るのにも特殊な技術や設備が必要だったようですが、インスタントカメラや携帯電話、スマートフォン等の普及により、今やその気になれば幼児だって写真を撮ることができます。 どこかの記事でも書いた気がしますが、今の私は気に入った作家さんの作品を一気読みするタイプの人間です。「この人の小説、面白い!」と思ったら、図書館でその作家さんの小説を探し、借りられるだけ借りるというのがいつものパターン。当然、自分が今、誰の著作を読んでいるかをしっかりチェックしておく必要があります。
どこかの記事でも書いた気がしますが、今の私は気に入った作家さんの作品を一気読みするタイプの人間です。「この人の小説、面白い!」と思ったら、図書館でその作家さんの小説を探し、借りられるだけ借りるというのがいつものパターン。当然、自分が今、誰の著作を読んでいるかをしっかりチェックしておく必要があります。 クリエイティブな世界には、複数の名義で作品を発表されている方がしばしば存在します。理由は人それぞれでしょうが、一番は、名前に付きまとうイメージや先入観を払拭するためではないでしょうか。〇〇先生は恋愛漫画とか、△△先生はロックミュージックとか、色々イメージがありますからね。
クリエイティブな世界には、複数の名義で作品を発表されている方がしばしば存在します。理由は人それぞれでしょうが、一番は、名前に付きまとうイメージや先入観を払拭するためではないでしょうか。〇〇先生は恋愛漫画とか、△△先生はロックミュージックとか、色々イメージがありますからね。 <不思議>という言葉を辞書で引いてみると、「そうであることの原因がよく分からず、なぜだろうと考えさせられること。その事柄」とあります。この「原因がよく分からない」というところが最大のポイント。<怖い小説>や<ハラハラさせられる小説>の場合、大抵はその原因が作中で判明しますが、<不思議な小説>はその限りではありません。登場人物にも読者にも、事態の真相や全容が分からないまま終わることだってあり得ます。
<不思議>という言葉を辞書で引いてみると、「そうであることの原因がよく分からず、なぜだろうと考えさせられること。その事柄」とあります。この「原因がよく分からない」というところが最大のポイント。<怖い小説>や<ハラハラさせられる小説>の場合、大抵はその原因が作中で判明しますが、<不思議な小説>はその限りではありません。登場人物にも読者にも、事態の真相や全容が分からないまま終わることだってあり得ます。 「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。
「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。 日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。
日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。 季節は夏。今はマスク着用が求められるご時世なせいもあり、暑さが余計に身に染みます。こういう時は、少しでも涼を取れる娯楽が欲しいですよね。例えば、風鈴を吊るすとか、オリジナルのかき氷を作ってみるとか・・・昔のように自由気ままに外出するのがまだ難しい分、自宅で気軽に涼める楽しみを探してしまいます。
季節は夏。今はマスク着用が求められるご時世なせいもあり、暑さが余計に身に染みます。こういう時は、少しでも涼を取れる娯楽が欲しいですよね。例えば、風鈴を吊るすとか、オリジナルのかき氷を作ってみるとか・・・昔のように自由気ままに外出するのがまだ難しい分、自宅で気軽に涼める楽しみを探してしまいます。