 「人は中身が大事」「外見より心の美しさの方が価値がある」誰しも一度は聞いたことのあるフレーズだと思います。そうであってほしいと心底思うものの、悲しいかな、人の立ち位置を決める上で、容姿が重要なファクターとなることは事実。美しい人間が尊ばれ、そうでない人間が蔑まれる場面は、日常の至る所に溢れています。
「人は中身が大事」「外見より心の美しさの方が価値がある」誰しも一度は聞いたことのあるフレーズだと思います。そうであってほしいと心底思うものの、悲しいかな、人の立ち位置を決める上で、容姿が重要なファクターとなることは事実。美しい人間が尊ばれ、そうでない人間が蔑まれる場面は、日常の至る所に溢れています。
美醜をテーマにした作品といえば、漫画なら岡崎京子さんの『ヘルタースケルター』や楳図かずおさんの『洗礼』、小説なら百田尚樹さんの『モンスター』、ブログでも紹介した唯川恵さんの『テティスの逆鱗』などがあります。これらの作品の共通点は、美に取りつかれた人間は時として化物じみてくるということ。美しさを求めるあまり人間離れしてしまうなんて、なんとも皮肉な話ですよね。今回取り上げる小説にも、美という呪いにかかった人間たちが登場します。澤村伊智さんの『うるはしみにくし あなたのともだち』です。
こんな人におすすめ
スクールカーストが出てくるホラーミステリーが読みたい人

 ミステリーやホラーのように<真相究明><問題解決>に重きが置かれる作品の場合、「なぜ主人公は必死に事件に取り組むのか」という動機付けが重要となります。ここをすんなりクリアするための方法の一つは、主人公の職業をマスコミ関係者にすること。何しろ調査・取材することが仕事ですし、犯罪性が高くないと捜査できない警察と違い、まだ物理的な被害が出ていない(判明していない)事件や、何十年も前に起きた未解決事件に対してでも動けます。
ミステリーやホラーのように<真相究明><問題解決>に重きが置かれる作品の場合、「なぜ主人公は必死に事件に取り組むのか」という動機付けが重要となります。ここをすんなりクリアするための方法の一つは、主人公の職業をマスコミ関係者にすること。何しろ調査・取材することが仕事ですし、犯罪性が高くないと捜査できない警察と違い、まだ物理的な被害が出ていない(判明していない)事件や、何十年も前に起きた未解決事件に対してでも動けます。 大変ありがたいことに、実家には今も私の部屋が残っています。子どもの頃に買った本も、量は減ったとはいえ保管してもらっており、それらを読み返すのが帰省の楽しみの一つです。ページが手垢で黒くなるほど読んだというのに、再読してもまだ面白いのだから、読書というのは奥深いものですね。
大変ありがたいことに、実家には今も私の部屋が残っています。子どもの頃に買った本も、量は減ったとはいえ保管してもらっており、それらを読み返すのが帰省の楽しみの一つです。ページが手垢で黒くなるほど読んだというのに、再読してもまだ面白いのだから、読書というのは奥深いものですね。 人がホテルに求めるものは一体何でしょう。楽しい旅のひと時を過ごすため、静かな空間でリフレッシュするため、落ち着いて仕事をするため・・・追手の目から隠れるため、などという理由もあるかもしれません。旅館と比べると、ホテルは従業員が客室内に出入りする機会が少なく、個人の空間が保たれるというのが特徴です。
人がホテルに求めるものは一体何でしょう。楽しい旅のひと時を過ごすため、静かな空間でリフレッシュするため、落ち着いて仕事をするため・・・追手の目から隠れるため、などという理由もあるかもしれません。旅館と比べると、ホテルは従業員が客室内に出入りする機会が少なく、個人の空間が保たれるというのが特徴です。 一昔前に比べると、調査活動や情報発信はとても効率良く行えるようになりました。特にインターネットが発展してから、その傾向は顕著になった気がします。ネットを使えば、百年以上前の出来事を調べることも、遥か遠くに住む人々とやり取りすることも思いのまま。そうやって目的を達成しようとする人達の奮闘記としては、櫛木理宇さんの『虎を追う』などがあります。
一昔前に比べると、調査活動や情報発信はとても効率良く行えるようになりました。特にインターネットが発展してから、その傾向は顕著になった気がします。ネットを使えば、百年以上前の出来事を調べることも、遥か遠くに住む人々とやり取りすることも思いのまま。そうやって目的を達成しようとする人達の奮闘記としては、櫛木理宇さんの『虎を追う』などがあります。 この世には数えきれないほどの主義・傾向がありますが、その中でも<ナルシズム>の認知度の高さは群を抜いていると思います。これはギリシャ神話に登場する美少年・ナルキッソスが、泉に映る自分の姿に恋したエピソードに由来し、自分自身を強く愛する精神状態と指すとのこと。あまりによく知られた用語なので、「あの人ってナルシストだよね」「今の言い方、ナスルシストっぽかったかな」等々、日常会話に登場する機会も多いです。
この世には数えきれないほどの主義・傾向がありますが、その中でも<ナルシズム>の認知度の高さは群を抜いていると思います。これはギリシャ神話に登場する美少年・ナルキッソスが、泉に映る自分の姿に恋したエピソードに由来し、自分自身を強く愛する精神状態と指すとのこと。あまりによく知られた用語なので、「あの人ってナルシストだよね」「今の言い方、ナスルシストっぽかったかな」等々、日常会話に登場する機会も多いです。 私は短編小説が大好きでよく読みますが、その上で、一つ問題があります。短編小説の場合、アンソロジー等に収録される可能性が高く、短編集発売の情報に期待していたらすでに読んでいた、ということがあり得るのです。優れた短編は何度読んでも面白いものですが、それでも、初めて読んだ瞬間の驚きはもう得られません。
私は短編小説が大好きでよく読みますが、その上で、一つ問題があります。短編小説の場合、アンソロジー等に収録される可能性が高く、短編集発売の情報に期待していたらすでに読んでいた、ということがあり得るのです。優れた短編は何度読んでも面白いものですが、それでも、初めて読んだ瞬間の驚きはもう得られません。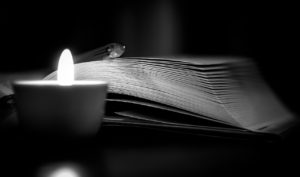 私はこれまでの人生で何度か転校を経験しています。幼稚園や小学校時代のことなので、勉強の遅れを感じることはほとんどありませんでしたが、新しい環境で一から立ち位置を築くのはなかなか大変でした。どこも比較的落ち着いた環境で、ひどいイジメに遭うことがなかったのはラッキーだったと思います。
私はこれまでの人生で何度か転校を経験しています。幼稚園や小学校時代のことなので、勉強の遅れを感じることはほとんどありませんでしたが、新しい環境で一から立ち位置を築くのはなかなか大変でした。どこも比較的落ち着いた環境で、ひどいイジメに遭うことがなかったのはラッキーだったと思います。 私は自他共に認めるホラー作品大好き人間ですが、そんな私をしても、ホラーというジャンルは人を選ぶと思います。<horror(恐怖)>という言葉が示す通り、恐怖現象を見聞きして楽しむことが目的なわけですが、「怖い思いをして楽しむなんてできっこないじゃん」という人は大勢いるでしょう。ジャンルの性質上、時に血飛沫が飛び内臓がまき散らされる・・・なんていう状況になり得ることも、人を選ぶ原因の一つかもしれません。
私は自他共に認めるホラー作品大好き人間ですが、そんな私をしても、ホラーというジャンルは人を選ぶと思います。<horror(恐怖)>という言葉が示す通り、恐怖現象を見聞きして楽しむことが目的なわけですが、「怖い思いをして楽しむなんてできっこないじゃん」という人は大勢いるでしょう。ジャンルの性質上、時に血飛沫が飛び内臓がまき散らされる・・・なんていう状況になり得ることも、人を選ぶ原因の一つかもしれません。 自分で言うのもなんですが、私はけっこう信心深い人間です。祖父母の家によく出入りしていたせいもあるのか、里帰りするとまず神棚と仏壇に手を合わせますし、厄年や大きな旅行に出かける時は必ずお祓いをしてもらいます。神仏に手を合わせる。簡単な動作ですが、なんだか落ち着いた気持ちになってきます。
自分で言うのもなんですが、私はけっこう信心深い人間です。祖父母の家によく出入りしていたせいもあるのか、里帰りするとまず神棚と仏壇に手を合わせますし、厄年や大きな旅行に出かける時は必ずお祓いをしてもらいます。神仏に手を合わせる。簡単な動作ですが、なんだか落ち着いた気持ちになってきます。