 コロナが流行り、自粛生活を強いられるようになってから、巷では猫ブームが起こったそうです。犬と違って散歩不要、過度に構ってやる必要もなく、マーキングの習性がないからトイレも楽、家にこもりきりの生活に癒しが生まれる・・・確かに一見、いいことだらけのように思えます。
コロナが流行り、自粛生活を強いられるようになってから、巷では猫ブームが起こったそうです。犬と違って散歩不要、過度に構ってやる必要もなく、マーキングの習性がないからトイレも楽、家にこもりきりの生活に癒しが生まれる・・・確かに一見、いいことだらけのように思えます。
しかし、生き物を飼うということは、そんなに気楽なものではありません。何しろ相手はぬいぐるみではなく、平均で十年以上生きる生き物です。思い通りにいかないこと、困らせられることなど山ほどあるでしょうし、身も蓋もない話、安くないお金もかかります。「それでも猫でしょ。飼うなんて楽ちん楽ちん」などと思う方、この作品を読めば猫を甘く見る気持ちなど吹っ飛ぶかもしれませんよ。「このミステリーがすごい!」編集部による『5分で読める!ひと駅ストーリー 猫の物語』です。
こんな人におすすめ
猫をテーマにしたアンソロジーが読みたい人

 「このトリックは映像化不可能!」。ミステリー小説等でしばしば目にするキャッチコピーです。叙述トリックをはじめ、小説の<文字を読む>という特性を活かしたトリックに対して用いられることが多いですね。ラストで世界が反転するようなどんでん返しが待っていることが多く、私も大好きなトリックです。
「このトリックは映像化不可能!」。ミステリー小説等でしばしば目にするキャッチコピーです。叙述トリックをはじめ、小説の<文字を読む>という特性を活かしたトリックに対して用いられることが多いですね。ラストで世界が反転するようなどんでん返しが待っていることが多く、私も大好きなトリックです。 今まで知らなかった作家さんの存在を認知し、その面白さを知る。本好きにとっては無上の喜びの一つです。この<はいくる>のような読書ブログやレビューサイトの存在意義は、そうした喜びのために在るといっても過言ではありません。
今まで知らなかった作家さんの存在を認知し、その面白さを知る。本好きにとっては無上の喜びの一つです。この<はいくる>のような読書ブログやレビューサイトの存在意義は、そうした喜びのために在るといっても過言ではありません。 私は本が好きですが、映画も負けず劣らず好きです。昔、家の近所に映画館やレンタルビデオショップがあったこともあり、一時は週に何度も映画鑑賞に出かけたり、興味のある映画のDVDを片っ端から借りたりしていました。おかげでバイト代が全然貯まりませんでしたが、今振り返っても、あれはあれで楽しかったです。
私は本が好きですが、映画も負けず劣らず好きです。昔、家の近所に映画館やレンタルビデオショップがあったこともあり、一時は週に何度も映画鑑賞に出かけたり、興味のある映画のDVDを片っ端から借りたりしていました。おかげでバイト代が全然貯まりませんでしたが、今振り返っても、あれはあれで楽しかったです。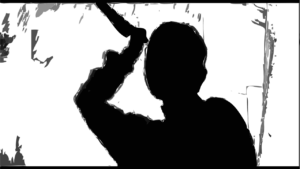 「悪法もまた法なり」。かつて、学者ソクラテスが言ったとされている言葉です(本当に言ったかどうかは諸説あり)。実際にはかなり哲学的な意味があるようですが、今はストレートに「たとえ間違った法律でも、法治国家である以上は従わないといけませんよ」という意味で使われることが多いようですね。確かに、各自が勝手に「あの法律は変だから守らない!」「こんな間違った法律に従う必要はない!」などと言い出したら、社会は成り立ちません。法律が間違っているなら、定められた法改正の手続きを取れというのは、決しておかしな話ではないでしょう。
「悪法もまた法なり」。かつて、学者ソクラテスが言ったとされている言葉です(本当に言ったかどうかは諸説あり)。実際にはかなり哲学的な意味があるようですが、今はストレートに「たとえ間違った法律でも、法治国家である以上は従わないといけませんよ」という意味で使われることが多いようですね。確かに、各自が勝手に「あの法律は変だから守らない!」「こんな間違った法律に従う必要はない!」などと言い出したら、社会は成り立ちません。法律が間違っているなら、定められた法改正の手続きを取れというのは、決しておかしな話ではないでしょう。 創作の世界には<パスティーシュ>という用語があります。これは一言で言うと、作風の模倣のことです。似たような用語に<オマージュ>があり、実際、日本では厳密な区別はない様子。ただ、色々なパスティーシュ作品、オマージュ作品を見る限り、前者は先行する作品の要素がはっきり表れているのに対し、後者は作家が先行作品を自分なりに読み取った上で作品化するので、「え、〇〇(作品名)のオマージュなの?」とびっくりさせられることが多い気がします。
創作の世界には<パスティーシュ>という用語があります。これは一言で言うと、作風の模倣のことです。似たような用語に<オマージュ>があり、実際、日本では厳密な区別はない様子。ただ、色々なパスティーシュ作品、オマージュ作品を見る限り、前者は先行する作品の要素がはっきり表れているのに対し、後者は作家が先行作品を自分なりに読み取った上で作品化するので、「え、〇〇(作品名)のオマージュなの?」とびっくりさせられることが多い気がします。 小説の人気キャラクターをイラストで描くのは、なかなか難しい仕事です。実写化でも言えることですが、キャラクター人気が高ければ高いほど、どれだけ上手くイラスト化しても「なんか思っていたのと違う」「〇〇(キャラクター名)はこんな顔じゃない」という不満が出ることは不可避。特に挿絵がない小説の場合、読者がキャラのイメージを膨らませる余地が大きいため、いざイラスト化されるとネガティブな感想を抱かれやすい気がします。
小説の人気キャラクターをイラストで描くのは、なかなか難しい仕事です。実写化でも言えることですが、キャラクター人気が高ければ高いほど、どれだけ上手くイラスト化しても「なんか思っていたのと違う」「〇〇(キャラクター名)はこんな顔じゃない」という不満が出ることは不可避。特に挿絵がない小説の場合、読者がキャラのイメージを膨らませる余地が大きいため、いざイラスト化されるとネガティブな感想を抱かれやすい気がします。 一昔前、この世における性的指向は異性愛、すなわち男女間で性的な愛情を抱き合うのが一般的とされていました。同性愛という概念自体は昔から存在したようですが、多少例外はあれど、それは基本的に不健全で非常識。差別の対象となったり、病気の一種と捉えられたり、最悪、魔女狩りのターゲットとされることすらあったと聞いています。
一昔前、この世における性的指向は異性愛、すなわち男女間で性的な愛情を抱き合うのが一般的とされていました。同性愛という概念自体は昔から存在したようですが、多少例外はあれど、それは基本的に不健全で非常識。差別の対象となったり、病気の一種と捉えられたり、最悪、魔女狩りのターゲットとされることすらあったと聞いています。 コロナが流行る前、<シェア>という言葉を頻繁に見聞きする時期がありました。大皿料理やスイーツを頼んで同席者同士でシェア、ステーションに停めてある車をみんなで利用するカーシェアリング、各自の能力を必要に応じて共有・マッチングさせるスキルシェア・・・中でも、一つの家に複数人で住むシェアハウスは、人気リアリティショーの設定となったこともあり、爆発的に知名度を伸ばしました。気の合う仲間同士と楽しく、しかし家族ほどべったり干渉することなく暮らせたら、さぞ快適なことでしょう。
コロナが流行る前、<シェア>という言葉を頻繁に見聞きする時期がありました。大皿料理やスイーツを頼んで同席者同士でシェア、ステーションに停めてある車をみんなで利用するカーシェアリング、各自の能力を必要に応じて共有・マッチングさせるスキルシェア・・・中でも、一つの家に複数人で住むシェアハウスは、人気リアリティショーの設定となったこともあり、爆発的に知名度を伸ばしました。気の合う仲間同士と楽しく、しかし家族ほどべったり干渉することなく暮らせたら、さぞ快適なことでしょう。 私は根が小心者ということもあり、体に異変を感じたらさっさと病院に行きます。「実は深刻な病気だったらどうしよう」「様子見している内に手遅れになったら・・・」等々、つい悪い想像を巡らせてしまうんです。そのため、昔から病院はけっこう馴染みのある場所でした。
私は根が小心者ということもあり、体に異変を感じたらさっさと病院に行きます。「実は深刻な病気だったらどうしよう」「様子見している内に手遅れになったら・・・」等々、つい悪い想像を巡らせてしまうんです。そのため、昔から病院はけっこう馴染みのある場所でした。