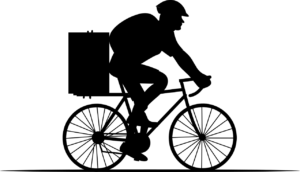 コロナ禍によって、これまであまり重要視されていなかったシステムや習慣に注目が集まるようになりました。例えば混雑した空間でのマスクの着用、手洗いうがいの徹底、オンラインでの会議や授業etcetc。コロナが第五類に移行した今もなお、すっかり社会に定着した感があります。
コロナ禍によって、これまであまり重要視されていなかったシステムや習慣に注目が集まるようになりました。例えば混雑した空間でのマスクの着用、手洗いうがいの徹底、オンラインでの会議や授業etcetc。コロナが第五類に移行した今もなお、すっかり社会に定着した感があります。
そんな<コロナによる需要増システム>の中の筆頭格は、ウーバーイーツではないでしょうか。もともとはアメリカ発祥のサービスで、一人分でも気楽にデリバリーを頼めたり、出前をやっていない個人店の料理を注文したりできるというメリットがあります。コロナで外出自粛やリモートワークが呼びかけられた結果、一気に日本での認知度が上がり、利用する店も人間も増えました。となると、創作の世界でもテーマにされるのがお約束というもの。今回取り上げるのは、ウーバーイーツが重要な役割を果たすミステリー、結城真一郎さんの『難問の多い料理店』です。
こんな人におすすめ
安楽椅子探偵が登場するミステリー短編集が読みたい人

 <死蝋>という現象をご存知でしょうか。これは遺体が腐敗菌の繁殖を免れ、かつ、長期間に渡って外気との接触を遮断された結果、蠟状ないしチーズ状に変化したもののことを指します。時として意図せず遺体が死蝋化することもあり、最古のものとしては、紀元前四世紀に生きていた男性の遺体が死蝋となって発見されています。
<死蝋>という現象をご存知でしょうか。これは遺体が腐敗菌の繁殖を免れ、かつ、長期間に渡って外気との接触を遮断された結果、蠟状ないしチーズ状に変化したもののことを指します。時として意図せず遺体が死蝋化することもあり、最古のものとしては、紀元前四世紀に生きていた男性の遺体が死蝋となって発見されています。 かつて、漫画家の藤子・F・不二雄さんは、SFのことを<S(すこし)F(不思議)>と解釈しました。その言葉通り、この方の作品は『ドラえもん』に代表されるように、日常の中に不思議要素が混ざっていることが多いです。『スターウォーズ』のような壮大なSF叙事詩もいいけれど、身近なところから非日常を感じさせてくれる作品もまた面白いですよね。
かつて、漫画家の藤子・F・不二雄さんは、SFのことを<S(すこし)F(不思議)>と解釈しました。その言葉通り、この方の作品は『ドラえもん』に代表されるように、日常の中に不思議要素が混ざっていることが多いです。『スターウォーズ』のような壮大なSF叙事詩もいいけれど、身近なところから非日常を感じさせてくれる作品もまた面白いですよね。 「お気に入りの作品に出てくる土地を見てみたい」「あの作者が愛した店に行ってみたい」。そう願うファンは少なくないと思います。かくいう私もその一人。映画『ロード・オブ・ザ・リングシリーズ』の大ファンでもあるため、お金を貯めて、いつかニュージーランドの撮影地すべてを回るのが生涯の夢です。
「お気に入りの作品に出てくる土地を見てみたい」「あの作者が愛した店に行ってみたい」。そう願うファンは少なくないと思います。かくいう私もその一人。映画『ロード・オブ・ザ・リングシリーズ』の大ファンでもあるため、お金を貯めて、いつかニュージーランドの撮影地すべてを回るのが生涯の夢です。 私が人生で初めて行った外国はハワイです。特大サイズの料理に、日本のそれとは色合いが違う海や浜辺、華やかな民族衣装を着た現地の人々・・・ドラマや漫画で見るような光景にワクワクしっぱなしだったことを覚えています。
私が人生で初めて行った外国はハワイです。特大サイズの料理に、日本のそれとは色合いが違う海や浜辺、華やかな民族衣装を着た現地の人々・・・ドラマや漫画で見るような光景にワクワクしっぱなしだったことを覚えています。 巷でよく言われる話ですが、日本人は宗教に対するハードルが低い民族です。何しろ国内に存在する神様の数は八百万。仏教やキリスト教の宗教施設がご近所同士ということも珍しくなく、カレンダーを見れば世界各国の宗教行事が目白押し。「宗教?まあ、各自で好きなように信じればいいじゃん」という風土があります。身びいきかもしれませんが、こういう精神性って大好きです。
巷でよく言われる話ですが、日本人は宗教に対するハードルが低い民族です。何しろ国内に存在する神様の数は八百万。仏教やキリスト教の宗教施設がご近所同士ということも珍しくなく、カレンダーを見れば世界各国の宗教行事が目白押し。「宗教?まあ、各自で好きなように信じればいいじゃん」という風土があります。身びいきかもしれませんが、こういう精神性って大好きです。 因習ミステリー、因習サスペンス、因習ホラー・・・悪しき習慣をテーマにした作品は、こうした呼ばれ方をすることが多いです。都会ではダメというわけではないのでしょうが、設定の都合上、閉鎖的な田舎が舞台となる傾向にあるようですね。行動の不自由さ、人間関係の濃密さ、外部からの情報伝達の遅さなどが、作品の陰湿な雰囲気を盛り上げてくれます。
因習ミステリー、因習サスペンス、因習ホラー・・・悪しき習慣をテーマにした作品は、こうした呼ばれ方をすることが多いです。都会ではダメというわけではないのでしょうが、設定の都合上、閉鎖的な田舎が舞台となる傾向にあるようですね。行動の不自由さ、人間関係の濃密さ、外部からの情報伝達の遅さなどが、作品の陰湿な雰囲気を盛り上げてくれます。 血が繋がった肉親同士が争うことを<骨肉の争い>と呼びます。<骨肉>とは<骨と肉のような間柄>を指すとのことで、推察するに<極めて身近な、生死を共有することもあり得る関係>という意味でしょう。文字からして血生臭さが漂ってくるようで、先人の表現って秀逸だなと感心させられます。
血が繋がった肉親同士が争うことを<骨肉の争い>と呼びます。<骨肉>とは<骨と肉のような間柄>を指すとのことで、推察するに<極めて身近な、生死を共有することもあり得る関係>という意味でしょう。文字からして血生臭さが漂ってくるようで、先人の表現って秀逸だなと感心させられます。 シリーズ物の作品には、しばしば<大きな変化がなく、決まった流れを繰り返す>というパターンが存在します。よく<サザエさん時空>と呼ばれる、日常系の作品に多いパターンですね。現実には往々にして悲劇的な変化が多い分、物語には不変・不動が求められるのかもしれません。
シリーズ物の作品には、しばしば<大きな変化がなく、決まった流れを繰り返す>というパターンが存在します。よく<サザエさん時空>と呼ばれる、日常系の作品に多いパターンですね。現実には往々にして悲劇的な変化が多い分、物語には不変・不動が求められるのかもしれません。 私は読む本を選ぶ時、必ずあらすじをチェックします。「好きな作家さんの作品は事前情報ゼロで楽しみたい!」という方も多いのでしょうが、私は大まかなところを把握してから読み始めたいタイプ。ばっちり好みに合いそうな話だった時は、読書前のワクワク感もより高まります。
私は読む本を選ぶ時、必ずあらすじをチェックします。「好きな作家さんの作品は事前情報ゼロで楽しみたい!」という方も多いのでしょうが、私は大まかなところを把握してから読み始めたいタイプ。ばっちり好みに合いそうな話だった時は、読書前のワクワク感もより高まります。