 子どもの頃から推理小説好きだった私には、憧れのシチュエーションがあります。それは<警察の信頼を得て捜査協力を求められる少年少女>というもの。現実にはおよそあり得ないんでしょうが、「もし自分がこんな風に事件に関わることができたなら・・・」とワクワクドキドキしたものです。
子どもの頃から推理小説好きだった私には、憧れのシチュエーションがあります。それは<警察の信頼を得て捜査協力を求められる少年少女>というもの。現実にはおよそあり得ないんでしょうが、「もし自分がこんな風に事件に関わることができたなら・・・」とワクワクドキドキしたものです。
この手の設定で一番有名なのは赤川次郎さんの作品でしょう。『三姉妹探偵団シリーズ』『悪魔シリーズ』『杉原爽香シリーズ』などには、刑事顔負けの推理力・行動力を発揮するティーンエイジャーがたくさん登場します。人気を集めやすい状況だからか、長期シリーズ化することも多いようですね。だったら、この作品も今後シリーズ化されるのかな。中山七里さんの『TAS 特別師弟捜査員』です。
こんな人におすすめ
高校生探偵が登場する学園ミステリーが読みたい人
続きを読む
 私は友人知人から<スイーツ女王>と言われるほどの甘党です。中でも目がないのは、チョコレートパフェやガトーショコラといったチョコレート系のスイーツ。昔、デザートビュッフェでチョコレート系のスイーツばかり三十個近く食べ、カフェインを摂りすぎたせいか全く眠れなくなったこともありました(笑)
私は友人知人から<スイーツ女王>と言われるほどの甘党です。中でも目がないのは、チョコレートパフェやガトーショコラといったチョコレート系のスイーツ。昔、デザートビュッフェでチョコレート系のスイーツばかり三十個近く食べ、カフェインを摂りすぎたせいか全く眠れなくなったこともありました(笑)
美味しそうなスイーツが登場する小説はたくさんあるものの、チョコレートがメインとなると、意外と少ないです。有名どころだと、ロアルド・ダールの『チョコレート工場の秘密』と、大石真さんの『チョコレート戦争』くらいでしょうか。この二作品ほどの知名度はないかもしれませんが、今回ご紹介する小説にも、それはそれは美味しそうなチョコレート・スイーツが出てきますよ。上田早夕里さんの『ショコラティエの勲章』です。
こんな人におすすめ
スイーツが登場するコージー・ミステリーが読みたい人
続きを読む
 幸せないっぱいの人生を送りたい。これは、私を含む大多数の人間の望みでしょう。自分で言うのも何ですが私は甘ったれな人間なので、「贅沢言わないから、健康で、普通に遊んだり美味しい物を食べたりできる程度の財産があって、人間関係にも恵まれた一生を送りたいな」などと、ぼんやり夢見ることがよくあります。
幸せないっぱいの人生を送りたい。これは、私を含む大多数の人間の望みでしょう。自分で言うのも何ですが私は甘ったれな人間なので、「贅沢言わないから、健康で、普通に遊んだり美味しい物を食べたりできる程度の財産があって、人間関係にも恵まれた一生を送りたいな」などと、ぼんやり夢見ることがよくあります。
現実では幸せを願うのが一般的なんでしょうが、小説や映画の世界ならば、登場人物が悲惨な目に遭うことで逆に物語の面白さが増すこともあります。ヴィクトル・ユーゴーの『ああ無情』はその典型的な例ですよね。他にも、山田宗樹さんの『嫌われ松子の一生』、百田尚樹さんの『モンスター』、田中慎弥さんの『共喰い』などの登場人物たちは、幸福とは程遠い人生を歩んでいますが、その重苦しさが読者を強く魅了します。今回取り上げるのは、湊かなえさんの直木三十五賞候補作『未来』。この作品で描かれる不幸の数々もかなりのものでした。
こんな人におすすめ
陰鬱な雰囲気のミステリーが読みたい人
続きを読む
 映画『羊たちの沈黙』を初めて見た時の衝撃は、今でもよく覚えています。ヒロイン役のジョディ・フォスターの演技やスリリングなストーリー展開、手に汗握るクライマックスなど見所はたくさんありますが、何と言っても一番インパクトがあるのはアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の存在感でしょう。残虐な猟奇殺人を犯しておきながら人並み外れた知能を持ち、収監されているにも関わらず警察から捜査協力を求められるほどの天才犯罪者。その紳士的でありながら凶悪なキャラクターは、現在に至るまで多くの観客を魅了し続けています。
映画『羊たちの沈黙』を初めて見た時の衝撃は、今でもよく覚えています。ヒロイン役のジョディ・フォスターの演技やスリリングなストーリー展開、手に汗握るクライマックスなど見所はたくさんありますが、何と言っても一番インパクトがあるのはアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の存在感でしょう。残虐な猟奇殺人を犯しておきながら人並み外れた知能を持ち、収監されているにも関わらず警察から捜査協力を求められるほどの天才犯罪者。その紳士的でありながら凶悪なキャラクターは、現在に至るまで多くの観客を魅了し続けています。
現実でこんなことがあるのかどうかは分かりませんが、「犯罪者が獄中から捜査協力する」というシチュエーションはなかなか面白いです。視覚的に映えるからか映画やドラマではよくあるんですが、小説ではあまりないな・・・と思っていたら、最近読んだ小説がまさにそういう設定でした。真梨幸子さんの『ツキマトウ 警視庁ストーカー対策室ゼロ係』です。
こんな人におすすめ
ストーカー犯罪を扱ったイヤミスが読みたい人
続きを読む
 別の記事でも書きましたが、フィクションの世界において、被告人のために戦う弁護士はやや特殊なポジションであり、強烈な個性付けがなされることが多いです。一方、これと対照的なのは、弁護士と法廷で争う検事。良くも悪くも生真面目な法の番人として描かれがちな気がします。
別の記事でも書きましたが、フィクションの世界において、被告人のために戦う弁護士はやや特殊なポジションであり、強烈な個性付けがなされることが多いです。一方、これと対照的なのは、弁護士と法廷で争う検事。良くも悪くも生真面目な法の番人として描かれがちな気がします。
とはいえ、小説の中の検事全員が杓子定規な堅物ばかりというわけではありません。高木彬光さんの『検事霧島三郎シリーズ』や和久峻三さんの『赤かぶ検事シリーズ』には個性豊かな検事が登場しますし、柚月裕子さんの『佐方貞人シリーズ』でも主人公・佐方の検事時代を描いた作品があります。私が最近読んだ検事小説は中山七里さんの『能面検事』。この検事もなかなかインパクトありました。
こんな人におすすめ
検事が主人公の小説が読みたい人
続きを読む
 「人間が動物に変身する(逆もあり)」というのは、SFやホラーでお馴染みの設定です。お馴染みすぎて初めて見た変身ものが何だったか思い出せないくらいですが、記憶に残っているのは映画『ウルフ』。段々と狼に変わっていくジャック・ニコルソンの変貌ぶりが印象的でした。
「人間が動物に変身する(逆もあり)」というのは、SFやホラーでお馴染みの設定です。お馴染みすぎて初めて見た変身ものが何だったか思い出せないくらいですが、記憶に残っているのは映画『ウルフ』。段々と狼に変わっていくジャック・ニコルソンの変貌ぶりが印象的でした。
人間が違う生き物に変身するというシチュエーションは、古今東西、たくさんの創作物で扱われてきました。青年が獣に変身する『美女と野獣』はその代表例ですし、フランツ・カフカの『変身』で主人公は巨大な毒虫に変身します。中島敦さんの『山月記』には、挫折の末に人喰い虎に変身する男が出てきますね。これらの作品の中で、登場人物達は人間の体を捨て、動物に姿を変える羽目になってしまいます。ですが、この作品の主人公の変身はちょっと違いますよ。西澤保彦さんの『いつか、ふたりは二匹』です。
こんな人におすすめ
人の残酷さをテーマにしたミステリーが読みたい人
続きを読む
 SF作品の中では、しばしば「パラレルワールド」という言葉が登場します。この世界と並行して存在する別の世界のことで、A世界で死んだ人間がB世界では生存していたり、C世界では敵同士だった人間がD世界では恋人同士だったりと、無限のパターンがあります。現実離れした考えと思われがちですが、実は物理学の世界でも存在が議論されるテーマだそうですね。
SF作品の中では、しばしば「パラレルワールド」という言葉が登場します。この世界と並行して存在する別の世界のことで、A世界で死んだ人間がB世界では生存していたり、C世界では敵同士だった人間がD世界では恋人同士だったりと、無限のパターンがあります。現実離れした考えと思われがちですが、実は物理学の世界でも存在が議論されるテーマだそうですね。
「もしあの時、違う選択肢を選んでいたら」・・・そんなifの世界を描くことができる特性上、パラレルワールドを扱った作品はSF分野に偏りがちです。ちなみに私が見た最初のパラレルワールド作品は、アニメ映画『ドラえもん のび太の魔界大冒険』。子ども向けアニメとは思えないくらい練られた世界観と緻密な伏線の張り方が印象的な名作でした。SF方面のパラレルワールド作品は山のようにあるので、今回はちょっと毛色の違う「もう一つの世界」を描いた小説をご紹介します。真梨幸子さんの『向こう側の、ヨーコ』です。
こんな人におすすめ
中年女性の愛憎ミステリーに興味がある人
続きを読む
 古今東西、「鏡」は神秘的なアイテムとして扱われてきました。人や物をそっくりそのまま(正確には逆転した姿ですが)映し出したり、使い方次第で無限に続く空間ができたように見えたりするせいでしょうね。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏から銅鏡を贈られていますし、鏡を奉っている神社も存在します。
古今東西、「鏡」は神秘的なアイテムとして扱われてきました。人や物をそっくりそのまま(正確には逆転した姿ですが)映し出したり、使い方次第で無限に続く空間ができたように見えたりするせいでしょうね。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏から銅鏡を贈られていますし、鏡を奉っている神社も存在します。
ミステリアスな特性のせいか、鏡がキーワードとなる小説は、どこか謎めいたものが多いです。古くは『白雪姫』『鏡の国のアリス』がありますし、梨木香歩さんの『裏庭』、田中芳樹さんの『窓辺には夜の歌』、坂東眞砂子さんの『蛇鏡』などにも不思議な鏡が登場しました。そして、今回ご紹介する秋吉理香子さんの『鏡じかけの夢』。この鏡の不思議さもなかなかのものですよ。
こんな人におすすめ
愛憎絡み合うホラー短編集が読みたい人
続きを読む
 私が最初に読んだ海外の小説は、ヴィクトル・ユーゴ―の『ああ無情』でした。小学生向けのバージョンだったので、表現はかなりマイルドになっていましたが、作品の持つ切なさや痛々しさ、美しさはよく伝わってきました。そのインパクトがあまりに大きかったせいか、私の中でフランスというと、美しさと儚さ、残酷さと哀しさが並び立つ国です。
私が最初に読んだ海外の小説は、ヴィクトル・ユーゴ―の『ああ無情』でした。小学生向けのバージョンだったので、表現はかなりマイルドになっていましたが、作品の持つ切なさや痛々しさ、美しさはよく伝わってきました。そのインパクトがあまりに大きかったせいか、私の中でフランスというと、美しさと儚さ、残酷さと哀しさが並び立つ国です。
きらびやかなようでいて混沌としており、閉鎖的でいながら多くの人を魅了する国、フランス。そういう印象があるからでしょうか。フランスにはミステリーやサスペンスの雰囲気がよく似合う気がします。先日読んだ小説は、まさに私の持つフランスのイメージにぴったりでした。今回は、深木章子さんの『螺旋の底』を紹介します。
こんな人におすすめ
外国を舞台にした本格ミステリーが読みたい人
続きを読む
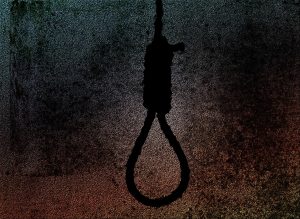 「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
冤罪をテーマにした小説といえば、高野和明さんの『13階段』や大門剛明さんの『テミスの求刑』、ややテイストは違いますが伊坂幸太郎さんの『ゴールデンスランバー』などが有名です。これらの作品の中で犯罪者として告発された人物は、自分は潔白だと訴えていました。では、自らが犯罪者であることは認めた上で、告発された罪の一部が冤罪だと訴えた場合はどうでしょうか?ただでさえ難しい冤罪問題が、より複雑になることは想像に難くありません。今日紹介するのは、櫛木理宇さんの『チェインドッグ』。タイトルの意味も含めて、考えさせられるところの多い作品でした。
こんな人におすすめ
サイコパスが出てくるミステリー小説が読みたい人
続きを読む
 子どもの頃から推理小説好きだった私には、憧れのシチュエーションがあります。それは<警察の信頼を得て捜査協力を求められる少年少女>というもの。現実にはおよそあり得ないんでしょうが、「もし自分がこんな風に事件に関わることができたなら・・・」とワクワクドキドキしたものです。
子どもの頃から推理小説好きだった私には、憧れのシチュエーションがあります。それは<警察の信頼を得て捜査協力を求められる少年少女>というもの。現実にはおよそあり得ないんでしょうが、「もし自分がこんな風に事件に関わることができたなら・・・」とワクワクドキドキしたものです。
 私は友人知人から<スイーツ女王>と言われるほどの甘党です。中でも目がないのは、チョコレートパフェやガトーショコラといったチョコレート系のスイーツ。昔、デザートビュッフェでチョコレート系のスイーツばかり三十個近く食べ、カフェインを摂りすぎたせいか全く眠れなくなったこともありました(笑)
私は友人知人から<スイーツ女王>と言われるほどの甘党です。中でも目がないのは、チョコレートパフェやガトーショコラといったチョコレート系のスイーツ。昔、デザートビュッフェでチョコレート系のスイーツばかり三十個近く食べ、カフェインを摂りすぎたせいか全く眠れなくなったこともありました(笑) 幸せないっぱいの人生を送りたい。これは、私を含む大多数の人間の望みでしょう。自分で言うのも何ですが私は甘ったれな人間なので、「贅沢言わないから、健康で、普通に遊んだり美味しい物を食べたりできる程度の財産があって、人間関係にも恵まれた一生を送りたいな」などと、ぼんやり夢見ることがよくあります。
幸せないっぱいの人生を送りたい。これは、私を含む大多数の人間の望みでしょう。自分で言うのも何ですが私は甘ったれな人間なので、「贅沢言わないから、健康で、普通に遊んだり美味しい物を食べたりできる程度の財産があって、人間関係にも恵まれた一生を送りたいな」などと、ぼんやり夢見ることがよくあります。 映画『羊たちの沈黙』を初めて見た時の衝撃は、今でもよく覚えています。ヒロイン役のジョディ・フォスターの演技やスリリングなストーリー展開、手に汗握るクライマックスなど見所はたくさんありますが、何と言っても一番インパクトがあるのはアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の存在感でしょう。残虐な猟奇殺人を犯しておきながら人並み外れた知能を持ち、収監されているにも関わらず警察から捜査協力を求められるほどの天才犯罪者。その紳士的でありながら凶悪なキャラクターは、現在に至るまで多くの観客を魅了し続けています。
映画『羊たちの沈黙』を初めて見た時の衝撃は、今でもよく覚えています。ヒロイン役のジョディ・フォスターの演技やスリリングなストーリー展開、手に汗握るクライマックスなど見所はたくさんありますが、何と言っても一番インパクトがあるのはアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の存在感でしょう。残虐な猟奇殺人を犯しておきながら人並み外れた知能を持ち、収監されているにも関わらず警察から捜査協力を求められるほどの天才犯罪者。その紳士的でありながら凶悪なキャラクターは、現在に至るまで多くの観客を魅了し続けています。 別の記事でも書きましたが、フィクションの世界において、被告人のために戦う弁護士はやや特殊なポジションであり、強烈な個性付けがなされることが多いです。一方、これと対照的なのは、弁護士と法廷で争う検事。良くも悪くも生真面目な法の番人として描かれがちな気がします。
別の記事でも書きましたが、フィクションの世界において、被告人のために戦う弁護士はやや特殊なポジションであり、強烈な個性付けがなされることが多いです。一方、これと対照的なのは、弁護士と法廷で争う検事。良くも悪くも生真面目な法の番人として描かれがちな気がします。 「人間が動物に変身する(逆もあり)」というのは、SFやホラーでお馴染みの設定です。お馴染みすぎて初めて見た変身ものが何だったか思い出せないくらいですが、記憶に残っているのは映画『ウルフ』。段々と狼に変わっていくジャック・ニコルソンの変貌ぶりが印象的でした。
「人間が動物に変身する(逆もあり)」というのは、SFやホラーでお馴染みの設定です。お馴染みすぎて初めて見た変身ものが何だったか思い出せないくらいですが、記憶に残っているのは映画『ウルフ』。段々と狼に変わっていくジャック・ニコルソンの変貌ぶりが印象的でした。 SF作品の中では、しばしば「パラレルワールド」という言葉が登場します。この世界と並行して存在する別の世界のことで、A世界で死んだ人間がB世界では生存していたり、C世界では敵同士だった人間がD世界では恋人同士だったりと、無限のパターンがあります。現実離れした考えと思われがちですが、実は物理学の世界でも存在が議論されるテーマだそうですね。
SF作品の中では、しばしば「パラレルワールド」という言葉が登場します。この世界と並行して存在する別の世界のことで、A世界で死んだ人間がB世界では生存していたり、C世界では敵同士だった人間がD世界では恋人同士だったりと、無限のパターンがあります。現実離れした考えと思われがちですが、実は物理学の世界でも存在が議論されるテーマだそうですね。 古今東西、「鏡」は神秘的なアイテムとして扱われてきました。人や物をそっくりそのまま(正確には逆転した姿ですが)映し出したり、使い方次第で無限に続く空間ができたように見えたりするせいでしょうね。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏から銅鏡を贈られていますし、鏡を奉っている神社も存在します。
古今東西、「鏡」は神秘的なアイテムとして扱われてきました。人や物をそっくりそのまま(正確には逆転した姿ですが)映し出したり、使い方次第で無限に続く空間ができたように見えたりするせいでしょうね。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏から銅鏡を贈られていますし、鏡を奉っている神社も存在します。 私が最初に読んだ海外の小説は、ヴィクトル・ユーゴ―の『ああ無情』でした。小学生向けのバージョンだったので、表現はかなりマイルドになっていましたが、作品の持つ切なさや痛々しさ、美しさはよく伝わってきました。そのインパクトがあまりに大きかったせいか、私の中でフランスというと、美しさと儚さ、残酷さと哀しさが並び立つ国です。
私が最初に読んだ海外の小説は、ヴィクトル・ユーゴ―の『ああ無情』でした。小学生向けのバージョンだったので、表現はかなりマイルドになっていましたが、作品の持つ切なさや痛々しさ、美しさはよく伝わってきました。そのインパクトがあまりに大きかったせいか、私の中でフランスというと、美しさと儚さ、残酷さと哀しさが並び立つ国です。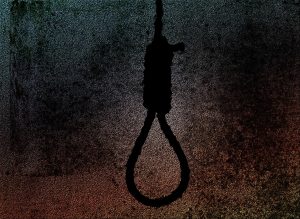 「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。