 私が大人になったらやりたいと思っていたことの一つ、それは「行きつけのカフェを見つけること」です。家の近所に居心地のいい店を見つけ、店員さんとも顔馴染みになり、お茶やスイーツを楽しみながらのんびりとした時間を過ごす・・・たぶん、ドラマか何かで見たシチュエーションだと思いますが、子どもの頃から本気で憧れていました。
私が大人になったらやりたいと思っていたことの一つ、それは「行きつけのカフェを見つけること」です。家の近所に居心地のいい店を見つけ、店員さんとも顔馴染みになり、お茶やスイーツを楽しみながらのんびりとした時間を過ごす・・・たぶん、ドラマか何かで見たシチュエーションだと思いますが、子どもの頃から本気で憧れていました。
そんな夢を持っていたからなのか、カフェを舞台にした小説も大好き。森沢明夫さんの『虹の岬の喫茶店』、池永陽さんの『珈琲屋の人々』、村山早紀さんの『カフェかもめ亭』など、どれも面白かったです。最近読んだカフェの出てくる小説といえば、近藤史恵さんの『ときどき旅に出るカフェ』。こんなカフェが近所にあったらなぁ。
続きを読む
 「盲目的」という言葉を辞書で引くと、「愛情や情熱・衝動などによって、理性的な判断ができないさま」とあります。文字通り、目が見えなくなるほど強い感情。そんな感情に突き動かされて誰か・何かを思うのは、果たして幸せなことなのでしょうか。
「盲目的」という言葉を辞書で引くと、「愛情や情熱・衝動などによって、理性的な判断ができないさま」とあります。文字通り、目が見えなくなるほど強い感情。そんな感情に突き動かされて誰か・何かを思うのは、果たして幸せなことなのでしょうか。
フィクションの世界には、盲目的な愛情や友情、嫉妬心に憎悪などがしばしば登場します。良いものであれ悪いものであれ、五感を狂わせるくらい強烈な感情というのは、創作物のテーマにしやすいんでしょうね。今日は、あまりに強く恋と友情にのめり込んだ女性達の物語を紹介します。瑞々しく希望のある作風で有名な辻村深月さん。そんな彼女にしては珍しいイヤミス作品『盲目的な恋と友情』です。
続きを読む
 「ごあいさつ」欄にも書いてある通り、私は九州出身で、人生の大半を九州で過ごしてきました。海もあれば山もあり、ラーメンと明太子以外にも美味しい食べ物が色々あり、よその土地への移動もしやすい。身びいきかもしれませんが、いいところがたくさんある土地ですよ。
「ごあいさつ」欄にも書いてある通り、私は九州出身で、人生の大半を九州で過ごしてきました。海もあれば山もあり、ラーメンと明太子以外にも美味しい食べ物が色々あり、よその土地への移動もしやすい。身びいきかもしれませんが、いいところがたくさんある土地ですよ。
自分の故郷だからということもあるでしょうが、九州を舞台にした作品を見かけると、ついつい手が伸びてしまいます。重厚な歴史もの、どろどろしたイヤミス、胸がきゅんとするようなラブストーリーなど様々な作品がありますが、ハートウォーミングな成長物語が読みたい時はこれ。加納朋子さんの『ぐるぐる猿と歌う鳥』がおすすめです。
続きを読む
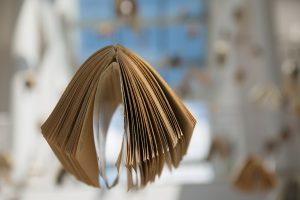 本屋や図書館でうろうろしていると、「アンソロジー」という本を見かけることがよくあります。「アンソロジー」とは、複数の作家による短編作品などを収めた出版物のこと。現代的な名前で呼ばれていますが、万葉集や古今和歌集、新約聖書などもアンソロジーに当たります。
本屋や図書館でうろうろしていると、「アンソロジー」という本を見かけることがよくあります。「アンソロジー」とは、複数の作家による短編作品などを収めた出版物のこと。現代的な名前で呼ばれていますが、万葉集や古今和歌集、新約聖書などもアンソロジーに当たります。
複数の作家の作品が収録されるという形式上、内容の質にばらつきが見られるアンソロジー。たとえ話のレベル自体は高くても、「この設定は苦手」などいうこともあり、大満足の作品を見つけることは難しいです。ですが、最近読んだアンソロジーはレベルが高かったですよ。当代の人気作家が一堂に会したアンソロジー『宮辻薬東宮』です。
続きを読む
 この世には、どれほど議論を尽くしても正解が出ないであろう問題があります。例えば死刑制度や少年犯罪への厳罰化。賛成派と反対派、どちらの言うことにも一理あり、是非を決めることは恐らくできないでしょう。
この世には、どれほど議論を尽くしても正解が出ないであろう問題があります。例えば死刑制度や少年犯罪への厳罰化。賛成派と反対派、どちらの言うことにも一理あり、是非を決めることは恐らくできないでしょう。
答えの出ない問題の筆頭格として、安楽死が挙げられます。自分自身、あるいは家族が不治の病にかかり、地獄の苦しみを味わっていたとしたら・・・安楽死を考えることは、果たして罪なのでしょうか。安楽死問題を扱った小説はたくさんありますが、今回は中山七里さんの『ドクター・デスの遺産』を取り上げたいと思います。
続きを読む
 大抵の図書館には「予約」というシステムがあります。本を確実に借りることができるよう予め予約しておく方法で、人気作家の新刊や大作映画の原作本などには予約が殺到します。予約件数が数百ということも決して珍しくなく、その場合、本が手元に届くのは何カ月も先ということにもなりかねません。
大抵の図書館には「予約」というシステムがあります。本を確実に借りることができるよう予め予約しておく方法で、人気作家の新刊や大作映画の原作本などには予約が殺到します。予約件数が数百ということも決して珍しくなく、その場合、本が手元に届くのは何カ月も先ということにもなりかねません。
小学生の頃から図書館通いを初めてウン十年。ほとんどの場合、予約で出遅れてしまっていた私ですが、先日初めて「予約一番目をゲット」という出来事を経験しました。大好きな作家さんの新刊なので、喜びもひとしおです。それがこれ。芦沢央さんの『バック・ステージ』です。
続きを読む
 写真撮影は好きですか。私自身は撮る方は決して上手ではありませんが、見るのは大好き。インターネットで美味しそうなスイーツの写真を見つけては、一人ニンマリしていることもしばしばです。
写真撮影は好きですか。私自身は撮る方は決して上手ではありませんが、見るのは大好き。インターネットで美味しそうなスイーツの写真を見つけては、一人ニンマリしていることもしばしばです。
今はスマートフォンなどの普及により、一昔前よりずっと手軽に写真が撮れるようになりました。それはもちろん楽しいことだけれど、時にはしっかりとカメラを構えて写真撮影するのも面白いかもしれません。今日取り上げるのは、柴田よしきさんの『風味さんのカメラ日和』。最近忘れていた、「レンズを通して物を見ることの楽しさ」を思い出せた気がします。
続きを読む
 ある日突然、病気で余命宣告されたら。そんな状況に直面した時、人はどういう行動を取るのでしょうか。愛する人とたくさん思い出を作る?やり残した大仕事を片付ける?百人に聞けば百通りの答えが返ってくると思います。
ある日突然、病気で余命宣告されたら。そんな状況に直面した時、人はどういう行動を取るのでしょうか。愛する人とたくさん思い出を作る?やり残した大仕事を片付ける?百人に聞けば百通りの答えが返ってくると思います。
悔いなく最期の瞬間を迎えるための活動「終活」は、今や社会現象となりつつあります。終活を通じて心の整理を行い、限りある人生を豊かに送る人もいるでしょう。反面、終活を行うことで、忘れたい過去を掘り返すことになったりして・・・そんな「黒い終活」を描いた作品がこれ。真梨幸子さんの『カウントダウン』です。
続きを読む
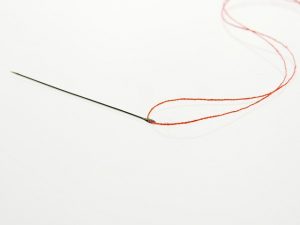 子どもの頃、人形遊びが好きでした。私の子ども時代に主流だったのはタカラトミーから発売された「ジェニーちゃん」。細かなキャラクター設定やお洒落な洋服の数々に夢中になったことを覚えています。
子どもの頃、人形遊びが好きでした。私の子ども時代に主流だったのはタカラトミーから発売された「ジェニーちゃん」。細かなキャラクター設定やお洒落な洋服の数々に夢中になったことを覚えています。
その名前の通り人の形をしているだけあって、人間と人形の間には強い繋がりがあります。そのせいか、ホラー界では時として恐ろしいキーアイテムになることもありますね。最近読んだホラー小説にも、不気味な人形が登場しました。澤村伊智さんの『ずうのめ人形』です。
続きを読む
 私が面白いと思う作品には、名コンビが登場することが多いです。ホームズの横にはワトソン、ポアロの横にはヘイスティングズ。異なる長所を持つ二人が助け合い、自分の持ち味を活かして物事に臨む様子は、読んでいてわくわくさせられます。
私が面白いと思う作品には、名コンビが登場することが多いです。ホームズの横にはワトソン、ポアロの横にはヘイスティングズ。異なる長所を持つ二人が助け合い、自分の持ち味を活かして物事に臨む様子は、読んでいてわくわくさせられます。
最近は、パートナーが動物や悪魔など人外の存在だったり、主人公と仲が悪かったりするなど、ユニークなコンビが登場する作品もありますね。では、この作品に出てくる二人はどうでしょうか。柚月裕子さんの『合理的にあり得ない 上水流涼子の解明』です。
続きを読む
 私が大人になったらやりたいと思っていたことの一つ、それは「行きつけのカフェを見つけること」です。家の近所に居心地のいい店を見つけ、店員さんとも顔馴染みになり、お茶やスイーツを楽しみながらのんびりとした時間を過ごす・・・たぶん、ドラマか何かで見たシチュエーションだと思いますが、子どもの頃から本気で憧れていました。
私が大人になったらやりたいと思っていたことの一つ、それは「行きつけのカフェを見つけること」です。家の近所に居心地のいい店を見つけ、店員さんとも顔馴染みになり、お茶やスイーツを楽しみながらのんびりとした時間を過ごす・・・たぶん、ドラマか何かで見たシチュエーションだと思いますが、子どもの頃から本気で憧れていました。
 「盲目的」という言葉を辞書で引くと、「愛情や情熱・衝動などによって、理性的な判断ができないさま」とあります。文字通り、目が見えなくなるほど強い感情。そんな感情に突き動かされて誰か・何かを思うのは、果たして幸せなことなのでしょうか。
「盲目的」という言葉を辞書で引くと、「愛情や情熱・衝動などによって、理性的な判断ができないさま」とあります。文字通り、目が見えなくなるほど強い感情。そんな感情に突き動かされて誰か・何かを思うのは、果たして幸せなことなのでしょうか。 「ごあいさつ」欄にも書いてある通り、私は九州出身で、人生の大半を九州で過ごしてきました。海もあれば山もあり、ラーメンと明太子以外にも美味しい食べ物が色々あり、よその土地への移動もしやすい。身びいきかもしれませんが、いいところがたくさんある土地ですよ。
「ごあいさつ」欄にも書いてある通り、私は九州出身で、人生の大半を九州で過ごしてきました。海もあれば山もあり、ラーメンと明太子以外にも美味しい食べ物が色々あり、よその土地への移動もしやすい。身びいきかもしれませんが、いいところがたくさんある土地ですよ。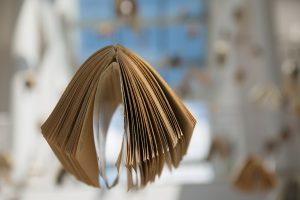 本屋や図書館でうろうろしていると、「アンソロジー」という本を見かけることがよくあります。「アンソロジー」とは、複数の作家による短編作品などを収めた出版物のこと。現代的な名前で呼ばれていますが、万葉集や古今和歌集、新約聖書などもアンソロジーに当たります。
本屋や図書館でうろうろしていると、「アンソロジー」という本を見かけることがよくあります。「アンソロジー」とは、複数の作家による短編作品などを収めた出版物のこと。現代的な名前で呼ばれていますが、万葉集や古今和歌集、新約聖書などもアンソロジーに当たります。 この世には、どれほど議論を尽くしても正解が出ないであろう問題があります。例えば死刑制度や少年犯罪への厳罰化。賛成派と反対派、どちらの言うことにも一理あり、是非を決めることは恐らくできないでしょう。
この世には、どれほど議論を尽くしても正解が出ないであろう問題があります。例えば死刑制度や少年犯罪への厳罰化。賛成派と反対派、どちらの言うことにも一理あり、是非を決めることは恐らくできないでしょう。 大抵の図書館には「予約」というシステムがあります。本を確実に借りることができるよう予め予約しておく方法で、人気作家の新刊や大作映画の原作本などには予約が殺到します。予約件数が数百ということも決して珍しくなく、その場合、本が手元に届くのは何カ月も先ということにもなりかねません。
大抵の図書館には「予約」というシステムがあります。本を確実に借りることができるよう予め予約しておく方法で、人気作家の新刊や大作映画の原作本などには予約が殺到します。予約件数が数百ということも決して珍しくなく、その場合、本が手元に届くのは何カ月も先ということにもなりかねません。 写真撮影は好きですか。私自身は撮る方は決して上手ではありませんが、見るのは大好き。インターネットで美味しそうなスイーツの写真を見つけては、一人ニンマリしていることもしばしばです。
写真撮影は好きですか。私自身は撮る方は決して上手ではありませんが、見るのは大好き。インターネットで美味しそうなスイーツの写真を見つけては、一人ニンマリしていることもしばしばです。 ある日突然、病気で余命宣告されたら。そんな状況に直面した時、人はどういう行動を取るのでしょうか。愛する人とたくさん思い出を作る?やり残した大仕事を片付ける?百人に聞けば百通りの答えが返ってくると思います。
ある日突然、病気で余命宣告されたら。そんな状況に直面した時、人はどういう行動を取るのでしょうか。愛する人とたくさん思い出を作る?やり残した大仕事を片付ける?百人に聞けば百通りの答えが返ってくると思います。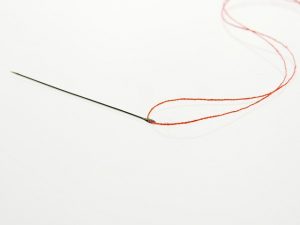 子どもの頃、人形遊びが好きでした。私の子ども時代に主流だったのはタカラトミーから発売された「ジェニーちゃん」。細かなキャラクター設定やお洒落な洋服の数々に夢中になったことを覚えています。
子どもの頃、人形遊びが好きでした。私の子ども時代に主流だったのはタカラトミーから発売された「ジェニーちゃん」。細かなキャラクター設定やお洒落な洋服の数々に夢中になったことを覚えています。 私が面白いと思う作品には、名コンビが登場することが多いです。ホームズの横にはワトソン、ポアロの横にはヘイスティングズ。異なる長所を持つ二人が助け合い、自分の持ち味を活かして物事に臨む様子は、読んでいてわくわくさせられます。
私が面白いと思う作品には、名コンビが登場することが多いです。ホームズの横にはワトソン、ポアロの横にはヘイスティングズ。異なる長所を持つ二人が助け合い、自分の持ち味を活かして物事に臨む様子は、読んでいてわくわくさせられます。