 短編集の中には、<連作短編集>という形態があります。話同士が何らかの繋がりを持った短編集のことで、登場人物や場所が共通しているパターンが多いですね。いくつかの話をまとめると一つの大きな物語が出来上がることもあり、長編・短編とはまた違った面白さがあります。
短編集の中には、<連作短編集>という形態があります。話同士が何らかの繋がりを持った短編集のことで、登場人物や場所が共通しているパターンが多いですね。いくつかの話をまとめると一つの大きな物語が出来上がることもあり、長編・短編とはまた違った面白さがあります。
これまで読んだことのある連作短編集では、有川浩さんの『阪急電車』、東野圭吾さんの『ナミヤ雑貨店の奇跡』、若竹七海さんの『ぼくのミステリな日常』などが面白かったです。今回ご紹介するのは、今邑彩さんの『つきまとわれて』。まさに連作短編集ならではの面白さを堪能できました。
こんな人におすすめ
・連作短編集が好きな人
・毒のあるミステリーが読みたい人

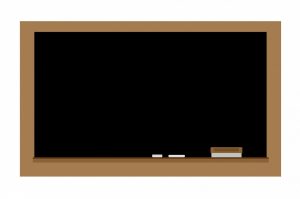 社会には様々な仕事、様々な勤務形態が存在しますが、その中に<非常勤>というものがあります。簡単に言えば、労働時間がフルタイム勤務者より短い労働者のことで、単純な補助作業を行う者もいれば、法律や税制のような専門知識を駆使して働くケースもあります。非常勤労働者を使う業界・会社は多いですが、中でも一番耳にするのは教育現場での<非常勤講師>ではないでしょうか。
社会には様々な仕事、様々な勤務形態が存在しますが、その中に<非常勤>というものがあります。簡単に言えば、労働時間がフルタイム勤務者より短い労働者のことで、単純な補助作業を行う者もいれば、法律や税制のような専門知識を駆使して働くケースもあります。非常勤労働者を使う業界・会社は多いですが、中でも一番耳にするのは教育現場での<非常勤講師>ではないでしょうか。 生まれ変わり、輪廻転生、リインカーネーション。生き物が死後に再び肉体を得てこの世に戻ってくるという考え方は、世界中に存在します。この思想を信じるか否かでは意見が分かれるのでしょうが、私自身はかなり信じている方。実際、偶然や勘違いでは片づけられない事例もたくさんあるようです。
生まれ変わり、輪廻転生、リインカーネーション。生き物が死後に再び肉体を得てこの世に戻ってくるという考え方は、世界中に存在します。この思想を信じるか否かでは意見が分かれるのでしょうが、私自身はかなり信じている方。実際、偶然や勘違いでは片づけられない事例もたくさんあるようです。 <予言>という単語を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、かの有名な<ノストラダムスの大予言>でしょう。<一九九九年七か月、空から恐怖の大王が来るだろう>という一文が<一九九九年に人類は滅びる>と解釈され、一時期、テレビや雑誌もその話題で持ちきりでした。かくいう私も、ハラハラドキドキしながら特集雑誌を買い求めた一人です。
<予言>という単語を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、かの有名な<ノストラダムスの大予言>でしょう。<一九九九年七か月、空から恐怖の大王が来るだろう>という一文が<一九九九年に人類は滅びる>と解釈され、一時期、テレビや雑誌もその話題で持ちきりでした。かくいう私も、ハラハラドキドキしながら特集雑誌を買い求めた一人です。 小説の中にはしばしば実在した歴史上の人物が登場します。その人物が主役の話ももちろん面白いですが、個人的には、創作キャラクター主役の話に脇役として実在の人物が登場する方が好きですね。歴史に名を残す人物が、周囲の目にどんな風に映っていたか。そんな描写を読むのが好きなんです。
小説の中にはしばしば実在した歴史上の人物が登場します。その人物が主役の話ももちろん面白いですが、個人的には、創作キャラクター主役の話に脇役として実在の人物が登場する方が好きですね。歴史に名を残す人物が、周囲の目にどんな風に映っていたか。そんな描写を読むのが好きなんです。 ミステリーにおけるトリックの一つに、<叙述トリック>というものがあります。一部の情報をわざと曖昧に記述し、読者に思い込みや先入観を抱かせてミスリードを誘うトリックのことです。男性かと思われた人物が実は女性だったり、同じ時代を生きる登場人物たちの物語と見せかけて、実は片方は数十年前の人物だったりと、色々な仕掛け方がありますね。
ミステリーにおけるトリックの一つに、<叙述トリック>というものがあります。一部の情報をわざと曖昧に記述し、読者に思い込みや先入観を抱かせてミスリードを誘うトリックのことです。男性かと思われた人物が実は女性だったり、同じ時代を生きる登場人物たちの物語と見せかけて、実は片方は数十年前の人物だったりと、色々な仕掛け方がありますね。 一口でミステリーと言ってもそこには様々なジャンルがあり、人それぞれ好みが分かれます。刑事が地道な捜査で真相を暴くモダンなものが好きな人がいれば、時刻表トリックが駆使されたトラベルミステリーが好みだという人、殺人鬼が暴れ回るホラー寄りの作品に目がないという人もいるでしょう。私はといえば基本的にどんなジャンルも好きなのですが、一番心惹かれるのは吹雪の山荘や絶海の孤島を舞台にしたクローズド・サークル作品です。
一口でミステリーと言ってもそこには様々なジャンルがあり、人それぞれ好みが分かれます。刑事が地道な捜査で真相を暴くモダンなものが好きな人がいれば、時刻表トリックが駆使されたトラベルミステリーが好みだという人、殺人鬼が暴れ回るホラー寄りの作品に目がないという人もいるでしょう。私はといえば基本的にどんなジャンルも好きなのですが、一番心惹かれるのは吹雪の山荘や絶海の孤島を舞台にしたクローズド・サークル作品です。 <身内同士が協力して(あるいは影響を受けて)事件に挑む>という設定は、バディ系ミステリの王道パターンです。刑事や探偵というならともかく、素人が謎解きに挑戦する場合、「そもそもなぜ彼らは組んで事件を追うのか→身内で信頼できるから」という理由づけがしやすいからかもしれません。
<身内同士が協力して(あるいは影響を受けて)事件に挑む>という設定は、バディ系ミステリの王道パターンです。刑事や探偵というならともかく、素人が謎解きに挑戦する場合、「そもそもなぜ彼らは組んで事件を追うのか→身内で信頼できるから」という理由づけがしやすいからかもしれません。 <鬼>という言葉を聞くと、頭に角を生やし、口から牙がむき出しになった猛々しい姿を想像する人が多いと思います。意外かもしれませんが<鬼>の語源は<隠(おぬ)>が転じたものであり、本来は<姿が見えないもの>という意味なんだとか。能楽で鬼が<人が孤独や憎悪などから怨霊と化したもの>として描かれるのは、案外、この辺りに理由があるのかもしれません。
<鬼>という言葉を聞くと、頭に角を生やし、口から牙がむき出しになった猛々しい姿を想像する人が多いと思います。意外かもしれませんが<鬼>の語源は<隠(おぬ)>が転じたものであり、本来は<姿が見えないもの>という意味なんだとか。能楽で鬼が<人が孤独や憎悪などから怨霊と化したもの>として描かれるのは、案外、この辺りに理由があるのかもしれません。 あいつさえいなければ・・・誰しも一度や二度、そんな思いを抱いたことがあると思います。とはいえ、実際に憎い相手を<消す=殺す>決断をする人間は少数派。理由は色々あると思いますが、その一つは「殺してやりたいが殺人犯として逮捕されるのは嫌」というものでしょう。そこでフィクション界の登場人物たち(もしかしたら現実の人間も)は、自分が逮捕されずに済むよう、様々なトリックを駆使するわけです。そのトリックの一つに<交換殺人>があります。
あいつさえいなければ・・・誰しも一度や二度、そんな思いを抱いたことがあると思います。とはいえ、実際に憎い相手を<消す=殺す>決断をする人間は少数派。理由は色々あると思いますが、その一つは「殺してやりたいが殺人犯として逮捕されるのは嫌」というものでしょう。そこでフィクション界の登場人物たち(もしかしたら現実の人間も)は、自分が逮捕されずに済むよう、様々なトリックを駆使するわけです。そのトリックの一つに<交換殺人>があります。