 桃太郎、かぐや姫、シンデレラ、眠れる森の美女・・・・・世界各国には様々な童話が存在します。一見、非現実的なフィクションと思われがちですが、童話には現実世界でも通用する教訓が込められているもの。だからこそ、何百年、何千年にも渡って各地で伝わり続けてきたのでしょう。
桃太郎、かぐや姫、シンデレラ、眠れる森の美女・・・・・世界各国には様々な童話が存在します。一見、非現実的なフィクションと思われがちですが、童話には現実世界でも通用する教訓が込められているもの。だからこそ、何百年、何千年にも渡って各地で伝わり続けてきたのでしょう。
そんな童話の初版を調べてみると、子どものトラウマになりかねないほど残酷なものが多いです。『白雪姫』の初版で、悪いお妃が焼けた鉄靴を履かされ死ぬまで踊らされるという展開など、そのいい例と言えるでしょう。上記の特性から、童話を現代風にアレンジした小説はたくさんあります。『ヘンゼルとグレーテル』『赤ずきん』『ラプンツェル』などはモチーフになりやすいので、今回は目新しい作品を取り上げたいと思います。真梨幸子さんの『三匹の子豚』です。
こんな人におすすめ
母と娘にまつわる愛憎劇が読みたい人
続きを読む
 フィクション作品における時間の経過方法は、主に二つのパターンに分かれます。一つはいわゆる<サザエさん時空>で、登場人物たちが年を取らない方式です。いつまでも変わらない日常感を味わうことができるという長所から、特に『サザエさん』『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』などの子ども向け作品でよく見られますね。
フィクション作品における時間の経過方法は、主に二つのパターンに分かれます。一つはいわゆる<サザエさん時空>で、登場人物たちが年を取らない方式です。いつまでも変わらない日常感を味わうことができるという長所から、特に『サザエさん』『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』などの子ども向け作品でよく見られますね。
もう一つは、物語が進むにつれて登場人物たちも年を取り、卒業・結婚・出産・死別といったライフイベントを経験していくパターンです。このパターンで一番有名なのは、赤川次郎さんの『杉原爽香シリーズ』ではないでしょうか。一年に一冊、新作が刊行されていくごとにヒロインも一歳年を取るという形式は、世界的にも珍しいんだとか。ここまで厳密に時間が経過していく作品は少ないかもしれませんが、作品ごとに登場人物たちの成長が見られると、読者としてはまるで親戚の子を見守るような感慨深さを味わうものです。今回ご紹介する作品の登場人物たちも、出会いと別れを繰り返しながら一歩ずつ前進していきます。西澤保彦さんの『匠千暁シリーズ』の長編第一弾『彼女が死んだ夜』です。
こんな人におすすめ
大学生が活躍するミステリーが読みたい人
続きを読む
 古今東西、創作の世界には様々なシリーズ物が存在します。中には作者が死去した後、弟子やプロダクション関係者が続編を作り続けている作品もあり、何十年もの長期シリーズと化すことも珍しくありません。この手のシリーズ物の魅力の一つは、「最後には水〇黄門が現れて悪党を成敗してくれるんだろうな」「十津〇警部が出てくるなら時刻表トリックが使われているのかな」等々、安定した世界観を楽しめる点でしょう。
古今東西、創作の世界には様々なシリーズ物が存在します。中には作者が死去した後、弟子やプロダクション関係者が続編を作り続けている作品もあり、何十年もの長期シリーズと化すことも珍しくありません。この手のシリーズ物の魅力の一つは、「最後には水〇黄門が現れて悪党を成敗してくれるんだろうな」「十津〇警部が出てくるなら時刻表トリックが使われているのかな」等々、安定した世界観を楽しめる点でしょう。
ですが、長期シリーズ化した作品の中には、これまでのお約束から外れた<異色作>が登場することがしばしばあります。例を挙げるなら、例えばアガサ・クリスティーの『ビッグ4』。『名探偵ポワロシリーズ』の中の一作なのですが、ここでポワロが対峙するのは国際的な悪の組織です。秘密諜報員が出るわ立ち回りはあるわで、<ポワロ=上流階級を舞台にした犯罪者との頭脳戦>をイメージしていた私はかなりびっくりしました。今回は、そんなシリーズ物の中の異色作をご紹介したいと思います。三津田信三さんの『首無の如き祟るもの』です。
こんな人におすすめ
おどろおどろしいホラーミステリーが読みたい人
続きを読む
 私が本を愛する理由は色々ありますが、その一つは<現実にはなかなか味わえない出来事を体験できる>というものです。医者になって病院内の陰謀劇に関わることも、拳銃ぶっ放しながらゾンビ軍団と戦うことも、宇宙飛行士として未知の惑星に降り立つことも、小説の中ならお茶の子さいさい。ここ最近は外国を舞台にした小説を読みまくり、旅行した気分を味わっています。
私が本を愛する理由は色々ありますが、その一つは<現実にはなかなか味わえない出来事を体験できる>というものです。医者になって病院内の陰謀劇に関わることも、拳銃ぶっ放しながらゾンビ軍団と戦うことも、宇宙飛行士として未知の惑星に降り立つことも、小説の中ならお茶の子さいさい。ここ最近は外国を舞台にした小説を読みまくり、旅行した気分を味わっています。
外国で物語が展開する小説はたくさんありますが、冒険小説寄りの作品が多い気がします。私はどちらかというとミステリーやヒューマンストーリー寄りな小説が好きなので、近藤史恵さんの『エデン』、深木章子さんの『螺旋の底』、村山由佳さんの『翼 cry for the moon』などが印象深かったですね。これらはすべて長編なので、今回はさくさく読める短編集を取り上げたいと思います。貫井徳郎さんの『ミハスの落日』です。
こんな人におすすめ
異国情緒溢れるミステリーが読みたい人
続きを読む
 学生時代、進路指導の先生から「どんな職業でもいい。プライドと責任を持てる仕事をしてください」と言われたことがあります。この言葉の意味が少しずつ分かってきたのは、恥ずかしながら社会人になってから。会社員だろうと自営業だろうと専業主婦(夫)だろうと、自分のやることに誇りを持っている人は素敵です。
学生時代、進路指導の先生から「どんな職業でもいい。プライドと責任を持てる仕事をしてください」と言われたことがあります。この言葉の意味が少しずつ分かってきたのは、恥ずかしながら社会人になってから。会社員だろうと自営業だろうと専業主婦(夫)だろうと、自分のやることに誇りを持っている人は素敵です。
そんな人々を主人公にした<お仕事小説>というジャンルがあります。天祢涼さんの『謎解き広報課』では田舎の町役場職員の、荻原浩さんの『神様からひと言』では民間企業のお客様相談室の、坂木司さんの『シンデレラ・ティース』では歯科医受付の、様々な葛藤や挫折、やり甲斐や楽しさが描かれました。今日ご紹介するのは、普段は日が当たりにくい仕事の悲喜こもごもをテーマにした作品です。元新聞記者という経歴を持つ、横山秀夫さんの『看守眼』です。
こんな人におすすめ
様々な職業の主人公が出てくるミステリーが読みたい人
続きを読む
 子どもという存在は無邪気なもの、裏表なく素直なもの・・・そんなイメージを抱いている人は多いでしょうし、実際にそういう面もあります。しかし、油断は禁物です。無邪気さや素直さは、残酷さや遠慮のなさに繋がるもの。「なんでそんなことをしてしまったの」と大人を唖然とさせる子どもは、現実にも存在します。
子どもという存在は無邪気なもの、裏表なく素直なもの・・・そんなイメージを抱いている人は多いでしょうし、実際にそういう面もあります。しかし、油断は禁物です。無邪気さや素直さは、残酷さや遠慮のなさに繋がるもの。「なんでそんなことをしてしまったの」と大人を唖然とさせる子どもは、現実にも存在します。
この手の<残酷な子ども>を描いた作品で私が一番衝撃を受けたのは、S.キングの『トウモロコシ畑の子どもたち』とスペインのホラー映画『ザ・チャイルド』。集団で襲って来る子どもたちと、訳も分からぬまま惨殺されていく大人たちの描写が凄惨で、しばらく呆然としてしまいました。この二作品はグロテスクな部分が多く、かなり人を選ぶと思うので、今回はもう少しマイルドな<怖い子どもたち>を紹介したいと思います。赤川次郎さんの『充ち足りた悪漢たち』です。
こんな人におすすめ
子どもの恐ろしさをテーマにした短編集が読みたい人
続きを読む
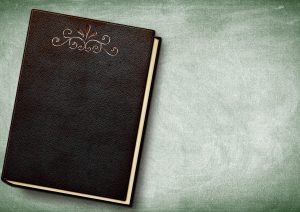 芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。
芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。
そんな文学賞の中で、私が一番注目しているのは『このミステリーがすごい!』大賞です。二〇〇二年に創設された新しい賞ですが、海堂尊さんの『チーム・バチスタの栄光』や柚月裕子さんの『臨床心理』、中山七里さんの『さよならドビュッシー』など、受賞を機にスターダムの仲間入りをした人気作家さんも多いです。今回は、そんな『このミステリーがすごい!』大賞受賞作家さんがずらりと並んだアンソロジーをご紹介します。『10分間ミステリー』です。
こんな人におすすめ
ショートショートが詰まった短編集が読みたい人
続きを読む
 私は基本的にどんなジャンルの小説も読む人間です。切なくも甘酸っぱい青春ラブコメだろうと、血飛沫が飛び内臓はみ出るスプラッターホラーだろうと、面白ければ何でもOK。そんな私が唯一、「なんとなくとっつきにくいかな」と思うジャンル、それが金融・経済小説です。根っからの文系人間のせいか、用語や世界観がなかなか頭に入ってこないんです。
私は基本的にどんなジャンルの小説も読む人間です。切なくも甘酸っぱい青春ラブコメだろうと、血飛沫が飛び内臓はみ出るスプラッターホラーだろうと、面白ければ何でもOK。そんな私が唯一、「なんとなくとっつきにくいかな」と思うジャンル、それが金融・経済小説です。根っからの文系人間のせいか、用語や世界観がなかなか頭に入ってこないんです。
ですが、面白いと感じた金融小説が一冊もないわけではありません。特に、池井戸潤さんの『半沢直樹シリーズ』と真山仁さんの『ハゲタカシリーズ』は、映像化されたこともあって世間一般の知名度も高いですね。今回ご紹介するのは、中山七里さんの『笑え、シャイロック』。もしかしたら上記の作品と並ぶ人気シリーズになるかもしれません。
こんな人におすすめ
銀行員が主役のミステリーが読みたい人
続きを読む
 以前、別作品のレビューで、「<家>という場所には、人をとらえるイメージもある」と書きました。一説によると、<家>は<宀(家)>と<豕(豚)>が組み合わさってできた漢字であり、<豚などの家畜を生贄に捧げた呪法的な護りのある場所>という意味があるんだとか。どの程度信憑性がある話かは分かりませんが、もしこれが本当なら、<家>がホラーやミステリーの舞台になりやすいのも納得です。
以前、別作品のレビューで、「<家>という場所には、人をとらえるイメージもある」と書きました。一説によると、<家>は<宀(家)>と<豕(豚)>が組み合わさってできた漢字であり、<豚などの家畜を生贄に捧げた呪法的な護りのある場所>という意味があるんだとか。どの程度信憑性がある話かは分かりませんが、もしこれが本当なら、<家>がホラーやミステリーの舞台になりやすいのも納得です。
前回ご紹介した<家>にまつわる作品はホラーだったので、今回はミステリーを取り上げたいと思います。歌野晶午さんの『家守』。この方の短編集を読むのは久々ですが、安定の面白さで大満足でした。
こんな人におすすめ
<家>をテーマにしたミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 ミステリーには、<主役にしやすい職業>というものがあります。高い調査能力や行動力を持ち、事件と関わる確率の高い職業の方が、物語を始めやすいですからね。たとえば刑事や弁護士、検事、ジャーナリストなどなど。探偵もその一つです。
ミステリーには、<主役にしやすい職業>というものがあります。高い調査能力や行動力を持ち、事件と関わる確率の高い職業の方が、物語を始めやすいですからね。たとえば刑事や弁護士、検事、ジャーナリストなどなど。探偵もその一つです。
日本の名探偵といえば金田一耕助や明智小五郎などが有名ですが、現代日本において探偵が堂々と大事件に関わる機会はそうそうありません。現代では<探偵事務所>や<興信所>の職員が、人探しや素行調査を行う過程で事件と関わるというパターンが多いです。加納朋子さんの『アリスシリーズ』、柴田よしきさんの『花咲慎一郎シリーズ』などがそうですね。今回ご紹介する小説もその一つ。真梨幸子さんの『初恋さがし』です。
こんな人におすすめ
テンポの良いイヤミスが読みたい人
続きを読む
 桃太郎、かぐや姫、シンデレラ、眠れる森の美女・・・・・世界各国には様々な童話が存在します。一見、非現実的なフィクションと思われがちですが、童話には現実世界でも通用する教訓が込められているもの。だからこそ、何百年、何千年にも渡って各地で伝わり続けてきたのでしょう。
桃太郎、かぐや姫、シンデレラ、眠れる森の美女・・・・・世界各国には様々な童話が存在します。一見、非現実的なフィクションと思われがちですが、童話には現実世界でも通用する教訓が込められているもの。だからこそ、何百年、何千年にも渡って各地で伝わり続けてきたのでしょう。
 フィクション作品における時間の経過方法は、主に二つのパターンに分かれます。一つはいわゆる<サザエさん時空>で、登場人物たちが年を取らない方式です。いつまでも変わらない日常感を味わうことができるという長所から、特に『サザエさん』『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』などの子ども向け作品でよく見られますね。
フィクション作品における時間の経過方法は、主に二つのパターンに分かれます。一つはいわゆる<サザエさん時空>で、登場人物たちが年を取らない方式です。いつまでも変わらない日常感を味わうことができるという長所から、特に『サザエさん』『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』などの子ども向け作品でよく見られますね。 古今東西、創作の世界には様々なシリーズ物が存在します。中には作者が死去した後、弟子やプロダクション関係者が続編を作り続けている作品もあり、何十年もの長期シリーズと化すことも珍しくありません。この手のシリーズ物の魅力の一つは、「最後には水〇黄門が現れて悪党を成敗してくれるんだろうな」「十津〇警部が出てくるなら時刻表トリックが使われているのかな」等々、安定した世界観を楽しめる点でしょう。
古今東西、創作の世界には様々なシリーズ物が存在します。中には作者が死去した後、弟子やプロダクション関係者が続編を作り続けている作品もあり、何十年もの長期シリーズと化すことも珍しくありません。この手のシリーズ物の魅力の一つは、「最後には水〇黄門が現れて悪党を成敗してくれるんだろうな」「十津〇警部が出てくるなら時刻表トリックが使われているのかな」等々、安定した世界観を楽しめる点でしょう。 私が本を愛する理由は色々ありますが、その一つは<現実にはなかなか味わえない出来事を体験できる>というものです。医者になって病院内の陰謀劇に関わることも、拳銃ぶっ放しながらゾンビ軍団と戦うことも、宇宙飛行士として未知の惑星に降り立つことも、小説の中ならお茶の子さいさい。ここ最近は外国を舞台にした小説を読みまくり、旅行した気分を味わっています。
私が本を愛する理由は色々ありますが、その一つは<現実にはなかなか味わえない出来事を体験できる>というものです。医者になって病院内の陰謀劇に関わることも、拳銃ぶっ放しながらゾンビ軍団と戦うことも、宇宙飛行士として未知の惑星に降り立つことも、小説の中ならお茶の子さいさい。ここ最近は外国を舞台にした小説を読みまくり、旅行した気分を味わっています。 学生時代、進路指導の先生から「どんな職業でもいい。プライドと責任を持てる仕事をしてください」と言われたことがあります。この言葉の意味が少しずつ分かってきたのは、恥ずかしながら社会人になってから。会社員だろうと自営業だろうと専業主婦(夫)だろうと、自分のやることに誇りを持っている人は素敵です。
学生時代、進路指導の先生から「どんな職業でもいい。プライドと責任を持てる仕事をしてください」と言われたことがあります。この言葉の意味が少しずつ分かってきたのは、恥ずかしながら社会人になってから。会社員だろうと自営業だろうと専業主婦(夫)だろうと、自分のやることに誇りを持っている人は素敵です。 子どもという存在は無邪気なもの、裏表なく素直なもの・・・そんなイメージを抱いている人は多いでしょうし、実際にそういう面もあります。しかし、油断は禁物です。無邪気さや素直さは、残酷さや遠慮のなさに繋がるもの。「なんでそんなことをしてしまったの」と大人を唖然とさせる子どもは、現実にも存在します。
子どもという存在は無邪気なもの、裏表なく素直なもの・・・そんなイメージを抱いている人は多いでしょうし、実際にそういう面もあります。しかし、油断は禁物です。無邪気さや素直さは、残酷さや遠慮のなさに繋がるもの。「なんでそんなことをしてしまったの」と大人を唖然とさせる子どもは、現実にも存在します。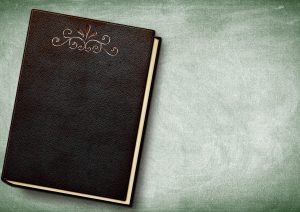 芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。
芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。 私は基本的にどんなジャンルの小説も読む人間です。切なくも甘酸っぱい青春ラブコメだろうと、血飛沫が飛び内臓はみ出るスプラッターホラーだろうと、面白ければ何でもOK。そんな私が唯一、「なんとなくとっつきにくいかな」と思うジャンル、それが金融・経済小説です。根っからの文系人間のせいか、用語や世界観がなかなか頭に入ってこないんです。
私は基本的にどんなジャンルの小説も読む人間です。切なくも甘酸っぱい青春ラブコメだろうと、血飛沫が飛び内臓はみ出るスプラッターホラーだろうと、面白ければ何でもOK。そんな私が唯一、「なんとなくとっつきにくいかな」と思うジャンル、それが金融・経済小説です。根っからの文系人間のせいか、用語や世界観がなかなか頭に入ってこないんです。 以前、別作品のレビューで、「<家>という場所には、人をとらえるイメージもある」と書きました。一説によると、<家>は<宀(家)>と<豕(豚)>が組み合わさってできた漢字であり、<豚などの家畜を生贄に捧げた呪法的な護りのある場所>という意味があるんだとか。どの程度信憑性がある話かは分かりませんが、もしこれが本当なら、<家>がホラーやミステリーの舞台になりやすいのも納得です。
以前、別作品のレビューで、「<家>という場所には、人をとらえるイメージもある」と書きました。一説によると、<家>は<宀(家)>と<豕(豚)>が組み合わさってできた漢字であり、<豚などの家畜を生贄に捧げた呪法的な護りのある場所>という意味があるんだとか。どの程度信憑性がある話かは分かりませんが、もしこれが本当なら、<家>がホラーやミステリーの舞台になりやすいのも納得です。 ミステリーには、<主役にしやすい職業>というものがあります。高い調査能力や行動力を持ち、事件と関わる確率の高い職業の方が、物語を始めやすいですからね。たとえば刑事や弁護士、検事、ジャーナリストなどなど。探偵もその一つです。
ミステリーには、<主役にしやすい職業>というものがあります。高い調査能力や行動力を持ち、事件と関わる確率の高い職業の方が、物語を始めやすいですからね。たとえば刑事や弁護士、検事、ジャーナリストなどなど。探偵もその一つです。