 「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。
「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。
ですが、人間が社会生活を営む生き物である以上、社会に受け入れられ祝福される恋愛と、そうでない恋愛があることはどうしようもありません。中年男が少女に恋をし、破滅していく様を描いたウラジミール・ナボコフの『ロリータ』などがいい例でしょう。今回ご紹介する作品にも、決して祝福されないであろう恋愛がたくさん出てきました。朱川湊人さんの『月蝕楽園』です。
こんな人におすすめ
許されざる愛をテーマにしたダークな短編集が読みたい人

 日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。
日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。 皆さんは公共交通機関で移動中、何をして時間を潰しますか?スマホで動画鑑賞やゲームをする人、クロスワードパズルをする人、睡眠不足解消のため眠る人・・・過ごし方は人それぞれです。私の場合、ほぼ迷わず読書一択。昔、新幹線での出張が多い仕事をしていた時は、どの本を持って行くかを考えるのが最優先の検討事案でした(笑)
皆さんは公共交通機関で移動中、何をして時間を潰しますか?スマホで動画鑑賞やゲームをする人、クロスワードパズルをする人、睡眠不足解消のため眠る人・・・過ごし方は人それぞれです。私の場合、ほぼ迷わず読書一択。昔、新幹線での出張が多い仕事をしていた時は、どの本を持って行くかを考えるのが最優先の検討事案でした(笑) 季節は夏。今はマスク着用が求められるご時世なせいもあり、暑さが余計に身に染みます。こういう時は、少しでも涼を取れる娯楽が欲しいですよね。例えば、風鈴を吊るすとか、オリジナルのかき氷を作ってみるとか・・・昔のように自由気ままに外出するのがまだ難しい分、自宅で気軽に涼める楽しみを探してしまいます。
季節は夏。今はマスク着用が求められるご時世なせいもあり、暑さが余計に身に染みます。こういう時は、少しでも涼を取れる娯楽が欲しいですよね。例えば、風鈴を吊るすとか、オリジナルのかき氷を作ってみるとか・・・昔のように自由気ままに外出するのがまだ難しい分、自宅で気軽に涼める楽しみを探してしまいます。 フィクションの世界においては、しばしば、登場シーンはわずかにも関わらず存在感を発揮するキャラクターがいます。こういったキャラクターで私が真っ先に思いつくのは、西澤保彦さん『仔羊たちの聖夜』に登場する事件関係者の弟・英生さん(分かる方、います?)。出てくるのはたった数ページなものの、明晰な言動といい、<肉体的にも精神的にもぜい肉をそぎ落としたようなストイックな凄みがある>容姿といい、やたら印象的なんですよ。私はちょっと影のあるキャラに惹かれてしまいがちなので、「いつか別作品の主要登場人物になってくれないかな」と今でも思っています。
フィクションの世界においては、しばしば、登場シーンはわずかにも関わらず存在感を発揮するキャラクターがいます。こういったキャラクターで私が真っ先に思いつくのは、西澤保彦さん『仔羊たちの聖夜』に登場する事件関係者の弟・英生さん(分かる方、います?)。出てくるのはたった数ページなものの、明晰な言動といい、<肉体的にも精神的にもぜい肉をそぎ落としたようなストイックな凄みがある>容姿といい、やたら印象的なんですよ。私はちょっと影のあるキャラに惹かれてしまいがちなので、「いつか別作品の主要登場人物になってくれないかな」と今でも思っています。 学生時代、とてもスタイルの良い女性の先生がいました。背が高く、手足が長く、スーツ姿で佇む様子は舞台女優さながら。そんな見た目とは裏腹に、とある疾患を抱えていて、長時間立ったり歩いたりすることが難しいそうです。ただ、何しろ容姿が健康的かつ華やかなので、バスや電車で優先席に座っていると「年寄りに席を譲れ」と怒られることもあるとのことでした。
学生時代、とてもスタイルの良い女性の先生がいました。背が高く、手足が長く、スーツ姿で佇む様子は舞台女優さながら。そんな見た目とは裏腹に、とある疾患を抱えていて、長時間立ったり歩いたりすることが難しいそうです。ただ、何しろ容姿が健康的かつ華やかなので、バスや電車で優先席に座っていると「年寄りに席を譲れ」と怒られることもあるとのことでした。 日本は島国であるため、比較的気軽にマリンスポーツを楽しむことができます。私自身、子どもの頃は親に連れられて海水浴に行ったり、海辺で花火をしたりしました。そういう時、海によってはボードを抱えたサーファーを目にすることもあり、「あれはどういうスポーツなんだろう?」と不思議に思ったものです。波打ち際でちゃぷちゃぷ遊ぶのと違い、サーフィンには技術や道具が必要ということもあって、今でもなんとなく縁遠いです。
日本は島国であるため、比較的気軽にマリンスポーツを楽しむことができます。私自身、子どもの頃は親に連れられて海水浴に行ったり、海辺で花火をしたりしました。そういう時、海によってはボードを抱えたサーファーを目にすることもあり、「あれはどういうスポーツなんだろう?」と不思議に思ったものです。波打ち際でちゃぷちゃぷ遊ぶのと違い、サーフィンには技術や道具が必要ということもあって、今でもなんとなく縁遠いです。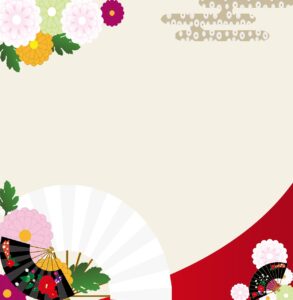 「最初から最後まできっちり読み通したことはないけど、大まかなあらすじは知っている」「漫画版や実写版しか見たことない」という小説って、意外と多いです。私の場合、ぱっと思いつくのは森鷗外の『舞姫』や太宰治の『人間失格』。一昔前の文豪の作品は、文体が現代と異なっていることもあり、なんとなくとっつきにくく感じてしまいます。
「最初から最後まできっちり読み通したことはないけど、大まかなあらすじは知っている」「漫画版や実写版しか見たことない」という小説って、意外と多いです。私の場合、ぱっと思いつくのは森鷗外の『舞姫』や太宰治の『人間失格』。一昔前の文豪の作品は、文体が現代と異なっていることもあり、なんとなくとっつきにくく感じてしまいます。 海外の創作物が日本でヒットする要因は何でしょうか。内容が肝心なのは言うまでもありませんが、翻訳の出来も、かなり重要な位置を占めます。学生時代、授業でやった英語一つ取っても、訳する人間が違えばニュアンスが大きく変わるもの。まして、商業的な作品、それも映像で物語を説明できない小説となると、翻訳のレベルが成功の鍵と言っても過言ではありません。
海外の創作物が日本でヒットする要因は何でしょうか。内容が肝心なのは言うまでもありませんが、翻訳の出来も、かなり重要な位置を占めます。学生時代、授業でやった英語一つ取っても、訳する人間が違えばニュアンスが大きく変わるもの。まして、商業的な作品、それも映像で物語を説明できない小説となると、翻訳のレベルが成功の鍵と言っても過言ではありません。 サスペンスやホラーにおける子どもの役割は、大抵二分されます。登場人物達に未来や希望を感じさせる清涼剤的存在か、子ども特有の残酷さや凶暴さを発揮する恐怖の対象か。どちらも面白いですが、イヤミス大好きな私としては、後者の子どもに惹かれてしまいます。
サスペンスやホラーにおける子どもの役割は、大抵二分されます。登場人物達に未来や希望を感じさせる清涼剤的存在か、子ども特有の残酷さや凶暴さを発揮する恐怖の対象か。どちらも面白いですが、イヤミス大好きな私としては、後者の子どもに惹かれてしまいます。