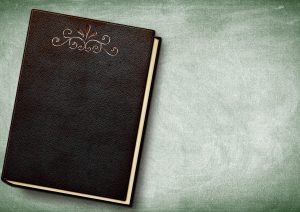 芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。
芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。
そんな文学賞の中で、私が一番注目しているのは『このミステリーがすごい!』大賞です。二〇〇二年に創設された新しい賞ですが、海堂尊さんの『チーム・バチスタの栄光』や柚月裕子さんの『臨床心理』、中山七里さんの『さよならドビュッシー』など、受賞を機にスターダムの仲間入りをした人気作家さんも多いです。今回は、そんな『このミステリーがすごい!』大賞受賞作家さんがずらりと並んだアンソロジーをご紹介します。『10分間ミステリー』です。
こんな人におすすめ
ショートショートが詰まった短編集が読みたい人

 今までこのブログでは、<怖い女>が登場する小説をたくさん取り上げてきました。別に狙ったわけではありませんが、それらの小説の大半は、作者が女性だった気がします。女性作家の手で綴られる女の狂気や愛憎の恐ろしさはやはり格別。読んでいて鳥肌が立ちそうになることすらあるほどです。
今までこのブログでは、<怖い女>が登場する小説をたくさん取り上げてきました。別に狙ったわけではありませんが、それらの小説の大半は、作者が女性だった気がします。女性作家の手で綴られる女の狂気や愛憎の恐ろしさはやはり格別。読んでいて鳥肌が立ちそうになることすらあるほどです。 今更言うまでもない話ですが、殺人という犯罪は多くのものを奪っていきます。被害者本人の命や尊厳はもちろん、その家族の人生をも大きく揺るがし、ひっくり返し、時に破壊してしまうことすらあり得ます。昔見たドラマで、息子を殺された父親が言っていた「家族全員殺されたようなものだ」という台詞は、決して大げさなものではないのでしょう。
今更言うまでもない話ですが、殺人という犯罪は多くのものを奪っていきます。被害者本人の命や尊厳はもちろん、その家族の人生をも大きく揺るがし、ひっくり返し、時に破壊してしまうことすらあり得ます。昔見たドラマで、息子を殺された父親が言っていた「家族全員殺されたようなものだ」という台詞は、決して大げさなものではないのでしょう。 ミステリーには、<主役にしやすい職業>というものがあります。高い調査能力や行動力を持ち、事件と関わる確率の高い職業の方が、物語を始めやすいですからね。たとえば刑事や弁護士、検事、ジャーナリストなどなど。探偵もその一つです。
ミステリーには、<主役にしやすい職業>というものがあります。高い調査能力や行動力を持ち、事件と関わる確率の高い職業の方が、物語を始めやすいですからね。たとえば刑事や弁護士、検事、ジャーナリストなどなど。探偵もその一つです。 生まれ変わり、輪廻転生、リインカーネーション。生き物が死後に再び肉体を得てこの世に戻ってくるという考え方は、世界中に存在します。この思想を信じるか否かでは意見が分かれるのでしょうが、私自身はかなり信じている方。実際、偶然や勘違いでは片づけられない事例もたくさんあるようです。
生まれ変わり、輪廻転生、リインカーネーション。生き物が死後に再び肉体を得てこの世に戻ってくるという考え方は、世界中に存在します。この思想を信じるか否かでは意見が分かれるのでしょうが、私自身はかなり信じている方。実際、偶然や勘違いでは片づけられない事例もたくさんあるようです。 <予言>という単語を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、かの有名な<ノストラダムスの大予言>でしょう。<一九九九年七か月、空から恐怖の大王が来るだろう>という一文が<一九九九年に人類は滅びる>と解釈され、一時期、テレビや雑誌もその話題で持ちきりでした。かくいう私も、ハラハラドキドキしながら特集雑誌を買い求めた一人です。
<予言>という単語を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、かの有名な<ノストラダムスの大予言>でしょう。<一九九九年七か月、空から恐怖の大王が来るだろう>という一文が<一九九九年に人類は滅びる>と解釈され、一時期、テレビや雑誌もその話題で持ちきりでした。かくいう私も、ハラハラドキドキしながら特集雑誌を買い求めた一人です。 ミステリーにおけるトリックの一つに、<叙述トリック>というものがあります。一部の情報をわざと曖昧に記述し、読者に思い込みや先入観を抱かせてミスリードを誘うトリックのことです。男性かと思われた人物が実は女性だったり、同じ時代を生きる登場人物たちの物語と見せかけて、実は片方は数十年前の人物だったりと、色々な仕掛け方がありますね。
ミステリーにおけるトリックの一つに、<叙述トリック>というものがあります。一部の情報をわざと曖昧に記述し、読者に思い込みや先入観を抱かせてミスリードを誘うトリックのことです。男性かと思われた人物が実は女性だったり、同じ時代を生きる登場人物たちの物語と見せかけて、実は片方は数十年前の人物だったりと、色々な仕掛け方がありますね。 <魔女>と聞くと、どういう存在を連想するでしょうか。恐らく、黒い服を着てホウキにまたがった女性を思い浮かべる人が多いと思います。実はこれは日本的な発想であり、発生の地であるヨーロッパではもっと多種多様な意味を持つ存在であるとのこと。男性だっているし、年齢も年寄りから少年少女まで様々です。数多くの学説があるようですが、まとめると<人知を超えた力で災いを為す存在>ということでしょう。
<魔女>と聞くと、どういう存在を連想するでしょうか。恐らく、黒い服を着てホウキにまたがった女性を思い浮かべる人が多いと思います。実はこれは日本的な発想であり、発生の地であるヨーロッパではもっと多種多様な意味を持つ存在であるとのこと。男性だっているし、年齢も年寄りから少年少女まで様々です。数多くの学説があるようですが、まとめると<人知を超えた力で災いを為す存在>ということでしょう。 一口でミステリーと言ってもそこには様々なジャンルがあり、人それぞれ好みが分かれます。刑事が地道な捜査で真相を暴くモダンなものが好きな人がいれば、時刻表トリックが駆使されたトラベルミステリーが好みだという人、殺人鬼が暴れ回るホラー寄りの作品に目がないという人もいるでしょう。私はといえば基本的にどんなジャンルも好きなのですが、一番心惹かれるのは吹雪の山荘や絶海の孤島を舞台にしたクローズド・サークル作品です。
一口でミステリーと言ってもそこには様々なジャンルがあり、人それぞれ好みが分かれます。刑事が地道な捜査で真相を暴くモダンなものが好きな人がいれば、時刻表トリックが駆使されたトラベルミステリーが好みだという人、殺人鬼が暴れ回るホラー寄りの作品に目がないという人もいるでしょう。私はといえば基本的にどんなジャンルも好きなのですが、一番心惹かれるのは吹雪の山荘や絶海の孤島を舞台にしたクローズド・サークル作品です。 <鬼>という言葉を聞くと、頭に角を生やし、口から牙がむき出しになった猛々しい姿を想像する人が多いと思います。意外かもしれませんが<鬼>の語源は<隠(おぬ)>が転じたものであり、本来は<姿が見えないもの>という意味なんだとか。能楽で鬼が<人が孤独や憎悪などから怨霊と化したもの>として描かれるのは、案外、この辺りに理由があるのかもしれません。
<鬼>という言葉を聞くと、頭に角を生やし、口から牙がむき出しになった猛々しい姿を想像する人が多いと思います。意外かもしれませんが<鬼>の語源は<隠(おぬ)>が転じたものであり、本来は<姿が見えないもの>という意味なんだとか。能楽で鬼が<人が孤独や憎悪などから怨霊と化したもの>として描かれるのは、案外、この辺りに理由があるのかもしれません。