 ゆっくりと穏やかな生活を目指す<スローライフ>が注目されるようになったのは、二〇〇年を過ぎた頃かららしいです。同時に、都会の喧騒を離れた田舎暮らしに憧れる人達も増え始めました。この流れを受けたせいでしょうか。最近は田舎暮らしをテーマにした小説でも、<都会から来た主人公が、色々ありながらも近隣住民と絆を作り、困難を乗り越えて田舎暮らしに馴染む>という爽やかな作風のものが多い気がします。
ゆっくりと穏やかな生活を目指す<スローライフ>が注目されるようになったのは、二〇〇年を過ぎた頃かららしいです。同時に、都会の喧騒を離れた田舎暮らしに憧れる人達も増え始めました。この流れを受けたせいでしょうか。最近は田舎暮らしをテーマにした小説でも、<都会から来た主人公が、色々ありながらも近隣住民と絆を作り、困難を乗り越えて田舎暮らしに馴染む>という爽やかな作風のものが多い気がします。
もちろん、こういう小説も面白いのですが、あくまでフィクションの世界限定ならば、田舎の閉鎖的でドロドロした空気を描く作品もけっこう好きだったりします。この手の作品で一番有名なのは、やはり『金田一耕介シリーズ』でしょうか。ここ最近なら、辻村深月さんの『水底フェスタ』や中山七里さんの『ワルツを踊ろう』も、地方都市の閉ざされた世界観が巧みに描写されていました。今回ご紹介する作品でも、日本の村社会の恐ろしさがテーマになっています。櫛木理宇さんの『鵜頭川村事件』です。
こんな人におすすめ
田舎を舞台にしたパニック小説が読みたい人
続きを読む
 映画『羊たちの沈黙』を初めて見た時の衝撃は、今でもよく覚えています。ヒロイン役のジョディ・フォスターの演技やスリリングなストーリー展開、手に汗握るクライマックスなど見所はたくさんありますが、何と言っても一番インパクトがあるのはアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の存在感でしょう。残虐な猟奇殺人を犯しておきながら人並み外れた知能を持ち、収監されているにも関わらず警察から捜査協力を求められるほどの天才犯罪者。その紳士的でありながら凶悪なキャラクターは、現在に至るまで多くの観客を魅了し続けています。
映画『羊たちの沈黙』を初めて見た時の衝撃は、今でもよく覚えています。ヒロイン役のジョディ・フォスターの演技やスリリングなストーリー展開、手に汗握るクライマックスなど見所はたくさんありますが、何と言っても一番インパクトがあるのはアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の存在感でしょう。残虐な猟奇殺人を犯しておきながら人並み外れた知能を持ち、収監されているにも関わらず警察から捜査協力を求められるほどの天才犯罪者。その紳士的でありながら凶悪なキャラクターは、現在に至るまで多くの観客を魅了し続けています。
現実でこんなことがあるのかどうかは分かりませんが、「犯罪者が獄中から捜査協力する」というシチュエーションはなかなか面白いです。視覚的に映えるからか映画やドラマではよくあるんですが、小説ではあまりないな・・・と思っていたら、最近読んだ小説がまさにそういう設定でした。真梨幸子さんの『ツキマトウ 警視庁ストーカー対策室ゼロ係』です。
こんな人におすすめ
ストーカー犯罪を扱ったイヤミスが読みたい人
続きを読む
 SF作品の中では、しばしば「パラレルワールド」という言葉が登場します。この世界と並行して存在する別の世界のことで、A世界で死んだ人間がB世界では生存していたり、C世界では敵同士だった人間がD世界では恋人同士だったりと、無限のパターンがあります。現実離れした考えと思われがちですが、実は物理学の世界でも存在が議論されるテーマだそうですね。
SF作品の中では、しばしば「パラレルワールド」という言葉が登場します。この世界と並行して存在する別の世界のことで、A世界で死んだ人間がB世界では生存していたり、C世界では敵同士だった人間がD世界では恋人同士だったりと、無限のパターンがあります。現実離れした考えと思われがちですが、実は物理学の世界でも存在が議論されるテーマだそうですね。
「もしあの時、違う選択肢を選んでいたら」・・・そんなifの世界を描くことができる特性上、パラレルワールドを扱った作品はSF分野に偏りがちです。ちなみに私が見た最初のパラレルワールド作品は、アニメ映画『ドラえもん のび太の魔界大冒険』。子ども向けアニメとは思えないくらい練られた世界観と緻密な伏線の張り方が印象的な名作でした。SF方面のパラレルワールド作品は山のようにあるので、今回はちょっと毛色の違う「もう一つの世界」を描いた小説をご紹介します。真梨幸子さんの『向こう側の、ヨーコ』です。
こんな人におすすめ
中年女性の愛憎ミステリーに興味がある人
続きを読む
 誰しも「こういう人間になりたい」という理想があると思います。依存心が強く運動神経ゼロの私の理想は、男性顔負けの戦闘をもこなす強い女性。映画『バイオ・ハザード』シリーズのミラ・ジョヴォヴィッチなんて、まさに理想そのものでした。
誰しも「こういう人間になりたい」という理想があると思います。依存心が強く運動神経ゼロの私の理想は、男性顔負けの戦闘をもこなす強い女性。映画『バイオ・ハザード』シリーズのミラ・ジョヴォヴィッチなんて、まさに理想そのものでした。
映画のキャラクターなどは難しいにしても、理想に向けて邁進する人は素敵です。努力する姿は美しく、周囲の尊敬を集めることでしょう。ですが、あまりに「理想」を追い求めるあまり、「本当の自分」が押し潰されてしまったら・・・?それはもう妄執としか言えないのではないでしょうか。この本を読んで、そんなことを考えました。春口裕子さんの『女優』です。
こんな人におすすめ
女性の嫌な面を扱ったサスペンス小説が読みたい人
続きを読む
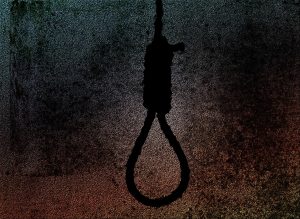 「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
冤罪をテーマにした小説といえば、高野和明さんの『13階段』や大門剛明さんの『テミスの求刑』、ややテイストは違いますが伊坂幸太郎さんの『ゴールデンスランバー』などが有名です。これらの作品の中で犯罪者として告発された人物は、自分は潔白だと訴えていました。では、自らが犯罪者であることは認めた上で、告発された罪の一部が冤罪だと訴えた場合はどうでしょうか?ただでさえ難しい冤罪問題が、より複雑になることは想像に難くありません。今日紹介するのは、櫛木理宇さんの『チェインドッグ』。タイトルの意味も含めて、考えさせられるところの多い作品でした。
こんな人におすすめ
サイコパスが出てくるミステリー小説が読みたい人
続きを読む
 スクールカースト。読んで字のごとく、学校内における人気順位をカースト制度になぞられた言葉です。上位に位置する者ほど発言権が強く、下位の者はクラスの日陰者、どころか下手すればいじめの対象にもなりえます。私の学生時代にも似たような上下関係はありましたが、当時はネットなどがそれほど普及していなかった分、少なくとも校外には逃げ場がありました。今はSNSなどを使えば、最悪の場合、全世界に悪口をばらまかれる可能性もあるわけですから、つくづく怖いなと思います。
スクールカースト。読んで字のごとく、学校内における人気順位をカースト制度になぞられた言葉です。上位に位置する者ほど発言権が強く、下位の者はクラスの日陰者、どころか下手すればいじめの対象にもなりえます。私の学生時代にも似たような上下関係はありましたが、当時はネットなどがそれほど普及していなかった分、少なくとも校外には逃げ場がありました。今はSNSなどを使えば、最悪の場合、全世界に悪口をばらまかれる可能性もあるわけですから、つくづく怖いなと思います。
言葉自体が定着したのは割と最近なような気がしますが、スクールカーストを扱った小説は昔からありました。山田詠美さんの『風葬の教室』など一九八八年の作品ですし、二〇〇三年に芥川賞を受賞した綿谷りささんの『蹴りたい背中』も学校内での人間模様がテーマです。最近では、映画版も話題になった朝井リョウさんの『桐島、部活やめるってよ』などが有名ですね。今回は、私が読んだスクールカーストものの中でもトップ3に入るほど陰惨な作品を紹介します。降田天さんの『女王はかえらない』です。
続きを読む
 昔、家にギリシア神話の本が置いてありました。子ども向けにリライトされたバージョンだったので、私へのプレゼントか何かだったのかもしれません。子ども向けとはいえ当時の私にはショッキングなシーンが多く、驚いた記憶があります。
昔、家にギリシア神話の本が置いてありました。子ども向けにリライトされたバージョンだったので、私へのプレゼントか何かだったのかもしれません。子ども向けとはいえ当時の私にはショッキングなシーンが多く、驚いた記憶があります。
ギリシア神話に限らず、神話はしばしば残酷だったり生臭かったりするものです。それは、かつて神話が教訓や警告の役目を果たしていたからかもしれませんね。恐ろしいといえば、日本神話だって負けてはいませんよ。今日は、日本神話に登場する禍々しい鬼をテーマにした作品を紹介します。団鬼六賞で文壇デビューを果たした小説家、花房観音さんの『黄泉醜女』です。
続きを読む
 インターネットを通じて友達を作った経験はありますか。私自身はというと、趣味や仕事、生活環境について楽しく話せる友達が何人かいます。中には、遠く離れた場所に住んでいたり、生活サイクルが違いすぎたりするため、現実世界ではなかなか知り合えなかったであろう人もいます。そういう相手とでも友達になれることが、インターネットの利点の一つですよね。
インターネットを通じて友達を作った経験はありますか。私自身はというと、趣味や仕事、生活環境について楽しく話せる友達が何人かいます。中には、遠く離れた場所に住んでいたり、生活サイクルが違いすぎたりするため、現実世界ではなかなか知り合えなかったであろう人もいます。そういう相手とでも友達になれることが、インターネットの利点の一つですよね。
ただ、直接会うとなると、インターネット上でやり取りするほど簡単にはいかない場合もあります。それも、オフ会などの複数名がいる場所ではなく、二人きりで会うとしたら・・・その相手に、誰にも知られたくない秘密を知られているとしたら・・・そんな不穏な状況を描いた作品があります。松本清張賞受賞作家、明野照葉さんの『25時のイヴたち』です。
続きを読む
 ウツボカズラという植物をご存知でしょうか。東南アジアに多い食虫植物で、甘い蜜を餌に虫をおびき寄せ、壺のようになった体内に誘い込んで捕食するという習性を持っています。昔、テレビでウツボカズラの内部を調べるという企画を見たことがありますが、凄まじい数の虫を体内にため込んでいて驚いたものです。
ウツボカズラという植物をご存知でしょうか。東南アジアに多い食虫植物で、甘い蜜を餌に虫をおびき寄せ、壺のようになった体内に誘い込んで捕食するという習性を持っています。昔、テレビでウツボカズラの内部を調べるという企画を見たことがありますが、凄まじい数の虫を体内にため込んでいて驚いたものです。
甘い蜜をちらつかせてターゲットを誘い、食らいついて自分のものにしてしまうウツボカズラ。この生態から、ウツボカズラはしばしばフィクションの世界で「悪女」の象徴として登場します。最近の作品では、これを覚えている方が多いのではないでしょうか。二〇一七年に志田未来さん主演でドラマ化もされた、乃南アサさんの『ウツボカズラの夢』です。
続きを読む
 殺人鬼。これほど禍々しい響きを与える言葉ってそうそうないんじゃないでしょうか。「殺人」だけでも十分恐ろしいのに、その後に「鬼」が付くなんて。何より恐ろしいのは、そんな殺人鬼が現実にもしっかり存在することでしょう。
殺人鬼。これほど禍々しい響きを与える言葉ってそうそうないんじゃないでしょうか。「殺人」だけでも十分恐ろしいのに、その後に「鬼」が付くなんて。何より恐ろしいのは、そんな殺人鬼が現実にもしっかり存在することでしょう。
一方、フィクションの世界に登場する殺人鬼は、決して恐ろしいだけの存在ではありません。貴志祐介さん『悪の教典』の蓮見聖司然り、トマス・ハリス『羊たちの沈黙』のレクター博士然り、殺人鬼たちはその残酷さを以て読者を惹きつけます。そんな小説界の殺人鬼名鑑には、彼女の名前も載せるべきでしょう。真梨幸子さんの『殺人鬼フジコの衝動』に登場するフジコです。
続きを読む
 ゆっくりと穏やかな生活を目指す<スローライフ>が注目されるようになったのは、二〇〇年を過ぎた頃かららしいです。同時に、都会の喧騒を離れた田舎暮らしに憧れる人達も増え始めました。この流れを受けたせいでしょうか。最近は田舎暮らしをテーマにした小説でも、<都会から来た主人公が、色々ありながらも近隣住民と絆を作り、困難を乗り越えて田舎暮らしに馴染む>という爽やかな作風のものが多い気がします。
ゆっくりと穏やかな生活を目指す<スローライフ>が注目されるようになったのは、二〇〇年を過ぎた頃かららしいです。同時に、都会の喧騒を離れた田舎暮らしに憧れる人達も増え始めました。この流れを受けたせいでしょうか。最近は田舎暮らしをテーマにした小説でも、<都会から来た主人公が、色々ありながらも近隣住民と絆を作り、困難を乗り越えて田舎暮らしに馴染む>という爽やかな作風のものが多い気がします。
 映画『羊たちの沈黙』を初めて見た時の衝撃は、今でもよく覚えています。ヒロイン役のジョディ・フォスターの演技やスリリングなストーリー展開、手に汗握るクライマックスなど見所はたくさんありますが、何と言っても一番インパクトがあるのはアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の存在感でしょう。残虐な猟奇殺人を犯しておきながら人並み外れた知能を持ち、収監されているにも関わらず警察から捜査協力を求められるほどの天才犯罪者。その紳士的でありながら凶悪なキャラクターは、現在に至るまで多くの観客を魅了し続けています。
映画『羊たちの沈黙』を初めて見た時の衝撃は、今でもよく覚えています。ヒロイン役のジョディ・フォスターの演技やスリリングなストーリー展開、手に汗握るクライマックスなど見所はたくさんありますが、何と言っても一番インパクトがあるのはアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の存在感でしょう。残虐な猟奇殺人を犯しておきながら人並み外れた知能を持ち、収監されているにも関わらず警察から捜査協力を求められるほどの天才犯罪者。その紳士的でありながら凶悪なキャラクターは、現在に至るまで多くの観客を魅了し続けています。 SF作品の中では、しばしば「パラレルワールド」という言葉が登場します。この世界と並行して存在する別の世界のことで、A世界で死んだ人間がB世界では生存していたり、C世界では敵同士だった人間がD世界では恋人同士だったりと、無限のパターンがあります。現実離れした考えと思われがちですが、実は物理学の世界でも存在が議論されるテーマだそうですね。
SF作品の中では、しばしば「パラレルワールド」という言葉が登場します。この世界と並行して存在する別の世界のことで、A世界で死んだ人間がB世界では生存していたり、C世界では敵同士だった人間がD世界では恋人同士だったりと、無限のパターンがあります。現実離れした考えと思われがちですが、実は物理学の世界でも存在が議論されるテーマだそうですね。 誰しも「こういう人間になりたい」という理想があると思います。依存心が強く運動神経ゼロの私の理想は、男性顔負けの戦闘をもこなす強い女性。映画『バイオ・ハザード』シリーズのミラ・ジョヴォヴィッチなんて、まさに理想そのものでした。
誰しも「こういう人間になりたい」という理想があると思います。依存心が強く運動神経ゼロの私の理想は、男性顔負けの戦闘をもこなす強い女性。映画『バイオ・ハザード』シリーズのミラ・ジョヴォヴィッチなんて、まさに理想そのものでした。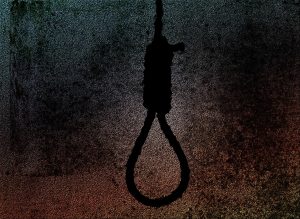 「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。 スクールカースト。読んで字のごとく、学校内における人気順位をカースト制度になぞられた言葉です。上位に位置する者ほど発言権が強く、下位の者はクラスの日陰者、どころか下手すればいじめの対象にもなりえます。私の学生時代にも似たような上下関係はありましたが、当時はネットなどがそれほど普及していなかった分、少なくとも校外には逃げ場がありました。今はSNSなどを使えば、最悪の場合、全世界に悪口をばらまかれる可能性もあるわけですから、つくづく怖いなと思います。
スクールカースト。読んで字のごとく、学校内における人気順位をカースト制度になぞられた言葉です。上位に位置する者ほど発言権が強く、下位の者はクラスの日陰者、どころか下手すればいじめの対象にもなりえます。私の学生時代にも似たような上下関係はありましたが、当時はネットなどがそれほど普及していなかった分、少なくとも校外には逃げ場がありました。今はSNSなどを使えば、最悪の場合、全世界に悪口をばらまかれる可能性もあるわけですから、つくづく怖いなと思います。 昔、家にギリシア神話の本が置いてありました。子ども向けにリライトされたバージョンだったので、私へのプレゼントか何かだったのかもしれません。子ども向けとはいえ当時の私にはショッキングなシーンが多く、驚いた記憶があります。
昔、家にギリシア神話の本が置いてありました。子ども向けにリライトされたバージョンだったので、私へのプレゼントか何かだったのかもしれません。子ども向けとはいえ当時の私にはショッキングなシーンが多く、驚いた記憶があります。 インターネットを通じて友達を作った経験はありますか。私自身はというと、趣味や仕事、生活環境について楽しく話せる友達が何人かいます。中には、遠く離れた場所に住んでいたり、生活サイクルが違いすぎたりするため、現実世界ではなかなか知り合えなかったであろう人もいます。そういう相手とでも友達になれることが、インターネットの利点の一つですよね。
インターネットを通じて友達を作った経験はありますか。私自身はというと、趣味や仕事、生活環境について楽しく話せる友達が何人かいます。中には、遠く離れた場所に住んでいたり、生活サイクルが違いすぎたりするため、現実世界ではなかなか知り合えなかったであろう人もいます。そういう相手とでも友達になれることが、インターネットの利点の一つですよね。 ウツボカズラという植物をご存知でしょうか。東南アジアに多い食虫植物で、甘い蜜を餌に虫をおびき寄せ、壺のようになった体内に誘い込んで捕食するという習性を持っています。昔、テレビでウツボカズラの内部を調べるという企画を見たことがありますが、凄まじい数の虫を体内にため込んでいて驚いたものです。
ウツボカズラという植物をご存知でしょうか。東南アジアに多い食虫植物で、甘い蜜を餌に虫をおびき寄せ、壺のようになった体内に誘い込んで捕食するという習性を持っています。昔、テレビでウツボカズラの内部を調べるという企画を見たことがありますが、凄まじい数の虫を体内にため込んでいて驚いたものです。 殺人鬼。これほど禍々しい響きを与える言葉ってそうそうないんじゃないでしょうか。「殺人」だけでも十分恐ろしいのに、その後に「鬼」が付くなんて。何より恐ろしいのは、そんな殺人鬼が現実にもしっかり存在することでしょう。
殺人鬼。これほど禍々しい響きを与える言葉ってそうそうないんじゃないでしょうか。「殺人」だけでも十分恐ろしいのに、その後に「鬼」が付くなんて。何より恐ろしいのは、そんな殺人鬼が現実にもしっかり存在することでしょう。