 家事。読んで字の如く、掃除・洗濯・食事の支度といった<家の仕事>を指す言葉です。今は家電が発達し、資金に余裕があれば外注という手段もあるとはいえ、細々とした家事の数はそれこそ無限大。不器用で要領の悪い私など、やるべき家事が多い時は、しばらくフリーズして現実逃避に走ることさえあります。
家事。読んで字の如く、掃除・洗濯・食事の支度といった<家の仕事>を指す言葉です。今は家電が発達し、資金に余裕があれば外注という手段もあるとはいえ、細々とした家事の数はそれこそ無限大。不器用で要領の悪い私など、やるべき家事が多い時は、しばらくフリーズして現実逃避に走ることさえあります。
一昔前の<男は外、女は内>という時代では、家事は女性の仕事でした。その影響か、共働きが珍しくもなんともない現代でさえ、女性が家事の中心と見なされる場面が少なくない気がします。当事者同士が納得しているならそれで全然構わないのですが、こういう場合、往々にして家事従事者の方に一方的にしわ寄せが行き、不満を溜めやすいもの。どんな形で家事分担をするにせよ、構成員全員が「自分の家庭の一員である」ことを自覚して行動しないと、取り返しのつかないことになりかねません。この作品を読んで、改めそう実感しました。近藤史恵さんの『山の上の家事学校』です。
こんな人におすすめ
家事をテーマにしたヒューマンストーリーに興味がある人

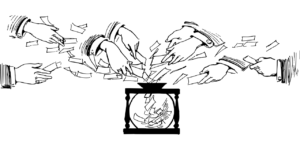 明けましておめでとうございます。毎週水曜更新を基本としている当ブログ、今年は偶然にも一月一日が更新日でした。だからどうというわけではないものの、たまたまこういう記念日に当たると、なんとなく嬉しいものですね。今年も変わらず偏った趣味丸出しの読書レビューを投稿し続けるつもりなので、どうぞよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。毎週水曜更新を基本としている当ブログ、今年は偶然にも一月一日が更新日でした。だからどうというわけではないものの、たまたまこういう記念日に当たると、なんとなく嬉しいものですね。今年も変わらず偏った趣味丸出しの読書レビューを投稿し続けるつもりなので、どうぞよろしくお願いします。 「お気に入りの作品に出てくる土地を見てみたい」「あの作者が愛した店に行ってみたい」。そう願うファンは少なくないと思います。かくいう私もその一人。映画『ロード・オブ・ザ・リングシリーズ』の大ファンでもあるため、お金を貯めて、いつかニュージーランドの撮影地すべてを回るのが生涯の夢です。
「お気に入りの作品に出てくる土地を見てみたい」「あの作者が愛した店に行ってみたい」。そう願うファンは少なくないと思います。かくいう私もその一人。映画『ロード・オブ・ザ・リングシリーズ』の大ファンでもあるため、お金を貯めて、いつかニュージーランドの撮影地すべてを回るのが生涯の夢です。 図書館に入庫された新刊の予約は、一種の戦争だと思っています。人気のある作家さんの最新刊や、映像化された話題作などは、図書館HPに新刊情報が載ると同時に予約が殺到。あっという間に何百人もの待機リストができることも珍しくありません。私はこの手の予約戦争に遅れがちなので、パソコン画面前で何度も「あーあ」とため息をつきました。
図書館に入庫された新刊の予約は、一種の戦争だと思っています。人気のある作家さんの最新刊や、映像化された話題作などは、図書館HPに新刊情報が載ると同時に予約が殺到。あっという間に何百人もの待機リストができることも珍しくありません。私はこの手の予約戦争に遅れがちなので、パソコン画面前で何度も「あーあ」とため息をつきました。 子どもが家から離れ、旅をする。ジュブナイル作品の王道とも言えるシチュエーションです。旅先での出来事を経て子どもが成長していく様子は、文章で読んでも映像で見てもワクワクするものですよね。このジャンルには、スティーブン・キングの『スタンド・バイ・ミー』をはじめ、名作がたくさんあります。
子どもが家から離れ、旅をする。ジュブナイル作品の王道とも言えるシチュエーションです。旅先での出来事を経て子どもが成長していく様子は、文章で読んでも映像で見てもワクワクするものですよね。このジャンルには、スティーブン・キングの『スタンド・バイ・ミー』をはじめ、名作がたくさんあります。 現代には、エンターテインメントが溢れています。漫画に小説、ドラマ、映画、ゲームetc。漫画一つ取っても、紙媒体もあれば電子書籍もありと、その数はまさに無数。この分だと、三年後、五年後には、きっとまた新しい娯楽が誕生していることでしょう。
現代には、エンターテインメントが溢れています。漫画に小説、ドラマ、映画、ゲームetc。漫画一つ取っても、紙媒体もあれば電子書籍もありと、その数はまさに無数。この分だと、三年後、五年後には、きっとまた新しい娯楽が誕生していることでしょう。 私が子どもの頃、オカルト界隈では<ノストラダムスの大予言>が有名でした。最近は名前が出る機会もめっきり減ったので一応解説しておくと、これはフランスの医師兼占星術師であるノストラダムスが書き残した予言のこと。実物は相当な量の詩集なのですが、日本ではその中の第十巻七十二番『一九九九年七の月、空から恐怖の大王が来るだろう』という一文がやたらと広まり、「一九九九年の七月の世界へ滅亡するんだ!」という騒ぎになったのです。実際のところ、ノストラダムス自身は世界滅亡に関する記述は何一つ残しておらず、そもそも詩の和訳が間違っているという指摘すらあるものの、ホラー好きとしては印象深いブームでした。
私が子どもの頃、オカルト界隈では<ノストラダムスの大予言>が有名でした。最近は名前が出る機会もめっきり減ったので一応解説しておくと、これはフランスの医師兼占星術師であるノストラダムスが書き残した予言のこと。実物は相当な量の詩集なのですが、日本ではその中の第十巻七十二番『一九九九年七の月、空から恐怖の大王が来るだろう』という一文がやたらと広まり、「一九九九年の七月の世界へ滅亡するんだ!」という騒ぎになったのです。実際のところ、ノストラダムス自身は世界滅亡に関する記述は何一つ残しておらず、そもそも詩の和訳が間違っているという指摘すらあるものの、ホラー好きとしては印象深いブームでした。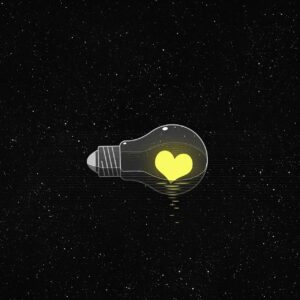 万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・
万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・ <墓>という場所は、石器時代から存在していたそうです。当時はただ遺体を埋めた後に土を盛り上げておいただけのようですが、徐々に形式ができ、宗派による違いも生まれ、現在の形に至りました。故人の魂を労わると同時に、遺された人達の慰めとなる場所は、大昔から必要だったということですね。
<墓>という場所は、石器時代から存在していたそうです。当時はただ遺体を埋めた後に土を盛り上げておいただけのようですが、徐々に形式ができ、宗派による違いも生まれ、現在の形に至りました。故人の魂を労わると同時に、遺された人達の慰めとなる場所は、大昔から必要だったということですね。 小説を読んでいると、しばしば「この話は映像化向きだな」と思うことがあります。動きが派手で、キャラクターの個性が強く、叙述トリック等、文章ならではの技法が使われていない小説がこう言われることが多いですね(一部例外あり)。「これは画面で見てみたい!」と思った小説が実写化された時の喜びは大きいです。
小説を読んでいると、しばしば「この話は映像化向きだな」と思うことがあります。動きが派手で、キャラクターの個性が強く、叙述トリック等、文章ならではの技法が使われていない小説がこう言われることが多いですね(一部例外あり)。「これは画面で見てみたい!」と思った小説が実写化された時の喜びは大きいです。