 他のジャンルがそうであるように、ホラーという分野にも「ブーム」が存在します。ここ最近ヒットしたホラー作品を見る限り、今は「一番怖いのは人間だよ」ブーム。人間の欲望や狂気が引き起こす恐怖は、現実にも起こりそうな臨場感があって怖いですよね。
他のジャンルがそうであるように、ホラーという分野にも「ブーム」が存在します。ここ最近ヒットしたホラー作品を見る限り、今は「一番怖いのは人間だよ」ブーム。人間の欲望や狂気が引き起こす恐怖は、現実にも起こりそうな臨場感があって怖いですよね。
ですが、人外の存在が巻き起こす意味不明な恐怖もまた恐ろしいです。この世の常識が通用せず、ただ「関わってしまったから」という理由で怪異に見舞われる登場人物たち。この手の作風は三津田信三さんがお得意ですが、この方の小説もかなりのものでした。今回取り上げるのは恩田陸さんの『私の家では何も起こらない』。王道をいく幽霊譚が楽しめますよ。
こんな人におすすめ
スタンダードな幽霊屋敷小説を読みたい人
続きを読む
 「この作家さんはこういう作品を書く」というイメージってあると思います。綾辻行人さんなら叙述トリックを駆使した新本格ミステリーだし、瀬尾まいこさんなら心温まる成長物語、唯川恵さんなら女性主人公の恋愛模様etcetc。人それぞれ好きなジャンルがありますから、「これこれこんな物語を読みたい時はこの人の小説がお薦め」という知識があれば、作品選びが楽になります。
「この作家さんはこういう作品を書く」というイメージってあると思います。綾辻行人さんなら叙述トリックを駆使した新本格ミステリーだし、瀬尾まいこさんなら心温まる成長物語、唯川恵さんなら女性主人公の恋愛模様etcetc。人それぞれ好きなジャンルがありますから、「これこれこんな物語を読みたい時はこの人の小説がお薦め」という知識があれば、作品選びが楽になります。
その一方で、「この作家さんってこんな小説も書くんだ!!」と驚かされることもあります。私は『和菓子のアン』『女子的生活』などの爽やかな作風のイメージがあった坂木司さんが、『短劇』『何が困るかって』で意外にブラックな小説も書くと知り、びっくりしたものです。こういう驚きもまた、読書の醍醐味の一つではないでしょうか。びっくりと言えば、芦沢央さんの『火のないところに煙は』。芦沢さんの新境地、楽しませてもらいました。
こんな人におすすめ
実話風ホラー小説が読みたい人
続きを読む
 ホラー好きな私が思うに、怪談話が発生するためにはいくつか条件があります。例えば<過去にその場所で悲惨な出来事が起こっている(ex.遺体発見現場)>だったり<すぐには逃げられないほど無防備になる場所(ex.トイレ)>だったり。意外かもしれませんが、「人の気配を感じる場所である」というのもその一つ。この世はすべて表裏一体、生者がいるからこそ死者がいて、幽霊もいます。簡単に行き来できない無人島が怪談の舞台になりにくいのは、この辺りが原因ではないでしょうか。
ホラー好きな私が思うに、怪談話が発生するためにはいくつか条件があります。例えば<過去にその場所で悲惨な出来事が起こっている(ex.遺体発見現場)>だったり<すぐには逃げられないほど無防備になる場所(ex.トイレ)>だったり。意外かもしれませんが、「人の気配を感じる場所である」というのもその一つ。この世はすべて表裏一体、生者がいるからこそ死者がいて、幽霊もいます。簡単に行き来できない無人島が怪談の舞台になりにくいのは、この辺りが原因ではないでしょうか。
大勢の人の気配を感じるホラースポットの代表格と言えば、やはり「学校」。普段はたくさんの子どもや教職員が出入りして賑やかな分、無人になった時の不気味さが際立ち、多くの怪談話が発生しました。学校を舞台にしたホラー小説といえば、綾辻行人さんの『Another』や辻村深月さんの『冷たい校舎の時は止まる』などが有名です。最近読んだ学園ホラーはこちら。近藤史恵さんの『震える教室』です。
こんな人におすすめ
・学校を舞台にしたホラー小説が好きな人
・ホラー小説デビューしたい人
続きを読む
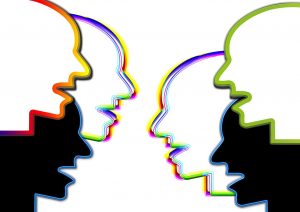 私は創作物に年齢制限を設けることが嫌いです。ですが、大人向けの作品というものはあると思います。これは内容が卑猥だとか残酷だとかいう意味ではなく、「ある程度以上の年月を生きてきた大人だからこそより面白さが理解できる作品」という意味です。
私は創作物に年齢制限を設けることが嫌いです。ですが、大人向けの作品というものはあると思います。これは内容が卑猥だとか残酷だとかいう意味ではなく、「ある程度以上の年月を生きてきた大人だからこそより面白さが理解できる作品」という意味です。
映画『スタンド・バイ・ミー』などその代表格だと思いますし、恩田陸さんの『夜のピクニック』や朱川湊人さんの『花まんま』には、懐かしくノスタルジックな雰囲気が漂っていました。そう言えば私は、小学生の時に観てイマイチだと思った『おもひでぽろぽろ』の面白さが大人になってから分かり、「ああ、年を取るってこういうことか」と実感したものです。ここまで挙げた作品は郷愁を誘う切ないものばかりですので、少し趣の違う「大人向けの作品」を紹介したいと思います。辻村深月さんの『噛みあわない会話と、ある過去について』です。
こんな人におすすめ
いじめやいじりに関する短編集が読みたい人
続きを読む
 古今東西、「鏡」は神秘的なアイテムとして扱われてきました。人や物をそっくりそのまま(正確には逆転した姿ですが)映し出したり、使い方次第で無限に続く空間ができたように見えたりするせいでしょうね。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏から銅鏡を贈られていますし、鏡を奉っている神社も存在します。
古今東西、「鏡」は神秘的なアイテムとして扱われてきました。人や物をそっくりそのまま(正確には逆転した姿ですが)映し出したり、使い方次第で無限に続く空間ができたように見えたりするせいでしょうね。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏から銅鏡を贈られていますし、鏡を奉っている神社も存在します。
ミステリアスな特性のせいか、鏡がキーワードとなる小説は、どこか謎めいたものが多いです。古くは『白雪姫』『鏡の国のアリス』がありますし、梨木香歩さんの『裏庭』、田中芳樹さんの『窓辺には夜の歌』、坂東眞砂子さんの『蛇鏡』などにも不思議な鏡が登場しました。そして、今回ご紹介する秋吉理香子さんの『鏡じかけの夢』。この鏡の不思議さもなかなかのものですよ。
こんな人におすすめ
愛憎絡み合うホラー短編集が読みたい人
続きを読む
 振り返ってみると、私の怖い話好きは小学生の頃から始まっていました。学校の図書室にあった『学校の怪談シリーズ』を次々借り、それが終わると市民図書館で怪談本を探してうろうろうろ・・・「この話を読んだ人の所に〇〇が訪れる」という、いわゆる「自己責任系」の怖い話を読み、怯えて親に泣きついたりしたものです。
振り返ってみると、私の怖い話好きは小学生の頃から始まっていました。学校の図書室にあった『学校の怪談シリーズ』を次々借り、それが終わると市民図書館で怪談本を探してうろうろうろ・・・「この話を読んだ人の所に〇〇が訪れる」という、いわゆる「自己責任系」の怖い話を読み、怯えて親に泣きついたりしたものです。
そんな怖い話好きの私から言わせてもらうと、文章で人を怖がらせるのはとても難しいです。映像なら一瞬で分かる怪異を文章で伝える。だらだら書き連ねればただの説明文だし、あっさり書くと簡潔すぎて何が何だか分からない。そういうハードルを乗り越え、「これは怖い」と読者を震え上がらせるホラー小説もたくさんありますが、今回はその中の一冊を紹介したいと思います。三津田信三さんの『ついてくるもの』です。
こんな人におすすめ
「自分にも起こりそう」と思わせるホラー小説が読みたい人
続きを読む
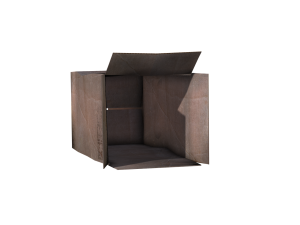 四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。
四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。
新居での生活には期待と不安が付きまとうもの。素晴らしい家を得たならば、新生活はより良いものとなるでしょう。でも、もしその家がおぞましく恐ろしいものだったなら・・・?この作品に登場する一家は、そんな恐ろしい家に住んでしまいます。小池真理子さんの『墓地を見おろす家』です。
続きを読む
 昔、家にギリシア神話の本が置いてありました。子ども向けにリライトされたバージョンだったので、私へのプレゼントか何かだったのかもしれません。子ども向けとはいえ当時の私にはショッキングなシーンが多く、驚いた記憶があります。
昔、家にギリシア神話の本が置いてありました。子ども向けにリライトされたバージョンだったので、私へのプレゼントか何かだったのかもしれません。子ども向けとはいえ当時の私にはショッキングなシーンが多く、驚いた記憶があります。
ギリシア神話に限らず、神話はしばしば残酷だったり生臭かったりするものです。それは、かつて神話が教訓や警告の役目を果たしていたからかもしれませんね。恐ろしいといえば、日本神話だって負けてはいませんよ。今日は、日本神話に登場する禍々しい鬼をテーマにした作品を紹介します。団鬼六賞で文壇デビューを果たした小説家、花房観音さんの『黄泉醜女』です。
続きを読む
 「オカルト」と「科学」、この二つは相反するものと考えられがちです。実際、その手の検証番組などでは、超自然学者と科学者が喧々諤々の討論を繰り広げていたりしますよね。漫画やドラマなどでも、上記の二者は犬猿の仲として描写されることが多い気がします。
「オカルト」と「科学」、この二つは相反するものと考えられがちです。実際、その手の検証番組などでは、超自然学者と科学者が喧々諤々の討論を繰り広げていたりしますよね。漫画やドラマなどでも、上記の二者は犬猿の仲として描写されることが多い気がします。
ですが、この世にオカルトなど絶対存在しないという証明は今のところできていません。それならば、「幽霊」「呪い」といった超常現象も「人類」「進化論」などと同じように科学的に証明できる可能性だってあるわけです。一見、摩訶不思議な超常現象に論理的な解釈ができるとしたら・・・そんな面白い作品を読みました。石持浅海さんの『二歩前を歩く』です。
続きを読む
 実は私、若干閉所恐怖症の気があります。幼稚園の頃、エレベーターに閉じ込められた(実際は私がボタンを押していなかっただけ)経験があるからでしょうか。今でも、閉鎖的な空間はどうも苦手です。
実は私、若干閉所恐怖症の気があります。幼稚園の頃、エレベーターに閉じ込められた(実際は私がボタンを押していなかっただけ)経験があるからでしょうか。今でも、閉鎖的な空間はどうも苦手です。
様々な人間模様が生まれやすいせいか、閉ざされた状況を扱った小説は多いです。有名なのはアガサ・クリスティ『そして誰もいなくなった』に代表されるクローズド・サークルものでしょうか。しかし、「閉鎖空間」とは、何も物理的に移動できないことばかりではありません。移動そのものは可能でも、様々な原因により今の状況から脱することができない・・・そんなシチュエーションもあると思います。今回取り上げるのは、様々な「逃げられない」状況を扱った短編集、現役サラリーマンでもある石持浅海さんの『三階に止まる』です。
続きを読む
 他のジャンルがそうであるように、ホラーという分野にも「ブーム」が存在します。ここ最近ヒットしたホラー作品を見る限り、今は「一番怖いのは人間だよ」ブーム。人間の欲望や狂気が引き起こす恐怖は、現実にも起こりそうな臨場感があって怖いですよね。
他のジャンルがそうであるように、ホラーという分野にも「ブーム」が存在します。ここ最近ヒットしたホラー作品を見る限り、今は「一番怖いのは人間だよ」ブーム。人間の欲望や狂気が引き起こす恐怖は、現実にも起こりそうな臨場感があって怖いですよね。
 「この作家さんはこういう作品を書く」というイメージってあると思います。綾辻行人さんなら叙述トリックを駆使した新本格ミステリーだし、瀬尾まいこさんなら心温まる成長物語、唯川恵さんなら女性主人公の恋愛模様etcetc。人それぞれ好きなジャンルがありますから、「これこれこんな物語を読みたい時はこの人の小説がお薦め」という知識があれば、作品選びが楽になります。
「この作家さんはこういう作品を書く」というイメージってあると思います。綾辻行人さんなら叙述トリックを駆使した新本格ミステリーだし、瀬尾まいこさんなら心温まる成長物語、唯川恵さんなら女性主人公の恋愛模様etcetc。人それぞれ好きなジャンルがありますから、「これこれこんな物語を読みたい時はこの人の小説がお薦め」という知識があれば、作品選びが楽になります。 ホラー好きな私が思うに、怪談話が発生するためにはいくつか条件があります。例えば<過去にその場所で悲惨な出来事が起こっている(ex.遺体発見現場)>だったり<すぐには逃げられないほど無防備になる場所(ex.トイレ)>だったり。意外かもしれませんが、「人の気配を感じる場所である」というのもその一つ。この世はすべて表裏一体、生者がいるからこそ死者がいて、幽霊もいます。簡単に行き来できない無人島が怪談の舞台になりにくいのは、この辺りが原因ではないでしょうか。
ホラー好きな私が思うに、怪談話が発生するためにはいくつか条件があります。例えば<過去にその場所で悲惨な出来事が起こっている(ex.遺体発見現場)>だったり<すぐには逃げられないほど無防備になる場所(ex.トイレ)>だったり。意外かもしれませんが、「人の気配を感じる場所である」というのもその一つ。この世はすべて表裏一体、生者がいるからこそ死者がいて、幽霊もいます。簡単に行き来できない無人島が怪談の舞台になりにくいのは、この辺りが原因ではないでしょうか。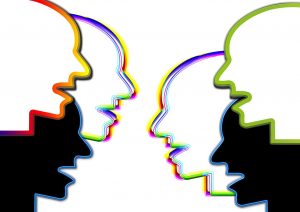 私は創作物に年齢制限を設けることが嫌いです。ですが、大人向けの作品というものはあると思います。これは内容が卑猥だとか残酷だとかいう意味ではなく、「ある程度以上の年月を生きてきた大人だからこそより面白さが理解できる作品」という意味です。
私は創作物に年齢制限を設けることが嫌いです。ですが、大人向けの作品というものはあると思います。これは内容が卑猥だとか残酷だとかいう意味ではなく、「ある程度以上の年月を生きてきた大人だからこそより面白さが理解できる作品」という意味です。 古今東西、「鏡」は神秘的なアイテムとして扱われてきました。人や物をそっくりそのまま(正確には逆転した姿ですが)映し出したり、使い方次第で無限に続く空間ができたように見えたりするせいでしょうね。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏から銅鏡を贈られていますし、鏡を奉っている神社も存在します。
古今東西、「鏡」は神秘的なアイテムとして扱われてきました。人や物をそっくりそのまま(正確には逆転した姿ですが)映し出したり、使い方次第で無限に続く空間ができたように見えたりするせいでしょうね。日本でも、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏から銅鏡を贈られていますし、鏡を奉っている神社も存在します。 振り返ってみると、私の怖い話好きは小学生の頃から始まっていました。学校の図書室にあった『学校の怪談シリーズ』を次々借り、それが終わると市民図書館で怪談本を探してうろうろうろ・・・「この話を読んだ人の所に〇〇が訪れる」という、いわゆる「自己責任系」の怖い話を読み、怯えて親に泣きついたりしたものです。
振り返ってみると、私の怖い話好きは小学生の頃から始まっていました。学校の図書室にあった『学校の怪談シリーズ』を次々借り、それが終わると市民図書館で怪談本を探してうろうろうろ・・・「この話を読んだ人の所に〇〇が訪れる」という、いわゆる「自己責任系」の怖い話を読み、怯えて親に泣きついたりしたものです。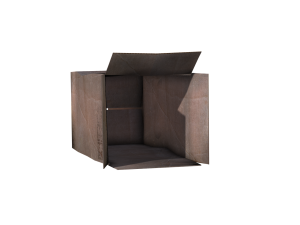 四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。
四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。 昔、家にギリシア神話の本が置いてありました。子ども向けにリライトされたバージョンだったので、私へのプレゼントか何かだったのかもしれません。子ども向けとはいえ当時の私にはショッキングなシーンが多く、驚いた記憶があります。
昔、家にギリシア神話の本が置いてありました。子ども向けにリライトされたバージョンだったので、私へのプレゼントか何かだったのかもしれません。子ども向けとはいえ当時の私にはショッキングなシーンが多く、驚いた記憶があります。 「オカルト」と「科学」、この二つは相反するものと考えられがちです。実際、その手の検証番組などでは、超自然学者と科学者が喧々諤々の討論を繰り広げていたりしますよね。漫画やドラマなどでも、上記の二者は犬猿の仲として描写されることが多い気がします。
「オカルト」と「科学」、この二つは相反するものと考えられがちです。実際、その手の検証番組などでは、超自然学者と科学者が喧々諤々の討論を繰り広げていたりしますよね。漫画やドラマなどでも、上記の二者は犬猿の仲として描写されることが多い気がします。 実は私、若干閉所恐怖症の気があります。幼稚園の頃、エレベーターに閉じ込められた(実際は私がボタンを押していなかっただけ)経験があるからでしょうか。今でも、閉鎖的な空間はどうも苦手です。
実は私、若干閉所恐怖症の気があります。幼稚園の頃、エレベーターに閉じ込められた(実際は私がボタンを押していなかっただけ)経験があるからでしょうか。今でも、閉鎖的な空間はどうも苦手です。