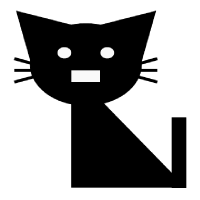<下町>という言葉があります。読んで字の如く、市街地の低地となった部分を指す言葉で、東京では日本橋や浅草、神田などがそれに当たります。また、<下町気質>と言えば、人情味があってお祭り好き、カッとなりやすい所もあるが終わったことは気にしない、面倒見が良くて竹を割ったような性格・・・などが連想されるのではないでしょうか。
<下町>という言葉があります。読んで字の如く、市街地の低地となった部分を指す言葉で、東京では日本橋や浅草、神田などがそれに当たります。また、<下町気質>と言えば、人情味があってお祭り好き、カッとなりやすい所もあるが終わったことは気にしない、面倒見が良くて竹を割ったような性格・・・などが連想されるのではないでしょうか。
独特の文化や気質がある下町は、しばしば物語の舞台に選ばれます。小路幸也さんの『東京バンドワゴンシリーズ』や瀬尾まいこさんの『戸村飯店 青春100連発』など、騒動は起こりつつもどこか心温まる作風が多いような気がしますね。今回は、下町を舞台にしたミステリーをご紹介しようと思います。宮部みゆきさんの『東京下町殺人暮色』です。
こんな人におすすめ
少年が活躍するミステリーが読みたい人
続きを読む
 新年明けましておめでとうございます。令和初のお正月、いかがお過ごしでしょうか。二〇一六年に始まったこのブログは、今年で四年目を迎えます。今後も変わらず独断と偏見に満ちた内容になることが予想されますが、呆れずお付き合いいただければ幸いです。
新年明けましておめでとうございます。令和初のお正月、いかがお過ごしでしょうか。二〇一六年に始まったこのブログは、今年で四年目を迎えます。今後も変わらず独断と偏見に満ちた内容になることが予想されますが、呆れずお付き合いいただければ幸いです。
毎年、新年一作目となる本を何にしようかと悩むのですが、今年は楽しみにしていた図書館の予約本がタイミング良く回ってきたので、悩む必要ありませんでした。二〇二〇年初投稿は、中山七里さんの『死にゆく者の祈り』。ミステリーとしてだけでなく、仏教の在り方についても考えることができ、仏教校出身の私には興味深かったです。
こんな人におすすめ
冤罪が絡んだミステリーが読みたい人
続きを読む
 メリークリスマス!今年もクリスマスがやって来ました。この時期は街のあちこちにクリスマスツリーやリースが飾られ、クリスマスソングが流れます。キリスト教徒でなくても、なんとなくウキウキする人が多いのではないでしょうか。
メリークリスマス!今年もクリスマスがやって来ました。この時期は街のあちこちにクリスマスツリーやリースが飾られ、クリスマスソングが流れます。キリスト教徒でなくても、なんとなくウキウキする人が多いのではないでしょうか。
そんな雰囲気のせいか、クリスマスをテーマにした小説は、心温まるヒューマンストーリーが多いです。チャールズ・ディケンズの『クリスマス・キャロル』はもちろん、有川浩さんの『キャロリング』や伊坂幸太郎さんの『クリスマスを探偵と』、百田尚樹さんの『聖夜の贈り物』など、どれも希望と未来のある名作でした。たぶん、こういうヒューマンストーリーを取り上げるサイトは山ほどあると思うので、ここではあえてブラックな作品を取り上げたいと思います。ジェフリー・ディーヴァーの『クリスマス・プレゼント』です。
こんな人におすすめ
どんでん返しのあるミステリー短編集を読みたい人
続きを読む
 「最近疲れて病んでるんだよね」「あの人、ヤバいよ。壊れてるって」そんな会話を交わしたことがある人も多いのではないでしょうか。<病む>とか<壊れる>とかいう言い方は、気軽に使われることがけっこうあります。私自身、簡単に「めっちゃ病み気味なんだ」とか言っちゃう方かもしれません。
「最近疲れて病んでるんだよね」「あの人、ヤバいよ。壊れてるって」そんな会話を交わしたことがある人も多いのではないでしょうか。<病む>とか<壊れる>とかいう言い方は、気軽に使われることがけっこうあります。私自身、簡単に「めっちゃ病み気味なんだ」とか言っちゃう方かもしれません。
ですが、本当に<病んで><壊れた>人間がいた場合、この言葉はとても重くなります。それは、スティーブヴン・キングの『ミザリー』や五十嵐貴久さんの『リカ』などを読めばよく分かりますね。この短編集にも、それぞれの理由で壊れてしまった女性たちが登場します。柴田よしきさんの『猫と魚、あたしと恋』です。
こんな人におすすめ
女性中心の心理サスペンス小説が読みたい人
続きを読む
 サスペンス、ホラー、ハードボイルドなどの創作物の場合、<なぜそういう状況になったのか>という設定作りが重要です。登場人物たちは日常とはかけ離れた世界に身を投じるわけですから、あまりにぶっ飛んだシチュエーションだと、読者が感情移入できません。例えばパニックアクション作品で<大災害>という設定を持ってくると、「確かに、こういう非常事態が起こったら、人間はこういう行動を取るかもな」と想像しやすいわけです。
サスペンス、ホラー、ハードボイルドなどの創作物の場合、<なぜそういう状況になったのか>という設定作りが重要です。登場人物たちは日常とはかけ離れた世界に身を投じるわけですから、あまりにぶっ飛んだシチュエーションだと、読者が感情移入できません。例えばパニックアクション作品で<大災害>という設定を持ってくると、「確かに、こういう非常事態が起こったら、人間はこういう行動を取るかもな」と想像しやすいわけです。
こうした設定の王道パターンとして<復讐>があります。自分自身や大事な相手が傷つけられ、その復讐のため過酷な世界に身を投じる主人公。こういう状況は読者の同情を集め、主人公が道に外れた行いをしても「あれだけのことをされたんだから、気持ちは分かる」と共感されます。『巌窟王』や『嵐が丘』が今なお世界的名作として読み継がれているのは、そんな理由があるからかもしれません。最近読んだ小説も、一人の女性の悲しい復讐劇でした。秋吉理香子さんの『灼熱』です。
こんな人におすすめ
愛憎絡んだサスペンス小説が読みたい人
続きを読む
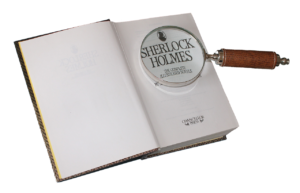 私は学生時代、家庭教師を付けていたことがあります。相手は大学生の女性で、勉強だけでなくプライベートの話も色々することができました。ああいうやり取りは、塾ではできないものだったでしょう。
私は学生時代、家庭教師を付けていたことがあります。相手は大学生の女性で、勉強だけでなくプライベートの話も色々することができました。ああいうやり取りは、塾ではできないものだったでしょう。
家に招き入れるという性質上、家庭教師と生徒の距離は、学校や塾のそれより近くなりがちですし、時に家庭内のトラブルに関わることもあり得ます。いい師弟関係を築ければ最高ですが、家庭教師という存在が家の中に思わぬ波紋を呼ぶこともないとは言い切れません。本間洋平さんの『家族ゲーム』では、強烈な家庭教師が一つの家族を揺るがす様を描いていました。では、この家庭教師はどうでしょうか。坂木司さんの『先生と僕』です。
こんな人におすすめ
利発な少年が登場するコージーミステリーが読みたい人
続きを読む
 「学生時代の内、一番楽しかったのはいつ?」と聞かれたら、私は「高校時代」と答えます。中学時代はぎすぎすしていて大変なことの方が多かったし、大学時代は格段に自由が増えた分、密度は薄まったかな、というのが正直な感想。その点、高校時代はそれなりに濃密ではあったけど、中学校ほど息苦しくなく、振り返ってみると楽しい思い出の方が多いです。
「学生時代の内、一番楽しかったのはいつ?」と聞かれたら、私は「高校時代」と答えます。中学時代はぎすぎすしていて大変なことの方が多かったし、大学時代は格段に自由が増えた分、密度は薄まったかな、というのが正直な感想。その点、高校時代はそれなりに濃密ではあったけど、中学校ほど息苦しくなく、振り返ってみると楽しい思い出の方が多いです。
中学生ほど子どもではないけれど、まだ大人には程遠い。高校時代を扱った小説は、そんな不安定さをテーマにしたものが多いです。ジャンルも幅広く、部活動を題材にしたものなら平田オリザさんの『幕が上がる』や誉田哲也さんの『武士道シックスティーン』、ミステリーなら今邑彩さんの『そして誰もいなくなる』や辻村深月さんの『名前探しの放課後』、ホラー寄りなら秋吉理香子さんの『暗黒女子』や恩田陸さんの『六番目の小夜子』などなど、映像化された作品も少なくありません。当ブログではミステリーやサスペンス系の作品を取り上げることが多いので、今回は少し趣向を変え、恋愛小説をご紹介したいと思います。山田詠美さんの『放課後の音符(キイノート)』です。
こんな人におすすめ
女子高生の恋愛模様を読みたい人
続きを読む
 雑誌やインターネットの悩み相談コーナーを見ていると、しばしば<マウンティング>という言葉を目にします。本来は馬乗りになって相手を押さえ込む状態を指しますが、昨今は<自分の方が周囲より幸福>とランク付けし、それを主張するという意味で使われることが多いです。ファッション業界を舞台にしたドラマ『ファーストクラス』に登場したことがきっかけで広まり、流行語大賞にもノミネートされましたね。
雑誌やインターネットの悩み相談コーナーを見ていると、しばしば<マウンティング>という言葉を目にします。本来は馬乗りになって相手を押さえ込む状態を指しますが、昨今は<自分の方が周囲より幸福>とランク付けし、それを主張するという意味で使われることが多いです。ファッション業界を舞台にしたドラマ『ファーストクラス』に登場したことがきっかけで広まり、流行語大賞にもノミネートされましたね。
我が身と他人を比較することは、必ずしも悪いことではありません。場合によっては、比較することで発奮したり、頭が冷えたりすることもあるでしょう。ですが、自分の方が幸せだと優越感を抱き、他人を見下すようになれば、それは傲慢というものです。今日ご紹介するのは、宮西真冬さんの『誰かが見ている』。女性のマウンティングの怖さを味わえました。
こんな人におすすめ
女性目線の心理サスペンスが読みたい人
続きを読む
 昔、私は2ちゃんねる(現5ちゃんねる)が好きで、手持無沙汰な時間にちょこちょこ覗いていました。以前と比べると頻度が落ちましたが、唯一、<後味の悪い話>というスレッドのみ、今も定期的に進行をチェックしています。タイトルが示す通り、自分の知っている後味の悪い話を投稿するスレッドで、実体験・小説・映画・アニメなどジャンルは不問。イヤミス好きな私の心をくすぐる投稿も多く、ここでこれから読む本を見つけることもありました。
昔、私は2ちゃんねる(現5ちゃんねる)が好きで、手持無沙汰な時間にちょこちょこ覗いていました。以前と比べると頻度が落ちましたが、唯一、<後味の悪い話>というスレッドのみ、今も定期的に進行をチェックしています。タイトルが示す通り、自分の知っている後味の悪い話を投稿するスレッドで、実体験・小説・映画・アニメなどジャンルは不問。イヤミス好きな私の心をくすぐる投稿も多く、ここでこれから読む本を見つけることもありました。
このスレッドを見ていてつくづく思うのは、「後味の悪い話を簡潔かつ面白くまとめるのって難しいな」ということです。もちろん、どんな話だって難しいんでしょうが、後味の悪い話の場合、内容が重苦しい分、だらだら文章を書き連ねると<読みにくい><中身が暗い>のダブルパンチでウンザリ度合も上がるというか・・・真梨幸子さんや櫛木理宇さんのようなどんより暗い長編イヤミス作品も大好きですが、コンパクトで切れ味鋭い短編イヤミスを見つけた時は嬉しさもひとしおです。今回は、そんな短くも後味悪い小説を集めた短編集を取り上げたいと思います。誉田哲也さんの『あなたの本』です。
こんな人におすすめ
『世にも奇妙な物語』のような短編小説が読みたい人
続きを読む
 昨今は近所付き合いが希薄な世の中だと言われています。私自身、生まれてから今まで何度か引っ越しを経験しましたが、隣近所と親しく付き合った経験は皆無。せいぜい顔を知っている程度だったり、最初から最後まで隣人と一度も顔を合わせないままだったことさえあります。
昨今は近所付き合いが希薄な世の中だと言われています。私自身、生まれてから今まで何度か引っ越しを経験しましたが、隣近所と親しく付き合った経験は皆無。せいぜい顔を知っている程度だったり、最初から最後まで隣人と一度も顔を合わせないままだったことさえあります。
もっとも、「どんな人なのかよく分からない」というのは、何も近所付き合いに限った話ではありません。親子、兄弟姉妹、友達、恋人、夫婦・・・どれだけ近い関係でも、いえ、近い関係だからこそ、相手の本性や本音が分からなくなることは多々あります。今回ご紹介するのは永井するみさんの『隣人』。身近な人の知られざる一面にゾクッとさせられました。
こんな人におすすめ
イヤ~なサスペンス短編集が読みたい人
続きを読む
 <下町>という言葉があります。読んで字の如く、市街地の低地となった部分を指す言葉で、東京では日本橋や浅草、神田などがそれに当たります。また、<下町気質>と言えば、人情味があってお祭り好き、カッとなりやすい所もあるが終わったことは気にしない、面倒見が良くて竹を割ったような性格・・・などが連想されるのではないでしょうか。
<下町>という言葉があります。読んで字の如く、市街地の低地となった部分を指す言葉で、東京では日本橋や浅草、神田などがそれに当たります。また、<下町気質>と言えば、人情味があってお祭り好き、カッとなりやすい所もあるが終わったことは気にしない、面倒見が良くて竹を割ったような性格・・・などが連想されるのではないでしょうか。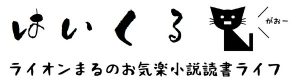
 新年明けましておめでとうございます。令和初のお正月、いかがお過ごしでしょうか。二〇一六年に始まったこのブログは、今年で四年目を迎えます。今後も変わらず独断と偏見に満ちた内容になることが予想されますが、呆れずお付き合いいただければ幸いです。
新年明けましておめでとうございます。令和初のお正月、いかがお過ごしでしょうか。二〇一六年に始まったこのブログは、今年で四年目を迎えます。今後も変わらず独断と偏見に満ちた内容になることが予想されますが、呆れずお付き合いいただければ幸いです。 メリークリスマス!今年もクリスマスがやって来ました。この時期は街のあちこちにクリスマスツリーやリースが飾られ、クリスマスソングが流れます。キリスト教徒でなくても、なんとなくウキウキする人が多いのではないでしょうか。
メリークリスマス!今年もクリスマスがやって来ました。この時期は街のあちこちにクリスマスツリーやリースが飾られ、クリスマスソングが流れます。キリスト教徒でなくても、なんとなくウキウキする人が多いのではないでしょうか。 「最近疲れて病んでるんだよね」「あの人、ヤバいよ。壊れてるって」そんな会話を交わしたことがある人も多いのではないでしょうか。<病む>とか<壊れる>とかいう言い方は、気軽に使われることがけっこうあります。私自身、簡単に「めっちゃ病み気味なんだ」とか言っちゃう方かもしれません。
「最近疲れて病んでるんだよね」「あの人、ヤバいよ。壊れてるって」そんな会話を交わしたことがある人も多いのではないでしょうか。<病む>とか<壊れる>とかいう言い方は、気軽に使われることがけっこうあります。私自身、簡単に「めっちゃ病み気味なんだ」とか言っちゃう方かもしれません。 サスペンス、ホラー、ハードボイルドなどの創作物の場合、<なぜそういう状況になったのか>という設定作りが重要です。登場人物たちは日常とはかけ離れた世界に身を投じるわけですから、あまりにぶっ飛んだシチュエーションだと、読者が感情移入できません。例えばパニックアクション作品で<大災害>という設定を持ってくると、「確かに、こういう非常事態が起こったら、人間はこういう行動を取るかもな」と想像しやすいわけです。
サスペンス、ホラー、ハードボイルドなどの創作物の場合、<なぜそういう状況になったのか>という設定作りが重要です。登場人物たちは日常とはかけ離れた世界に身を投じるわけですから、あまりにぶっ飛んだシチュエーションだと、読者が感情移入できません。例えばパニックアクション作品で<大災害>という設定を持ってくると、「確かに、こういう非常事態が起こったら、人間はこういう行動を取るかもな」と想像しやすいわけです。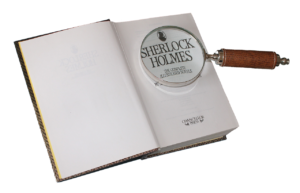 私は学生時代、家庭教師を付けていたことがあります。相手は大学生の女性で、勉強だけでなくプライベートの話も色々することができました。ああいうやり取りは、塾ではできないものだったでしょう。
私は学生時代、家庭教師を付けていたことがあります。相手は大学生の女性で、勉強だけでなくプライベートの話も色々することができました。ああいうやり取りは、塾ではできないものだったでしょう。 「学生時代の内、一番楽しかったのはいつ?」と聞かれたら、私は「高校時代」と答えます。中学時代はぎすぎすしていて大変なことの方が多かったし、大学時代は格段に自由が増えた分、密度は薄まったかな、というのが正直な感想。その点、高校時代はそれなりに濃密ではあったけど、中学校ほど息苦しくなく、振り返ってみると楽しい思い出の方が多いです。
「学生時代の内、一番楽しかったのはいつ?」と聞かれたら、私は「高校時代」と答えます。中学時代はぎすぎすしていて大変なことの方が多かったし、大学時代は格段に自由が増えた分、密度は薄まったかな、というのが正直な感想。その点、高校時代はそれなりに濃密ではあったけど、中学校ほど息苦しくなく、振り返ってみると楽しい思い出の方が多いです。 雑誌やインターネットの悩み相談コーナーを見ていると、しばしば<マウンティング>という言葉を目にします。本来は馬乗りになって相手を押さえ込む状態を指しますが、昨今は<自分の方が周囲より幸福>とランク付けし、それを主張するという意味で使われることが多いです。ファッション業界を舞台にしたドラマ『ファーストクラス』に登場したことがきっかけで広まり、流行語大賞にもノミネートされましたね。
雑誌やインターネットの悩み相談コーナーを見ていると、しばしば<マウンティング>という言葉を目にします。本来は馬乗りになって相手を押さえ込む状態を指しますが、昨今は<自分の方が周囲より幸福>とランク付けし、それを主張するという意味で使われることが多いです。ファッション業界を舞台にしたドラマ『ファーストクラス』に登場したことがきっかけで広まり、流行語大賞にもノミネートされましたね。 昔、私は2ちゃんねる(現5ちゃんねる)が好きで、手持無沙汰な時間にちょこちょこ覗いていました。以前と比べると頻度が落ちましたが、唯一、<後味の悪い話>というスレッドのみ、今も定期的に進行をチェックしています。タイトルが示す通り、自分の知っている後味の悪い話を投稿するスレッドで、実体験・小説・映画・アニメなどジャンルは不問。イヤミス好きな私の心をくすぐる投稿も多く、ここでこれから読む本を見つけることもありました。
昔、私は2ちゃんねる(現5ちゃんねる)が好きで、手持無沙汰な時間にちょこちょこ覗いていました。以前と比べると頻度が落ちましたが、唯一、<後味の悪い話>というスレッドのみ、今も定期的に進行をチェックしています。タイトルが示す通り、自分の知っている後味の悪い話を投稿するスレッドで、実体験・小説・映画・アニメなどジャンルは不問。イヤミス好きな私の心をくすぐる投稿も多く、ここでこれから読む本を見つけることもありました。 昨今は近所付き合いが希薄な世の中だと言われています。私自身、生まれてから今まで何度か引っ越しを経験しましたが、隣近所と親しく付き合った経験は皆無。せいぜい顔を知っている程度だったり、最初から最後まで隣人と一度も顔を合わせないままだったことさえあります。
昨今は近所付き合いが希薄な世の中だと言われています。私自身、生まれてから今まで何度か引っ越しを経験しましたが、隣近所と親しく付き合った経験は皆無。せいぜい顔を知っている程度だったり、最初から最後まで隣人と一度も顔を合わせないままだったことさえあります。