 子どもという存在は無邪気なもの、裏表なく素直なもの・・・そんなイメージを抱いている人は多いでしょうし、実際にそういう面もあります。しかし、油断は禁物です。無邪気さや素直さは、残酷さや遠慮のなさに繋がるもの。「なんでそんなことをしてしまったの」と大人を唖然とさせる子どもは、現実にも存在します。
子どもという存在は無邪気なもの、裏表なく素直なもの・・・そんなイメージを抱いている人は多いでしょうし、実際にそういう面もあります。しかし、油断は禁物です。無邪気さや素直さは、残酷さや遠慮のなさに繋がるもの。「なんでそんなことをしてしまったの」と大人を唖然とさせる子どもは、現実にも存在します。
この手の<残酷な子ども>を描いた作品で私が一番衝撃を受けたのは、S.キングの『トウモロコシ畑の子どもたち』とスペインのホラー映画『ザ・チャイルド』。集団で襲って来る子どもたちと、訳も分からぬまま惨殺されていく大人たちの描写が凄惨で、しばらく呆然としてしまいました。この二作品はグロテスクな部分が多く、かなり人を選ぶと思うので、今回はもう少しマイルドな<怖い子どもたち>を紹介したいと思います。赤川次郎さんの『充ち足りた悪漢たち』です。
こんな人におすすめ
子どもの恐ろしさをテーマにした短編集が読みたい人

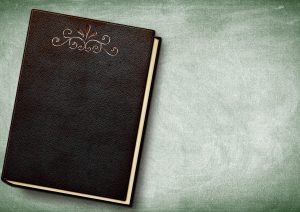 芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。
芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。 テレビや新聞のニュースを見ていると、数日と置かずして家庭内暴力に関する事件が目に付きます。言葉の使用法としては、配偶者への暴力を<ドメスティックバイオレンス>、子どもへの暴力を<児童虐待>と使い分けるんだとか。もちろん、暴力は誰に対してだろうと悪いことなのですが、腕力のない女性や子どもが犠牲になると、「許せない」という気持ちが一層強まります。
テレビや新聞のニュースを見ていると、数日と置かずして家庭内暴力に関する事件が目に付きます。言葉の使用法としては、配偶者への暴力を<ドメスティックバイオレンス>、子どもへの暴力を<児童虐待>と使い分けるんだとか。もちろん、暴力は誰に対してだろうと悪いことなのですが、腕力のない女性や子どもが犠牲になると、「許せない」という気持ちが一層強まります。 <超能力の例を一つ挙げてみなさい>と言われたら、どんな能力が出て来るでしょうか。口から言葉を発せずに意思を伝えるテレパシー、視界に入らないはずの出来事を見る透視能力、手を使わずに物を動かす念動力・・・どれもこれも有名な能力ですが、それらと並んで知名度が高いのが<予知能力>です。文字通り、その時点で起こっていない出来事を予め知る力のことで、かの有名なノストラダムスもこの能力の持ち主として知られています。
<超能力の例を一つ挙げてみなさい>と言われたら、どんな能力が出て来るでしょうか。口から言葉を発せずに意思を伝えるテレパシー、視界に入らないはずの出来事を見る透視能力、手を使わずに物を動かす念動力・・・どれもこれも有名な能力ですが、それらと並んで知名度が高いのが<予知能力>です。文字通り、その時点で起こっていない出来事を予め知る力のことで、かの有名なノストラダムスもこの能力の持ち主として知られています。 私は基本的にどんなジャンルの小説も読む人間です。切なくも甘酸っぱい青春ラブコメだろうと、血飛沫が飛び内臓はみ出るスプラッターホラーだろうと、面白ければ何でもOK。そんな私が唯一、「なんとなくとっつきにくいかな」と思うジャンル、それが金融・経済小説です。根っからの文系人間のせいか、用語や世界観がなかなか頭に入ってこないんです。
私は基本的にどんなジャンルの小説も読む人間です。切なくも甘酸っぱい青春ラブコメだろうと、血飛沫が飛び内臓はみ出るスプラッターホラーだろうと、面白ければ何でもOK。そんな私が唯一、「なんとなくとっつきにくいかな」と思うジャンル、それが金融・経済小説です。根っからの文系人間のせいか、用語や世界観がなかなか頭に入ってこないんです。 ホラー作品は、大きく分けて二つのタイプがあると思います。それは<自業自得>系と<理不尽>系。前者は、恐怖体験をする原因が(善意悪意は問わず)自分自身にあるタイプで、五十嵐貴久さんの『リカ』や今邑彩さんの『赤いべべ着せよ・・・』などがこれに当たります。
ホラー作品は、大きく分けて二つのタイプがあると思います。それは<自業自得>系と<理不尽>系。前者は、恐怖体験をする原因が(善意悪意は問わず)自分自身にあるタイプで、五十嵐貴久さんの『リカ』や今邑彩さんの『赤いべべ着せよ・・・』などがこれに当たります。 今までこのブログでは、<怖い女>が登場する小説をたくさん取り上げてきました。別に狙ったわけではありませんが、それらの小説の大半は、作者が女性だった気がします。女性作家の手で綴られる女の狂気や愛憎の恐ろしさはやはり格別。読んでいて鳥肌が立ちそうになることすらあるほどです。
今までこのブログでは、<怖い女>が登場する小説をたくさん取り上げてきました。別に狙ったわけではありませんが、それらの小説の大半は、作者が女性だった気がします。女性作家の手で綴られる女の狂気や愛憎の恐ろしさはやはり格別。読んでいて鳥肌が立ちそうになることすらあるほどです。 今更言うまでもない話ですが、殺人という犯罪は多くのものを奪っていきます。被害者本人の命や尊厳はもちろん、その家族の人生をも大きく揺るがし、ひっくり返し、時に破壊してしまうことすらあり得ます。昔見たドラマで、息子を殺された父親が言っていた「家族全員殺されたようなものだ」という台詞は、決して大げさなものではないのでしょう。
今更言うまでもない話ですが、殺人という犯罪は多くのものを奪っていきます。被害者本人の命や尊厳はもちろん、その家族の人生をも大きく揺るがし、ひっくり返し、時に破壊してしまうことすらあり得ます。昔見たドラマで、息子を殺された父親が言っていた「家族全員殺されたようなものだ」という台詞は、決して大げさなものではないのでしょう。 季節は夏真っ盛り。この時期は全国各地で楽しいイベントが催され、どことなく明るいムードがそこここに漂います。夏という季節は私達に活気をもたらしますが、同時に、胸を打つ悲しい事実をもまた思い起こさせます。それが戦争です。
季節は夏真っ盛り。この時期は全国各地で楽しいイベントが催され、どことなく明るいムードがそこここに漂います。夏という季節は私達に活気をもたらしますが、同時に、胸を打つ悲しい事実をもまた思い起こさせます。それが戦争です。 以前、別作品のレビューで、「<家>という場所には、人をとらえるイメージもある」と書きました。一説によると、<家>は<宀(家)>と<豕(豚)>が組み合わさってできた漢字であり、<豚などの家畜を生贄に捧げた呪法的な護りのある場所>という意味があるんだとか。どの程度信憑性がある話かは分かりませんが、もしこれが本当なら、<家>がホラーやミステリーの舞台になりやすいのも納得です。
以前、別作品のレビューで、「<家>という場所には、人をとらえるイメージもある」と書きました。一説によると、<家>は<宀(家)>と<豕(豚)>が組み合わさってできた漢字であり、<豚などの家畜を生贄に捧げた呪法的な護りのある場所>という意味があるんだとか。どの程度信憑性がある話かは分かりませんが、もしこれが本当なら、<家>がホラーやミステリーの舞台になりやすいのも納得です。