 <シリアルキラー>という言葉が使われ出したのは、一九八四年、捜査関係者がアメリカの連続殺人鬼テッド・バンディを指して言ったことが始まりだそうです。意味は、何らかの心理的欲求のもと、長期間に渡って殺人を繰り返す連続殺人犯のこと。<serial=続きの>という言葉が示す通り、複数の犠牲者を出すことがシリアルキラーの定義とされています。
<シリアルキラー>という言葉が使われ出したのは、一九八四年、捜査関係者がアメリカの連続殺人鬼テッド・バンディを指して言ったことが始まりだそうです。意味は、何らかの心理的欲求のもと、長期間に渡って殺人を繰り返す連続殺人犯のこと。<serial=続きの>という言葉が示す通り、複数の犠牲者を出すことがシリアルキラーの定義とされています。
シリアルキラーが小説に登場するパターンとして一番多いのは、<犯行を繰り返す殺人鬼vs犯人と戦う善人>ではないでしょうか。トマス・ハリスの『羊たちの沈黙』はこの典型的なケースですし、貴志祐介さんの『悪の教典』や宮部みゆきさんの『模倣犯』などもこれに当たります。今回取り上げる作品もそのパターン・・・と思っていたら、ちょっと予想外の展開を迎えました。中山七里さんの『隣はシリアルキラー』です。
こんな人におすすめ
連続殺人が出てくるサスペンスミステリーが読みたい人
続きを読む
 <心中>とはもともと<真心>を意味する言葉であり、転じて<男女が相手に真心を尽くし、愛を貫くこと>を意味するようになったそうです。それがさらに変化し、何物にも邪魔をされない究極の愛の行為として、男女が一緒に死ぬことを指すようになったんだとか。一家心中、無理心中、ネット心中など、一言で<心中>と言っても様々ですが、言葉のイメージとして一番世間に浸透しているのは、上記のケースだと思います。
<心中>とはもともと<真心>を意味する言葉であり、転じて<男女が相手に真心を尽くし、愛を貫くこと>を意味するようになったそうです。それがさらに変化し、何物にも邪魔をされない究極の愛の行為として、男女が一緒に死ぬことを指すようになったんだとか。一家心中、無理心中、ネット心中など、一言で<心中>と言っても様々ですが、言葉のイメージとして一番世間に浸透しているのは、上記のケースだと思います。
かつては幕府が厳しく禁じるほど社会的注目を集めたテーマであり、必然的に心中を扱った作品もたくさん生まれました。江戸時代には<心中物>というジャンルが存在しましたし、現代でも石田衣良さんの『親指の恋人』や渡辺淳一さんの『失楽園』というように、心中がキーワードとなった小説は多いです。そして、恋愛小説では恋人同士の愛の形として扱われる<心中>ですが、ミステリーやホラーだと今後の事件への布石となるパターンが多いですよね。今回ご紹介するのは、長江俊和さんの『出版禁止』。この方の謎の仕掛け方、やっぱり好きだなぁ。
こんな人におすすめ
ノンフィクション風ミステリーが好きな人
続きを読む
 医療問題は総じてデリケートなものですが、中でも臓器移植問題の複雑さは群を抜いています。「虫歯になったら歯医者に行こう」とは言えても「病気になったら臓器移植を受けよう」とはなかなか言えるものではありません。理由は色々あるけれど、その中の一つは<臓器提供が行われる=提供者は体にメスを入れて臓器を摘出されている、場合によっては死んでいる>からではないでしょうか。病気や怪我なら仕方ないが、五体満足の体を開いて内臓を取り出すなんて不自然だ、親しい身内ならともかく他人のために手術なんて受けたくない、臓器移植を待つということはどこかの誰かが死ぬのを待つことではないか・・・そういったネガティブな考え方があるのが現実です。
医療問題は総じてデリケートなものですが、中でも臓器移植問題の複雑さは群を抜いています。「虫歯になったら歯医者に行こう」とは言えても「病気になったら臓器移植を受けよう」とはなかなか言えるものではありません。理由は色々あるけれど、その中の一つは<臓器提供が行われる=提供者は体にメスを入れて臓器を摘出されている、場合によっては死んでいる>からではないでしょうか。病気や怪我なら仕方ないが、五体満足の体を開いて内臓を取り出すなんて不自然だ、親しい身内ならともかく他人のために手術なんて受けたくない、臓器移植を待つということはどこかの誰かが死ぬのを待つことではないか・・・そういったネガティブな考え方があるのが現実です。
しかし、どれだけ否定的な意見が出ようと、自分自身や大切な人が臓器移植を待つ身となれば、誰だって手術を望むでしょう。こうしたアンビバレントな状況から、臓器移植はフィクション界でも常に注目されるテーマです。私が初めて読んだ臓器移植に関する小説は、貫井徳郎さんの『転生』でした。どうしても重くなりがちな題材を、後味の良いラブストーリー&ミステリーに仕上げた良作でしたよ。では、最近読んだこの作品はどうでしょうか。中山七里さんの『カインの傲慢』です。
こんな人におすすめ
臓器移植が絡んだミステリーが読みたい人
続きを読む
 何をもってその作品を好きと思うか。基準は人それぞれです。ストーリーが何より大事と言う人もいれば、その作家さんの作品なら何でも読んでみるという人もいるでしょう。タイトルや挿絵に重きを置く人だっているかもしれません。<登場人物>もその一つ。「このキャラ大好き」「この人が主人公なら続編も読んでみよう」。そうやって読む本を決めることって、案外多いのではないでしょうか。
何をもってその作品を好きと思うか。基準は人それぞれです。ストーリーが何より大事と言う人もいれば、その作家さんの作品なら何でも読んでみるという人もいるでしょう。タイトルや挿絵に重きを置く人だっているかもしれません。<登場人物>もその一つ。「このキャラ大好き」「この人が主人公なら続編も読んでみよう」。そうやって読む本を決めることって、案外多いのではないでしょうか。
小説界の人気キャラといえば、私が真っ先に思い浮かべるのは有栖川有栖さんの『作家アリスシリーズ』に出てくる火村英生と、森博嗣さんの『S&Mシリーズ』に出てくる犀川創平。どちらもコミカライズや映像化されている人気作品なので、ご存知の方も多いと思います。私も二人とも大好きですが、ここ数年で、彼らをしのぐほど好きなキャラクターと出会ってしまいました。中山七里さんの『毒島刑事最後の事件』に登場する毒島真理です。
こんな人におすすめ
皮肉の効いたミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 自慢して言うようなことではありませんが、私は単純な人間です。物事の裏側を読んだり、水面下に秘められた事実を察するというのが苦手。おかげで昔からさんざん「鈍い」「KY」と言われたものです。
自慢して言うようなことではありませんが、私は単純な人間です。物事の裏側を読んだり、水面下に秘められた事実を察するというのが苦手。おかげで昔からさんざん「鈍い」「KY」と言われたものです。
ですが、読書においては、鈍感さが役立ったこともあります。どんでん返しが仕掛けられた小説を読む時、作中の手がかりからオチを見抜くという器用さが全然ないため、真相判明時にはいつも特大のビックリを味わえるのです。綾辻行人さんの『十角館の殺人』や歌野晶午さんの『葉桜の季節に君を想うということ』の真相を知った時なんて、本当に「ええーっ!?」と声に出して驚いたものだっけ。今回ご紹介する作品にも、世界がひっくり返るようなどんでん返しが用意されていました。長江俊和さんの『出版禁止 死刑囚の歌』です。
こんな人におすすめ
・ノンフィクション風ミステリーが読みたい人
・どんでん返しが仕掛けられた小説が好きな人
続きを読む
 結婚については、世界各国の偉人達が様々な名言を残しています。「人類は太古の昔から、帰りが遅いと心配してくれる人を必要としている」と言ったのはマーガレット・ミード、「右の靴は左足には合わない。でも両方ないと一足とは言えない」と言ったのは山本有三、「あなたがもし孤独を恐れるならば、結婚すべきではない」と言ったのはチェーホフ、「恋は人を盲目にするが、結婚は視力を戻してくれる」と言ったのはリヒテンベルクです。温かいものもあれば皮肉の効いたものもありますが、そもそも結婚自体、良い面と悪い面の両方を持つものなのでしょう。
結婚については、世界各国の偉人達が様々な名言を残しています。「人類は太古の昔から、帰りが遅いと心配してくれる人を必要としている」と言ったのはマーガレット・ミード、「右の靴は左足には合わない。でも両方ないと一足とは言えない」と言ったのは山本有三、「あなたがもし孤独を恐れるならば、結婚すべきではない」と言ったのはチェーホフ、「恋は人を盲目にするが、結婚は視力を戻してくれる」と言ったのはリヒテンベルクです。温かいものもあれば皮肉の効いたものもありますが、そもそも結婚自体、良い面と悪い面の両方を持つものなのでしょう。
現実の結婚が幸福なものであってほしいのは言うまでもありませんが、フィクションの世界ならば、結婚にまつわるトラブルは物語を盛り上げるスパイスにもなり得ます。秋吉理香子さんの『サイレンス』、垣谷美雨さんの『結婚相手は抽選で』、辻村深月さんの『傲慢と善良』等々、主人公が結婚を意識したことで事件や騒動に巻き込まれる小説はたくさんありますね。今日ご紹介する小説を読んだら、結婚するのがなんだか怖くなってしまうかもしれません。貫井徳郎さんの『崩れる 結婚にまつわる八つの風景』です。
こんな人におすすめ
結婚をテーマにしたサスペンス短編集が読みたい人
続きを読む
 いわゆる<バディもの>と言われる作品の場合、主人公コンビの信頼関係が物語を左右する鍵となります。アガサ・クリスティーの『シャーロック・ホームズシリーズ』でも、名探偵ホームズと助手のワトソン博士の名コンビぶりは世界に知れ渡っています。信頼し、支え合うコンビの姿は、読者をわくわくさせてくれるものです。
いわゆる<バディもの>と言われる作品の場合、主人公コンビの信頼関係が物語を左右する鍵となります。アガサ・クリスティーの『シャーロック・ホームズシリーズ』でも、名探偵ホームズと助手のワトソン博士の名コンビぶりは世界に知れ渡っています。信頼し、支え合うコンビの姿は、読者をわくわくさせてくれるものです。
その一方、決して友好的とは言い難いコンビの存在も、それはそれで面白いです。例えば、漫画ですが、柩やなさんの『黒執事』。幼い少年貴族と彼に仕える執事が主人公ですが、実はこの執事の正体は悪魔で、少年貴族の魂欲しさに仕えているだけ。当然、両者の間に真の信頼関係などないものの、お互い打算のため主従関係を結ぶ二人の姿は、見ていてとてもスリリングです。最近読んだ小説にも、決して仲良しこよしとは言えない名(迷?)コンビが出てきました。中山七里さんの『人面瘡探偵』です。
こんな人におすすめ
閉鎖的な田舎での連続殺人ミステリーが読みたい人
続きを読む
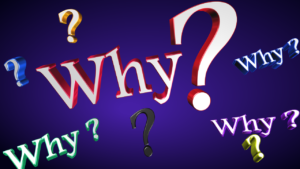 SF作品の中には、<タイムリープ>という言葉が登場するものがあります。直訳すると<時間跳躍>で、文字通り時間を飛び越えて移動することを意味します。よく似た言葉に<タイムトラベル>があり、正確な差異は定義されていないようですが、<タイムトラベル=移動先を自分で決められる><タイムリープ=勝手に別の時間に移動してしまう>と使い分けられているパターンが多いような気がします。
SF作品の中には、<タイムリープ>という言葉が登場するものがあります。直訳すると<時間跳躍>で、文字通り時間を飛び越えて移動することを意味します。よく似た言葉に<タイムトラベル>があり、正確な差異は定義されていないようですが、<タイムトラベル=移動先を自分で決められる><タイムリープ=勝手に別の時間に移動してしまう>と使い分けられているパターンが多いような気がします。
実はタイムリープという言葉は日本製の造語であり、初出は筒井康隆さんの『時をかける少女』だそうです。何度も映像化・アニメ化され、海外でも人気の高い名作なので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。これは有名すぎるほど有名なので、今回は別のタイムリープ小説を取り上げたいと思います。西澤保彦さんの『七回死んだ男』です。
こんな人におすすめ
ユーモラスなSFミステリーが読みたい人
続きを読む
 作品名も内容も忘れてしまいましたが、ずいぶん昔に見た映画で、登場人物がこんな台詞を口にしていました。「身代金目当ての誘拐は、この世で一番成功率の低い犯罪だ」その理由は色々ありますが、一番は、金の受け渡しをしなくてはならないという性質上、絶対に加害者側と被害者(の関係者)側が接触するからでしょう。実際、戦後日本で起きた誘拐事件で、犯人が身代金奪取に成功した例は一つもありません。
作品名も内容も忘れてしまいましたが、ずいぶん昔に見た映画で、登場人物がこんな台詞を口にしていました。「身代金目当ての誘拐は、この世で一番成功率の低い犯罪だ」その理由は色々ありますが、一番は、金の受け渡しをしなくてはならないという性質上、絶対に加害者側と被害者(の関係者)側が接触するからでしょう。実際、戦後日本で起きた誘拐事件で、犯人が身代金奪取に成功した例は一つもありません。
現実に起きたら凶悪極まりない誘拐事件ですが、フィクションの世界限定なら、面白いテーマとなり得ます。荻原浩さんの『誘拐ラプソディー』や天藤真さんの『大誘拐』、東野圭吾さんの『ゲームの名は誘拐』など、誘拐事件を扱った小説は多いです。今回取り上げるのも、悲しい誘拐事件をテーマにした作品です。貫井徳郎さんの『罪と祈り』です。
こんな人におすすめ
誘拐事件が出てくるミステリー小説が読みたい人
続きを読む
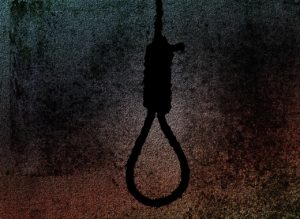 新年明けましておめでとうございます。令和初のお正月、いかがお過ごしでしょうか。二〇一六年に始まったこのブログは、今年で四年目を迎えます。今後も変わらず独断と偏見に満ちた内容になることが予想されますが、呆れずお付き合いいただければ幸いです。
新年明けましておめでとうございます。令和初のお正月、いかがお過ごしでしょうか。二〇一六年に始まったこのブログは、今年で四年目を迎えます。今後も変わらず独断と偏見に満ちた内容になることが予想されますが、呆れずお付き合いいただければ幸いです。
毎年、新年一作目となる本を何にしようかと悩むのですが、今年は楽しみにしていた図書館の予約本がタイミング良く回ってきたので、悩む必要ありませんでした。二〇二〇年初投稿は、中山七里さんの『死にゆく者の祈り』。ミステリーとしてだけでなく、仏教の在り方についても考えることができ、仏教校出身の私には興味深かったです。
こんな人におすすめ
冤罪が絡んだミステリーが読みたい人
続きを読む
 <シリアルキラー>という言葉が使われ出したのは、一九八四年、捜査関係者がアメリカの連続殺人鬼テッド・バンディを指して言ったことが始まりだそうです。意味は、何らかの心理的欲求のもと、長期間に渡って殺人を繰り返す連続殺人犯のこと。<serial=続きの>という言葉が示す通り、複数の犠牲者を出すことがシリアルキラーの定義とされています。
<シリアルキラー>という言葉が使われ出したのは、一九八四年、捜査関係者がアメリカの連続殺人鬼テッド・バンディを指して言ったことが始まりだそうです。意味は、何らかの心理的欲求のもと、長期間に渡って殺人を繰り返す連続殺人犯のこと。<serial=続きの>という言葉が示す通り、複数の犠牲者を出すことがシリアルキラーの定義とされています。
 <心中>とはもともと<真心>を意味する言葉であり、転じて<男女が相手に真心を尽くし、愛を貫くこと>を意味するようになったそうです。それがさらに変化し、何物にも邪魔をされない究極の愛の行為として、男女が一緒に死ぬことを指すようになったんだとか。一家心中、無理心中、ネット心中など、一言で<心中>と言っても様々ですが、言葉のイメージとして一番世間に浸透しているのは、上記のケースだと思います。
<心中>とはもともと<真心>を意味する言葉であり、転じて<男女が相手に真心を尽くし、愛を貫くこと>を意味するようになったそうです。それがさらに変化し、何物にも邪魔をされない究極の愛の行為として、男女が一緒に死ぬことを指すようになったんだとか。一家心中、無理心中、ネット心中など、一言で<心中>と言っても様々ですが、言葉のイメージとして一番世間に浸透しているのは、上記のケースだと思います。 医療問題は総じてデリケートなものですが、中でも臓器移植問題の複雑さは群を抜いています。「虫歯になったら歯医者に行こう」とは言えても「病気になったら臓器移植を受けよう」とはなかなか言えるものではありません。理由は色々あるけれど、その中の一つは<臓器提供が行われる=提供者は体にメスを入れて臓器を摘出されている、場合によっては死んでいる>からではないでしょうか。病気や怪我なら仕方ないが、五体満足の体を開いて内臓を取り出すなんて不自然だ、親しい身内ならともかく他人のために手術なんて受けたくない、臓器移植を待つということはどこかの誰かが死ぬのを待つことではないか・・・そういったネガティブな考え方があるのが現実です。
医療問題は総じてデリケートなものですが、中でも臓器移植問題の複雑さは群を抜いています。「虫歯になったら歯医者に行こう」とは言えても「病気になったら臓器移植を受けよう」とはなかなか言えるものではありません。理由は色々あるけれど、その中の一つは<臓器提供が行われる=提供者は体にメスを入れて臓器を摘出されている、場合によっては死んでいる>からではないでしょうか。病気や怪我なら仕方ないが、五体満足の体を開いて内臓を取り出すなんて不自然だ、親しい身内ならともかく他人のために手術なんて受けたくない、臓器移植を待つということはどこかの誰かが死ぬのを待つことではないか・・・そういったネガティブな考え方があるのが現実です。 何をもってその作品を好きと思うか。基準は人それぞれです。ストーリーが何より大事と言う人もいれば、その作家さんの作品なら何でも読んでみるという人もいるでしょう。タイトルや挿絵に重きを置く人だっているかもしれません。<登場人物>もその一つ。「このキャラ大好き」「この人が主人公なら続編も読んでみよう」。そうやって読む本を決めることって、案外多いのではないでしょうか。
何をもってその作品を好きと思うか。基準は人それぞれです。ストーリーが何より大事と言う人もいれば、その作家さんの作品なら何でも読んでみるという人もいるでしょう。タイトルや挿絵に重きを置く人だっているかもしれません。<登場人物>もその一つ。「このキャラ大好き」「この人が主人公なら続編も読んでみよう」。そうやって読む本を決めることって、案外多いのではないでしょうか。 自慢して言うようなことではありませんが、私は単純な人間です。物事の裏側を読んだり、水面下に秘められた事実を察するというのが苦手。おかげで昔からさんざん「鈍い」「KY」と言われたものです。
自慢して言うようなことではありませんが、私は単純な人間です。物事の裏側を読んだり、水面下に秘められた事実を察するというのが苦手。おかげで昔からさんざん「鈍い」「KY」と言われたものです。 結婚については、世界各国の偉人達が様々な名言を残しています。「人類は太古の昔から、帰りが遅いと心配してくれる人を必要としている」と言ったのはマーガレット・ミード、「右の靴は左足には合わない。でも両方ないと一足とは言えない」と言ったのは山本有三、「あなたがもし孤独を恐れるならば、結婚すべきではない」と言ったのはチェーホフ、「恋は人を盲目にするが、結婚は視力を戻してくれる」と言ったのはリヒテンベルクです。温かいものもあれば皮肉の効いたものもありますが、そもそも結婚自体、良い面と悪い面の両方を持つものなのでしょう。
結婚については、世界各国の偉人達が様々な名言を残しています。「人類は太古の昔から、帰りが遅いと心配してくれる人を必要としている」と言ったのはマーガレット・ミード、「右の靴は左足には合わない。でも両方ないと一足とは言えない」と言ったのは山本有三、「あなたがもし孤独を恐れるならば、結婚すべきではない」と言ったのはチェーホフ、「恋は人を盲目にするが、結婚は視力を戻してくれる」と言ったのはリヒテンベルクです。温かいものもあれば皮肉の効いたものもありますが、そもそも結婚自体、良い面と悪い面の両方を持つものなのでしょう。 いわゆる<バディもの>と言われる作品の場合、主人公コンビの信頼関係が物語を左右する鍵となります。アガサ・クリスティーの『シャーロック・ホームズシリーズ』でも、名探偵ホームズと助手のワトソン博士の名コンビぶりは世界に知れ渡っています。信頼し、支え合うコンビの姿は、読者をわくわくさせてくれるものです。
いわゆる<バディもの>と言われる作品の場合、主人公コンビの信頼関係が物語を左右する鍵となります。アガサ・クリスティーの『シャーロック・ホームズシリーズ』でも、名探偵ホームズと助手のワトソン博士の名コンビぶりは世界に知れ渡っています。信頼し、支え合うコンビの姿は、読者をわくわくさせてくれるものです。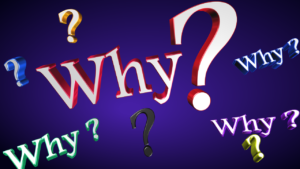 SF作品の中には、<タイムリープ>という言葉が登場するものがあります。直訳すると<時間跳躍>で、文字通り時間を飛び越えて移動することを意味します。よく似た言葉に<タイムトラベル>があり、正確な差異は定義されていないようですが、<タイムトラベル=移動先を自分で決められる><タイムリープ=勝手に別の時間に移動してしまう>と使い分けられているパターンが多いような気がします。
SF作品の中には、<タイムリープ>という言葉が登場するものがあります。直訳すると<時間跳躍>で、文字通り時間を飛び越えて移動することを意味します。よく似た言葉に<タイムトラベル>があり、正確な差異は定義されていないようですが、<タイムトラベル=移動先を自分で決められる><タイムリープ=勝手に別の時間に移動してしまう>と使い分けられているパターンが多いような気がします。 作品名も内容も忘れてしまいましたが、ずいぶん昔に見た映画で、登場人物がこんな台詞を口にしていました。「身代金目当ての誘拐は、この世で一番成功率の低い犯罪だ」その理由は色々ありますが、一番は、金の受け渡しをしなくてはならないという性質上、絶対に加害者側と被害者(の関係者)側が接触するからでしょう。実際、戦後日本で起きた誘拐事件で、犯人が身代金奪取に成功した例は一つもありません。
作品名も内容も忘れてしまいましたが、ずいぶん昔に見た映画で、登場人物がこんな台詞を口にしていました。「身代金目当ての誘拐は、この世で一番成功率の低い犯罪だ」その理由は色々ありますが、一番は、金の受け渡しをしなくてはならないという性質上、絶対に加害者側と被害者(の関係者)側が接触するからでしょう。実際、戦後日本で起きた誘拐事件で、犯人が身代金奪取に成功した例は一つもありません。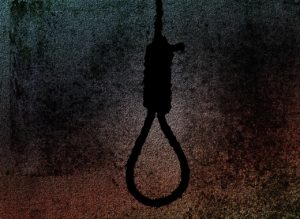 新年明けましておめでとうございます。令和初のお正月、いかがお過ごしでしょうか。二〇一六年に始まったこのブログは、今年で四年目を迎えます。今後も変わらず独断と偏見に満ちた内容になることが予想されますが、呆れずお付き合いいただければ幸いです。
新年明けましておめでとうございます。令和初のお正月、いかがお過ごしでしょうか。二〇一六年に始まったこのブログは、今年で四年目を迎えます。今後も変わらず独断と偏見に満ちた内容になることが予想されますが、呆れずお付き合いいただければ幸いです。