 小説の人気キャラクターをイラストで描くのは、なかなか難しい仕事です。実写化でも言えることですが、キャラクター人気が高ければ高いほど、どれだけ上手くイラスト化しても「なんか思っていたのと違う」「〇〇(キャラクター名)はこんな顔じゃない」という不満が出ることは不可避。特に挿絵がない小説の場合、読者がキャラのイメージを膨らませる余地が大きいため、いざイラスト化されるとネガティブな感想を抱かれやすい気がします。
小説の人気キャラクターをイラストで描くのは、なかなか難しい仕事です。実写化でも言えることですが、キャラクター人気が高ければ高いほど、どれだけ上手くイラスト化しても「なんか思っていたのと違う」「〇〇(キャラクター名)はこんな顔じゃない」という不満が出ることは不可避。特に挿絵がない小説の場合、読者がキャラのイメージを膨らませる余地が大きいため、いざイラスト化されるとネガティブな感想を抱かれやすい気がします。
反面、好きなキャラクターが自分の想像通りの形でイラスト化された時の喜びは大きいです。以前、片山愁さんによる『銀河鉄道の夜』の漫画化を見た時は、イメージとぴったりのカンパネラやジョバンニの姿に大興奮しました。それから先日読んだこの作品のイラストも、「これこれ!」と言いたくなるほどハマっていたと思います。中山七里さんの『作家刑事毒島の嘲笑』です。
こんな人におすすめ
・皮肉の効いたミステリー短編集が読みたい人
・毒舌キャラが活躍する作品が好きな人

 クローズド・サークルものの定番シチュエーションといえば、洋館、辺鄙な場所にある村、孤島の三つだと思います(すべて交通網・連絡ツールが遮断されていることが前提)。この三つの内、一番行き来するのに労力が要るのは、孤島ではないでしょうか。洋館や僻地の村の場合、死ぬ気で頑張れば自分の足で移動可能ですが、孤島の場合、どうにかして船等の移動手段を確保しなければなりません。となると、操縦は誰がするのか、エンジンは無事なのか等の問題が生じ、物語がよりスリリングなものになります。
クローズド・サークルものの定番シチュエーションといえば、洋館、辺鄙な場所にある村、孤島の三つだと思います(すべて交通網・連絡ツールが遮断されていることが前提)。この三つの内、一番行き来するのに労力が要るのは、孤島ではないでしょうか。洋館や僻地の村の場合、死ぬ気で頑張れば自分の足で移動可能ですが、孤島の場合、どうにかして船等の移動手段を確保しなければなりません。となると、操縦は誰がするのか、エンジンは無事なのか等の問題が生じ、物語がよりスリリングなものになります。 人は時に<恐らく絶対実現不可能だろうけど、願わずにはいられない夢>を見てしまうことがあります。世界中の富をすべて手中に収めてしまいたい、かもしれない。片思いの相手が一夜にして自分に夢中になればいいのに、かもしれない。人によって願う夢も様々でしょうが、<亡くなった人が甦ればいいのに><死んでもまた生き返りたい>と思う人は相当数いそうな気がします。
人は時に<恐らく絶対実現不可能だろうけど、願わずにはいられない夢>を見てしまうことがあります。世界中の富をすべて手中に収めてしまいたい、かもしれない。片思いの相手が一夜にして自分に夢中になればいいのに、かもしれない。人によって願う夢も様々でしょうが、<亡くなった人が甦ればいいのに><死んでもまた生き返りたい>と思う人は相当数いそうな気がします。 <猟奇的>というのは、本来、<奇怪・異常なものを強く求める様子>を指す言葉です。現代では、もともとの意味から少し離れ、<残酷な><グロテスクな>という意味で使われることが多いですね。特に、遺体が激しく損壊されていたり連続殺人だったりする事件を<猟奇殺人>と表現するケースが多いと思います。
<猟奇的>というのは、本来、<奇怪・異常なものを強く求める様子>を指す言葉です。現代では、もともとの意味から少し離れ、<残酷な><グロテスクな>という意味で使われることが多いですね。特に、遺体が激しく損壊されていたり連続殺人だったりする事件を<猟奇殺人>と表現するケースが多いと思います。 私はこの十年ほど日記をつけ続けています。日付、天気、その日の出来事と食事のメニューを書いた数行程度のものですが、後日、過去の記憶が曖昧な時に振り返ることができて便利ですよ。たまに昔の日記を読み直してみると、「あ、そういえばこんなことがあったっけ」「私、五年前と同じことしてるじゃん」等々、色々と思うところがって面白いです。
私はこの十年ほど日記をつけ続けています。日付、天気、その日の出来事と食事のメニューを書いた数行程度のものですが、後日、過去の記憶が曖昧な時に振り返ることができて便利ですよ。たまに昔の日記を読み直してみると、「あ、そういえばこんなことがあったっけ」「私、五年前と同じことしてるじゃん」等々、色々と思うところがって面白いです。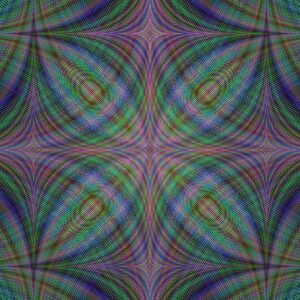 現実に起きた出来事とフィクションとをいかに上手く絡めるか。それは、面白い物語を作る上で重要な要素です。イエス・キリストがキリスト教の始祖であること、徳川家康が江戸幕府を開いたこと、ドイツにアドルフ・ヒトラーという独裁者が存在したこと。すべて歴史的事実であり、なかったことにすることはできません。
現実に起きた出来事とフィクションとをいかに上手く絡めるか。それは、面白い物語を作る上で重要な要素です。イエス・キリストがキリスト教の始祖であること、徳川家康が江戸幕府を開いたこと、ドイツにアドルフ・ヒトラーという独裁者が存在したこと。すべて歴史的事実であり、なかったことにすることはできません。 人あるところにドラマあり。一人の人間が存在すれば、そこには必ず悲喜こもごもが生まれます。それは創作物の世界においても同じこと。だからこそ、多くの人間達が集う場所は、様々なフィクション作品の舞台となってきました。
人あるところにドラマあり。一人の人間が存在すれば、そこには必ず悲喜こもごもが生まれます。それは創作物の世界においても同じこと。だからこそ、多くの人間達が集う場所は、様々なフィクション作品の舞台となってきました。 一説によると、日本人のような農耕民族は、家に対する愛着が強いそうです。一カ所に定住し、畑を作って暮らしてきた記憶が遺伝子に刻み込まれていて、<立派な家を持つ>ということに大きな価値を見出すのだとか。もちろん、「雨風がしのげればOK」という価値観の人もたくさんいるでしょうが、そういう人にしたって、住み心地が良いのと悪いのとでは、前者を選ぶに決まっています。
一説によると、日本人のような農耕民族は、家に対する愛着が強いそうです。一カ所に定住し、畑を作って暮らしてきた記憶が遺伝子に刻み込まれていて、<立派な家を持つ>ということに大きな価値を見出すのだとか。もちろん、「雨風がしのげればOK」という価値観の人もたくさんいるでしょうが、そういう人にしたって、住み心地が良いのと悪いのとでは、前者を選ぶに決まっています。 クローンという言葉が最初に考案されたのは、一九〇〇年代初頭のことだそうです。意味は、分子・DNA・細胞・生体などのコピー。園芸技法の一つである<挿し木>はクローンの一種ですし、動物でもマウス、犬、羊、猿などでクローンが作成されています。人間のクローンは今のところ作られていないとされていますが・・・実際はどうなんでしょうか?
クローンという言葉が最初に考案されたのは、一九〇〇年代初頭のことだそうです。意味は、分子・DNA・細胞・生体などのコピー。園芸技法の一つである<挿し木>はクローンの一種ですし、動物でもマウス、犬、羊、猿などでクローンが作成されています。人間のクローンは今のところ作られていないとされていますが・・・実際はどうなんでしょうか? <クロスオーバー>という手法があります。これは異なる作品同士が一時的にストーリーを共有する手法のことで、主にアメリカンコミックの世界で発達したのだとか。映画化もされた『アベンジャーズシリーズ』で、アイアンマンやハルク等、違う作品のキャラクター達が共演して大活躍したことは、ご存知の方も多いと思います。
<クロスオーバー>という手法があります。これは異なる作品同士が一時的にストーリーを共有する手法のことで、主にアメリカンコミックの世界で発達したのだとか。映画化もされた『アベンジャーズシリーズ』で、アイアンマンやハルク等、違う作品のキャラクター達が共演して大活躍したことは、ご存知の方も多いと思います。