 小説の分野においては、「最後の一撃(フィニッシング・ストローク)」というものが存在します。文字通り、最後の最後で読者に衝撃を与える物語のことで、ミステリーやホラーのジャンルに多いですね。作品の最終ページが近づき、やれやれ・・・と思った瞬間に与えられる驚きや恐怖は、読者に強烈なインパクトを与えます。
小説の分野においては、「最後の一撃(フィニッシング・ストローク)」というものが存在します。文字通り、最後の最後で読者に衝撃を与える物語のことで、ミステリーやホラーのジャンルに多いですね。作品の最終ページが近づき、やれやれ・・・と思った瞬間に与えられる驚きや恐怖は、読者に強烈なインパクトを与えます。
この手の小説で有名なものはたくさんありますが、インターネットで検索すると、「最後の一撃にこだわった」と作者本人が公言する米澤穂信さんの『儚い羊たちの祝宴』が一番多くヒットするようです。その他、我孫子武丸さんの『殺戮にいたる病』や百田尚樹さんの『幸福な生活』、このブログでも紹介した荻原浩さんの『噂』など、どれも面白い作品でした。そういえば、この作品の最後の一行も強烈だったなぁ。貫井徳郎さんのデビュー作『慟哭』です。
こんな人におすすめ
・読後感の悪い本格推理小説が読みたい人
・新興宗教を扱った作品に興味がある人

 以前、別の記事で、図書館の予約システムについて書きました。読みたい本を確実に読めるよう貸出予約を入れるというもので、当然、人気の本には何百件もの予約が殺到します。となると、なかなか本を借りにこない予約者をいつまでも待ち続けるわけにもいかないので、大多数の図書館では予約本の取り置き期間というものを設けています。自治体によって違うようですが、基本、十日~二週間というケースが多いようですね。
以前、別の記事で、図書館の予約システムについて書きました。読みたい本を確実に読めるよう貸出予約を入れるというもので、当然、人気の本には何百件もの予約が殺到します。となると、なかなか本を借りにこない予約者をいつまでも待ち続けるわけにもいかないので、大多数の図書館では予約本の取り置き期間というものを設けています。自治体によって違うようですが、基本、十日~二週間というケースが多いようですね。 子どもの頃から推理小説好きだった私には、憧れのシチュエーションがあります。それは<警察の信頼を得て捜査協力を求められる少年少女>というもの。現実にはおよそあり得ないんでしょうが、「もし自分がこんな風に事件に関わることができたなら・・・」とワクワクドキドキしたものです。
子どもの頃から推理小説好きだった私には、憧れのシチュエーションがあります。それは<警察の信頼を得て捜査協力を求められる少年少女>というもの。現実にはおよそあり得ないんでしょうが、「もし自分がこんな風に事件に関わることができたなら・・・」とワクワクドキドキしたものです。 別の記事でも書きましたが、フィクションの世界において、被告人のために戦う弁護士はやや特殊なポジションであり、強烈な個性付けがなされることが多いです。一方、これと対照的なのは、弁護士と法廷で争う検事。良くも悪くも生真面目な法の番人として描かれがちな気がします。
別の記事でも書きましたが、フィクションの世界において、被告人のために戦う弁護士はやや特殊なポジションであり、強烈な個性付けがなされることが多いです。一方、これと対照的なのは、弁護士と法廷で争う検事。良くも悪くも生真面目な法の番人として描かれがちな気がします。 「人間が動物に変身する(逆もあり)」というのは、SFやホラーでお馴染みの設定です。お馴染みすぎて初めて見た変身ものが何だったか思い出せないくらいですが、記憶に残っているのは映画『ウルフ』。段々と狼に変わっていくジャック・ニコルソンの変貌ぶりが印象的でした。
「人間が動物に変身する(逆もあり)」というのは、SFやホラーでお馴染みの設定です。お馴染みすぎて初めて見た変身ものが何だったか思い出せないくらいですが、記憶に残っているのは映画『ウルフ』。段々と狼に変わっていくジャック・ニコルソンの変貌ぶりが印象的でした。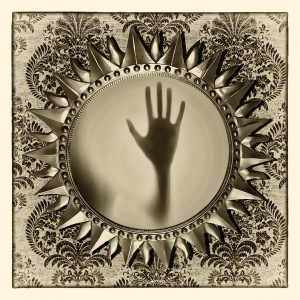 甘ったれで気弱な子どもだった私が怖かったもの、それは「親から離れてのお泊まり」です。幼稚園のお泊まり教室などはもちろんのこと、祖母の家へのお泊まりさえ途中で寂しくなり、夜に自宅に帰ったこともありました。小学校の修学旅行にも戦々恐々としながら参加し、いざ始まってみて「あれ、意外と楽しいじゃん」と思ったことを覚えています。
甘ったれで気弱な子どもだった私が怖かったもの、それは「親から離れてのお泊まり」です。幼稚園のお泊まり教室などはもちろんのこと、祖母の家へのお泊まりさえ途中で寂しくなり、夜に自宅に帰ったこともありました。小学校の修学旅行にも戦々恐々としながら参加し、いざ始まってみて「あれ、意外と楽しいじゃん」と思ったことを覚えています。 人はどんな時に役所を利用するのでしょうか。引っ越しや結婚、出産などによる諸々の手続き、各所へ提出する戸籍等の重要書類の請求、自治体が運営するイベントへの参加etcetc・・・ぱっと思いつくだけでも色々あります。最近は役所内の飲食施設も結構充実しているそうですから、そういうところを利用する人もいるかもしれません。
人はどんな時に役所を利用するのでしょうか。引っ越しや結婚、出産などによる諸々の手続き、各所へ提出する戸籍等の重要書類の請求、自治体が運営するイベントへの参加etcetc・・・ぱっと思いつくだけでも色々あります。最近は役所内の飲食施設も結構充実しているそうですから、そういうところを利用する人もいるかもしれません。 貧富の差。日常生活の中でも頻繁に耳にする言葉です。この言葉を見聞きする時、どんな映像が思い浮かぶでしょうか。アフリカや中東などの開発途上国?江戸や明治といった昔の時代?それも間違いではありませんが、今この瞬間、平和なはずの日本国内にも貧富の差は存在します。
貧富の差。日常生活の中でも頻繁に耳にする言葉です。この言葉を見聞きする時、どんな映像が思い浮かぶでしょうか。アフリカや中東などの開発途上国?江戸や明治といった昔の時代?それも間違いではありませんが、今この瞬間、平和なはずの日本国内にも貧富の差は存在します。 ウツボカズラという植物をご存知でしょうか。東南アジアに多い食虫植物で、甘い蜜を餌に虫をおびき寄せ、壺のようになった体内に誘い込んで捕食するという習性を持っています。昔、テレビでウツボカズラの内部を調べるという企画を見たことがありますが、凄まじい数の虫を体内にため込んでいて驚いたものです。
ウツボカズラという植物をご存知でしょうか。東南アジアに多い食虫植物で、甘い蜜を餌に虫をおびき寄せ、壺のようになった体内に誘い込んで捕食するという習性を持っています。昔、テレビでウツボカズラの内部を調べるという企画を見たことがありますが、凄まじい数の虫を体内にため込んでいて驚いたものです。 「団地」という言葉ができたのは昭和十年代だそうです。住宅や工場を計画的に一カ所に集めて建設した地区、またはそこに立地している建造物のことで、住宅団地、工業団地、商業団地などがあります。「団地」と聞くと、住宅団地を真っ先に思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
「団地」という言葉ができたのは昭和十年代だそうです。住宅や工場を計画的に一カ所に集めて建設した地区、またはそこに立地している建造物のことで、住宅団地、工業団地、商業団地などがあります。「団地」と聞くと、住宅団地を真っ先に思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。