 <ブランド>という言葉は、ある財貨・サービスを、その他の財貨・サービスと区別するための印を意味するのだそうです。もともとの語源は<焼印>で、北欧の牧場主が自分の家畜とよその家畜を区別するため、家畜に焼印を押していたことから誕生した言葉なのだとか。それを知ってみると、やたら生々しく強烈な響きに聞こえますね。
<ブランド>という言葉は、ある財貨・サービスを、その他の財貨・サービスと区別するための印を意味するのだそうです。もともとの語源は<焼印>で、北欧の牧場主が自分の家畜とよその家畜を区別するため、家畜に焼印を押していたことから誕生した言葉なのだとか。それを知ってみると、やたら生々しく強烈な響きに聞こえますね。
ありとあらゆる分野に<ブランド>は存在しますが、一番連想されやすいのはファッション業界ではないでしょうか。もちろん、一言でブランド品と言っても色々あり、目の玉が飛び出るほどの値段がつく高級品から、学生がバイト代を貯めて買えるお手頃商品まで、千差万別。そして、商品に込められた作り手の思い、買い手の思いもまた様々です。今回ご紹介するのは、永井するみさんの『さくら草』。ファッションブランドに関わる人間達の業の深さを堪能できました。
こんな人におすすめ
ファッションにまつわるサスペンスに興味がある人
続きを読む
 調査によると、初恋の平均年齢は男性が十一歳で女性が九歳、初めて恋人ができたのは男女共に十六歳が平均だそうです。初めて人に恋愛感情を抱き、その人のことを思って一喜一憂したり、デートの約束に浮かれたりする・・・そんな初々しい恋心は、本人達だけでなく、見ている周囲の人間をも温かな気持ちにさせてくれるものです。
調査によると、初恋の平均年齢は男性が十一歳で女性が九歳、初めて恋人ができたのは男女共に十六歳が平均だそうです。初めて人に恋愛感情を抱き、その人のことを思って一喜一憂したり、デートの約束に浮かれたりする・・・そんな初々しい恋心は、本人達だけでなく、見ている周囲の人間をも温かな気持ちにさせてくれるものです。
ですが、イヤミスやホラーの世界となると話は別。若く未熟であるがゆえの幼稚さ、周囲の事情が見えない軽率さが強調され、とんでもない悲劇が引き起こされることも少なくありません。そんな狂気とも言える恋心を描かせたら、この作家さんは本当に上手いですね。今回は、新津きよみさんの『婚約者』をご紹介したいと思います。
こんな人におすすめ
女性の狂気を描いたホラーサスペンスが読みたい人
続きを読む
 <無敵の人>という言葉をご存知でしょうか。二〇〇八年、実業家であり論客のひろゆき氏が使い始めたインターネットスラングで、失うものが何もないため躊躇なく犯罪に走る人を指すのだそうです。つい魔が差し、一瞬、「こいつをぶん殴ってやりたい」とか「ここで暴れ回ったらすっきりするだろうな」とか思ってしまうのは誰でもあること。ただ、実際に行動してしまうと犯罪者となり、家族や仕事、築いた財産を失う可能性があります。そこで多くの人は罪を犯すことを思いとどまるわけですが、失いたくないものを持たない人間は、「もうどうにでもなっちまえ!」と破滅的な行動に走ってしまうことがあり得ます。二〇〇一年の附属池田小事件や、二〇一九年の京都アニメーション放火殺人事件等、実際に大惨事となったケースも少なくありません。
<無敵の人>という言葉をご存知でしょうか。二〇〇八年、実業家であり論客のひろゆき氏が使い始めたインターネットスラングで、失うものが何もないため躊躇なく犯罪に走る人を指すのだそうです。つい魔が差し、一瞬、「こいつをぶん殴ってやりたい」とか「ここで暴れ回ったらすっきりするだろうな」とか思ってしまうのは誰でもあること。ただ、実際に行動してしまうと犯罪者となり、家族や仕事、築いた財産を失う可能性があります。そこで多くの人は罪を犯すことを思いとどまるわけですが、失いたくないものを持たない人間は、「もうどうにでもなっちまえ!」と破滅的な行動に走ってしまうことがあり得ます。二〇〇一年の附属池田小事件や、二〇一九年の京都アニメーション放火殺人事件等、実際に大惨事となったケースも少なくありません。
社会の耳目を集める存在なだけあって、無敵の人は多くのフィクション作品に登場します。作品の知名度として有名なのは、映画『ジョーカー』のアーサー・フレック辺りでしょうか。どん底の男が良識を手放し、ジョークとして凶悪犯罪を起こしていく様は、決して創作と言い切れないほどの迫力と臨場感がありました。さすがにアメコミのヴィランほどではありませんが、今日取り上げる作品にも、社会を混乱に陥れる無敵の人が登場します。中山七里さんの『能面検事の死闘』です。
こんな人におすすめ
・『能面検事シリーズ』が好きな人
・<無敵の人>を扱った作品に興味がある人
続きを読む
 修練を積み重ねた末にできるようになる巧みな技のことを<職人技>といいます。こんな言葉ができることからも分かる通り、職人とは熟練した技術で物を生み出すプロフェッショナル。根っからの不器用人間である私からすれば、同じ人間とは思えないレベルの技術を持った人達です。
修練を積み重ねた末にできるようになる巧みな技のことを<職人技>といいます。こんな言葉ができることからも分かる通り、職人とは熟練した技術で物を生み出すプロフェッショナル。根っからの不器用人間である私からすれば、同じ人間とは思えないレベルの技術を持った人達です。
ただ、職人をテーマにした小説となると、有名なのは専ら時代小説。現代小説となると意外に少ない気がします。特殊技術を用いる仕事である関係上、活躍する場面が限定され、物語にうまく絡めることが難しいせいでしょうか。確かに、せっかく職人がテーマなのだから、その技巧が作中で活かされていないと意味がありません。そんな中、この作品では、職人達の持つ技と業が巧みに描かれていました。乃南アサさんの『氷雨心中』です。
こんな人におすすめ
職人の世界をテーマにしたサスペンス短編集が読みたい人
続きを読む
 小説や漫画を読んでいると「このキャラは作者のお気に入りなんだな」と感じることがしばしばあります。作家とはいえ人間なのですから、特定のキャラクターに感情移入することもあって当然。他キャラに比べて登場シーンが多かったり、描写が丁寧だったり、必要以上に過酷な目に遭わされたり(笑)と、インパクトのある描き方をされることがしばしばです。
小説や漫画を読んでいると「このキャラは作者のお気に入りなんだな」と感じることがしばしばあります。作家とはいえ人間なのですから、特定のキャラクターに感情移入することもあって当然。他キャラに比べて登場シーンが多かったり、描写が丁寧だったり、必要以上に過酷な目に遭わされたり(笑)と、インパクトのある描き方をされることがしばしばです。
ただ、作者お気に入りキャラの例としてよく挙がるのは、さくらももこさん『ちびまる子ちゃん』の永沢君や、諫山創さん『進撃の巨人』のライナー等、漫画のキャラクターが多い気がします。やはり、キャラクターの活躍ぶりが目で見て分かりやすいからでしょうか。でも、小説の世界にも、作者の寵愛を受けて活躍するキャラクターがたくさんいるんですよ。このシリーズの探偵役も、絶対に作者のお気に入りだと勝手に思っています。西澤保彦さんの『腕貫探偵 残業中』です。
こんな人におすすめ
安楽椅子探偵もののミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 「さあ、今日は一杯やるぞ!」となった時、まずどんなお酒に手を出すでしょうか。缶チューハイ、カクテル、ワイン、日本酒・・・それこそ無限に出てきそうですが、割合で言うなら、「まずビールで」となる人が多い気がします。家にしろ飲食店にしろ準備するのに時間がかからず、アルコール度数もさほどではないビールは、多くの人に好まれています。
「さあ、今日は一杯やるぞ!」となった時、まずどんなお酒に手を出すでしょうか。缶チューハイ、カクテル、ワイン、日本酒・・・それこそ無限に出てきそうですが、割合で言うなら、「まずビールで」となる人が多い気がします。家にしろ飲食店にしろ準備するのに時間がかからず、アルコール度数もさほどではないビールは、多くの人に好まれています。
国内外問わずポピュラーなお酒なだけあって、ビールがキーアイテムとして登場する小説はたくさんあります。竹内真さんの『ビールボーイズ』や吉村喜彦さんの『ビア・ボーイ』などは、お酒好きな人が読めばつい一杯やりたくなってしまうかもしれません。そう言えば、「村上春樹さんの小説を読むと、ビールが飲みたくなる」という声もあるのだとか。こんな言葉が出ることからしても、ビールというお酒がどれだけ世間に浸透しているかが分かります。今回ご紹介する作品にも、ビールが重要な小道具として登場しますよ。西澤保彦さんの『麦酒の家の冒険』です。
こんな人におすすめ
・多重解決ミステリーが読みたい人
・ビールがたくさん出てくる小説に興味がある人
続きを読む
 『必殺シリーズ』『怨み屋本舗』『善悪の屑』・・・ドラマや漫画として人気を博したこれらの作品には、一つの共通項があります。それは、何らかの事情で法の裁きを逃れた、あるいは裁かれたものの罪に不釣り合いな軽い刑罰だった標的を密かに裁く存在が出てくるということ。悲しいかな、罪を犯しておきながらのうのうとのさばる人間は、いつの世にも存在します。「誰かがあいつらに罰を与えてくれたらいいのに・・・」。法的な是非はともかく、そういう感情は誰しもあるでしょう。だからこそ、例に挙げたような作品が人気を集めるのかもしれません。
『必殺シリーズ』『怨み屋本舗』『善悪の屑』・・・ドラマや漫画として人気を博したこれらの作品には、一つの共通項があります。それは、何らかの事情で法の裁きを逃れた、あるいは裁かれたものの罪に不釣り合いな軽い刑罰だった標的を密かに裁く存在が出てくるということ。悲しいかな、罪を犯しておきながらのうのうとのさばる人間は、いつの世にも存在します。「誰かがあいつらに罰を与えてくれたらいいのに・・・」。法的な是非はともかく、そういう感情は誰しもあるでしょう。だからこそ、例に挙げたような作品が人気を集めるのかもしれません。
ただ、仕置き人稼業を扱った作品を探してみると、漫画か、もしくは時代劇が多く、現代を舞台にした小説は少ない気がします。設定上、絵的に映える展開が多かったり、時代劇の方が復讐代行を行いやすかったりするからでしょうか。ですから、この作品を読んだ時は、なんだか新鮮な気分でした。中山七里さんの『祝祭のハングマン』です。
こんな人におすすめ
復讐代行人が出てくる小説が読みたい人
続きを読む
 <多重解決ミステリー>と呼ばれるミステリー作品があります。これは、複数の探偵役が試行錯誤・推理合戦を繰り返しながら真相に迫っていくタイプのミステリーのこと。傑出した天才名探偵がいないことが多い分、探偵役に感情移入がしやすい上、新説が披露されるたび新たな驚きと楽しみを味わうことができます。
<多重解決ミステリー>と呼ばれるミステリー作品があります。これは、複数の探偵役が試行錯誤・推理合戦を繰り返しながら真相に迫っていくタイプのミステリーのこと。傑出した天才名探偵がいないことが多い分、探偵役に感情移入がしやすい上、新説が披露されるたび新たな驚きと楽しみを味わうことができます。
多重解決ミステリーの例を挙げると、歌野晶午さんの『密室殺人ゲームシリーズ』、辻村深月さんの『冷たい校舎の時は止まる』。海外作品なら、アントニイ・バークリーの『毒入りチョコレート事件』などが有名です。そして、この手の作品なら、やっぱり西澤保彦さんを外すことはできません。今回ご紹介するのは『聯愁殺』。多重解決ミステリーの醍醐味を存分に堪能できました。
こんな人におすすめ
多重解決ミステリーを読みたい人
続きを読む
 人が誰にも看取られることなく病気・事故等で死亡することを<孤独死>といいます。死に方の性質上、場所は主に当人の自宅なのだとか。概念自体は明治時代から存在していましたが、注目されるようになったのは一九九五年の阪神淡路大震災後からだそうです。被災者が自宅等で誰にも気づかれないまま死亡する事態が問題視され、それに伴い、これまで<自然死>の一言で片づけられてきた孤独死に関心が集まるようになりました。
人が誰にも看取られることなく病気・事故等で死亡することを<孤独死>といいます。死に方の性質上、場所は主に当人の自宅なのだとか。概念自体は明治時代から存在していましたが、注目されるようになったのは一九九五年の阪神淡路大震災後からだそうです。被災者が自宅等で誰にも気づかれないまま死亡する事態が問題視され、それに伴い、これまで<自然死>の一言で片づけられてきた孤独死に関心が集まるようになりました。
孤独死の多くは病気や怪我が原因であり、事件性が考慮されることはあまりありません。ですが、人一人が一生を終える。誰かに寄り添われることなく、すべてを胸に秘めたままひっそりと死ぬ。そんな場所に、思いが残らないなどということがあるでしょうか。今回取り上げるのは、孤独死から浮かび上がる思いをテーマにした小説です。中山七里さんの『特殊清掃人』です。
こんな人におすすめ
特殊清掃業がテーマの小説に興味がある人
続きを読む
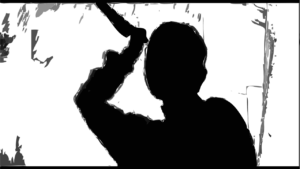 「悪法もまた法なり」。かつて、学者ソクラテスが言ったとされている言葉です(本当に言ったかどうかは諸説あり)。実際にはかなり哲学的な意味があるようですが、今はストレートに「たとえ間違った法律でも、法治国家である以上は従わないといけませんよ」という意味で使われることが多いようですね。確かに、各自が勝手に「あの法律は変だから守らない!」「こんな間違った法律に従う必要はない!」などと言い出したら、社会は成り立ちません。法律が間違っているなら、定められた法改正の手続きを取れというのは、決しておかしな話ではないでしょう。
「悪法もまた法なり」。かつて、学者ソクラテスが言ったとされている言葉です(本当に言ったかどうかは諸説あり)。実際にはかなり哲学的な意味があるようですが、今はストレートに「たとえ間違った法律でも、法治国家である以上は従わないといけませんよ」という意味で使われることが多いようですね。確かに、各自が勝手に「あの法律は変だから守らない!」「こんな間違った法律に従う必要はない!」などと言い出したら、社会は成り立ちません。法律が間違っているなら、定められた法改正の手続きを取れというのは、決しておかしな話ではないでしょう。
しかし、法律を作るのが人間である以上、完璧にはなり得ないというのもまた事実です。法律が誰かを救う一方、また別の誰かを苦しめていたとしたら・・・・・少年法をはじめ、多くの法律が長年論争の種になるのは、この辺りが原因ではないでしょうか。今回取り上げるのは、貫井徳郎さんの『紙の梟 ハーシュソサエティ』。法と社会の在り方について考えさせられました。
こんな人におすすめ
死刑をテーマにしたサスペンス短編集が読みたい人
続きを読む
 <ブランド>という言葉は、ある財貨・サービスを、その他の財貨・サービスと区別するための印を意味するのだそうです。もともとの語源は<焼印>で、北欧の牧場主が自分の家畜とよその家畜を区別するため、家畜に焼印を押していたことから誕生した言葉なのだとか。それを知ってみると、やたら生々しく強烈な響きに聞こえますね。
<ブランド>という言葉は、ある財貨・サービスを、その他の財貨・サービスと区別するための印を意味するのだそうです。もともとの語源は<焼印>で、北欧の牧場主が自分の家畜とよその家畜を区別するため、家畜に焼印を押していたことから誕生した言葉なのだとか。それを知ってみると、やたら生々しく強烈な響きに聞こえますね。
 調査によると、初恋の平均年齢は男性が十一歳で女性が九歳、初めて恋人ができたのは男女共に十六歳が平均だそうです。初めて人に恋愛感情を抱き、その人のことを思って一喜一憂したり、デートの約束に浮かれたりする・・・そんな初々しい恋心は、本人達だけでなく、見ている周囲の人間をも温かな気持ちにさせてくれるものです。
調査によると、初恋の平均年齢は男性が十一歳で女性が九歳、初めて恋人ができたのは男女共に十六歳が平均だそうです。初めて人に恋愛感情を抱き、その人のことを思って一喜一憂したり、デートの約束に浮かれたりする・・・そんな初々しい恋心は、本人達だけでなく、見ている周囲の人間をも温かな気持ちにさせてくれるものです。 <無敵の人>という言葉をご存知でしょうか。二〇〇八年、実業家であり論客のひろゆき氏が使い始めたインターネットスラングで、失うものが何もないため躊躇なく犯罪に走る人を指すのだそうです。つい魔が差し、一瞬、「こいつをぶん殴ってやりたい」とか「ここで暴れ回ったらすっきりするだろうな」とか思ってしまうのは誰でもあること。ただ、実際に行動してしまうと犯罪者となり、家族や仕事、築いた財産を失う可能性があります。そこで多くの人は罪を犯すことを思いとどまるわけですが、失いたくないものを持たない人間は、「もうどうにでもなっちまえ!」と破滅的な行動に走ってしまうことがあり得ます。二〇〇一年の附属池田小事件や、二〇一九年の京都アニメーション放火殺人事件等、実際に大惨事となったケースも少なくありません。
<無敵の人>という言葉をご存知でしょうか。二〇〇八年、実業家であり論客のひろゆき氏が使い始めたインターネットスラングで、失うものが何もないため躊躇なく犯罪に走る人を指すのだそうです。つい魔が差し、一瞬、「こいつをぶん殴ってやりたい」とか「ここで暴れ回ったらすっきりするだろうな」とか思ってしまうのは誰でもあること。ただ、実際に行動してしまうと犯罪者となり、家族や仕事、築いた財産を失う可能性があります。そこで多くの人は罪を犯すことを思いとどまるわけですが、失いたくないものを持たない人間は、「もうどうにでもなっちまえ!」と破滅的な行動に走ってしまうことがあり得ます。二〇〇一年の附属池田小事件や、二〇一九年の京都アニメーション放火殺人事件等、実際に大惨事となったケースも少なくありません。 修練を積み重ねた末にできるようになる巧みな技のことを<職人技>といいます。こんな言葉ができることからも分かる通り、職人とは熟練した技術で物を生み出すプロフェッショナル。根っからの不器用人間である私からすれば、同じ人間とは思えないレベルの技術を持った人達です。
修練を積み重ねた末にできるようになる巧みな技のことを<職人技>といいます。こんな言葉ができることからも分かる通り、職人とは熟練した技術で物を生み出すプロフェッショナル。根っからの不器用人間である私からすれば、同じ人間とは思えないレベルの技術を持った人達です。 小説や漫画を読んでいると「このキャラは作者のお気に入りなんだな」と感じることがしばしばあります。作家とはいえ人間なのですから、特定のキャラクターに感情移入することもあって当然。他キャラに比べて登場シーンが多かったり、描写が丁寧だったり、必要以上に過酷な目に遭わされたり(笑)と、インパクトのある描き方をされることがしばしばです。
小説や漫画を読んでいると「このキャラは作者のお気に入りなんだな」と感じることがしばしばあります。作家とはいえ人間なのですから、特定のキャラクターに感情移入することもあって当然。他キャラに比べて登場シーンが多かったり、描写が丁寧だったり、必要以上に過酷な目に遭わされたり(笑)と、インパクトのある描き方をされることがしばしばです。 「さあ、今日は一杯やるぞ!」となった時、まずどんなお酒に手を出すでしょうか。缶チューハイ、カクテル、ワイン、日本酒・・・それこそ無限に出てきそうですが、割合で言うなら、「まずビールで」となる人が多い気がします。家にしろ飲食店にしろ準備するのに時間がかからず、アルコール度数もさほどではないビールは、多くの人に好まれています。
「さあ、今日は一杯やるぞ!」となった時、まずどんなお酒に手を出すでしょうか。缶チューハイ、カクテル、ワイン、日本酒・・・それこそ無限に出てきそうですが、割合で言うなら、「まずビールで」となる人が多い気がします。家にしろ飲食店にしろ準備するのに時間がかからず、アルコール度数もさほどではないビールは、多くの人に好まれています。 『必殺シリーズ』『怨み屋本舗』『善悪の屑』・・・ドラマや漫画として人気を博したこれらの作品には、一つの共通項があります。それは、何らかの事情で法の裁きを逃れた、あるいは裁かれたものの罪に不釣り合いな軽い刑罰だった標的を密かに裁く存在が出てくるということ。悲しいかな、罪を犯しておきながらのうのうとのさばる人間は、いつの世にも存在します。「誰かがあいつらに罰を与えてくれたらいいのに・・・」。法的な是非はともかく、そういう感情は誰しもあるでしょう。だからこそ、例に挙げたような作品が人気を集めるのかもしれません。
『必殺シリーズ』『怨み屋本舗』『善悪の屑』・・・ドラマや漫画として人気を博したこれらの作品には、一つの共通項があります。それは、何らかの事情で法の裁きを逃れた、あるいは裁かれたものの罪に不釣り合いな軽い刑罰だった標的を密かに裁く存在が出てくるということ。悲しいかな、罪を犯しておきながらのうのうとのさばる人間は、いつの世にも存在します。「誰かがあいつらに罰を与えてくれたらいいのに・・・」。法的な是非はともかく、そういう感情は誰しもあるでしょう。だからこそ、例に挙げたような作品が人気を集めるのかもしれません。 <多重解決ミステリー>と呼ばれるミステリー作品があります。これは、複数の探偵役が試行錯誤・推理合戦を繰り返しながら真相に迫っていくタイプのミステリーのこと。傑出した天才名探偵がいないことが多い分、探偵役に感情移入がしやすい上、新説が披露されるたび新たな驚きと楽しみを味わうことができます。
<多重解決ミステリー>と呼ばれるミステリー作品があります。これは、複数の探偵役が試行錯誤・推理合戦を繰り返しながら真相に迫っていくタイプのミステリーのこと。傑出した天才名探偵がいないことが多い分、探偵役に感情移入がしやすい上、新説が披露されるたび新たな驚きと楽しみを味わうことができます。 人が誰にも看取られることなく病気・事故等で死亡することを<孤独死>といいます。死に方の性質上、場所は主に当人の自宅なのだとか。概念自体は明治時代から存在していましたが、注目されるようになったのは一九九五年の阪神淡路大震災後からだそうです。被災者が自宅等で誰にも気づかれないまま死亡する事態が問題視され、それに伴い、これまで<自然死>の一言で片づけられてきた孤独死に関心が集まるようになりました。
人が誰にも看取られることなく病気・事故等で死亡することを<孤独死>といいます。死に方の性質上、場所は主に当人の自宅なのだとか。概念自体は明治時代から存在していましたが、注目されるようになったのは一九九五年の阪神淡路大震災後からだそうです。被災者が自宅等で誰にも気づかれないまま死亡する事態が問題視され、それに伴い、これまで<自然死>の一言で片づけられてきた孤独死に関心が集まるようになりました。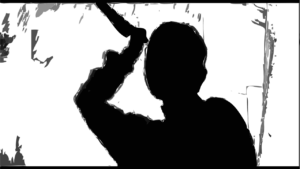 「悪法もまた法なり」。かつて、学者ソクラテスが言ったとされている言葉です(本当に言ったかどうかは諸説あり)。実際にはかなり哲学的な意味があるようですが、今はストレートに「たとえ間違った法律でも、法治国家である以上は従わないといけませんよ」という意味で使われることが多いようですね。確かに、各自が勝手に「あの法律は変だから守らない!」「こんな間違った法律に従う必要はない!」などと言い出したら、社会は成り立ちません。法律が間違っているなら、定められた法改正の手続きを取れというのは、決しておかしな話ではないでしょう。
「悪法もまた法なり」。かつて、学者ソクラテスが言ったとされている言葉です(本当に言ったかどうかは諸説あり)。実際にはかなり哲学的な意味があるようですが、今はストレートに「たとえ間違った法律でも、法治国家である以上は従わないといけませんよ」という意味で使われることが多いようですね。確かに、各自が勝手に「あの法律は変だから守らない!」「こんな間違った法律に従う必要はない!」などと言い出したら、社会は成り立ちません。法律が間違っているなら、定められた法改正の手続きを取れというのは、決しておかしな話ではないでしょう。