 二〇二五年最後の一日となりました。今年も色々あったものの、無事にブログを続けることができて感無量です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
二〇二五年最後の一日となりました。今年も色々あったものの、無事にブログを続けることができて感無量です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
何かと慌ただしいご時世ですが、小説界隈に関していえば、個人的に一番衝撃的だったのは作家・西澤保彦さんが亡くなられたことです。まだ六十代。多作な作家さんだし、てっきり今後も新作がたくさん楽しめると思っていたのに、本当にショックです。心よりご冥福をお祈りするとともに、哀悼の意を表するため、今年の「はいくる」は西澤保彦さんの短編集『パズラー 謎と論理のエンタテイメント』で締めようと思います。
こんな人におすすめ
アクロバティックなミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 SFやホラーのジャンルにおいては、超能力・霊能力・魔力といった異能が頻繁に登場します。と同時に、異能を取り締まったり、サポートしたりする組織や職員が出てくる機会も多いです。日本に限らず海外でも同様なので、万国共通の発想なのかもしれません。
SFやホラーのジャンルにおいては、超能力・霊能力・魔力といった異能が頻繁に登場します。と同時に、異能を取り締まったり、サポートしたりする組織や職員が出てくる機会も多いです。日本に限らず海外でも同様なので、万国共通の発想なのかもしれません。
この手の存在としては、マーベル・シネマスティック・ユニバースに登場する武装組織<S.H.I.E.L.D>、SCP作品世界で暗躍する<SCP財団>などが有名です。タイムリープやタイムトラベルといった能力が登場する作品だと、能力者によって勝手に歴史改変が行われないよう管理する<時空管理局>(名称は違うことも有)なる存在が出てくることも多いですね。「自分もこうした組織の一員だったら・・・」と空想した経験がある方、私を含めて、結構多いのではないでしょうか。今回は、私が大好きな秘密組織・捜査員が登場する作品をご紹介したいと思います。西澤保彦さんの『念力密室!』です。
こんな人におすすめ
SF設定が絡んだミステリーが読みたい人
続きを読む
 子どもから大人まで、長く社会生活を送っていると、グループを組む機会がしばしばあります。純粋に気が合ってできた仲良しグループもあれば、教師や上司の指示でチームを作ることもあるでしょう。ここでの人間関係が円滑か否かで、物事の成否は大きく変わります。
子どもから大人まで、長く社会生活を送っていると、グループを組む機会がしばしばあります。純粋に気が合ってできた仲良しグループもあれば、教師や上司の指示でチームを作ることもあるでしょう。ここでの人間関係が円滑か否かで、物事の成否は大きく変わります。
そんなグループ行動ですが、集まるきっかけとして、意外と<この人たちとつるむしかなかったから>というパターンが多いです。一人よりも集団でいた方が助かる局面は多いので、この動機自体は決して悪いものではありません。とはいえ、私自身を振り返ってみると、こういう<別に気が合ったからではない、不可抗力的に集まったグループ>が、一番揉め事が多かった気がします。ただ揉めるだけならまだしも、取り返しがつかないことが起きる可能性だってあるかも・・・この作品を読んで、そんなことを考えました。貫井徳郎さんの『不等辺五角形』です。
こんな人におすすめ
・<藪の中>状態の推理小説が読みたい人
・インタビュー形式の小説が好きな人
続きを読む
 フィクション作品においては、現実では珍しい部類に入る名前の登場人物がしばしば出てきます。大場つぐみさん原作による漫画『DEATH NOTE』の主人公は<夜神 月(やがみ らいと>ですし、西尾維新さん『物語シリーズ』ヒロインは<戦場ヶ原 ひたぎ(せんじょうがはら ひたぎ>です。少し昔のものでは、吉川英治さん『宮本武蔵』に準主人公格で出てくる<本位田 又八(ほんいでん またはち)>も結構珍しい名前と言えるでしょう。
フィクション作品においては、現実では珍しい部類に入る名前の登場人物がしばしば出てきます。大場つぐみさん原作による漫画『DEATH NOTE』の主人公は<夜神 月(やがみ らいと>ですし、西尾維新さん『物語シリーズ』ヒロインは<戦場ヶ原 ひたぎ(せんじょうがはら ひたぎ>です。少し昔のものでは、吉川英治さん『宮本武蔵』に準主人公格で出てくる<本位田 又八(ほんいでん またはち)>も結構珍しい名前と言えるでしょう。
なぜ登場人物に変わった名前を付けるのか、理由は色々あります。主なものとしては、<作中での登場人物の扱いにより、現実で同じ名前の人が中傷されるのを防ぐため><「勝手に自分のことを書くなんて許せない」というクレームを防ぐため>といったところでしょうか。ただ、この作家さんに関しては、何より自分のこだわりで珍名を出している気がするんですよね。今回取り上げるのは、西澤保彦さんの『帰ってきた腕貫探偵』です。
こんな人におすすめ
安楽椅子探偵もののミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 現代は個人主義の時代だと言われています。個人の意思や多様性というものが重視され、公より私を充実させることの方が大事。求人案内でも、<アットホームな社風><休日に社員同士でレジャーに出かけます>などといった文言は喜ばれない傾向にあるようです。
現代は個人主義の時代だと言われています。個人の意思や多様性というものが重視され、公より私を充実させることの方が大事。求人案内でも、<アットホームな社風><休日に社員同士でレジャーに出かけます>などといった文言は喜ばれない傾向にあるようです。
しかし、どれだけ個人主義が広がろうと、人間は社会生活を営む生き物であり、他者との関わりをゼロにすることは相当難しいです。そして、どうせ人と関わらなくてはならないのなら、できれば円満に付き合っていきたいのが人情というもの。特に身近にいる相手とは、いい関係を築くに越したことはないでしょう。でも、隣りにいるのがこんな存在だったら・・・?今回ご紹介するのは、寝舟はやせさんの『入居条件:隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』です。
こんな人におすすめ
日常侵食系ホラーが浮きな人
続きを読む
 <色>には、人の気持ちに働きかける力があるそうです。赤やオレンジは活力を呼び覚まし、緑は心をリラックスさせ、ピンクは幸福感を感じさせるのだとか。そういえば一昔前、戦隊ヒーローは、行動派の<赤>やクールな<青>というように、各々の個性と色が対応していることが多かったですね。実際にはそこまで明確に性質が分かれるようなことはないのでしょうが、色が印象を左右することは確かだと思います。
<色>には、人の気持ちに働きかける力があるそうです。赤やオレンジは活力を呼び覚まし、緑は心をリラックスさせ、ピンクは幸福感を感じさせるのだとか。そういえば一昔前、戦隊ヒーローは、行動派の<赤>やクールな<青>というように、各々の個性と色が対応していることが多かったですね。実際にはそこまで明確に性質が分かれるようなことはないのでしょうが、色が印象を左右することは確かだと思います。
小説の世界においても、色をテーマにした作品はたくさんあります。昔、当ブログでも取り上げた加納朋子さん『レインレイン・ボウ』でも、各話の主人公と、タイトルとなる色が上手く組み合わされていました。これはヒューマンドラマですが、色をテーマにしたイヤミスなら、今回ご紹介する作品がお勧めです。中山七里さんの『七色の毒』です。
こんな人におすすめ
どんでん返しのあるミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 昔から、雑誌の読み物ページにある小説紹介コーナーや、本屋のPOPを読むのが好きでした。あの手の紹介文って、短いながらビシッと決まった名文が多いんですよね。がっつり長いレビューとはまた違う面白さがあって、ついつい見入ってしまいます。
昔から、雑誌の読み物ページにある小説紹介コーナーや、本屋のPOPを読むのが好きでした。あの手の紹介文って、短いながらビシッと決まった名文が多いんですよね。がっつり長いレビューとはまた違う面白さがあって、ついつい見入ってしまいます。
そんな紹介文が高確率で載っている場所、それは本の巻末です。特に文庫本には、同じ出版社から刊行された新刊や人気本の紹介文が掲載されていることが多いため、時には本編より先に読んでしまうことさえあります。このコーナーのおかげで、面白い作品の存在をたくさん知ることができました。そういえばこの作品も、別の文庫本の巻末に載っていたことがきっかけで知ったんですよ。乃南アサさんの『来なけりゃいいのに』です。
こんな人におすすめ
女性目線のサイコサスペンス短編集が読みたい人
続きを読む
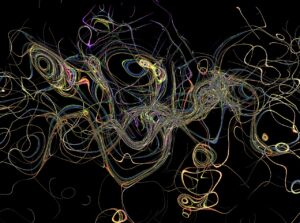 火村英生、犀川創平、湯川学、中禅寺秋彦・・・日本の小説界には、たくさんの名キャラクターがいます。物語を盛り上げる上で、魅力的な主要登場人物の存在は不可欠。『S&Mシリーズ』や『ガリレオシリーズ』がこれほど人気なのは、話自体の面白さもさることながら、上記のキャラクター達の吸引力に依るところも大きいです。
火村英生、犀川創平、湯川学、中禅寺秋彦・・・日本の小説界には、たくさんの名キャラクターがいます。物語を盛り上げる上で、魅力的な主要登場人物の存在は不可欠。『S&Mシリーズ』や『ガリレオシリーズ』がこれほど人気なのは、話自体の面白さもさることながら、上記のキャラクター達の吸引力に依るところも大きいです。
こうしたキャラクターって、実は作品が長期シリーズ化される前、短編作品にさらりと登場していることがままあります。予想以上に作者の筆が乗り、一作きりの登場で終わらせるのはもったいないと思ったのかな?それが自分の好きなキャラクターだった時は、読者としても喜び倍増です。今日取り上げる短編集には、後にシリーズ作品の主人公となるキャラクターが複数出てくるんですよ。西澤保彦さんの『赤い糸の呻き』です。
こんな人におすすめ
バラエティ豊かな本格ミステリー短編集が読みたい人
続きを読む
 「こんな結末は読んだことがない」「予想を遥かに超えた奇想天外なストーリー」。物語を評する上で、これらの文言はしばしば誉め言葉として使われます。私自身、事前の予想を裏切られるビックリ展開は大好物。この話は一体どう落着するのだろうと、手に汗握りながらページをめくったことも一度や二度ではありません。
「こんな結末は読んだことがない」「予想を遥かに超えた奇想天外なストーリー」。物語を評する上で、これらの文言はしばしば誉め言葉として使われます。私自身、事前の予想を裏切られるビックリ展開は大好物。この話は一体どう落着するのだろうと、手に汗握りながらページをめくったことも一度や二度ではありません。
その一方、期待通りに進む王道の物語も面白いものです。それは、『水戸黄門』や『必殺仕事人』が今なお支持されることからも分かります。私の中では、このシリーズもそういう安定・安心枠なんですよ。中山七里さん『毒島シリーズ』第四弾、『作家刑事毒島の暴言』です。
こんな人におすすめ
・皮肉の効いたミステリー短編集が読みたい人
・『毒島シリーズ』のファン
続きを読む
 この世には、様々な記念日や行事があります。大晦日、正月、ひな祭り、ハロウィン、バレンタイン。個人レベルなら誕生日や結婚記念日などもあるでしょう。こうした記念日には、プレゼントにごちそうなど、とにかく華やかできらきらしたイメージがあります。
この世には、様々な記念日や行事があります。大晦日、正月、ひな祭り、ハロウィン、バレンタイン。個人レベルなら誕生日や結婚記念日などもあるでしょう。こうした記念日には、プレゼントにごちそうなど、とにかく華やかできらきらしたイメージがあります。
反面、華やかであればあるほど、創作の世界ではしばしば血生臭く演出されることもあります。クリスマスなんて、まさにいい例ではないでしょうか。有名なスリラー映画『暗闇にベルが鳴る』や『ローズマリーの赤ちゃん』も、作中の季節はクリスマスシーズンでした。周りが賑やかで楽しげな分、登場人物達の恐怖や絶望が際立つのかもしれません。それからこの作品も、クリスマスが重要な要素なんですよ。西澤保彦さんの『仔羊たちの聖夜』です。
こんな人におすすめ
・多重解決ミステリーが読みたい人
・『匠千暁シリーズ』が好きな人
続きを読む
 二〇二五年最後の一日となりました。今年も色々あったものの、無事にブログを続けることができて感無量です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
二〇二五年最後の一日となりました。今年も色々あったものの、無事にブログを続けることができて感無量です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
 SFやホラーのジャンルにおいては、超能力・霊能力・魔力といった異能が頻繁に登場します。と同時に、異能を取り締まったり、サポートしたりする組織や職員が出てくる機会も多いです。日本に限らず海外でも同様なので、万国共通の発想なのかもしれません。
SFやホラーのジャンルにおいては、超能力・霊能力・魔力といった異能が頻繁に登場します。と同時に、異能を取り締まったり、サポートしたりする組織や職員が出てくる機会も多いです。日本に限らず海外でも同様なので、万国共通の発想なのかもしれません。 子どもから大人まで、長く社会生活を送っていると、グループを組む機会がしばしばあります。純粋に気が合ってできた仲良しグループもあれば、教師や上司の指示でチームを作ることもあるでしょう。ここでの人間関係が円滑か否かで、物事の成否は大きく変わります。
子どもから大人まで、長く社会生活を送っていると、グループを組む機会がしばしばあります。純粋に気が合ってできた仲良しグループもあれば、教師や上司の指示でチームを作ることもあるでしょう。ここでの人間関係が円滑か否かで、物事の成否は大きく変わります。 フィクション作品においては、現実では珍しい部類に入る名前の登場人物がしばしば出てきます。大場つぐみさん原作による漫画『DEATH NOTE』の主人公は<夜神 月(やがみ らいと>ですし、西尾維新さん『物語シリーズ』ヒロインは<戦場ヶ原 ひたぎ(せんじょうがはら ひたぎ>です。少し昔のものでは、吉川英治さん『宮本武蔵』に準主人公格で出てくる<本位田 又八(ほんいでん またはち)>も結構珍しい名前と言えるでしょう。
フィクション作品においては、現実では珍しい部類に入る名前の登場人物がしばしば出てきます。大場つぐみさん原作による漫画『DEATH NOTE』の主人公は<夜神 月(やがみ らいと>ですし、西尾維新さん『物語シリーズ』ヒロインは<戦場ヶ原 ひたぎ(せんじょうがはら ひたぎ>です。少し昔のものでは、吉川英治さん『宮本武蔵』に準主人公格で出てくる<本位田 又八(ほんいでん またはち)>も結構珍しい名前と言えるでしょう。 現代は個人主義の時代だと言われています。個人の意思や多様性というものが重視され、公より私を充実させることの方が大事。求人案内でも、<アットホームな社風><休日に社員同士でレジャーに出かけます>などといった文言は喜ばれない傾向にあるようです。
現代は個人主義の時代だと言われています。個人の意思や多様性というものが重視され、公より私を充実させることの方が大事。求人案内でも、<アットホームな社風><休日に社員同士でレジャーに出かけます>などといった文言は喜ばれない傾向にあるようです。 <色>には、人の気持ちに働きかける力があるそうです。赤やオレンジは活力を呼び覚まし、緑は心をリラックスさせ、ピンクは幸福感を感じさせるのだとか。そういえば一昔前、戦隊ヒーローは、行動派の<赤>やクールな<青>というように、各々の個性と色が対応していることが多かったですね。実際にはそこまで明確に性質が分かれるようなことはないのでしょうが、色が印象を左右することは確かだと思います。
<色>には、人の気持ちに働きかける力があるそうです。赤やオレンジは活力を呼び覚まし、緑は心をリラックスさせ、ピンクは幸福感を感じさせるのだとか。そういえば一昔前、戦隊ヒーローは、行動派の<赤>やクールな<青>というように、各々の個性と色が対応していることが多かったですね。実際にはそこまで明確に性質が分かれるようなことはないのでしょうが、色が印象を左右することは確かだと思います。 昔から、雑誌の読み物ページにある小説紹介コーナーや、本屋のPOPを読むのが好きでした。あの手の紹介文って、短いながらビシッと決まった名文が多いんですよね。がっつり長いレビューとはまた違う面白さがあって、ついつい見入ってしまいます。
昔から、雑誌の読み物ページにある小説紹介コーナーや、本屋のPOPを読むのが好きでした。あの手の紹介文って、短いながらビシッと決まった名文が多いんですよね。がっつり長いレビューとはまた違う面白さがあって、ついつい見入ってしまいます。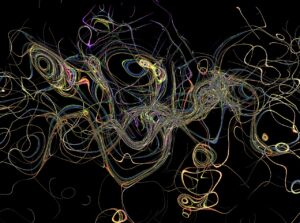 火村英生、犀川創平、湯川学、中禅寺秋彦・・・日本の小説界には、たくさんの名キャラクターがいます。物語を盛り上げる上で、魅力的な主要登場人物の存在は不可欠。『S&Mシリーズ』や『ガリレオシリーズ』がこれほど人気なのは、話自体の面白さもさることながら、上記のキャラクター達の吸引力に依るところも大きいです。
火村英生、犀川創平、湯川学、中禅寺秋彦・・・日本の小説界には、たくさんの名キャラクターがいます。物語を盛り上げる上で、魅力的な主要登場人物の存在は不可欠。『S&Mシリーズ』や『ガリレオシリーズ』がこれほど人気なのは、話自体の面白さもさることながら、上記のキャラクター達の吸引力に依るところも大きいです。 「こんな結末は読んだことがない」「予想を遥かに超えた奇想天外なストーリー」。物語を評する上で、これらの文言はしばしば誉め言葉として使われます。私自身、事前の予想を裏切られるビックリ展開は大好物。この話は一体どう落着するのだろうと、手に汗握りながらページをめくったことも一度や二度ではありません。
「こんな結末は読んだことがない」「予想を遥かに超えた奇想天外なストーリー」。物語を評する上で、これらの文言はしばしば誉め言葉として使われます。私自身、事前の予想を裏切られるビックリ展開は大好物。この話は一体どう落着するのだろうと、手に汗握りながらページをめくったことも一度や二度ではありません。 この世には、様々な記念日や行事があります。大晦日、正月、ひな祭り、ハロウィン、バレンタイン。個人レベルなら誕生日や結婚記念日などもあるでしょう。こうした記念日には、プレゼントにごちそうなど、とにかく華やかできらきらしたイメージがあります。
この世には、様々な記念日や行事があります。大晦日、正月、ひな祭り、ハロウィン、バレンタイン。個人レベルなら誕生日や結婚記念日などもあるでしょう。こうした記念日には、プレゼントにごちそうなど、とにかく華やかできらきらしたイメージがあります。