 小説では、しばしば<パンドラの箱>という表現が登場します。元ネタは、ギリシア神話に登場する、ゼウスによってすべての悪と災いが詰め込まれた箱(本来は壺ですが)。人類最初の女性・パンドラがこの箱を開けてしまったことで、この世には様々な不幸が蔓延するようになります。このことから、<パンドラの箱>とは<暴いてはならない秘密><知りたくなかった真相>というような意味で使われることが多いですね。
小説では、しばしば<パンドラの箱>という表現が登場します。元ネタは、ギリシア神話に登場する、ゼウスによってすべての悪と災いが詰め込まれた箱(本来は壺ですが)。人類最初の女性・パンドラがこの箱を開けてしまったことで、この世には様々な不幸が蔓延するようになります。このことから、<パンドラの箱>とは<暴いてはならない秘密><知りたくなかった真相>というような意味で使われることが多いですね。
パンドラの箱を開けてしまったことが導入となる物語はたくさんあります。特にミステリーやホラーといったジャンルに多いのではないでしょうか。この作品でも、封印されていたパンドラの箱が開いたことで、登場人物たちは混乱と不安のどん底に突き落とされます。小池真理子さんの『懐かしい骨』です。
こんな人におすすめ
記憶にまつわるミステリーが読みたい人
続きを読む
 ゆっくりと穏やかな生活を目指す<スローライフ>が注目されるようになったのは、二〇〇年を過ぎた頃かららしいです。同時に、都会の喧騒を離れた田舎暮らしに憧れる人達も増え始めました。この流れを受けたせいでしょうか。最近は田舎暮らしをテーマにした小説でも、<都会から来た主人公が、色々ありながらも近隣住民と絆を作り、困難を乗り越えて田舎暮らしに馴染む>という爽やかな作風のものが多い気がします。
ゆっくりと穏やかな生活を目指す<スローライフ>が注目されるようになったのは、二〇〇年を過ぎた頃かららしいです。同時に、都会の喧騒を離れた田舎暮らしに憧れる人達も増え始めました。この流れを受けたせいでしょうか。最近は田舎暮らしをテーマにした小説でも、<都会から来た主人公が、色々ありながらも近隣住民と絆を作り、困難を乗り越えて田舎暮らしに馴染む>という爽やかな作風のものが多い気がします。
もちろん、こういう小説も面白いのですが、あくまでフィクションの世界限定ならば、田舎の閉鎖的でドロドロした空気を描く作品もけっこう好きだったりします。この手の作品で一番有名なのは、やはり『金田一耕介シリーズ』でしょうか。ここ最近なら、辻村深月さんの『水底フェスタ』や中山七里さんの『ワルツを踊ろう』も、地方都市の閉ざされた世界観が巧みに描写されていました。今回ご紹介する作品でも、日本の村社会の恐ろしさがテーマになっています。櫛木理宇さんの『鵜頭川村事件』です。
こんな人におすすめ
田舎を舞台にしたパニック小説が読みたい人
続きを読む
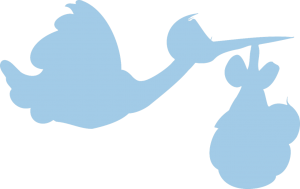 厚生労働省の発表によると、国内のひとり親家庭の数は二〇一一年度の時点で母子家庭が一二三.八万世帯、父子家庭が二二.三万世帯だそうです。この記事を書いている時(二〇一八年)にはもっと増えていることでしょう。私が注目したのは、一九八八年度の調査の時と比べて、離別や死別ではなく未婚によるひとり親家庭が増えている点です。結婚しないまま子どもをもうけ、育てる生活スタイルは、もはや海外だけのものではありません。
厚生労働省の発表によると、国内のひとり親家庭の数は二〇一一年度の時点で母子家庭が一二三.八万世帯、父子家庭が二二.三万世帯だそうです。この記事を書いている時(二〇一八年)にはもっと増えていることでしょう。私が注目したのは、一九八八年度の調査の時と比べて、離別や死別ではなく未婚によるひとり親家庭が増えている点です。結婚しないまま子どもをもうけ、育てる生活スタイルは、もはや海外だけのものではありません。
とはいえ、日本において未婚のまま親になるということは、様々な困難に見舞われることも事実。永井するみさんの『俯いていたつもりはない』、柚木麻子さんの『本屋さんのダイアナ』、唯川恵さんの『100万回の言い訳』などでもひとり親家庭が登場し、多くの試練に立ち向かっていました。私が最近読んだこの作品にも、悪戦苦闘する未婚の親が出てきましたよ。垣谷美雨さんの『四十歳、未婚出産』です。
こんな人におすすめ
シングルマザーの奮闘記が読みたい人
続きを読む
 ホラー好きな私が思うに、怪談話が発生するためにはいくつか条件があります。例えば<過去にその場所で悲惨な出来事が起こっている(ex.遺体発見現場)>だったり<すぐには逃げられないほど無防備になる場所(ex.トイレ)>だったり。意外かもしれませんが、「人の気配を感じる場所である」というのもその一つ。この世はすべて表裏一体、生者がいるからこそ死者がいて、幽霊もいます。簡単に行き来できない無人島が怪談の舞台になりにくいのは、この辺りが原因ではないでしょうか。
ホラー好きな私が思うに、怪談話が発生するためにはいくつか条件があります。例えば<過去にその場所で悲惨な出来事が起こっている(ex.遺体発見現場)>だったり<すぐには逃げられないほど無防備になる場所(ex.トイレ)>だったり。意外かもしれませんが、「人の気配を感じる場所である」というのもその一つ。この世はすべて表裏一体、生者がいるからこそ死者がいて、幽霊もいます。簡単に行き来できない無人島が怪談の舞台になりにくいのは、この辺りが原因ではないでしょうか。
大勢の人の気配を感じるホラースポットの代表格と言えば、やはり「学校」。普段はたくさんの子どもや教職員が出入りして賑やかな分、無人になった時の不気味さが際立ち、多くの怪談話が発生しました。学校を舞台にしたホラー小説といえば、綾辻行人さんの『Another』や辻村深月さんの『冷たい校舎の時は止まる』などが有名です。最近読んだ学園ホラーはこちら。近藤史恵さんの『震える教室』です。
こんな人におすすめ
・学校を舞台にしたホラー小説が好きな人
・ホラー小説デビューしたい人
続きを読む
 「下着が大好き」と言われた時、人はどんな反応を返すでしょうか。「分かる分かる」と頷く人もいるでしょうが、「いやらしい」「はしたない」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。身に付ける場所が場所なだけに、下着は性的なものを連想させてしまうからかもしれません。
「下着が大好き」と言われた時、人はどんな反応を返すでしょうか。「分かる分かる」と頷く人もいるでしょうが、「いやらしい」「はしたない」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。身に付ける場所が場所なだけに、下着は性的なものを連想させてしまうからかもしれません。
ですが、考えてみれば変な話です。公道を下着姿で闊歩するというならともかく、大多数の人は服の下に下着を身に付けているはず。それなら誰にも迷惑はかけないわけですし、「ワンピースが好き」「ジーパン最高」と同じ感覚で「下着が大好き」と言っても何一つ問題はありません。あらゆる衣類の中で最も肌に触れる製品なのですから、熱心に選び、機能性だけでなく美しさや可愛さを求めることはある意味で当然とも言えます。そんな下着に対する夢や愛着を描いた本を読みました。近藤史恵さんの『シフォン・リボン・シフォン』です。
こんな人におすすめ
下着を軸にしたヒューマンストーリーを読みたい人
続きを読む
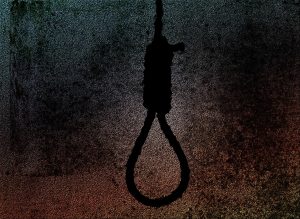 「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
冤罪をテーマにした小説といえば、高野和明さんの『13階段』や大門剛明さんの『テミスの求刑』、ややテイストは違いますが伊坂幸太郎さんの『ゴールデンスランバー』などが有名です。これらの作品の中で犯罪者として告発された人物は、自分は潔白だと訴えていました。では、自らが犯罪者であることは認めた上で、告発された罪の一部が冤罪だと訴えた場合はどうでしょうか?ただでさえ難しい冤罪問題が、より複雑になることは想像に難くありません。今日紹介するのは、櫛木理宇さんの『チェインドッグ』。タイトルの意味も含めて、考えさせられるところの多い作品でした。
こんな人におすすめ
サイコパスが出てくるミステリー小説が読みたい人
続きを読む
 <記憶喪失>という言葉を見聞きしたことがない人は、恐らくいないと思います。正確には<逆行性健忘>といい、過去の記憶を思い出すことが困難になる症状を指します。この三日間、どんな風に過ごしたかまるで思い出せないというだけで、ものすごく不安でしょう。まして、今まで生きてきた人生すべての記憶を失い、自分が何者か分からないとしたら・・・その恐怖は想像を絶するものがあります。
<記憶喪失>という言葉を見聞きしたことがない人は、恐らくいないと思います。正確には<逆行性健忘>といい、過去の記憶を思い出すことが困難になる症状を指します。この三日間、どんな風に過ごしたかまるで思い出せないというだけで、ものすごく不安でしょう。まして、今まで生きてきた人生すべての記憶を失い、自分が何者か分からないとしたら・・・その恐怖は想像を絶するものがあります。
現実では恐ろしい記憶喪失ですが、フィクションの世界においては、物語を盛り上げる要素となりえます。宮部みゆきさんの『レベル7』、東野圭吾さんの『むかし僕が死んだ家』、綾辻行人さんの『黒猫館の殺人』などは、<記憶喪失>というキーワードを上手く絡めた傑作ミステリーでした。この作品にも記憶喪失になったヒロインが登場します。近藤史恵さんの『わたしの本の空白は』です。
こんな人におすすめ
記憶喪失をテーマにした小説が読みたい人
続きを読む
 古来、双子というのは神秘的な存在として扱われる傾向がありました。母親の胎内で一緒に育ち、一緒に生まれてくるという状況や、(一卵性の場合)そっくりな容姿などが人に謎めいた印象を与えたのでしょうね。現代でさえ、「双子の片方が怪我をするともう片方も痛みを感じる」「生後すぐ離れ離れになってもそっくりな人生を歩む」などといったミステリアスな説まであるほどです。
古来、双子というのは神秘的な存在として扱われる傾向がありました。母親の胎内で一緒に育ち、一緒に生まれてくるという状況や、(一卵性の場合)そっくりな容姿などが人に謎めいた印象を与えたのでしょうね。現代でさえ、「双子の片方が怪我をするともう片方も痛みを感じる」「生後すぐ離れ離れになってもそっくりな人生を歩む」などといったミステリアスな説まであるほどです。
フィクションの世界において、双子は「他人には分からない絆や確執を持つ存在」として描写されることが多い気がします。ぱっと思いつく限りでは、双子の少女の入れ替わりをテーマにしたエーリッヒ・ケストナーの『ふたりのロッテ』、泥棒と双子の兄弟の同居生活を描く宮部みゆきさんの『ステップファザー・ステップ』、ルイ十四世双子説と鉄仮面伝説を絡めた藤本ひとみさんの『ブルボンの封印』などなど。今回取り上げる小説にも、複雑な絆を持つ双子が登場します。岸田るり子さんの『月のない夜に』です。
こんな人におすすめ
サイコパスの登場する心理サスペンスが読みたい人
続きを読む
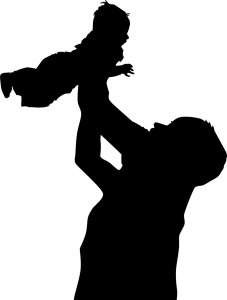 「濡れ落ち葉」という言葉が流行語大賞を受賞したのは一九八九年のことだそうです。意味は「濡れた落ち葉が払ってもなかなか落ちないように、主に定年退職後の夫が妻にべったりはりついて離れないこと」。男声差別だという意見もあったようですが、流行語大賞を取った以上、多くの国民の間に浸透していたことは事実でしょう。
「濡れ落ち葉」という言葉が流行語大賞を受賞したのは一九八九年のことだそうです。意味は「濡れた落ち葉が払ってもなかなか落ちないように、主に定年退職後の夫が妻にべったりはりついて離れないこと」。男声差別だという意見もあったようですが、流行語大賞を取った以上、多くの国民の間に浸透していたことは事実でしょう。
特にある程度以上の世代の男性の場合、仕事以外に趣味や交友関係を持たず、定年後にやることがなくて妻にまとわりつくというケースが多いようですね。まとわりつくならつくで、何か手伝いをしてくれるならまだしも、手は出さずに口だけ出すから嫌がられる、という話をよく聞きます。人間百年というこのご時世、リタイア後の人生を豊かに過ごせるか否かは自分自身の努力次第です。どう努力すればいいか分からないという人は、これを読んでみてはいかがでしょうか。垣谷美雨さんの『定年オヤジ改造計画』です。
続きを読む
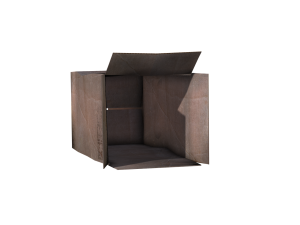 四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。
四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。
新居での生活には期待と不安が付きまとうもの。素晴らしい家を得たならば、新生活はより良いものとなるでしょう。でも、もしその家がおぞましく恐ろしいものだったなら・・・?この作品に登場する一家は、そんな恐ろしい家に住んでしまいます。小池真理子さんの『墓地を見おろす家』です。
続きを読む
 小説では、しばしば<パンドラの箱>という表現が登場します。元ネタは、ギリシア神話に登場する、ゼウスによってすべての悪と災いが詰め込まれた箱(本来は壺ですが)。人類最初の女性・パンドラがこの箱を開けてしまったことで、この世には様々な不幸が蔓延するようになります。このことから、<パンドラの箱>とは<暴いてはならない秘密><知りたくなかった真相>というような意味で使われることが多いですね。
小説では、しばしば<パンドラの箱>という表現が登場します。元ネタは、ギリシア神話に登場する、ゼウスによってすべての悪と災いが詰め込まれた箱(本来は壺ですが)。人類最初の女性・パンドラがこの箱を開けてしまったことで、この世には様々な不幸が蔓延するようになります。このことから、<パンドラの箱>とは<暴いてはならない秘密><知りたくなかった真相>というような意味で使われることが多いですね。
 ゆっくりと穏やかな生活を目指す<スローライフ>が注目されるようになったのは、二〇〇年を過ぎた頃かららしいです。同時に、都会の喧騒を離れた田舎暮らしに憧れる人達も増え始めました。この流れを受けたせいでしょうか。最近は田舎暮らしをテーマにした小説でも、<都会から来た主人公が、色々ありながらも近隣住民と絆を作り、困難を乗り越えて田舎暮らしに馴染む>という爽やかな作風のものが多い気がします。
ゆっくりと穏やかな生活を目指す<スローライフ>が注目されるようになったのは、二〇〇年を過ぎた頃かららしいです。同時に、都会の喧騒を離れた田舎暮らしに憧れる人達も増え始めました。この流れを受けたせいでしょうか。最近は田舎暮らしをテーマにした小説でも、<都会から来た主人公が、色々ありながらも近隣住民と絆を作り、困難を乗り越えて田舎暮らしに馴染む>という爽やかな作風のものが多い気がします。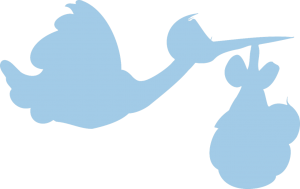 厚生労働省の発表によると、国内のひとり親家庭の数は二〇一一年度の時点で母子家庭が一二三.八万世帯、父子家庭が二二.三万世帯だそうです。この記事を書いている時(二〇一八年)にはもっと増えていることでしょう。私が注目したのは、一九八八年度の調査の時と比べて、離別や死別ではなく未婚によるひとり親家庭が増えている点です。結婚しないまま子どもをもうけ、育てる生活スタイルは、もはや海外だけのものではありません。
厚生労働省の発表によると、国内のひとり親家庭の数は二〇一一年度の時点で母子家庭が一二三.八万世帯、父子家庭が二二.三万世帯だそうです。この記事を書いている時(二〇一八年)にはもっと増えていることでしょう。私が注目したのは、一九八八年度の調査の時と比べて、離別や死別ではなく未婚によるひとり親家庭が増えている点です。結婚しないまま子どもをもうけ、育てる生活スタイルは、もはや海外だけのものではありません。 ホラー好きな私が思うに、怪談話が発生するためにはいくつか条件があります。例えば<過去にその場所で悲惨な出来事が起こっている(ex.遺体発見現場)>だったり<すぐには逃げられないほど無防備になる場所(ex.トイレ)>だったり。意外かもしれませんが、「人の気配を感じる場所である」というのもその一つ。この世はすべて表裏一体、生者がいるからこそ死者がいて、幽霊もいます。簡単に行き来できない無人島が怪談の舞台になりにくいのは、この辺りが原因ではないでしょうか。
ホラー好きな私が思うに、怪談話が発生するためにはいくつか条件があります。例えば<過去にその場所で悲惨な出来事が起こっている(ex.遺体発見現場)>だったり<すぐには逃げられないほど無防備になる場所(ex.トイレ)>だったり。意外かもしれませんが、「人の気配を感じる場所である」というのもその一つ。この世はすべて表裏一体、生者がいるからこそ死者がいて、幽霊もいます。簡単に行き来できない無人島が怪談の舞台になりにくいのは、この辺りが原因ではないでしょうか。 「下着が大好き」と言われた時、人はどんな反応を返すでしょうか。「分かる分かる」と頷く人もいるでしょうが、「いやらしい」「はしたない」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。身に付ける場所が場所なだけに、下着は性的なものを連想させてしまうからかもしれません。
「下着が大好き」と言われた時、人はどんな反応を返すでしょうか。「分かる分かる」と頷く人もいるでしょうが、「いやらしい」「はしたない」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。身に付ける場所が場所なだけに、下着は性的なものを連想させてしまうからかもしれません。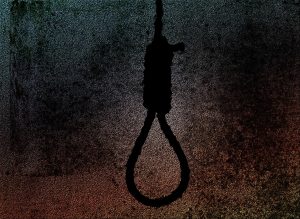 「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。
「この世で最も憎むべきものが何か分かる?戦争と冤罪なの」これは、私が昔見ていたドラマの台詞です。当時は子どもだったので聞き流しましたが、成長するにつれ、この言葉の意味が少しずつ分かるようになりました。犯人以外の人間が無実の罪で裁かれる。冤罪は、決して許されるものではありません。 <記憶喪失>という言葉を見聞きしたことがない人は、恐らくいないと思います。正確には<逆行性健忘>といい、過去の記憶を思い出すことが困難になる症状を指します。この三日間、どんな風に過ごしたかまるで思い出せないというだけで、ものすごく不安でしょう。まして、今まで生きてきた人生すべての記憶を失い、自分が何者か分からないとしたら・・・その恐怖は想像を絶するものがあります。
<記憶喪失>という言葉を見聞きしたことがない人は、恐らくいないと思います。正確には<逆行性健忘>といい、過去の記憶を思い出すことが困難になる症状を指します。この三日間、どんな風に過ごしたかまるで思い出せないというだけで、ものすごく不安でしょう。まして、今まで生きてきた人生すべての記憶を失い、自分が何者か分からないとしたら・・・その恐怖は想像を絶するものがあります。 古来、双子というのは神秘的な存在として扱われる傾向がありました。母親の胎内で一緒に育ち、一緒に生まれてくるという状況や、(一卵性の場合)そっくりな容姿などが人に謎めいた印象を与えたのでしょうね。現代でさえ、「双子の片方が怪我をするともう片方も痛みを感じる」「生後すぐ離れ離れになってもそっくりな人生を歩む」などといったミステリアスな説まであるほどです。
古来、双子というのは神秘的な存在として扱われる傾向がありました。母親の胎内で一緒に育ち、一緒に生まれてくるという状況や、(一卵性の場合)そっくりな容姿などが人に謎めいた印象を与えたのでしょうね。現代でさえ、「双子の片方が怪我をするともう片方も痛みを感じる」「生後すぐ離れ離れになってもそっくりな人生を歩む」などといったミステリアスな説まであるほどです。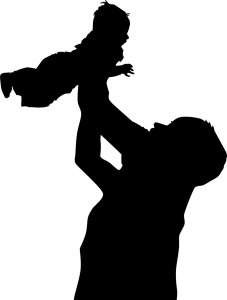 「濡れ落ち葉」という言葉が流行語大賞を受賞したのは一九八九年のことだそうです。意味は「濡れた落ち葉が払ってもなかなか落ちないように、主に定年退職後の夫が妻にべったりはりついて離れないこと」。男声差別だという意見もあったようですが、流行語大賞を取った以上、多くの国民の間に浸透していたことは事実でしょう。
「濡れ落ち葉」という言葉が流行語大賞を受賞したのは一九八九年のことだそうです。意味は「濡れた落ち葉が払ってもなかなか落ちないように、主に定年退職後の夫が妻にべったりはりついて離れないこと」。男声差別だという意見もあったようですが、流行語大賞を取った以上、多くの国民の間に浸透していたことは事実でしょう。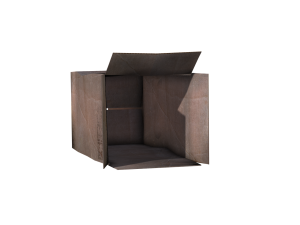 四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。
四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。