 高齢者ドライバーによる事故が取り沙汰されるようになったのはいつからでしょうか。正確なところは分かりませんが、ここ数年で、メディアが高齢者による事故を大きく取り上げる率は確実に上がっている気がします。年齢を重ねると、視力や筋力が落ちたり、反応速度が遅くなったりして、事故を引き起こす危険性が高まるとのこと。普通に扱えば便利な車も、ひとたび間違いを犯せば、走る凶器になりかねません。
高齢者ドライバーによる事故が取り沙汰されるようになったのはいつからでしょうか。正確なところは分かりませんが、ここ数年で、メディアが高齢者による事故を大きく取り上げる率は確実に上がっている気がします。年齢を重ねると、視力や筋力が落ちたり、反応速度が遅くなったりして、事故を引き起こす危険性が高まるとのこと。普通に扱えば便利な車も、ひとたび間違いを犯せば、走る凶器になりかねません。
しかし、だからといって「高齢者は運転させるな」と主張するのはあまりに一方的というものです。加齢により体力が落ちると、若者のように「これくらいの荷物、歩いて持ち運べるさ」「電車乗り継いで三十分の距離なんて近い近い」というわけにはいきません。居住地や家族構成、生活パターンなどによっては、運転しないと生活することが不可能というケースだってあるでしょう。そもそも、昨今やたら高齢者ドライバーの事故が多い気がするのは、車離れによる若者の事故率低下のせいであって、発生件数自体は数十年前から変わっていないんだとか。そうなると、単純に高齢者ドライバーだけを非難するわけにはいきませんね。今回は、そんな高齢者ドライバー問題について考えさせられる作品をご紹介します。垣谷美雨さんの『うちの父が運転をやめません』です。
こんな人におすすめ
高齢者ドライバー問題を絡めたヒューマン小説が読みたい人

 私は自他共に認める運動下手な人間ですので、体を動かす遊びはあまり得意ではありません。反面、インドア系の趣味は色々やりました。読書はもちろんのこと、映画鑑賞、音楽鑑賞、観劇、お菓子作り、ジグソーパズル、猫カフェ巡りetc。そんな中、歌舞伎には何となく興味を持てませんでした。あの独特の台詞回しや化粧に馴染めなかったんだと思います。
私は自他共に認める運動下手な人間ですので、体を動かす遊びはあまり得意ではありません。反面、インドア系の趣味は色々やりました。読書はもちろんのこと、映画鑑賞、音楽鑑賞、観劇、お菓子作り、ジグソーパズル、猫カフェ巡りetc。そんな中、歌舞伎には何となく興味を持てませんでした。あの独特の台詞回しや化粧に馴染めなかったんだと思います。 先日、雨上がりに虹を見ました。大はしゃぎするような年齢はとっくに過ぎてしまいましたが、青空にかかる七色の帯を見ると、なんとなく気持ちが明るくなります。そう思う人は多いのか、虹を神との契約と捉えたり、虹の根本には宝があると考えたりする文化もあるようです。
先日、雨上がりに虹を見ました。大はしゃぎするような年齢はとっくに過ぎてしまいましたが、青空にかかる七色の帯を見ると、なんとなく気持ちが明るくなります。そう思う人は多いのか、虹を神との契約と捉えたり、虹の根本には宝があると考えたりする文化もあるようです。 現在、インターネットは生活の至る所に浸透しています。一体いつからかは正確には分かりませんが、少なくとも私が大学生になる頃には、多くの人達が当たり前のようにネットで情報を検索したり、発言や創作物をネットに投稿したりしていました。ネットの危険性が声高に叫ばれるようになったのも、この頃からだと記憶しています。
現在、インターネットは生活の至る所に浸透しています。一体いつからかは正確には分かりませんが、少なくとも私が大学生になる頃には、多くの人達が当たり前のようにネットで情報を検索したり、発言や創作物をネットに投稿したりしていました。ネットの危険性が声高に叫ばれるようになったのも、この頃からだと記憶しています。 ものすごく忙しい時やトラブルが続いた時、ふとこんな風に思ったことはないでしょうか。「自分がもう一人いればいいのに・・・」と。鏡に映したかのようにそっくりな自分の分身。そんな存在がいれば、さぞ便利なように思えます。
ものすごく忙しい時やトラブルが続いた時、ふとこんな風に思ったことはないでしょうか。「自分がもう一人いればいいのに・・・」と。鏡に映したかのようにそっくりな自分の分身。そんな存在がいれば、さぞ便利なように思えます。 「嫁姑の仲よきはもっけの不思議」などという言葉もあるように、嫁と姑というのは多かれ少なかれ揉めるものと思われがちです。赤の他人の同性同士が身内になるという状況のせいでしょうか。もちろん、嫁姑関係が円満にいっている家庭もたくさんあるんでしょうが、小説やドラマの中には、確執を抱えた嫁と姑が大勢登場します。
「嫁姑の仲よきはもっけの不思議」などという言葉もあるように、嫁と姑というのは多かれ少なかれ揉めるものと思われがちです。赤の他人の同性同士が身内になるという状況のせいでしょうか。もちろん、嫁姑関係が円満にいっている家庭もたくさんあるんでしょうが、小説やドラマの中には、確執を抱えた嫁と姑が大勢登場します。 <超能力の例を一つ挙げてみなさい>と言われたら、どんな能力が出て来るでしょうか。口から言葉を発せずに意思を伝えるテレパシー、視界に入らないはずの出来事を見る透視能力、手を使わずに物を動かす念動力・・・どれもこれも有名な能力ですが、それらと並んで知名度が高いのが<予知能力>です。文字通り、その時点で起こっていない出来事を予め知る力のことで、かの有名なノストラダムスもこの能力の持ち主として知られています。
<超能力の例を一つ挙げてみなさい>と言われたら、どんな能力が出て来るでしょうか。口から言葉を発せずに意思を伝えるテレパシー、視界に入らないはずの出来事を見る透視能力、手を使わずに物を動かす念動力・・・どれもこれも有名な能力ですが、それらと並んで知名度が高いのが<予知能力>です。文字通り、その時点で起こっていない出来事を予め知る力のことで、かの有名なノストラダムスもこの能力の持ち主として知られています。 今更言うまでもない話ですが、殺人という犯罪は多くのものを奪っていきます。被害者本人の命や尊厳はもちろん、その家族の人生をも大きく揺るがし、ひっくり返し、時に破壊してしまうことすらあり得ます。昔見たドラマで、息子を殺された父親が言っていた「家族全員殺されたようなものだ」という台詞は、決して大げさなものではないのでしょう。
今更言うまでもない話ですが、殺人という犯罪は多くのものを奪っていきます。被害者本人の命や尊厳はもちろん、その家族の人生をも大きく揺るがし、ひっくり返し、時に破壊してしまうことすらあり得ます。昔見たドラマで、息子を殺された父親が言っていた「家族全員殺されたようなものだ」という台詞は、決して大げさなものではないのでしょう。 今や<婚活>という用語はすっかり一般的なものになりました。漢字にするとたった二文字ですが、そのやり方は様々です。インターネットの婚活サイトに登録したり、結婚相談所を介したり、大規模なパーティーに参加したり・・・最近は寺での座禅や農作業など、ユニークなイベントを利用した婚活も多いようですね。そんな婚活の中に<親婚活>というものがあります。
今や<婚活>という用語はすっかり一般的なものになりました。漢字にするとたった二文字ですが、そのやり方は様々です。インターネットの婚活サイトに登録したり、結婚相談所を介したり、大規模なパーティーに参加したり・・・最近は寺での座禅や農作業など、ユニークなイベントを利用した婚活も多いようですね。そんな婚活の中に<親婚活>というものがあります。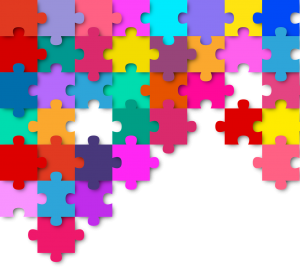 そこここで<断捨離>という言葉を見聞きするようになって、もうずいぶん経ちます。これは不要な物を捨てて身辺整理を行うことで心身の健康を得ようという思想で、元々はヨガから来ているんだとか。確かに、日本人には<もったいない>という考え方があるので、大量の不用品を延々と保管し続けるケースも少なくありません。
そこここで<断捨離>という言葉を見聞きするようになって、もうずいぶん経ちます。これは不要な物を捨てて身辺整理を行うことで心身の健康を得ようという思想で、元々はヨガから来ているんだとか。確かに、日本人には<もったいない>という考え方があるので、大量の不用品を延々と保管し続けるケースも少なくありません。