 物語が幸せな結末を迎える<ハッピーエンド>、主要キャラクターが不幸になる<バッドエンド>、傍から見れば不幸だけど当事者は満足している<メリーバッドエンド>、これまでのすべてがリセット・一からやり直しとなる<世界再編成エンド>・・・・・物語には、様々な結末があります。このエンディングが素晴らしいか否かで、作品の評価が決まると言っても過言ではありません。
物語が幸せな結末を迎える<ハッピーエンド>、主要キャラクターが不幸になる<バッドエンド>、傍から見れば不幸だけど当事者は満足している<メリーバッドエンド>、これまでのすべてがリセット・一からやり直しとなる<世界再編成エンド>・・・・・物語には、様々な結末があります。このエンディングが素晴らしいか否かで、作品の評価が決まると言っても過言ではありません。
こうしたエンディングの種類の一つに、<ビターエンド>というものがあります。読んで字のごとく、ほろ苦いエンディングのことで、バッドエンドほど不幸ではないがハッピーエンドとは言い難い・・・という結末を指します。個人的に、一番読者が身近に感じるエンディングはこれではないでしょうか。今日は、ビターエンドの恋愛小説を集めた短編集をご紹介したいと思います。唯川恵さんの『ゆうべ、もう恋なんかしないと誓った』です。
こんな人におすすめ
ほろ苦い読後感の恋愛ショートショートに興味がある人

 今年も残すところあとわずか。世間はすっかりクリスマスおよび年末ムードです。師走、などと言われるほど忙しない時期ですが、こういうバタバタした感じ、結構好きだったりします。
今年も残すところあとわずか。世間はすっかりクリスマスおよび年末ムードです。師走、などと言われるほど忙しない時期ですが、こういうバタバタした感じ、結構好きだったりします。 ダブル主人公というのは、手がける際に注意が必要な物語形式だそうです。描き方を間違えると片方だけが目立ってしまったり、最悪、もう片方がただの引き立て役になってしまうことがあり得ることが理由なのだとか。そのため、一時期、特にWeb小説界隈では<ダブル主人公は鬼門>という常識まで存在したらしいです。
ダブル主人公というのは、手がける際に注意が必要な物語形式だそうです。描き方を間違えると片方だけが目立ってしまったり、最悪、もう片方がただの引き立て役になってしまうことがあり得ることが理由なのだとか。そのため、一時期、特にWeb小説界隈では<ダブル主人公は鬼門>という常識まで存在したらしいです。 図書館には<開架>と<閉架>の二種類があるケースが多いです。<開架>とは、図書館利用者が自分で書棚の間を行き来し、自由に本を取り出して読むことができる利用方式のこと。<図書館>という言葉を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、こちらの形でしょう。
図書館には<開架>と<閉架>の二種類があるケースが多いです。<開架>とは、図書館利用者が自分で書棚の間を行き来し、自由に本を取り出して読むことができる利用方式のこと。<図書館>という言葉を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、こちらの形でしょう。 私は昔から魚介類が大好きです。海が近い地方で育ったせいか、肉より魚の方になじみ深さを感じます。子どもの頃はそれなりに好き嫌いがあったものの、魚に関しては、骨たっぷりの焼き魚だろうと、独特な匂いの青魚だろうと、ぱくぱく食べていたものです。
私は昔から魚介類が大好きです。海が近い地方で育ったせいか、肉より魚の方になじみ深さを感じます。子どもの頃はそれなりに好き嫌いがあったものの、魚に関しては、骨たっぷりの焼き魚だろうと、独特な匂いの青魚だろうと、ぱくぱく食べていたものです。 小説家になろう、カクヨム、アルファポリスetc。現在、国内には複数の創作物投稿サイトがあります。厳密に言えば、各サイトごとに違いがあり、メリット・デメリットも存在するようですが、私はあまり気にしないタイプ。時間がある時、目についたサイトで面白い作品が読めれば満足です。
小説家になろう、カクヨム、アルファポリスetc。現在、国内には複数の創作物投稿サイトがあります。厳密に言えば、各サイトごとに違いがあり、メリット・デメリットも存在するようですが、私はあまり気にしないタイプ。時間がある時、目についたサイトで面白い作品が読めれば満足です。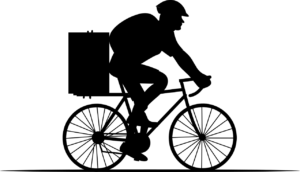 コロナ禍によって、これまであまり重要視されていなかったシステムや習慣に注目が集まるようになりました。例えば混雑した空間でのマスクの着用、手洗いうがいの徹底、オンラインでの会議や授業etcetc。コロナが第五類に移行した今もなお、すっかり社会に定着した感があります。
コロナ禍によって、これまであまり重要視されていなかったシステムや習慣に注目が集まるようになりました。例えば混雑した空間でのマスクの着用、手洗いうがいの徹底、オンラインでの会議や授業etcetc。コロナが第五類に移行した今もなお、すっかり社会に定着した感があります。 図書館に入庫された新刊の予約は、一種の戦争だと思っています。人気のある作家さんの最新刊や、映像化された話題作などは、図書館HPに新刊情報が載ると同時に予約が殺到。あっという間に何百人もの待機リストができることも珍しくありません。私はこの手の予約戦争に遅れがちなので、パソコン画面前で何度も「あーあ」とため息をつきました。
図書館に入庫された新刊の予約は、一種の戦争だと思っています。人気のある作家さんの最新刊や、映像化された話題作などは、図書館HPに新刊情報が載ると同時に予約が殺到。あっという間に何百人もの待機リストができることも珍しくありません。私はこの手の予約戦争に遅れがちなので、パソコン画面前で何度も「あーあ」とため息をつきました。 物語を創る上で、テーマ設定はとても重要です。中には、特にテーマを決めず自由気ままに創作するケースもあるでしょうが、これは恐らく少数派。「身分違いの恋を書こう」とか「サラリーマンの下剋上物語にしよう」とか、最初に設定しておくことの方が多いと思います。
物語を創る上で、テーマ設定はとても重要です。中には、特にテーマを決めず自由気ままに創作するケースもあるでしょうが、これは恐らく少数派。「身分違いの恋を書こう」とか「サラリーマンの下剋上物語にしよう」とか、最初に設定しておくことの方が多いと思います。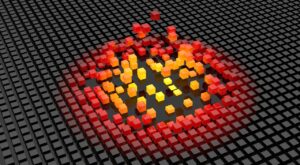 ミステリーの探偵役は、とにもかくにも個性的でインパクト抜群なタイプが多いです。シャーロック・ホームズや金田一耕助は言うに及ばず、坂木司さん『ひきこもり探偵シリーズ』の鳥井は精神的負荷がかかると幼児返りする引きこもりで、東川篤弥さん『謎解きはディナーのあとでシリーズ』の影山は毒舌執事。赤川次郎さん『三毛猫ホームズシリーズ』にいたっては、謎解きの中心となるのがなんと猫です。現実では到底出会えないようなキャラクターが生き生き事件解決しているのを見るのは楽しいですね。
ミステリーの探偵役は、とにもかくにも個性的でインパクト抜群なタイプが多いです。シャーロック・ホームズや金田一耕助は言うに及ばず、坂木司さん『ひきこもり探偵シリーズ』の鳥井は精神的負荷がかかると幼児返りする引きこもりで、東川篤弥さん『謎解きはディナーのあとでシリーズ』の影山は毒舌執事。赤川次郎さん『三毛猫ホームズシリーズ』にいたっては、謎解きの中心となるのがなんと猫です。現実では到底出会えないようなキャラクターが生き生き事件解決しているのを見るのは楽しいですね。