 ペットを飼うことは、ここで書ききれないほどの幸せをもたらしてくれます。毎日同じ屋根の下で寝起きし、食事をし、一緒に遊んだり、気まぐれに振り回されたり、甘えておねだりされたり・・・・・こんな風に家族として過ごしていれば、ペットの死により心を病む人がいるというのも頷けます。
ペットを飼うことは、ここで書ききれないほどの幸せをもたらしてくれます。毎日同じ屋根の下で寝起きし、食事をし、一緒に遊んだり、気まぐれに振り回されたり、甘えておねだりされたり・・・・・こんな風に家族として過ごしていれば、ペットの死により心を病む人がいるというのも頷けます。
ですが、ペットがもたらすのは喜びばかりではありません。どんな物事もそうであるように、辛いこと、大変なことも山ほどあります。体力的な辛さとか、精神的なプレッシャーとか、色々ありますが、突き詰めていけば最終的にお金の問題になるのではないでしょうか。動物を飼うためにはふさわしい住環境や餌を準備しなくてはなりませんし、病気や怪我をするたび、高額の医療費がかかります。こうやって列挙しただけでは苦労が分かりにくいかもしれませんが、この本を読めば少しはイメージが湧くかも・・・・・真梨幸子さんの『まりも日記』です。
こんな人におすすめ
猫を絡めたイヤミスが読みたい人

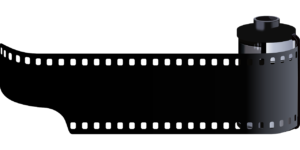 写真が発明されたのは、一九世紀前半のことです。この当時、産業革命によりいわゆる中産階級が多数出現し、彼らの間で肖像画が流行したことで、一気に写真の需要も高まったのだとか。そんな写真は一八四三年、長崎に入港したオランダ船により日本に入ってきました。当初は一枚撮るのにも特殊な技術や設備が必要だったようですが、インスタントカメラや携帯電話、スマートフォン等の普及により、今やその気になれば幼児だって写真を撮ることができます。
写真が発明されたのは、一九世紀前半のことです。この当時、産業革命によりいわゆる中産階級が多数出現し、彼らの間で肖像画が流行したことで、一気に写真の需要も高まったのだとか。そんな写真は一八四三年、長崎に入港したオランダ船により日本に入ってきました。当初は一枚撮るのにも特殊な技術や設備が必要だったようですが、インスタントカメラや携帯電話、スマートフォン等の普及により、今やその気になれば幼児だって写真を撮ることができます。 小説にせよ漫画にせよ映画にせよドラマにせよ、フィクションの世界での恋愛は、女性メインのストーリーになりがちです。男性より女性の方が恋愛のあれこれに対する関心度合が高く、読者・視聴者として取り込みやすいからでしょうか。そして、メインターゲットが女性である以上、女性中心の物語にした方がより共感を呼ぶのかもしれません。
小説にせよ漫画にせよ映画にせよドラマにせよ、フィクションの世界での恋愛は、女性メインのストーリーになりがちです。男性より女性の方が恋愛のあれこれに対する関心度合が高く、読者・視聴者として取り込みやすいからでしょうか。そして、メインターゲットが女性である以上、女性中心の物語にした方がより共感を呼ぶのかもしれません。 どこかの記事でも書いた気がしますが、今の私は気に入った作家さんの作品を一気読みするタイプの人間です。「この人の小説、面白い!」と思ったら、図書館でその作家さんの小説を探し、借りられるだけ借りるというのがいつものパターン。当然、自分が今、誰の著作を読んでいるかをしっかりチェックしておく必要があります。
どこかの記事でも書いた気がしますが、今の私は気に入った作家さんの作品を一気読みするタイプの人間です。「この人の小説、面白い!」と思ったら、図書館でその作家さんの小説を探し、借りられるだけ借りるというのがいつものパターン。当然、自分が今、誰の著作を読んでいるかをしっかりチェックしておく必要があります。 学生だった頃を振り返ってみると、一番ぎすぎすして精神的にきつかったのが中学時代。ただ、一番後悔が多いのは小学校時代です。何しろ小学生と言えば、まだ幼児に毛が生えたようなもの(言い過ぎ?)。後になってみれば、よくあんなこと言えたよな、なんであんなことしちゃったんだろう・・・と頭を抱えてしまうようなこともありました。
学生だった頃を振り返ってみると、一番ぎすぎすして精神的にきつかったのが中学時代。ただ、一番後悔が多いのは小学校時代です。何しろ小学生と言えば、まだ幼児に毛が生えたようなもの(言い過ぎ?)。後になってみれば、よくあんなこと言えたよな、なんであんなことしちゃったんだろう・・・と頭を抱えてしまうようなこともありました。 クリエイティブな世界には、複数の名義で作品を発表されている方がしばしば存在します。理由は人それぞれでしょうが、一番は、名前に付きまとうイメージや先入観を払拭するためではないでしょうか。〇〇先生は恋愛漫画とか、△△先生はロックミュージックとか、色々イメージがありますからね。
クリエイティブな世界には、複数の名義で作品を発表されている方がしばしば存在します。理由は人それぞれでしょうが、一番は、名前に付きまとうイメージや先入観を払拭するためではないでしょうか。〇〇先生は恋愛漫画とか、△△先生はロックミュージックとか、色々イメージがありますからね。 <不思議>という言葉を辞書で引いてみると、「そうであることの原因がよく分からず、なぜだろうと考えさせられること。その事柄」とあります。この「原因がよく分からない」というところが最大のポイント。<怖い小説>や<ハラハラさせられる小説>の場合、大抵はその原因が作中で判明しますが、<不思議な小説>はその限りではありません。登場人物にも読者にも、事態の真相や全容が分からないまま終わることだってあり得ます。
<不思議>という言葉を辞書で引いてみると、「そうであることの原因がよく分からず、なぜだろうと考えさせられること。その事柄」とあります。この「原因がよく分からない」というところが最大のポイント。<怖い小説>や<ハラハラさせられる小説>の場合、大抵はその原因が作中で判明しますが、<不思議な小説>はその限りではありません。登場人物にも読者にも、事態の真相や全容が分からないまま終わることだってあり得ます。 音楽とは文字通り<音を楽しむ>ものです。私は生憎音楽があまり得意ではありませんが、カラオケに行ったり歌を聞いたりするのは大好き。iPodにお気に入りの曲を入れ、登下校や通勤、ショッピング中などに聞くのが昔からの日課でした。
音楽とは文字通り<音を楽しむ>ものです。私は生憎音楽があまり得意ではありませんが、カラオケに行ったり歌を聞いたりするのは大好き。iPodにお気に入りの曲を入れ、登下校や通勤、ショッピング中などに聞くのが昔からの日課でした。 「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。
「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。 日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。
日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。