 一昔前、<お年寄り>という言葉が持つイメージは、貫禄や老練、泰然自若といったものでした。最近はどうでしょうか。老害、暴走老人、シルバーモンスター・・・残念ながら、そんなマイナスイメージのある単語が飛び交っているのが現状です。もちろん、老若男女問わず、非常識で悪質な人間はいつの時代も大勢いました。ただ、感情をコントロールする前頭葉の機能は、ただでさえ加齢により低下するもの。加えて、核家族化や非婚化が進む現代において、かつてのように家族と暮らすことができず、コミュニケーション能力が一気に衰えて暴走するお年寄りが増えたことは事実だと思います。
一昔前、<お年寄り>という言葉が持つイメージは、貫禄や老練、泰然自若といったものでした。最近はどうでしょうか。老害、暴走老人、シルバーモンスター・・・残念ながら、そんなマイナスイメージのある単語が飛び交っているのが現状です。もちろん、老若男女問わず、非常識で悪質な人間はいつの時代も大勢いました。ただ、感情をコントロールする前頭葉の機能は、ただでさえ加齢により低下するもの。加えて、核家族化や非婚化が進む現代において、かつてのように家族と暮らすことができず、コミュニケーション能力が一気に衰えて暴走するお年寄りが増えたことは事実だと思います。
これまでこのブログでは、中山七里さんの『要介護探偵の事件簿』や宮部みゆきさんの『淋しい狩人』といった、老いてなお気力も知力も若者に負けず、経験を活かして活躍するお年寄りの小説を取り上げてきました。こんなお年寄りばかりなら何の問題もないのですが、悲しいかな、善人もいれば悪人もいるのが世の常です。今回は、読者の背筋を凍らせるような老人が出てくる作品をご紹介します。櫛木理宇さんの『老い蜂』です。
こんな人におすすめ
老人ストーカーが絡んだサイコスリラーに興味がある人

 <クロスオーバー>という手法があります。これは異なる作品同士が一時的にストーリーを共有する手法のことで、主にアメリカンコミックの世界で発達したのだとか。映画化もされた『アベンジャーズシリーズ』で、アイアンマンやハルク等、違う作品のキャラクター達が共演して大活躍したことは、ご存知の方も多いと思います。
<クロスオーバー>という手法があります。これは異なる作品同士が一時的にストーリーを共有する手法のことで、主にアメリカンコミックの世界で発達したのだとか。映画化もされた『アベンジャーズシリーズ』で、アイアンマンやハルク等、違う作品のキャラクター達が共演して大活躍したことは、ご存知の方も多いと思います。 新年明けましておめでとうございます。二〇一六年に開設した当ブログは、あと数カ月でめでたく六年目を迎えます。開始当初は、三日坊主になるのではないか、ちょっと不安だったものですが、閲覧してくれる皆様のおかげでここまで続けることができました。相変わらず趣味丸出しの偏ったレビューサイトになると思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
新年明けましておめでとうございます。二〇一六年に開設した当ブログは、あと数カ月でめでたく六年目を迎えます。開始当初は、三日坊主になるのではないか、ちょっと不安だったものですが、閲覧してくれる皆様のおかげでここまで続けることができました。相変わらず趣味丸出しの偏ったレビューサイトになると思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 日本語って、とても美しい言語だと思います。もちろん、どの民族にとっても自国の言葉は誇れるものなのでしょうが、神々が出雲大社に集まる十月を<神無月>(出雲地方では神在月)と呼んだり、雪の結晶の多くが六角形をしていることから雪を<六花>と表現したりする感覚は、日本語独自のものではないでしょうか。こういう雅な表現が大好きな私は、学生時代、古文の資料集を読んで悦に入っていたものです。
日本語って、とても美しい言語だと思います。もちろん、どの民族にとっても自国の言葉は誇れるものなのでしょうが、神々が出雲大社に集まる十月を<神無月>(出雲地方では神在月)と呼んだり、雪の結晶の多くが六角形をしていることから雪を<六花>と表現したりする感覚は、日本語独自のものではないでしょうか。こういう雅な表現が大好きな私は、学生時代、古文の資料集を読んで悦に入っていたものです。 小説や漫画がシリーズ化するための条件は色々ありますが、まず第一は<一冊目が面白かったこと>だと思います。最初の一歩の出来が良く、人気を集めたからこそ続編が出るというのは自明の理。シリーズ作品の中で、一番好きなものとして第一作目を挙げる人が多いのは当然と言えるでしょう。
小説や漫画がシリーズ化するための条件は色々ありますが、まず第一は<一冊目が面白かったこと>だと思います。最初の一歩の出来が良く、人気を集めたからこそ続編が出るというのは自明の理。シリーズ作品の中で、一番好きなものとして第一作目を挙げる人が多いのは当然と言えるでしょう。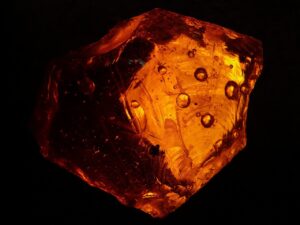 少し前から<親ガチャ>という言葉を聞くようになりました。これはカプセルトイやソーシャルゲームのアイテム課金方式の<ガチャ>になぞられた言い方で、<どんな親の元に生まれるか、事前に自分で選ぶことはできない>という意味だとか。「甘えだ」「責任転嫁に過ぎない」という非難もある一方、DV等に苦しんで育った人達からは賛同を得ているようです。
少し前から<親ガチャ>という言葉を聞くようになりました。これはカプセルトイやソーシャルゲームのアイテム課金方式の<ガチャ>になぞられた言い方で、<どんな親の元に生まれるか、事前に自分で選ぶことはできない>という意味だとか。「甘えだ」「責任転嫁に過ぎない」という非難もある一方、DV等に苦しんで育った人達からは賛同を得ているようです。 SFやファンタジーの世界では、しばしば超自然的な能力が登場します。創作物の中ではとても魅力的な要素となり得ますが、現実世界に置き換えた場合、「こんな能力があっても困るよな・・・」と思うものも多いです。<辺り一帯に大地震や地割れを起こす能力>なんて、現代日本で必要となる機会がそうそうあるとも思えません。
SFやファンタジーの世界では、しばしば超自然的な能力が登場します。創作物の中ではとても魅力的な要素となり得ますが、現実世界に置き換えた場合、「こんな能力があっても困るよな・・・」と思うものも多いです。<辺り一帯に大地震や地割れを起こす能力>なんて、現代日本で必要となる機会がそうそうあるとも思えません。 ミステリーないしサスペンス作品に最も多く登場する職業は何でしょうか。仮にランキングを作ったとしたら、上位三位の中には<警察関係者>が入っていると思います。というか、上記のジャンルの作品で、主要登場人物の中に警察関係者が一人もいないケースの方がレアでしょう。
ミステリーないしサスペンス作品に最も多く登場する職業は何でしょうか。仮にランキングを作ったとしたら、上位三位の中には<警察関係者>が入っていると思います。というか、上記のジャンルの作品で、主要登場人物の中に警察関係者が一人もいないケースの方がレアでしょう。 宗教とは本来、人を救い、拠り所となるための存在です。苦しいことがあれば乗り越えられるよう神に祈り、善行を積めば死後に天国に行けると信じる。そんな信仰心は、時に人に大きな力を与えました。「神様の加護があるのだから大丈夫」。そう確信し、自信を持って物事に臨めば、不安も緊張もなく一〇〇パーセント能力を発揮することも可能でしょう。
宗教とは本来、人を救い、拠り所となるための存在です。苦しいことがあれば乗り越えられるよう神に祈り、善行を積めば死後に天国に行けると信じる。そんな信仰心は、時に人に大きな力を与えました。「神様の加護があるのだから大丈夫」。そう確信し、自信を持って物事に臨めば、不安も緊張もなく一〇〇パーセント能力を発揮することも可能でしょう。 「結婚においては本人同士の気持ちが一番大事」「相手の家族なんて関係ない」。昨今ではこういう考え方が主流だと思います。もちろん、それも一つの真理なのでしょうが、やはり揉め事は少ない方が有難いもの。配偶者の家族が善人で、結婚後も円満に付き合っていけるなら、これほど嬉しいことはありません。
「結婚においては本人同士の気持ちが一番大事」「相手の家族なんて関係ない」。昨今ではこういう考え方が主流だと思います。もちろん、それも一つの真理なのでしょうが、やはり揉め事は少ない方が有難いもの。配偶者の家族が善人で、結婚後も円満に付き合っていけるなら、これほど嬉しいことはありません。