 <あの人は人が変わってしまった>という言い回しがあります。ある人の性格や行動パターンが唐突にガラッと変わった時によく用いられますね。現実では、本当に人が変わったわけではなく、何らかのきっかけにより人となりが激変したというケースがほとんどでしょう。
<あの人は人が変わってしまった>という言い回しがあります。ある人の性格や行動パターンが唐突にガラッと変わった時によく用いられますね。現実では、本当に人が変わったわけではなく、何らかのきっかけにより人となりが激変したというケースがほとんどでしょう。
一方、フィクションの世界の場合、例えでも何でもなく本当に<人が変わった>ということがあり得ます。こういう設定で有名なのは、東野圭吾さんの『秘密』。事故で死んだ娘の体に、同じく事故死した母親の魂が宿ってしまうというヒューマンファンタジーでした。何度も映像化されているので、ご存知の方も多いと思います。ただ、私が<人が変わった>系の小説で連想するのは、実はこちらの方なんですよ。西澤保彦さんの『人格転移の殺人』です。
こんな人におすすめ
SF設定が絡んだミステリーが読みたい人

 ペットを飼うことは、ここで書ききれないほどの幸せをもたらしてくれます。毎日同じ屋根の下で寝起きし、食事をし、一緒に遊んだり、気まぐれに振り回されたり、甘えておねだりされたり・・・・・こんな風に家族として過ごしていれば、ペットの死により心を病む人がいるというのも頷けます。
ペットを飼うことは、ここで書ききれないほどの幸せをもたらしてくれます。毎日同じ屋根の下で寝起きし、食事をし、一緒に遊んだり、気まぐれに振り回されたり、甘えておねだりされたり・・・・・こんな風に家族として過ごしていれば、ペットの死により心を病む人がいるというのも頷けます。 学生だった頃を振り返ってみると、一番ぎすぎすして精神的にきつかったのが中学時代。ただ、一番後悔が多いのは小学校時代です。何しろ小学生と言えば、まだ幼児に毛が生えたようなもの(言い過ぎ?)。後になってみれば、よくあんなこと言えたよな、なんであんなことしちゃったんだろう・・・と頭を抱えてしまうようなこともありました。
学生だった頃を振り返ってみると、一番ぎすぎすして精神的にきつかったのが中学時代。ただ、一番後悔が多いのは小学校時代です。何しろ小学生と言えば、まだ幼児に毛が生えたようなもの(言い過ぎ?)。後になってみれば、よくあんなこと言えたよな、なんであんなことしちゃったんだろう・・・と頭を抱えてしまうようなこともありました。 <不思議>という言葉を辞書で引いてみると、「そうであることの原因がよく分からず、なぜだろうと考えさせられること。その事柄」とあります。この「原因がよく分からない」というところが最大のポイント。<怖い小説>や<ハラハラさせられる小説>の場合、大抵はその原因が作中で判明しますが、<不思議な小説>はその限りではありません。登場人物にも読者にも、事態の真相や全容が分からないまま終わることだってあり得ます。
<不思議>という言葉を辞書で引いてみると、「そうであることの原因がよく分からず、なぜだろうと考えさせられること。その事柄」とあります。この「原因がよく分からない」というところが最大のポイント。<怖い小説>や<ハラハラさせられる小説>の場合、大抵はその原因が作中で判明しますが、<不思議な小説>はその限りではありません。登場人物にも読者にも、事態の真相や全容が分からないまま終わることだってあり得ます。 皆さんは公共交通機関で移動中、何をして時間を潰しますか?スマホで動画鑑賞やゲームをする人、クロスワードパズルをする人、睡眠不足解消のため眠る人・・・過ごし方は人それぞれです。私の場合、ほぼ迷わず読書一択。昔、新幹線での出張が多い仕事をしていた時は、どの本を持って行くかを考えるのが最優先の検討事案でした(笑)
皆さんは公共交通機関で移動中、何をして時間を潰しますか?スマホで動画鑑賞やゲームをする人、クロスワードパズルをする人、睡眠不足解消のため眠る人・・・過ごし方は人それぞれです。私の場合、ほぼ迷わず読書一択。昔、新幹線での出張が多い仕事をしていた時は、どの本を持って行くかを考えるのが最優先の検討事案でした(笑) フィクションの世界においては、しばしば、登場シーンはわずかにも関わらず存在感を発揮するキャラクターがいます。こういったキャラクターで私が真っ先に思いつくのは、西澤保彦さん『仔羊たちの聖夜』に登場する事件関係者の弟・英生さん(分かる方、います?)。出てくるのはたった数ページなものの、明晰な言動といい、<肉体的にも精神的にもぜい肉をそぎ落としたようなストイックな凄みがある>容姿といい、やたら印象的なんですよ。私はちょっと影のあるキャラに惹かれてしまいがちなので、「いつか別作品の主要登場人物になってくれないかな」と今でも思っています。
フィクションの世界においては、しばしば、登場シーンはわずかにも関わらず存在感を発揮するキャラクターがいます。こういったキャラクターで私が真っ先に思いつくのは、西澤保彦さん『仔羊たちの聖夜』に登場する事件関係者の弟・英生さん(分かる方、います?)。出てくるのはたった数ページなものの、明晰な言動といい、<肉体的にも精神的にもぜい肉をそぎ落としたようなストイックな凄みがある>容姿といい、やたら印象的なんですよ。私はちょっと影のあるキャラに惹かれてしまいがちなので、「いつか別作品の主要登場人物になってくれないかな」と今でも思っています。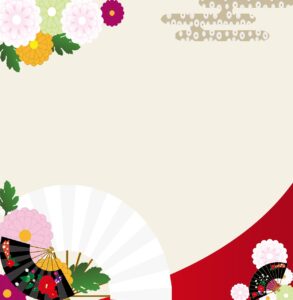 「最初から最後まできっちり読み通したことはないけど、大まかなあらすじは知っている」「漫画版や実写版しか見たことない」という小説って、意外と多いです。私の場合、ぱっと思いつくのは森鷗外の『舞姫』や太宰治の『人間失格』。一昔前の文豪の作品は、文体が現代と異なっていることもあり、なんとなくとっつきにくく感じてしまいます。
「最初から最後まできっちり読み通したことはないけど、大まかなあらすじは知っている」「漫画版や実写版しか見たことない」という小説って、意外と多いです。私の場合、ぱっと思いつくのは森鷗外の『舞姫』や太宰治の『人間失格』。一昔前の文豪の作品は、文体が現代と異なっていることもあり、なんとなくとっつきにくく感じてしまいます。 海外の創作物が日本でヒットする要因は何でしょうか。内容が肝心なのは言うまでもありませんが、翻訳の出来も、かなり重要な位置を占めます。学生時代、授業でやった英語一つ取っても、訳する人間が違えばニュアンスが大きく変わるもの。まして、商業的な作品、それも映像で物語を説明できない小説となると、翻訳のレベルが成功の鍵と言っても過言ではありません。
海外の創作物が日本でヒットする要因は何でしょうか。内容が肝心なのは言うまでもありませんが、翻訳の出来も、かなり重要な位置を占めます。学生時代、授業でやった英語一つ取っても、訳する人間が違えばニュアンスが大きく変わるもの。まして、商業的な作品、それも映像で物語を説明できない小説となると、翻訳のレベルが成功の鍵と言っても過言ではありません。 <ノックスの十戒>というものをご存知でしょうか。イギリスの作家・ノックスが考案した、推理小説を書く上での十個のルールです。半ばジョークとして作られたものらしく、十戒を破った推理小説もたくさん存在しますが、けっこう面白いのでチェックしてみる価値ありますよ。
<ノックスの十戒>というものをご存知でしょうか。イギリスの作家・ノックスが考案した、推理小説を書く上での十個のルールです。半ばジョークとして作られたものらしく、十戒を破った推理小説もたくさん存在しますが、けっこう面白いのでチェックしてみる価値ありますよ。 短編小説の良いところはたくさんあります。その一つは<収録作品中、どの話から読んでも楽しめる>ということ。一ページ目から読む必要のある長編と違い、短編の場合、ぱらぱらとめくってピンときたエピソードから読む、あるいは、苦手な用語が出てきそうなエピソードは飛ばす、ということも可能です。短編小説が仕事等で移動中に読むのに向いているのは、こういう特性があるからかもしれません。
短編小説の良いところはたくさんあります。その一つは<収録作品中、どの話から読んでも楽しめる>ということ。一ページ目から読む必要のある長編と違い、短編の場合、ぱらぱらとめくってピンときたエピソードから読む、あるいは、苦手な用語が出てきそうなエピソードは飛ばす、ということも可能です。短編小説が仕事等で移動中に読むのに向いているのは、こういう特性があるからかもしれません。