 <超能力>という言葉を聞くと、なんだかわくわくしてきます。手を触れずに物を動かしたり、未来の出来事を見通したり、一瞬で遠く離れた場所に移動したり・・・文字通り、普通の人間の力を超えた能力だからこそ、余計に憧れが募ります。
<超能力>という言葉を聞くと、なんだかわくわくしてきます。手を触れずに物を動かしたり、未来の出来事を見通したり、一瞬で遠く離れた場所に移動したり・・・文字通り、普通の人間の力を超えた能力だからこそ、余計に憧れが募ります。
超能力を扱った創作物の場合、その能力を使って敵と戦うアクション作品と、異能を持つがゆえに悩み苦しむ超能力者を描いたヒューマンドラマの二パターンに分かれることが多いです。前者は派手で迫力ある展開になるからか、漫画や映画でよくありますね。『X-MEN』などのようなアメコミ作品がその代表格でしょう。今回は、後者の作品を取り上げたいと思います。朱川湊人さんの『満月ケチャップライス』です。
こんな人におすすめ
超能力が出てくる、悲しくも心温まる物語が読みたい人
続きを読む
 悩みを抱えた時の一番スタンダードな解決方法は、「誰かに相談する」だと思います。ネットで調べる・占いに頼る・趣味に没頭して気を紛らわせる、などの方法もありますが、これだと正確性に欠けたり、根本的な問題解決にならなかったりしますよね。信頼できる誰かと向き合い、悩みを打ち明ければ、たとえ解決策が見つからなくても気持ちが軽くなるものです。
悩みを抱えた時の一番スタンダードな解決方法は、「誰かに相談する」だと思います。ネットで調べる・占いに頼る・趣味に没頭して気を紛らわせる、などの方法もありますが、これだと正確性に欠けたり、根本的な問題解決にならなかったりしますよね。信頼できる誰かと向き合い、悩みを打ち明ければ、たとえ解決策が見つからなくても気持ちが軽くなるものです。
となると次なる問題は「相談相手として誰を選ぶか」ということです。両親や配偶者など、確実に頼れる身内がいる人はいいでしょう。ですが、そういった身内を持たない人もいますし、場合によってはその身内が悩みの種だったりするケースもあります。恋人や友達にしたって、性格や能力その他諸々によっては、「好きだけど、的確な助言をくれる相手ではない」ということだってあり得ます。でも、この人が知人ならば、悩み相談する相手を迷わずに済むんじゃないでしょうか。林真理子さんの『中島ハルコはまだ懲りてない!』に登場する中島ハルコです。
こんな人におすすめ
コミカルで痛快な人間模様が読みたい人
続きを読む
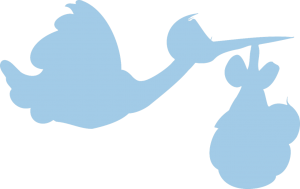 厚生労働省の発表によると、国内のひとり親家庭の数は二〇一一年度の時点で母子家庭が一二三.八万世帯、父子家庭が二二.三万世帯だそうです。この記事を書いている時(二〇一八年)にはもっと増えていることでしょう。私が注目したのは、一九八八年度の調査の時と比べて、離別や死別ではなく未婚によるひとり親家庭が増えている点です。結婚しないまま子どもをもうけ、育てる生活スタイルは、もはや海外だけのものではありません。
厚生労働省の発表によると、国内のひとり親家庭の数は二〇一一年度の時点で母子家庭が一二三.八万世帯、父子家庭が二二.三万世帯だそうです。この記事を書いている時(二〇一八年)にはもっと増えていることでしょう。私が注目したのは、一九八八年度の調査の時と比べて、離別や死別ではなく未婚によるひとり親家庭が増えている点です。結婚しないまま子どもをもうけ、育てる生活スタイルは、もはや海外だけのものではありません。
とはいえ、日本において未婚のまま親になるということは、様々な困難に見舞われることも事実。永井するみさんの『俯いていたつもりはない』、柚木麻子さんの『本屋さんのダイアナ』、唯川恵さんの『100万回の言い訳』などでもひとり親家庭が登場し、多くの試練に立ち向かっていました。私が最近読んだこの作品にも、悪戦苦闘する未婚の親が出てきましたよ。垣谷美雨さんの『四十歳、未婚出産』です。
こんな人におすすめ
シングルマザーの奮闘記が読みたい人
続きを読む
 読む本を選ぶ上で、あまり関係ないように見えて実はすごく重要な要素、それは「表紙」です。表紙によって物語の質が変わることはありませんが、魅力的な表紙の本は人の目を引き寄せるもの。「表紙につられて手に取ってみたら、予想以上に面白かった!」ということだってあるでしょう。
読む本を選ぶ上で、あまり関係ないように見えて実はすごく重要な要素、それは「表紙」です。表紙によって物語の質が変わることはありませんが、魅力的な表紙の本は人の目を引き寄せるもの。「表紙につられて手に取ってみたら、予想以上に面白かった!」ということだってあるでしょう。
かくいう私自身、表紙に惹かれて本を選んだ経験は数えきれないほどあります。中でも、恩田陸さんの『麦の海に沈む果実』、近藤史恵さんの『タルト・タタンの夢』、村山由佳さんの『野生の風 WILD WIND』の表紙は、その作家さんにはまるきっかけとなったこともあり、今もはっきりと覚えています。そう言えば、この作品の表紙もけっこうインパクトありますね。林真理子さんの『中島ハルコの恋愛相談室』です。
こんな人におすすめ
すっきり爽快なエンタメ小説が読みたい人
続きを読む
 記憶にある限り、今まで生きてきて「先輩」と言われたことはほとんどありません。中学校の部活では新入部員が入って来ず、高校は私が帰宅部。社会人になってからは後輩ができたものの、会社では「名字+さん」呼びが一般的でした。別に不自由はありませんでしたが、可愛い後輩に「先輩、先輩」と慕われるというシチュエーションには憧れちゃいますね。
記憶にある限り、今まで生きてきて「先輩」と言われたことはほとんどありません。中学校の部活では新入部員が入って来ず、高校は私が帰宅部。社会人になってからは後輩ができたものの、会社では「名字+さん」呼びが一般的でした。別に不自由はありませんでしたが、可愛い後輩に「先輩、先輩」と慕われるというシチュエーションには憧れちゃいますね。
小説の世界にはたくさんの先輩後輩が登場します。有栖川有栖さんの『学生アリスシリーズ』は頼もしい先輩が登場する青春ミステリ、秋吉理香子さんの『暗黒女子』は美しい女子高生を巡る愛憎劇を描いたイヤミス、森見登美彦さんの『夜は短し歩けよ乙女』は後輩に恋した大学生が主人公の恋愛小説です。どの先輩後輩の関係性も様々、愛や尊敬や信頼もあれば、憎しみや嫉妬や軽蔑もありました。では、この作品に出てくる先輩後輩はどうでしょうか。柚木麻子さんの『けむたい後輩』です。
こんな人におすすめ
ほろ苦い成長物語が読みたい人
続きを読む
 「下着が大好き」と言われた時、人はどんな反応を返すでしょうか。「分かる分かる」と頷く人もいるでしょうが、「いやらしい」「はしたない」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。身に付ける場所が場所なだけに、下着は性的なものを連想させてしまうからかもしれません。
「下着が大好き」と言われた時、人はどんな反応を返すでしょうか。「分かる分かる」と頷く人もいるでしょうが、「いやらしい」「はしたない」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。身に付ける場所が場所なだけに、下着は性的なものを連想させてしまうからかもしれません。
ですが、考えてみれば変な話です。公道を下着姿で闊歩するというならともかく、大多数の人は服の下に下着を身に付けているはず。それなら誰にも迷惑はかけないわけですし、「ワンピースが好き」「ジーパン最高」と同じ感覚で「下着が大好き」と言っても何一つ問題はありません。あらゆる衣類の中で最も肌に触れる製品なのですから、熱心に選び、機能性だけでなく美しさや可愛さを求めることはある意味で当然とも言えます。そんな下着に対する夢や愛着を描いた本を読みました。近藤史恵さんの『シフォン・リボン・シフォン』です。
こんな人におすすめ
下着を軸にしたヒューマンストーリーを読みたい人
続きを読む
 おもちゃが大嫌いという人ってあまりいない気がします。「テレビゲームは苦手」「パズルは好きじゃない」などという好みはあるにせよ、誰しもお気に入りだったおもちゃの一つや二つあるでしょう。かくいう私も子どもの頃はおもちゃ屋さんに行くのが大好き。今でさえ、時間がある時は、ショッピングセンターのおもちゃ売り場をぶらぶら歩くくらいです。
おもちゃが大嫌いという人ってあまりいない気がします。「テレビゲームは苦手」「パズルは好きじゃない」などという好みはあるにせよ、誰しもお気に入りだったおもちゃの一つや二つあるでしょう。かくいう私も子どもの頃はおもちゃ屋さんに行くのが大好き。今でさえ、時間がある時は、ショッピングセンターのおもちゃ売り場をぶらぶら歩くくらいです。
子どもを、時には大人をもワクワクさせるおもちゃの数々。一体どんな人が、そんなおもちゃを考え出しているのでしょうか。今回は、魅力的なおもちゃの作り手が登場する作品を取り上げたいと思います。柚木麻子さんの『ねじまき片想い~おもちゃプランナー・宝子の冒険~』です。
こんな人におすすめ
元気をもらえるお仕事・恋愛小説が読みたい人
続きを読む
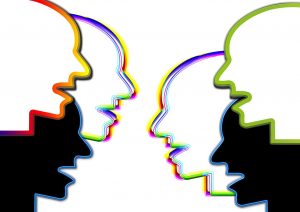 私は創作物に年齢制限を設けることが嫌いです。ですが、大人向けの作品というものはあると思います。これは内容が卑猥だとか残酷だとかいう意味ではなく、「ある程度以上の年月を生きてきた大人だからこそより面白さが理解できる作品」という意味です。
私は創作物に年齢制限を設けることが嫌いです。ですが、大人向けの作品というものはあると思います。これは内容が卑猥だとか残酷だとかいう意味ではなく、「ある程度以上の年月を生きてきた大人だからこそより面白さが理解できる作品」という意味です。
映画『スタンド・バイ・ミー』などその代表格だと思いますし、恩田陸さんの『夜のピクニック』や朱川湊人さんの『花まんま』には、懐かしくノスタルジックな雰囲気が漂っていました。そう言えば私は、小学生の時に観てイマイチだと思った『おもひでぽろぽろ』の面白さが大人になってから分かり、「ああ、年を取るってこういうことか」と実感したものです。ここまで挙げた作品は郷愁を誘う切ないものばかりですので、少し趣の違う「大人向けの作品」を紹介したいと思います。辻村深月さんの『噛みあわない会話と、ある過去について』です。
こんな人におすすめ
いじめやいじりに関する短編集が読みたい人
続きを読む
 学生時代の友達と定期的に会う機会はありますか。私は中学校から大学まで、同窓会の幹事を決めることなく卒業してしまったので、クラスメイトと大々的に集まったことは一、二度くらいしかありません。仲の良い友達数名でこぢんまりと会う機会はありましたが、各々の仕事や家庭の都合もあり、最近はめっきりご無沙汰です。仕方ないこととはいえ、ちょっと寂しくもありますね。
学生時代の友達と定期的に会う機会はありますか。私は中学校から大学まで、同窓会の幹事を決めることなく卒業してしまったので、クラスメイトと大々的に集まったことは一、二度くらいしかありません。仲の良い友達数名でこぢんまりと会う機会はありましたが、各々の仕事や家庭の都合もあり、最近はめっきりご無沙汰です。仕方ないこととはいえ、ちょっと寂しくもありますね。
職場や習い事、親同士の付き合いなどでも友達を作ることはできます。ですが、人生で一番未熟な時期を共有した学生時代の友達というのは、やはり特別なものなのではないでしょうか。そんな風に思ったのは、飛鳥井千砂さんの『女の子は、明日も。』を読んだから。久しぶりに昔の友達に会いたくなりました。
こんな人におすすめ
アラサー女性の友情をテーマにした小説が読みたい人
続きを読む
明るくポップな雰囲気の小説と暗く重厚な雰囲気の小説、世間ではどちらの方が人気なのでしょうか。私はどちらも好きですが、その時の気分によって作風を選ぶことは当然あります。仕事で大失敗した時に道尾秀介さんの『向日葵の咲かない夏』は読みたくないし、ダイエットしたい時は山口恵以子さんの『食堂のおばちゃん』は避けますね。
 そして、作家さんの中には、明るい小説と暗い小説の差が凄まじく、同一人物が書いたのかと疑いたくなるようなレベルの作品を書くがいらっしゃいます。作家なのだから当たり前、と言えばそれまでですが、やはりプロというのは凄いものなのだと感嘆せざるをえません。貫井徳郎さんの『慟哭』と『悪党たちは千里を走る』、重松清さんの『疾走』と『とんび』等々、その陰と陽の差に驚いたものです。そう言えばこの方も、明るい作品と暗い作品のギャップが大きいですよね。今回はそんな作家さん、宮木あや子さんの『憧憬☆カトマンズ』を取り上げたいと思います。
そして、作家さんの中には、明るい小説と暗い小説の差が凄まじく、同一人物が書いたのかと疑いたくなるようなレベルの作品を書くがいらっしゃいます。作家なのだから当たり前、と言えばそれまでですが、やはりプロというのは凄いものなのだと感嘆せざるをえません。貫井徳郎さんの『慟哭』と『悪党たちは千里を走る』、重松清さんの『疾走』と『とんび』等々、その陰と陽の差に驚いたものです。そう言えばこの方も、明るい作品と暗い作品のギャップが大きいですよね。今回はそんな作家さん、宮木あや子さんの『憧憬☆カトマンズ』を取り上げたいと思います。
こんな人におすすめ
気分すっきりなお仕事小説が読みたい人
続きを読む
 <超能力>という言葉を聞くと、なんだかわくわくしてきます。手を触れずに物を動かしたり、未来の出来事を見通したり、一瞬で遠く離れた場所に移動したり・・・文字通り、普通の人間の力を超えた能力だからこそ、余計に憧れが募ります。
<超能力>という言葉を聞くと、なんだかわくわくしてきます。手を触れずに物を動かしたり、未来の出来事を見通したり、一瞬で遠く離れた場所に移動したり・・・文字通り、普通の人間の力を超えた能力だからこそ、余計に憧れが募ります。
 悩みを抱えた時の一番スタンダードな解決方法は、「誰かに相談する」だと思います。ネットで調べる・占いに頼る・趣味に没頭して気を紛らわせる、などの方法もありますが、これだと正確性に欠けたり、根本的な問題解決にならなかったりしますよね。信頼できる誰かと向き合い、悩みを打ち明ければ、たとえ解決策が見つからなくても気持ちが軽くなるものです。
悩みを抱えた時の一番スタンダードな解決方法は、「誰かに相談する」だと思います。ネットで調べる・占いに頼る・趣味に没頭して気を紛らわせる、などの方法もありますが、これだと正確性に欠けたり、根本的な問題解決にならなかったりしますよね。信頼できる誰かと向き合い、悩みを打ち明ければ、たとえ解決策が見つからなくても気持ちが軽くなるものです。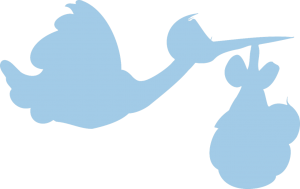 厚生労働省の発表によると、国内のひとり親家庭の数は二〇一一年度の時点で母子家庭が一二三.八万世帯、父子家庭が二二.三万世帯だそうです。この記事を書いている時(二〇一八年)にはもっと増えていることでしょう。私が注目したのは、一九八八年度の調査の時と比べて、離別や死別ではなく未婚によるひとり親家庭が増えている点です。結婚しないまま子どもをもうけ、育てる生活スタイルは、もはや海外だけのものではありません。
厚生労働省の発表によると、国内のひとり親家庭の数は二〇一一年度の時点で母子家庭が一二三.八万世帯、父子家庭が二二.三万世帯だそうです。この記事を書いている時(二〇一八年)にはもっと増えていることでしょう。私が注目したのは、一九八八年度の調査の時と比べて、離別や死別ではなく未婚によるひとり親家庭が増えている点です。結婚しないまま子どもをもうけ、育てる生活スタイルは、もはや海外だけのものではありません。 読む本を選ぶ上で、あまり関係ないように見えて実はすごく重要な要素、それは「表紙」です。表紙によって物語の質が変わることはありませんが、魅力的な表紙の本は人の目を引き寄せるもの。「表紙につられて手に取ってみたら、予想以上に面白かった!」ということだってあるでしょう。
読む本を選ぶ上で、あまり関係ないように見えて実はすごく重要な要素、それは「表紙」です。表紙によって物語の質が変わることはありませんが、魅力的な表紙の本は人の目を引き寄せるもの。「表紙につられて手に取ってみたら、予想以上に面白かった!」ということだってあるでしょう。 記憶にある限り、今まで生きてきて「先輩」と言われたことはほとんどありません。中学校の部活では新入部員が入って来ず、高校は私が帰宅部。社会人になってからは後輩ができたものの、会社では「名字+さん」呼びが一般的でした。別に不自由はありませんでしたが、可愛い後輩に「先輩、先輩」と慕われるというシチュエーションには憧れちゃいますね。
記憶にある限り、今まで生きてきて「先輩」と言われたことはほとんどありません。中学校の部活では新入部員が入って来ず、高校は私が帰宅部。社会人になってからは後輩ができたものの、会社では「名字+さん」呼びが一般的でした。別に不自由はありませんでしたが、可愛い後輩に「先輩、先輩」と慕われるというシチュエーションには憧れちゃいますね。 「下着が大好き」と言われた時、人はどんな反応を返すでしょうか。「分かる分かる」と頷く人もいるでしょうが、「いやらしい」「はしたない」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。身に付ける場所が場所なだけに、下着は性的なものを連想させてしまうからかもしれません。
「下着が大好き」と言われた時、人はどんな反応を返すでしょうか。「分かる分かる」と頷く人もいるでしょうが、「いやらしい」「はしたない」と眉をひそめる人も多いのではないでしょうか。身に付ける場所が場所なだけに、下着は性的なものを連想させてしまうからかもしれません。 おもちゃが大嫌いという人ってあまりいない気がします。「テレビゲームは苦手」「パズルは好きじゃない」などという好みはあるにせよ、誰しもお気に入りだったおもちゃの一つや二つあるでしょう。かくいう私も子どもの頃はおもちゃ屋さんに行くのが大好き。今でさえ、時間がある時は、ショッピングセンターのおもちゃ売り場をぶらぶら歩くくらいです。
おもちゃが大嫌いという人ってあまりいない気がします。「テレビゲームは苦手」「パズルは好きじゃない」などという好みはあるにせよ、誰しもお気に入りだったおもちゃの一つや二つあるでしょう。かくいう私も子どもの頃はおもちゃ屋さんに行くのが大好き。今でさえ、時間がある時は、ショッピングセンターのおもちゃ売り場をぶらぶら歩くくらいです。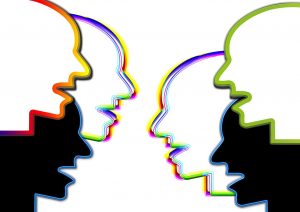 私は創作物に年齢制限を設けることが嫌いです。ですが、大人向けの作品というものはあると思います。これは内容が卑猥だとか残酷だとかいう意味ではなく、「ある程度以上の年月を生きてきた大人だからこそより面白さが理解できる作品」という意味です。
私は創作物に年齢制限を設けることが嫌いです。ですが、大人向けの作品というものはあると思います。これは内容が卑猥だとか残酷だとかいう意味ではなく、「ある程度以上の年月を生きてきた大人だからこそより面白さが理解できる作品」という意味です。 学生時代の友達と定期的に会う機会はありますか。私は中学校から大学まで、同窓会の幹事を決めることなく卒業してしまったので、クラスメイトと大々的に集まったことは一、二度くらいしかありません。仲の良い友達数名でこぢんまりと会う機会はありましたが、各々の仕事や家庭の都合もあり、最近はめっきりご無沙汰です。仕方ないこととはいえ、ちょっと寂しくもありますね。
学生時代の友達と定期的に会う機会はありますか。私は中学校から大学まで、同窓会の幹事を決めることなく卒業してしまったので、クラスメイトと大々的に集まったことは一、二度くらいしかありません。仲の良い友達数名でこぢんまりと会う機会はありましたが、各々の仕事や家庭の都合もあり、最近はめっきりご無沙汰です。仕方ないこととはいえ、ちょっと寂しくもありますね。 そして、作家さんの中には、明るい小説と暗い小説の差が凄まじく、同一人物が書いたのかと疑いたくなるようなレベルの作品を書くがいらっしゃいます。作家なのだから当たり前、と言えばそれまでですが、やはりプロというのは凄いものなのだと感嘆せざるをえません。貫井徳郎さんの『慟哭』と『悪党たちは千里を走る』、重松清さんの『疾走』と『とんび』等々、その陰と陽の差に驚いたものです。そう言えばこの方も、明るい作品と暗い作品のギャップが大きいですよね。今回はそんな作家さん、宮木あや子さんの『憧憬☆カトマンズ』を取り上げたいと思います。
そして、作家さんの中には、明るい小説と暗い小説の差が凄まじく、同一人物が書いたのかと疑いたくなるようなレベルの作品を書くがいらっしゃいます。作家なのだから当たり前、と言えばそれまでですが、やはりプロというのは凄いものなのだと感嘆せざるをえません。貫井徳郎さんの『慟哭』と『悪党たちは千里を走る』、重松清さんの『疾走』と『とんび』等々、その陰と陽の差に驚いたものです。そう言えばこの方も、明るい作品と暗い作品のギャップが大きいですよね。今回はそんな作家さん、宮木あや子さんの『憧憬☆カトマンズ』を取り上げたいと思います。