 日本は島国であるため、比較的気軽にマリンスポーツを楽しむことができます。私自身、子どもの頃は親に連れられて海水浴に行ったり、海辺で花火をしたりしました。そういう時、海によってはボードを抱えたサーファーを目にすることもあり、「あれはどういうスポーツなんだろう?」と不思議に思ったものです。波打ち際でちゃぷちゃぷ遊ぶのと違い、サーフィンには技術や道具が必要ということもあって、今でもなんとなく縁遠いです。
日本は島国であるため、比較的気軽にマリンスポーツを楽しむことができます。私自身、子どもの頃は親に連れられて海水浴に行ったり、海辺で花火をしたりしました。そういう時、海によってはボードを抱えたサーファーを目にすることもあり、「あれはどういうスポーツなんだろう?」と不思議に思ったものです。波打ち際でちゃぷちゃぷ遊ぶのと違い、サーフィンには技術や道具が必要ということもあって、今でもなんとなく縁遠いです。
そんな私でも、本の中でならサーフィンを楽しむことができます。サーフィンが登場する小説といえば、ぱっと思いつくのは豊田和馬さんの『キャッチ・ア・ウェーブ』や村山由佳さんの『海を抱く BAD KIDS』といったところでしょうか。大海原と戦うスポーツなだけあって、成長物語の題材としてよく取り上げられる気がします。この本でも、サーフィンをキーワードに、一回り大きくなる少年の姿が描かれていました。坂木司さんの『大きな音が聞こえるか』です。
こんな人におすすめ
世界を見て成長していく少年の青春小説が読みたい人

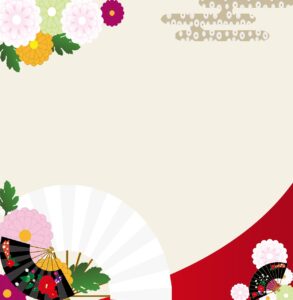 「最初から最後まできっちり読み通したことはないけど、大まかなあらすじは知っている」「漫画版や実写版しか見たことない」という小説って、意外と多いです。私の場合、ぱっと思いつくのは森鷗外の『舞姫』や太宰治の『人間失格』。一昔前の文豪の作品は、文体が現代と異なっていることもあり、なんとなくとっつきにくく感じてしまいます。
「最初から最後まできっちり読み通したことはないけど、大まかなあらすじは知っている」「漫画版や実写版しか見たことない」という小説って、意外と多いです。私の場合、ぱっと思いつくのは森鷗外の『舞姫』や太宰治の『人間失格』。一昔前の文豪の作品は、文体が現代と異なっていることもあり、なんとなくとっつきにくく感じてしまいます。 「あなたが一番好きな料理は何ですか?」という質問があり、結果をランキングにするとしたら、どんな答えが集まるでしょうか。さぞかし多くの回答が出るでしょうが、恐らくトップ5の中にはカレーが入っていると思います。ビーフ、ポーク、チキンにシーフード等、種類が豊富な上、辛さを調節したりスパイスで味を変えたりもしやすいので、老若男女問わず人気がある一品です。
「あなたが一番好きな料理は何ですか?」という質問があり、結果をランキングにするとしたら、どんな答えが集まるでしょうか。さぞかし多くの回答が出るでしょうが、恐らくトップ5の中にはカレーが入っていると思います。ビーフ、ポーク、チキンにシーフード等、種類が豊富な上、辛さを調節したりスパイスで味を変えたりもしやすいので、老若男女問わず人気がある一品です。 世界各国には様々な童話があります。勧善懲悪のヒーロー話からおどろおどろしい怪異譚、くすりと笑えるほのぼのストーリーまで、その作風は千差万別。物語として面白いだけでなく、現代にも通じる教訓や風刺が込められているものも多く、大人になってから読んでも楽しめます。
世界各国には様々な童話があります。勧善懲悪のヒーロー話からおどろおどろしい怪異譚、くすりと笑えるほのぼのストーリーまで、その作風は千差万別。物語として面白いだけでなく、現代にも通じる教訓や風刺が込められているものも多く、大人になってから読んでも楽しめます。 <ニート>の正式名称をご存知でしょうか。<Not in Education,Employment or Training>の略称で、勉強することも就労することも職業訓練を受けることもない者を指します。年齢は、一般的には十五歳から三十四歳までと定義されているとのこと。「五体満足な人間が、教育や勤労の義務も果たさずだらだらしているなんて」と、世間の厳しい目に晒されることが多い立場です。
<ニート>の正式名称をご存知でしょうか。<Not in Education,Employment or Training>の略称で、勉強することも就労することも職業訓練を受けることもない者を指します。年齢は、一般的には十五歳から三十四歳までと定義されているとのこと。「五体満足な人間が、教育や勤労の義務も果たさずだらだらしているなんて」と、世間の厳しい目に晒されることが多い立場です。 女子校という言葉を聞いて、どんなイメージが思い浮かぶでしょうか。お嬢様達が優雅に微笑み合う女の園か。あるいは、大奥ばりの権謀術数が渦巻く伏魔殿か。実際に女子高出身の私に言わせれば、どちらも否。共学校と同じく、楽しいこともあれば嫌なこともある、普通の学校です。ただ、同世代の異性の目がない分、女の良い所悪い所がより強調されるという面はあると思います。
女子校という言葉を聞いて、どんなイメージが思い浮かぶでしょうか。お嬢様達が優雅に微笑み合う女の園か。あるいは、大奥ばりの権謀術数が渦巻く伏魔殿か。実際に女子高出身の私に言わせれば、どちらも否。共学校と同じく、楽しいこともあれば嫌なこともある、普通の学校です。ただ、同世代の異性の目がない分、女の良い所悪い所がより強調されるという面はあると思います。 大人はしばしばこういう言葉を口にします。「子どもはいいな。何の悩みもなくて」。確かに、必死で生活費を稼いだり、育児や介護に追われたりする大人からすれば、子どもはいつも屈託なく無邪気に見えるかもしれません。というか、そうあって欲しいというのが、大人の本音なのでしょう。
大人はしばしばこういう言葉を口にします。「子どもはいいな。何の悩みもなくて」。確かに、必死で生活費を稼いだり、育児や介護に追われたりする大人からすれば、子どもはいつも屈託なく無邪気に見えるかもしれません。というか、そうあって欲しいというのが、大人の本音なのでしょう。 <兄弟は他人のはじまり>ということわざがあります。意味は<血を分けた兄弟(姉妹)でも、成長するにつれ環境や価値観が変わり、情が薄れ、他人のようになっていく>ということ。ちょっと寂しいですが、肉親とはいえ違う人間なのですから、仕方ないことなのかもしれません。
<兄弟は他人のはじまり>ということわざがあります。意味は<血を分けた兄弟(姉妹)でも、成長するにつれ環境や価値観が変わり、情が薄れ、他人のようになっていく>ということ。ちょっと寂しいですが、肉親とはいえ違う人間なのですから、仕方ないことなのかもしれません。 「長編小説は読むのに時間がかかる。短い時間でも気軽に読める短編小説の方が好き」という意見をしばしば耳にします。長編と短編、どちらが優れているかは決められないものの、所要時間の少なさという点では、短編に軍配が上がるでしょう。その短編よりさらに短い小説が<ショートショート>です。何をもってショートショートとするか、明確な定義はないようですが、<一ページから数ページに収まる長さであり、意外な結末を迎えるもの>という解釈が一般的なようですね。
「長編小説は読むのに時間がかかる。短い時間でも気軽に読める短編小説の方が好き」という意見をしばしば耳にします。長編と短編、どちらが優れているかは決められないものの、所要時間の少なさという点では、短編に軍配が上がるでしょう。その短編よりさらに短い小説が<ショートショート>です。何をもってショートショートとするか、明確な定義はないようですが、<一ページから数ページに収まる長さであり、意外な結末を迎えるもの>という解釈が一般的なようですね。 私は昔から食べることが大好きです。嫌なことがあれば好物を食べてリフレッシュしようとするし、旅先でまず調べるのは現地の美味しいお店や名物料理。だからこそ、美味しい料理を作ってくれるコックさんのことは無条件で尊敬してしまいます。
私は昔から食べることが大好きです。嫌なことがあれば好物を食べてリフレッシュしようとするし、旅先でまず調べるのは現地の美味しいお店や名物料理。だからこそ、美味しい料理を作ってくれるコックさんのことは無条件で尊敬してしまいます。