 昔読んだ小説の中で、こんなエピソードが紹介されていました。『チャレンジャー号爆発事故の発生後、阿鼻叫喚に陥る観客達を写した写真が話題となった。ところが後日、その写真は事故発生後ではなく、打ち上げ直後に撮られたものだと判明した。当初、恐怖と混乱の真っ只中と思われていた観客達の表情は、実は期待と興奮に沸いていたのだ』。その後同様のエピソードを見聞きしたことはないため、もしかしたら単なる噂なのかもしれませんが、十分あり得る話だと思います。物の見え方というものは、受け取る側の価値観や状況によって簡単に変化するものです。
昔読んだ小説の中で、こんなエピソードが紹介されていました。『チャレンジャー号爆発事故の発生後、阿鼻叫喚に陥る観客達を写した写真が話題となった。ところが後日、その写真は事故発生後ではなく、打ち上げ直後に撮られたものだと判明した。当初、恐怖と混乱の真っ只中と思われていた観客達の表情は、実は期待と興奮に沸いていたのだ』。その後同様のエピソードを見聞きしたことはないため、もしかしたら単なる噂なのかもしれませんが、十分あり得る話だと思います。物の見え方というものは、受け取る側の価値観や状況によって簡単に変化するものです。
絵よりもずっと正確に、被写体を写すことができる写真。そんな写真でさえ、解釈の違いというものは存在します。たった一枚の写真からだって、百人の人間がいれば百通りの物語を作り出すことも不可能ではないでしょう。今回取り上げるのは、写真にまつわるバラエティ豊かなショートショート集、道尾秀介さんの『フォトミステリー』です。
こんな人におすすめ
ブラックな作風のショートショートが好きな人

 創作の世界には<パスティーシュ>という用語があります。これは一言で言うと、作風の模倣のことです。似たような用語に<オマージュ>があり、実際、日本では厳密な区別はない様子。ただ、色々なパスティーシュ作品、オマージュ作品を見る限り、前者は先行する作品の要素がはっきり表れているのに対し、後者は作家が先行作品を自分なりに読み取った上で作品化するので、「え、〇〇(作品名)のオマージュなの?」とびっくりさせられることが多い気がします。
創作の世界には<パスティーシュ>という用語があります。これは一言で言うと、作風の模倣のことです。似たような用語に<オマージュ>があり、実際、日本では厳密な区別はない様子。ただ、色々なパスティーシュ作品、オマージュ作品を見る限り、前者は先行する作品の要素がはっきり表れているのに対し、後者は作家が先行作品を自分なりに読み取った上で作品化するので、「え、〇〇(作品名)のオマージュなの?」とびっくりさせられることが多い気がします。 暦の上では秋になり、店先に並ぶファッションアイテムも秋を意識したものが増えました。とはいえ、気候はまだまだ夏そのもの。半袖シャツも、帽子も、キンキンに冷えた飲み物も、当分手放せそうにありません。
暦の上では秋になり、店先に並ぶファッションアイテムも秋を意識したものが増えました。とはいえ、気候はまだまだ夏そのもの。半袖シャツも、帽子も、キンキンに冷えた飲み物も、当分手放せそうにありません。 クリエイティブな世界には、複数の名義で作品を発表されている方がしばしば存在します。理由は人それぞれでしょうが、一番は、名前に付きまとうイメージや先入観を払拭するためではないでしょうか。〇〇先生は恋愛漫画とか、△△先生はロックミュージックとか、色々イメージがありますからね。
クリエイティブな世界には、複数の名義で作品を発表されている方がしばしば存在します。理由は人それぞれでしょうが、一番は、名前に付きまとうイメージや先入観を払拭するためではないでしょうか。〇〇先生は恋愛漫画とか、△△先生はロックミュージックとか、色々イメージがありますからね。 昔、私は2ちゃんねる(現5ちゃんねる)が好きで、手持無沙汰な時間にちょこちょこ覗いていました。以前と比べると頻度が落ちましたが、唯一、<後味の悪い話>というスレッドのみ、今も定期的に進行をチェックしています。タイトルが示す通り、自分の知っている後味の悪い話を投稿するスレッドで、実体験・小説・映画・アニメなどジャンルは不問。イヤミス好きな私の心をくすぐる投稿も多く、ここでこれから読む本を見つけることもありました。
昔、私は2ちゃんねる(現5ちゃんねる)が好きで、手持無沙汰な時間にちょこちょこ覗いていました。以前と比べると頻度が落ちましたが、唯一、<後味の悪い話>というスレッドのみ、今も定期的に進行をチェックしています。タイトルが示す通り、自分の知っている後味の悪い話を投稿するスレッドで、実体験・小説・映画・アニメなどジャンルは不問。イヤミス好きな私の心をくすぐる投稿も多く、ここでこれから読む本を見つけることもありました。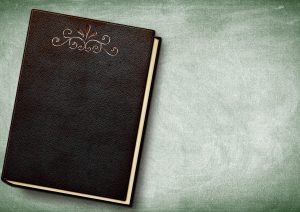 芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。
芥川龍之介賞、直木三十五賞、吉川英治文学賞、山本周五郎賞・・・・・文壇には様々な文学賞があります。インターネットなどを経て人気を集める作家さんや作品も増えてきましたが、それでもやはりこうした文学賞には価値があるもの。権威ある賞の受賞をきっかけにデビューした作家さんは大勢います。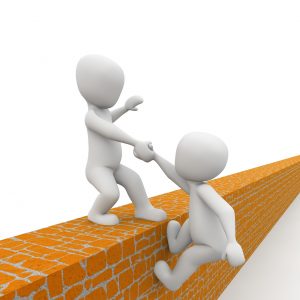 芸能人が小説を書くケースは多いです。その際、「芸能人に小説が書けるのか」という批判が巻き起こるのはお約束。特に、その芸能人が華やかな経歴の持ち主だった場合、批判が激しくなる傾向にあるようです。
芸能人が小説を書くケースは多いです。その際、「芸能人に小説が書けるのか」という批判が巻き起こるのはお約束。特に、その芸能人が華やかな経歴の持ち主だった場合、批判が激しくなる傾向にあるようです。 創作作品を見ていると、「このキャラってステレオタイプだよね」と思うことがあります。たとえば<日本人>なら<努力家で慎み深く、自己主張が苦手>とか、<田舎者>なら<流行に疎く方言丸出しで喋り、お節介だが人情味がある>とか。現実には怠け者ではっきり物を言う日本人も、お洒落でクールな田舎者も大勢いるに決まっていますが、なんとなくこういうイメージが付いてしまっています。こういう固定観念やレッテルのことを<ステレオタイプ>と言います。
創作作品を見ていると、「このキャラってステレオタイプだよね」と思うことがあります。たとえば<日本人>なら<努力家で慎み深く、自己主張が苦手>とか、<田舎者>なら<流行に疎く方言丸出しで喋り、お節介だが人情味がある>とか。現実には怠け者ではっきり物を言う日本人も、お洒落でクールな田舎者も大勢いるに決まっていますが、なんとなくこういうイメージが付いてしまっています。こういう固定観念やレッテルのことを<ステレオタイプ>と言います。 今や<婚活>という用語はすっかり一般的なものになりました。漢字にするとたった二文字ですが、そのやり方は様々です。インターネットの婚活サイトに登録したり、結婚相談所を介したり、大規模なパーティーに参加したり・・・最近は寺での座禅や農作業など、ユニークなイベントを利用した婚活も多いようですね。そんな婚活の中に<親婚活>というものがあります。
今や<婚活>という用語はすっかり一般的なものになりました。漢字にするとたった二文字ですが、そのやり方は様々です。インターネットの婚活サイトに登録したり、結婚相談所を介したり、大規模なパーティーに参加したり・・・最近は寺での座禅や農作業など、ユニークなイベントを利用した婚活も多いようですね。そんな婚活の中に<親婚活>というものがあります。 悩みを抱えた時の一番スタンダードな解決方法は、「誰かに相談する」だと思います。ネットで調べる・占いに頼る・趣味に没頭して気を紛らわせる、などの方法もありますが、これだと正確性に欠けたり、根本的な問題解決にならなかったりしますよね。信頼できる誰かと向き合い、悩みを打ち明ければ、たとえ解決策が見つからなくても気持ちが軽くなるものです。
悩みを抱えた時の一番スタンダードな解決方法は、「誰かに相談する」だと思います。ネットで調べる・占いに頼る・趣味に没頭して気を紛らわせる、などの方法もありますが、これだと正確性に欠けたり、根本的な問題解決にならなかったりしますよね。信頼できる誰かと向き合い、悩みを打ち明ければ、たとえ解決策が見つからなくても気持ちが軽くなるものです。