 ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。
ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。
ただ、一言で人形といっても、等身大のマネキンから、豪奢な装飾が施されたアンティークドール、子どもが片手で持てる着せ替え人形等々、たくさんの種類があります。その中でジャパニーズホラーにぴったりなのは、満場一致で日本人形でしょう。澤村伊智さんの『ずうのめ人形』や、漫画ですが山岸凉子さんの『わたしの人形は良い人形』には、読者の背筋を凍らせるほど怖い日本人形が登場します。それから、この作品に出てくる人形も、なかなかどうしてインパクト抜群でしたよ。藤崎翔さんの『お梅は呪いたい』です。
こんな人におすすめ
伏線たっぷりのホラーコメディが読みたい人
続きを読む
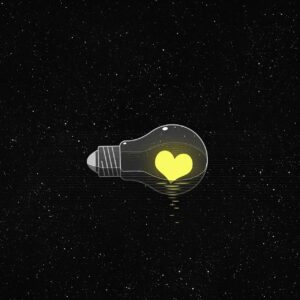 万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・
万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・
とはいえ、事前に内容をチェックしてさえいれば、改題は悪いことではありません。改題後の方がしっくりくるということだってあるでしょう。個人的には、真梨幸子さんの『更年期少女』は、改題後の『みんな邪魔』の方が好みだったりします。それからこの作品も、改題後の題名の方が好きなんですよ。藤崎翔さんの『三十年後の俺』です。
こんな人におすすめ
ブラックユーモアたっぷりの短編集が読みたい人
続きを読む
 物事の、中でも悲惨な物事の終わりとはいつでしょうか。たとえば戦争だとしたら、当事者間で終戦の合意がなされた時?自然災害だとしたら、避難生活が終わり、被災した人達が自宅で普通に暮らせるようになった時?幸せな出来事ならば永遠に続いてくれていいけれど、不幸な出来事ならはっきり終わってほしいと思うのが人情というものです。
物事の、中でも悲惨な物事の終わりとはいつでしょうか。たとえば戦争だとしたら、当事者間で終戦の合意がなされた時?自然災害だとしたら、避難生活が終わり、被災した人達が自宅で普通に暮らせるようになった時?幸せな出来事ならば永遠に続いてくれていいけれど、不幸な出来事ならはっきり終わってほしいと思うのが人情というものです。
しかし、悲しいかな、不幸な出来事であればあるほど、長く続いてしまうのが世の常。戦争や災害、凶悪犯罪などの場合、出来事そのものは終わっても、巻き込まれてしまった人達の心身の傷はそう簡単には癒えません。「もう終わったことなんだから忘れなさい」と言えるのは、きっと部外者だからこそでしょう。今回は、とある犯罪と、そこに関わってしまった人達の苦しみをテーマにした作品をご紹介します。降田天さんの『事件は終わった』です。
こんな人におすすめ
心の傷と再生を描いたヒューマンストーリーが読みたい人
続きを読む
 「このトリックは映像化不可能!」。ミステリー小説等でしばしば目にするキャッチコピーです。叙述トリックをはじめ、小説の<文字を読む>という特性を活かしたトリックに対して用いられることが多いですね。ラストで世界が反転するようなどんでん返しが待っていることが多く、私も大好きなトリックです。
「このトリックは映像化不可能!」。ミステリー小説等でしばしば目にするキャッチコピーです。叙述トリックをはじめ、小説の<文字を読む>という特性を活かしたトリックに対して用いられることが多いですね。ラストで世界が反転するようなどんでん返しが待っていることが多く、私も大好きなトリックです。
とはいえ、脚本の作り方や、進歩した映像技術により、映像化不可能と言われつつ映像化に成功した作品もたくさんあります。貫井徳郎さんの『愚行録』は、妻夫木聡さん・満島ひかりさん主演で映画化されていますが、個人的にその年一番と言えるくらいの傑作だったと思います。でも、どれだけやり方を考えても、この作品は本当に映像化不可能ではないでしょうか。藤崎翔さんの『逆転美人』です。
こんな人におすすめ
どんでん返しのあるイヤミスが読みたい人
続きを読む
 自殺はいけないこと。これは老若男女問わず誰もが断言することだと思います。その理由は色々あるでしょうが、多いのは「親からもらった命を粗末にしちゃだめ」「生きたくても生きられない人がいるのだから」辺りでしょうか。キリスト教圏なら「神が禁じているから」なんて理由もありそうです。
自殺はいけないこと。これは老若男女問わず誰もが断言することだと思います。その理由は色々あるでしょうが、多いのは「親からもらった命を粗末にしちゃだめ」「生きたくても生きられない人がいるのだから」辺りでしょうか。キリスト教圏なら「神が禁じているから」なんて理由もありそうです。
とはいえ、「いけないんだ。じゃあ、やめましょう」とはいかないのが人間というもの。特に東洋の場合、<殉死><切腹>などの慣習があり、のっぴきならない事態に直面した人間が自殺することを美徳とする時代さえありました。そういう意味で、欧米と比べると、自殺という行為との距離が近いような気がします。今日は、自殺をテーマにしたミステリーを取り上げたいと思います。降田天さんの『さんず』です。
こんな人におすすめ
自殺を巡るミステリーが読みたい人
続きを読む
 この世で最も許されざる犯罪の一つ、児童虐待。漢字で書けばたったの四文字ですが、そこにはいくつもの種別があります。殴る蹴るといった暴力を振るう身体的虐待、子どもを性欲の対象とする性的虐待、罵ったり兄弟姉妹間で扱いに差を付けたりする心理的虐待。以前は児童虐待と言えばこの三種類のうちどれかに区分されることが多かったようですが、現在よく取り沙汰される虐待はもう一つあります。それが、生活する上で必要な世話を怠り、最悪、死に至らしめることもある<育児放棄>です。日本は諸外国と比べて治安が良く、子どもが戸外に一人でいたり、車内にずっと放置されていても問題視されにくかったため、一昔前は虐待事件として扱われることも少なかったようです。
この世で最も許されざる犯罪の一つ、児童虐待。漢字で書けばたったの四文字ですが、そこにはいくつもの種別があります。殴る蹴るといった暴力を振るう身体的虐待、子どもを性欲の対象とする性的虐待、罵ったり兄弟姉妹間で扱いに差を付けたりする心理的虐待。以前は児童虐待と言えばこの三種類のうちどれかに区分されることが多かったようですが、現在よく取り沙汰される虐待はもう一つあります。それが、生活する上で必要な世話を怠り、最悪、死に至らしめることもある<育児放棄>です。日本は諸外国と比べて治安が良く、子どもが戸外に一人でいたり、車内にずっと放置されていても問題視されにくかったため、一昔前は虐待事件として扱われることも少なかったようです。
育児放棄を扱った小説といえば、当ブログで過去に美輪和音さんの『ウェンディのあやまち』を取り上げました。また、山田詠美さんは、二〇一〇年に大阪で起きた幼児二人の餓死事件をもとに『つみびと』を執筆されています。最近読んだこの作品にも、胸が痛くなるような育児放棄が出てきました。降田天さんの『朝と夕の犯罪』です。
こんな人におすすめ
児童虐待をテーマにしたミステリーに興味がある人
続きを読む
 日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。
日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。
その一方で、桜には妖しく底知れないイメージもあります。梶井基次郎は著作『桜の樹の下には』で「桜の樹の下には屍体が埋まっている」と書いていますし、そこから進化したのか「桜の花びらが薄紅色なのは、下に埋まった死体の血を吸っているからだ」などという怪談まで存在します。同じ美しい花でも、元気一杯に咲くチューリップや向日葵とは違う、どこか寂しげで妖艶な様のせいかもしれませんね。今回は、ちょっと季節外れですが、桜の持つミステリアスな雰囲気を活かした小説をご紹介したいと思います。花房観音さんの『鬼の家』です。
こんな人におすすめ
妖しくも哀しい怪談短編集が読みたい人
続きを読む
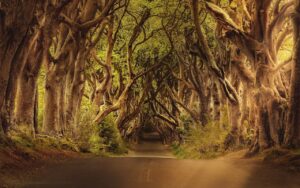 本好きなら恐らく誰もが持つ娯楽、それが本屋巡りです。当たり前の話ですが、本屋は見渡す限り本、本、本。新刊コーナーをチェックしたり、気になる本をめくって内容を確認したりするだけで、時間はあっという間に潰れます。コロナ禍ではどうか分かりませんが、以前は店内の各所にソファやテーブルが設置され、購入前に座ってゆっくり読むこともできました。初めて本屋で閲覧席を見た時、ここは地上の楽園かと思ったことを、今でもよく覚えています。
本好きなら恐らく誰もが持つ娯楽、それが本屋巡りです。当たり前の話ですが、本屋は見渡す限り本、本、本。新刊コーナーをチェックしたり、気になる本をめくって内容を確認したりするだけで、時間はあっという間に潰れます。コロナ禍ではどうか分かりませんが、以前は店内の各所にソファやテーブルが設置され、購入前に座ってゆっくり読むこともできました。初めて本屋で閲覧席を見た時、ここは地上の楽園かと思ったことを、今でもよく覚えています。
そして、本屋巡りの楽しみの一つに、特設コーナーの存在があります。季節や社会情勢、大きな賞の受賞など、その時々の状況に応じてテーマが設けられ、相応しい本が集められた特設コーナー。書店員さんが工夫を凝らした演出も多く、ここで読みたい本を見つけることも多いです。今回ご紹介する本も、とある本屋の特設コーナーで見つけました。誉田哲也さんの『ボーダレス』です。
こんな人におすすめ
群像劇から成るサスペンスが読みたい人
続きを読む
 古今東西、数多く存在する<心中>の形の中で、<ネット心中>の異質さは際立っています。そもそも<心中>とは、引き裂かれそうな恋人同士があの世で結ばれることを願ってとか、家族が生活苦から逃れるためとか、そこに何らかの個人的な感情が絡むもの。一方、ネット心中の場合、縁もゆかりもない人間達が「一人で死ぬのは嫌だから」という動機で集まり、一緒に死ぬもの。当然、お互いに対する深い愛憎はありません。インターネットが発達し、何の接点もない人間同士が簡単にコミュニケーションを取れるようになったからこそ現れた心中方法です。
古今東西、数多く存在する<心中>の形の中で、<ネット心中>の異質さは際立っています。そもそも<心中>とは、引き裂かれそうな恋人同士があの世で結ばれることを願ってとか、家族が生活苦から逃れるためとか、そこに何らかの個人的な感情が絡むもの。一方、ネット心中の場合、縁もゆかりもない人間達が「一人で死ぬのは嫌だから」という動機で集まり、一緒に死ぬもの。当然、お互いに対する深い愛憎はありません。インターネットが発達し、何の接点もない人間同士が簡単にコミュニケーションを取れるようになったからこそ現れた心中方法です。
世相を反映しているとも言えるネット心中ですが、それが登場する小説となると、私はあまり読んだことがありませんでした。ぱっと思いつくのは、樋口明雄さんの『ミッドナイト・ラン!』くらいでしょうか。なので、この小説を見つけた時は「おおっ」と思いました。藤崎翔さんの『OJOGIWA』です。
こんな人におすすめ
スピーディなエンタメ・サスペンス小説が読みたい人
続きを読む
 歌を聞く時、真っ先に注目するのはどこでしょうか。メロディが一番大事という人が多い気がしますが、同じくらい歌詞も重要だと思います。人の興味を惹きつける魅力的な歌詞は、長い時間を経ても語り継がれるもの。さらに、歌詞からは、その歌が作られた時代の社会情勢や文化が分かるという面白さがあります。一昔前は<夢><希望>といった前向きな歌詞の歌が流行ったようですが、今は<自分探し>をテーマにした歌詞が一番人気なんだとか。これも時代というものなのでしょう。
歌を聞く時、真っ先に注目するのはどこでしょうか。メロディが一番大事という人が多い気がしますが、同じくらい歌詞も重要だと思います。人の興味を惹きつける魅力的な歌詞は、長い時間を経ても語り継がれるもの。さらに、歌詞からは、その歌が作られた時代の社会情勢や文化が分かるという面白さがあります。一昔前は<夢><希望>といった前向きな歌詞の歌が流行ったようですが、今は<自分探し>をテーマにした歌詞が一番人気なんだとか。これも時代というものなのでしょう。
歌をテーマにした創作物となると、映画なら『スタンド・バイ・ミー』『プリティ・ウーマン』『精霊流し』『涙そうそう』等々、有名作がたくさんありますが、小説となると少ないです。小説の世界観を歌にする、というパターンなら結構あるんですけどね。なので、この作品を見つけた時は「おおっ」と思いました。藤崎翔さんの『あなたに会えて困った』です。
こんな人におすすめ
コミカルなどんでん返しミステリーが読みたい人
続きを読む
 ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。
ホラー界における三種の神器とも言える恐怖アイテム、人形(個人的な残り二つは鏡と日記)。人形が怖いのは、人の形を模していることと、本来可愛いものというイメージがあるからでしょうか。愛らしいはずの人形が恐怖シーンに登場した時の恐ろしさは、そのギャップから、本気で鳥肌立ちそうになるものです。
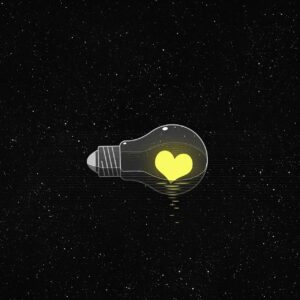 万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・
万事においておっちょこちょいな私が、読む本を選ぶ上で気を付けているポイント。それが<改題>です。単行本から文庫化されたり、新装版が出版されたりする時、題名が変わるのはままあること。前の題名を連想させるような改題ならいいのですが、あまりにかけ離れた題名に変わっていると、「好きな作家さんの新刊だ!やった!」→「・・・と思ったら、前に読んだやつだった」というガッカリを味わうこともあり得ます。櫛木理宇さんの『少女葬』が、すでに読破済みだった『FEED』の改題だと知った時は悲しかったなぁ・・・ 物事の、中でも悲惨な物事の終わりとはいつでしょうか。たとえば戦争だとしたら、当事者間で終戦の合意がなされた時?自然災害だとしたら、避難生活が終わり、被災した人達が自宅で普通に暮らせるようになった時?幸せな出来事ならば永遠に続いてくれていいけれど、不幸な出来事ならはっきり終わってほしいと思うのが人情というものです。
物事の、中でも悲惨な物事の終わりとはいつでしょうか。たとえば戦争だとしたら、当事者間で終戦の合意がなされた時?自然災害だとしたら、避難生活が終わり、被災した人達が自宅で普通に暮らせるようになった時?幸せな出来事ならば永遠に続いてくれていいけれど、不幸な出来事ならはっきり終わってほしいと思うのが人情というものです。 「このトリックは映像化不可能!」。ミステリー小説等でしばしば目にするキャッチコピーです。叙述トリックをはじめ、小説の<文字を読む>という特性を活かしたトリックに対して用いられることが多いですね。ラストで世界が反転するようなどんでん返しが待っていることが多く、私も大好きなトリックです。
「このトリックは映像化不可能!」。ミステリー小説等でしばしば目にするキャッチコピーです。叙述トリックをはじめ、小説の<文字を読む>という特性を活かしたトリックに対して用いられることが多いですね。ラストで世界が反転するようなどんでん返しが待っていることが多く、私も大好きなトリックです。 自殺はいけないこと。これは老若男女問わず誰もが断言することだと思います。その理由は色々あるでしょうが、多いのは「親からもらった命を粗末にしちゃだめ」「生きたくても生きられない人がいるのだから」辺りでしょうか。キリスト教圏なら「神が禁じているから」なんて理由もありそうです。
自殺はいけないこと。これは老若男女問わず誰もが断言することだと思います。その理由は色々あるでしょうが、多いのは「親からもらった命を粗末にしちゃだめ」「生きたくても生きられない人がいるのだから」辺りでしょうか。キリスト教圏なら「神が禁じているから」なんて理由もありそうです。 この世で最も許されざる犯罪の一つ、児童虐待。漢字で書けばたったの四文字ですが、そこにはいくつもの種別があります。殴る蹴るといった暴力を振るう身体的虐待、子どもを性欲の対象とする性的虐待、罵ったり兄弟姉妹間で扱いに差を付けたりする心理的虐待。以前は児童虐待と言えばこの三種類のうちどれかに区分されることが多かったようですが、現在よく取り沙汰される虐待はもう一つあります。それが、生活する上で必要な世話を怠り、最悪、死に至らしめることもある<育児放棄>です。日本は諸外国と比べて治安が良く、子どもが戸外に一人でいたり、車内にずっと放置されていても問題視されにくかったため、一昔前は虐待事件として扱われることも少なかったようです。
この世で最も許されざる犯罪の一つ、児童虐待。漢字で書けばたったの四文字ですが、そこにはいくつもの種別があります。殴る蹴るといった暴力を振るう身体的虐待、子どもを性欲の対象とする性的虐待、罵ったり兄弟姉妹間で扱いに差を付けたりする心理的虐待。以前は児童虐待と言えばこの三種類のうちどれかに区分されることが多かったようですが、現在よく取り沙汰される虐待はもう一つあります。それが、生活する上で必要な世話を怠り、最悪、死に至らしめることもある<育児放棄>です。日本は諸外国と比べて治安が良く、子どもが戸外に一人でいたり、車内にずっと放置されていても問題視されにくかったため、一昔前は虐待事件として扱われることも少なかったようです。 日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。
日本という国にとって、桜は特別な花です。様々な組織でシンボルマークとして使われ、桜のシーズンにはあちこちで花見が催され、桜をテーマにした歌や絵画は数知れず。薄紅色の花びらを一斉に付けた、華やかでいながら清々しい様子が愛される所以でしょうか。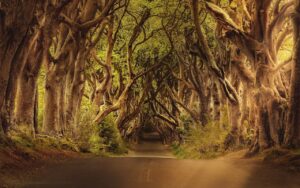 本好きなら恐らく誰もが持つ娯楽、それが本屋巡りです。当たり前の話ですが、本屋は見渡す限り本、本、本。新刊コーナーをチェックしたり、気になる本をめくって内容を確認したりするだけで、時間はあっという間に潰れます。コロナ禍ではどうか分かりませんが、以前は店内の各所にソファやテーブルが設置され、購入前に座ってゆっくり読むこともできました。初めて本屋で閲覧席を見た時、ここは地上の楽園かと思ったことを、今でもよく覚えています。
本好きなら恐らく誰もが持つ娯楽、それが本屋巡りです。当たり前の話ですが、本屋は見渡す限り本、本、本。新刊コーナーをチェックしたり、気になる本をめくって内容を確認したりするだけで、時間はあっという間に潰れます。コロナ禍ではどうか分かりませんが、以前は店内の各所にソファやテーブルが設置され、購入前に座ってゆっくり読むこともできました。初めて本屋で閲覧席を見た時、ここは地上の楽園かと思ったことを、今でもよく覚えています。 古今東西、数多く存在する<心中>の形の中で、<ネット心中>の異質さは際立っています。そもそも<心中>とは、引き裂かれそうな恋人同士があの世で結ばれることを願ってとか、家族が生活苦から逃れるためとか、そこに何らかの個人的な感情が絡むもの。一方、ネット心中の場合、縁もゆかりもない人間達が「一人で死ぬのは嫌だから」という動機で集まり、一緒に死ぬもの。当然、お互いに対する深い愛憎はありません。インターネットが発達し、何の接点もない人間同士が簡単にコミュニケーションを取れるようになったからこそ現れた心中方法です。
古今東西、数多く存在する<心中>の形の中で、<ネット心中>の異質さは際立っています。そもそも<心中>とは、引き裂かれそうな恋人同士があの世で結ばれることを願ってとか、家族が生活苦から逃れるためとか、そこに何らかの個人的な感情が絡むもの。一方、ネット心中の場合、縁もゆかりもない人間達が「一人で死ぬのは嫌だから」という動機で集まり、一緒に死ぬもの。当然、お互いに対する深い愛憎はありません。インターネットが発達し、何の接点もない人間同士が簡単にコミュニケーションを取れるようになったからこそ現れた心中方法です。 歌を聞く時、真っ先に注目するのはどこでしょうか。メロディが一番大事という人が多い気がしますが、同じくらい歌詞も重要だと思います。人の興味を惹きつける魅力的な歌詞は、長い時間を経ても語り継がれるもの。さらに、歌詞からは、その歌が作られた時代の社会情勢や文化が分かるという面白さがあります。一昔前は<夢><希望>といった前向きな歌詞の歌が流行ったようですが、今は<自分探し>をテーマにした歌詞が一番人気なんだとか。これも時代というものなのでしょう。
歌を聞く時、真っ先に注目するのはどこでしょうか。メロディが一番大事という人が多い気がしますが、同じくらい歌詞も重要だと思います。人の興味を惹きつける魅力的な歌詞は、長い時間を経ても語り継がれるもの。さらに、歌詞からは、その歌が作られた時代の社会情勢や文化が分かるという面白さがあります。一昔前は<夢><希望>といった前向きな歌詞の歌が流行ったようですが、今は<自分探し>をテーマにした歌詞が一番人気なんだとか。これも時代というものなのでしょう。