 そこそこ大きな自治体の場合、たいてい地域内に複数の図書館を持っています。多くの図書館利用者は、その中から自宅や学校、勤務先に近く、通いやすい図書館を選んで利用しているのではないでしょうか。私も自宅近くに図書館があるため、時間があるたびに通うようになって早数年。書棚の位置もすっかり頭に入り、読みたい本を探すのも楽ちんです。
そこそこ大きな自治体の場合、たいてい地域内に複数の図書館を持っています。多くの図書館利用者は、その中から自宅や学校、勤務先に近く、通いやすい図書館を選んで利用しているのではないでしょうか。私も自宅近くに図書館があるため、時間があるたびに通うようになって早数年。書棚の位置もすっかり頭に入り、読みたい本を探すのも楽ちんです。
ですが、たまには馴染みのない図書館に行くのも楽しいです。同じ作家さんでも、図書館によって蔵書が違うので、「あ、そういえばこの本書いたのもこの人だっけ」「この本、見かけるの久しぶりだなぁ」と驚かされることもしばしば。もちろん、図書館に取り寄せ依頼をすればどの本だろうと届くのですが、書棚の間をぶらぶらして読みたい本を見つけた時の喜びは格別ですよね。先日、普段利用しない図書館に立ち寄ってみたところ、数年ぶりにこの本を見つけたので再読しました。朱川湊人さんの『わくらば追慕抄』です。
こんな人におすすめ
・昭和を舞台にしたノスタルジックな小説が好きな人
・超能力が出てくる小説が読みたい人

 日本語って、とても美しい言語だと思います。もちろん、どの民族にとっても自国の言葉は誇れるものなのでしょうが、神々が出雲大社に集まる十月を<神無月>(出雲地方では神在月)と呼んだり、雪の結晶の多くが六角形をしていることから雪を<六花>と表現したりする感覚は、日本語独自のものではないでしょうか。こういう雅な表現が大好きな私は、学生時代、古文の資料集を読んで悦に入っていたものです。
日本語って、とても美しい言語だと思います。もちろん、どの民族にとっても自国の言葉は誇れるものなのでしょうが、神々が出雲大社に集まる十月を<神無月>(出雲地方では神在月)と呼んだり、雪の結晶の多くが六角形をしていることから雪を<六花>と表現したりする感覚は、日本語独自のものではないでしょうか。こういう雅な表現が大好きな私は、学生時代、古文の資料集を読んで悦に入っていたものです。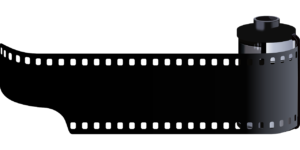 写真が発明されたのは、一九世紀前半のことです。この当時、産業革命によりいわゆる中産階級が多数出現し、彼らの間で肖像画が流行したことで、一気に写真の需要も高まったのだとか。そんな写真は一八四三年、長崎に入港したオランダ船により日本に入ってきました。当初は一枚撮るのにも特殊な技術や設備が必要だったようですが、インスタントカメラや携帯電話、スマートフォン等の普及により、今やその気になれば幼児だって写真を撮ることができます。
写真が発明されたのは、一九世紀前半のことです。この当時、産業革命によりいわゆる中産階級が多数出現し、彼らの間で肖像画が流行したことで、一気に写真の需要も高まったのだとか。そんな写真は一八四三年、長崎に入港したオランダ船により日本に入ってきました。当初は一枚撮るのにも特殊な技術や設備が必要だったようですが、インスタントカメラや携帯電話、スマートフォン等の普及により、今やその気になれば幼児だって写真を撮ることができます。 クリエイティブな世界には、複数の名義で作品を発表されている方がしばしば存在します。理由は人それぞれでしょうが、一番は、名前に付きまとうイメージや先入観を払拭するためではないでしょうか。〇〇先生は恋愛漫画とか、△△先生はロックミュージックとか、色々イメージがありますからね。
クリエイティブな世界には、複数の名義で作品を発表されている方がしばしば存在します。理由は人それぞれでしょうが、一番は、名前に付きまとうイメージや先入観を払拭するためではないでしょうか。〇〇先生は恋愛漫画とか、△△先生はロックミュージックとか、色々イメージがありますからね。 音楽とは文字通り<音を楽しむ>ものです。私は生憎音楽があまり得意ではありませんが、カラオケに行ったり歌を聞いたりするのは大好き。iPodにお気に入りの曲を入れ、登下校や通勤、ショッピング中などに聞くのが昔からの日課でした。
音楽とは文字通り<音を楽しむ>ものです。私は生憎音楽があまり得意ではありませんが、カラオケに行ったり歌を聞いたりするのは大好き。iPodにお気に入りの曲を入れ、登下校や通勤、ショッピング中などに聞くのが昔からの日課でした。 「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。
「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。 学生時代、とてもスタイルの良い女性の先生がいました。背が高く、手足が長く、スーツ姿で佇む様子は舞台女優さながら。そんな見た目とは裏腹に、とある疾患を抱えていて、長時間立ったり歩いたりすることが難しいそうです。ただ、何しろ容姿が健康的かつ華やかなので、バスや電車で優先席に座っていると「年寄りに席を譲れ」と怒られることもあるとのことでした。
学生時代、とてもスタイルの良い女性の先生がいました。背が高く、手足が長く、スーツ姿で佇む様子は舞台女優さながら。そんな見た目とは裏腹に、とある疾患を抱えていて、長時間立ったり歩いたりすることが難しいそうです。ただ、何しろ容姿が健康的かつ華やかなので、バスや電車で優先席に座っていると「年寄りに席を譲れ」と怒られることもあるとのことでした。 日本は島国であるため、比較的気軽にマリンスポーツを楽しむことができます。私自身、子どもの頃は親に連れられて海水浴に行ったり、海辺で花火をしたりしました。そういう時、海によってはボードを抱えたサーファーを目にすることもあり、「あれはどういうスポーツなんだろう?」と不思議に思ったものです。波打ち際でちゃぷちゃぷ遊ぶのと違い、サーフィンには技術や道具が必要ということもあって、今でもなんとなく縁遠いです。
日本は島国であるため、比較的気軽にマリンスポーツを楽しむことができます。私自身、子どもの頃は親に連れられて海水浴に行ったり、海辺で花火をしたりしました。そういう時、海によってはボードを抱えたサーファーを目にすることもあり、「あれはどういうスポーツなんだろう?」と不思議に思ったものです。波打ち際でちゃぷちゃぷ遊ぶのと違い、サーフィンには技術や道具が必要ということもあって、今でもなんとなく縁遠いです。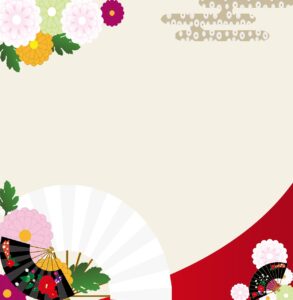 「最初から最後まできっちり読み通したことはないけど、大まかなあらすじは知っている」「漫画版や実写版しか見たことない」という小説って、意外と多いです。私の場合、ぱっと思いつくのは森鷗外の『舞姫』や太宰治の『人間失格』。一昔前の文豪の作品は、文体が現代と異なっていることもあり、なんとなくとっつきにくく感じてしまいます。
「最初から最後まできっちり読み通したことはないけど、大まかなあらすじは知っている」「漫画版や実写版しか見たことない」という小説って、意外と多いです。私の場合、ぱっと思いつくのは森鷗外の『舞姫』や太宰治の『人間失格』。一昔前の文豪の作品は、文体が現代と異なっていることもあり、なんとなくとっつきにくく感じてしまいます。 「人は中身が大事」「外見より心の美しさの方が価値がある」誰しも一度は聞いたことのあるフレーズだと思います。そうであってほしいと心底思うものの、悲しいかな、人の立ち位置を決める上で、容姿が重要なファクターとなることは事実。美しい人間が尊ばれ、そうでない人間が蔑まれる場面は、日常の至る所に溢れています。
「人は中身が大事」「外見より心の美しさの方が価値がある」誰しも一度は聞いたことのあるフレーズだと思います。そうであってほしいと心底思うものの、悲しいかな、人の立ち位置を決める上で、容姿が重要なファクターとなることは事実。美しい人間が尊ばれ、そうでない人間が蔑まれる場面は、日常の至る所に溢れています。