 一昔前、悪さをする悪霊や妖怪のことを<物の怪>と呼びました。この<物>とは<人間>の対義語で、超自然的な存在すべてを指すのだとか。ホラーになじみがなくても、ジブリ映画『もののけ姫』で名前を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
一昔前、悪さをする悪霊や妖怪のことを<物の怪>と呼びました。この<物>とは<人間>の対義語で、超自然的な存在すべてを指すのだとか。ホラーになじみがなくても、ジブリ映画『もののけ姫』で名前を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
今は<悪霊><怨霊><妖魔>などといった呼び方が広まったせいか、<物の怪>という言葉が出てくるのは、圧倒的に時代小説が多い気がします。最近の、怪異がスマホやパソコンを介して襲い掛かってくる作品も良いけれど、日本情緒たっぷりの時代ホラーも面白いものですよ。今回取り上げるのは、宮部みゆきさんの『ばんば憑き』。鬱々とした和風怪談を堪能できました。
こんな人におすすめ
日本情緒溢れる怪談短編集に興味がある人
疫病対策に詳しい問屋の秘密、子ども達の中に紛れ込んだ正体不明の影の謎、化け物に憑かれた一族に差し伸べられる救いの手、我が子に鬼が憑いたと言い張る男の罪と罰、老婆の昔語りから浮かび上がる業の行方、物の怪が浪人に持ち掛けた意外な頼み事・・・・・時代小説の名手が綴る、怪しく悲しい六つの怪異譚
やっぱり宮部みゆきさんの時代小説って好きだなと、改めて思った一作です。時代物ならではの文化や風習、幽霊とも化け物とも言い切れない彩り豊かな<物の怪>達、そこで息づく人々の人間模様が濃くて深くて・・・収録作品も、ほのぼのしたものから後味の悪いものまで幅広く、大満足でした。
「坊主の壺」・・・主人公・おつぎが奉公する材木問屋は不思議なお店だ。なぜかこの店の主人には、治療法などないはずの疫病への対策が分かるのである。江戸に病が流行るたび、主人は様々な手を打ち、人々を救ってきた。その秘密を、ある時、おつぎは意外な形で知ることとなり・・・
主人が打ち出す疫病への対処は「生ものは口にするな」「手洗いを徹底しろ」「厠は特に清潔に保て」「感染者は隔離しろ」という、現代人の感覚からすると至極真っ当なもの。それに対し、「まだ大して流行ってもいないのに疫病対策なんて、逆に縁起悪い」「感染者の枕元に置いた米は疫病に効くという言い伝えがあるのに」などといって誹謗中傷する人々はひどい・・・と思って、はたと気づきました。これって、コロナ禍で起こったこととまったく同じなんですよね。人間というものは、どれだけ月日が経とうと変わらないのだなと実感させられます。そんな中、使命を全うしようとする問屋主人や、おつぎの姿が清々しかったです。
「お文の影」・・・岡っ引きの政五郎は、ある日、知人の老人から不思議な相談を持ち掛けられる。長屋の子ども達が遊ぶ姿を眺めていると、なぜか遊んでいる人数より、影の数が多いのだという。まさか物の怪の類ではあるまいか。老人の人となりをよく知る政五郎は、それとなく調べてみることにするのだが・・・
『ぼんくらシリーズ』から岡っ引きの政五郎と、手下のおでこが登場します。宮部みゆきさんの時代小説には、時として弱者が容赦なく蹂躙される描写が出てきますが、それが顕著に表れたのがこの話。苦しみ抜いて死んだ幼い魂が本当に哀れで・・・ラスト、子どもがほんの少しでも救われたなら良かったです。なお、この話は短編集『あやし』収録の「灰神楽」の続編です。読んでいたらより理解が深まると思いますよ。
「博打眼」・・・醤油問屋・近江屋には、<博打眼>という物の怪が憑いている。一族の人間一人にとり憑き、死ぬまで博打に狂わせて精気を搾り取るのだ。どうにか抑えていた博打眼が再び暴れ出した時、救いの手を差し伸べてくれたのは、神社の古びた狛犬で・・・・・
この手の怪異が、人間をただ苦しめるだけでなく、代償と引き換えに一定の利益をもたらしてくれるというのはお約束です。博打眼にしろ、いきなり地面から湧いてきたものではなく、元々は一族の先祖が繁栄欲しさに契約したという辺り、人間の業の深さを感じました。その分、主要登場人物のお美代と太七、強い訛りがある竹次郎の奮闘ぶりはほのぼのしていて好印象。頼りになる狛犬も近くにいることだし、このまま元気に育っていってほしいものです。
「討債鬼」・・・手習い所を開く浪人・青野利一郎のもとに、教え子・信太郎の生家から恐ろしい頼み事が持ち込まれる。曰く、信太郎には<討債鬼>という鬼が憑いており、いずれ家長であり信太郎の父でもある宗吾郎に仇なすので、今のうちに斬り殺してほしいという。どうやらこの騒動の背景には、行然坊という謎の僧侶が絡んでいるようなのだが・・・
『三島屋変調百物語シリーズ』から、青野利一郎と行然坊が登場します。生臭坊主が名家にもたらす大騒動・・・と見せかけて、中盤で一ひねりあるのが面白いですね。最初は胡散臭かった行然坊が、途中から愛すべきトラブルメーカーに見えてくる描写も秀逸です。また、この話では『三島屋変調百物語シリーズ』では詳しく描かれなかった青野の過去が明かされます。想像以上に悲劇的なものでしたが、これを知ってからだと、手習い所で穏やかに過ごす青野の姿がより眩しく感じられます。
「ばんば憑き」・・・幼馴染のお志津と所帯を持ち、やや気詰まりながら不自由のない婿養子生活を送る佐一郎。ある時、夫婦で湯治に出かけた先で、上品な老婆と相部屋を頼まれる。夜半、佐一郎の耳に、老婆がすすり泣く声が聞こえた。様子を尋ねる佐一郎に対し、老婆は五十年前に起きた恐ろしい出来事について語り始め・・・・・
表題作にして、収録作品中一番後味の悪い話です。五十年前に起こった<ばんば憑き>を巡る出来事も怖いけど、私はやっぱり、老婆の話を通して佐一郎の心境が変わっていく描写が怖かったなぁ。無邪気で可愛いと思っていた若妻の性悪な部分に気づくとか、自分が婚家で軽視されていることを自覚してしまうとか、いかにも現実にありそうで・・・これから佐一郎が禁断の一歩を踏み出してしまわないか、気になって仕方ありません。
「野槌の墓」・・・浪人・源五郎衛門は、妻亡き後、一人娘の加奈と共に慎ましく暮らしている。そんなある日、源五郎衛門のもとに、加奈が可愛がっている猫のタマがなんと人間に化けて現れた。タマが言うには、物の怪仲間である野槌(木槌の化けたもの)が人を襲うようになったので、源五郎衛門に斬ってほしいらしい。物の怪と化す以前、この木槌は子ども殺しに使われたことがあるそうで・・・・・
前の話とは打って変わって、愛らしい物の怪がわらわら出てくるほのぼのストーリーでした。反面、加奈や物の怪達が可愛ければ可愛いほど、背景にある悲しい過去が際立ち、やるせない気持ちにもなります。でも、この親子なら、この先何があってもきっと健やかに乗り越えていけるでしょう。タマさん、人にもなれるのだから、これからもちょくちょく行き来しているといいな。
他シリーズの登場人物がちらほら出てきますが、基本的に未読でも問題ありません。また、本作は文庫化の際に『お文の影』と改題されています。なかなかの大作のためお値段もそれなりなので、購読派の方はご注意ください。
げに恐ろしきは人の性・・・度★★★★★
完全解決しない余韻が堪らない度★★★★☆



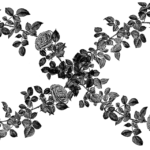




宮部みゆきさんの時代劇怪談は「三島屋変調百物語」が面白かったですが3作目までしか読んでいません。「荒神」も面白かったです。
「ソロモンの偽証」「魔術はささやく」「レベル7」などの現代小説の方がしっくり来るイメージです。
長編は好きで長ければ長いほど面白いと感じる方ですが、宮部みゆきさんは長過ぎると感じます。
これはそれほど長くなく「三島屋変調百物語」のような江戸情緒、人情のある怪談で読んでみたくなりました。
氏家京太郎、奔るを読んでます。
他の作品の中山キャラクターが登場して、理論的な会話の応酬で楽しんでます。
宮部みゆきさんの長編は名作揃いですが、「ソロモンの偽証」「模倣犯」「荒神」「この世の春」等々、ボリュームも相当なものなんですよね。
いくら面白いとはいえ、あまりに長いと集中力を保つのも一苦労。
その点、この作品は短編集なので、中だるみなく読むことができました。
氏家京太郎の二作目、書店で見かけました。
他作品のキャラクターは誰なのかなと、今からあれこれ想像して楽しんでいます。
こちらは藤崎翔さん「お梅は次こそ呪いたい」が予約順位一位まで来ました。
今月中には届くかな?
お梅は呪いたいの2作目があるとは知りませんでした。早速予約しました。氏家京太郞、奔る 読み終えました。東野圭吾さんのある作品にオチが似ていた気がするので読み終わったら感想を聞きたいです。
藤崎翔さんは有難いことに新作をどんどん出してくれるので、「気づかない内に次が出ていた!」ということが多々あるんですよね。
「氏家京太郎~」は、東野圭吾さんのどの作品に似ているんだろう・・・?
今から気になって仕方ないです。