 子どもが家から離れ、旅をする。ジュブナイル作品の王道とも言えるシチュエーションです。旅先での出来事を経て子どもが成長していく様子は、文章で読んでも映像で見てもワクワクするものですよね。このジャンルには、スティーブン・キングの『スタンド・バイ・ミー』をはじめ、名作がたくさんあります。
子どもが家から離れ、旅をする。ジュブナイル作品の王道とも言えるシチュエーションです。旅先での出来事を経て子どもが成長していく様子は、文章で読んでも映像で見てもワクワクするものですよね。このジャンルには、スティーブン・キングの『スタンド・バイ・ミー』をはじめ、名作がたくさんあります。
ただ、現代社会で子どもだけの旅を決行するとなると、それなりの理由付けが必要となります。恩田陸さんの『上と外』では主人公兄妹が外国のクーデターに巻き込まれますし、宮部みゆきさん『ブレイブ・ストーリー』の主人公は異世界に行ってしまいました。こういう特殊な設定の物語もとても面白いのですが、今回はもっと現実寄りの作品を取り上げようと思います。朱川湊人さんの『オルゴォル』です。
こんな人におすすめ
子ども目線の旅物語に興味がある人

 ホラーやイヤミスの世界において、<子ども>というのは特別な存在になりがちです。子どもは可能性の塊であり、未来の象徴。そのせいか、モンスターや殺人鬼が跋扈し、多数の犠牲者が出る中、子どもだけはなんとか生き残るという展開も多いです。
ホラーやイヤミスの世界において、<子ども>というのは特別な存在になりがちです。子どもは可能性の塊であり、未来の象徴。そのせいか、モンスターや殺人鬼が跋扈し、多数の犠牲者が出る中、子どもだけはなんとか生き残るという展開も多いです。 ものすごく有名な割に、日本の創作物で主要キャラになることが意外と少ない存在、それが<天使>と<悪魔>だと思います。どちらも外国の宗教に由来する存在だからでしょうか。海外作品の場合、主人公のピンチを天使が救ってくれたり悪魔がラスボスだったりすることがしばしばありますが、日本ではこれらの役割を<神仏><守護霊><怨霊><妖怪>等が担うことが多い気がします。
ものすごく有名な割に、日本の創作物で主要キャラになることが意外と少ない存在、それが<天使>と<悪魔>だと思います。どちらも外国の宗教に由来する存在だからでしょうか。海外作品の場合、主人公のピンチを天使が救ってくれたり悪魔がラスボスだったりすることがしばしばありますが、日本ではこれらの役割を<神仏><守護霊><怨霊><妖怪>等が担うことが多い気がします。 そこそこ大きな自治体の場合、たいてい地域内に複数の図書館を持っています。多くの図書館利用者は、その中から自宅や学校、勤務先に近く、通いやすい図書館を選んで利用しているのではないでしょうか。私も自宅近くに図書館があるため、時間があるたびに通うようになって早数年。書棚の位置もすっかり頭に入り、読みたい本を探すのも楽ちんです。
そこそこ大きな自治体の場合、たいてい地域内に複数の図書館を持っています。多くの図書館利用者は、その中から自宅や学校、勤務先に近く、通いやすい図書館を選んで利用しているのではないでしょうか。私も自宅近くに図書館があるため、時間があるたびに通うようになって早数年。書棚の位置もすっかり頭に入り、読みたい本を探すのも楽ちんです。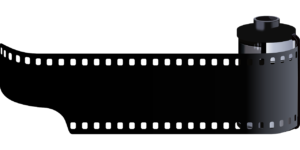 写真が発明されたのは、一九世紀前半のことです。この当時、産業革命によりいわゆる中産階級が多数出現し、彼らの間で肖像画が流行したことで、一気に写真の需要も高まったのだとか。そんな写真は一八四三年、長崎に入港したオランダ船により日本に入ってきました。当初は一枚撮るのにも特殊な技術や設備が必要だったようですが、インスタントカメラや携帯電話、スマートフォン等の普及により、今やその気になれば幼児だって写真を撮ることができます。
写真が発明されたのは、一九世紀前半のことです。この当時、産業革命によりいわゆる中産階級が多数出現し、彼らの間で肖像画が流行したことで、一気に写真の需要も高まったのだとか。そんな写真は一八四三年、長崎に入港したオランダ船により日本に入ってきました。当初は一枚撮るのにも特殊な技術や設備が必要だったようですが、インスタントカメラや携帯電話、スマートフォン等の普及により、今やその気になれば幼児だって写真を撮ることができます。 「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。
「恋愛にルールなんてない」「恋する気持ちを咎めることは誰にもできない」。小説内において、禁じられた恋に苦しむ登場人物達がしばしば口にする台詞です。まったくもってその通りで、好きという気持ちを否定したり、命令で動かしたりすることは不可能です。 <兄弟は他人のはじまり>ということわざがあります。意味は<血を分けた兄弟(姉妹)でも、成長するにつれ環境や価値観が変わり、情が薄れ、他人のようになっていく>ということ。ちょっと寂しいですが、肉親とはいえ違う人間なのですから、仕方ないことなのかもしれません。
<兄弟は他人のはじまり>ということわざがあります。意味は<血を分けた兄弟(姉妹)でも、成長するにつれ環境や価値観が変わり、情が薄れ、他人のようになっていく>ということ。ちょっと寂しいですが、肉親とはいえ違う人間なのですから、仕方ないことなのかもしれません。 実は私、頭に大が付く虫嫌いです。刺されたとか噛まれたとかいう経験があるわけでもないのですが、あの細い手足やもぞもぞした動きが嫌で嫌で・・・ゴキブリやスズメバチはもちろんのこと、チョウチョやテントウ虫さえ冷や汗をかくレベルです。
実は私、頭に大が付く虫嫌いです。刺されたとか噛まれたとかいう経験があるわけでもないのですが、あの細い手足やもぞもぞした動きが嫌で嫌で・・・ゴキブリやスズメバチはもちろんのこと、チョウチョやテントウ虫さえ冷や汗をかくレベルです。 <超能力>という言葉を聞くと、なんだかわくわくしてきます。手を触れずに物を動かしたり、未来の出来事を見通したり、一瞬で遠く離れた場所に移動したり・・・文字通り、普通の人間の力を超えた能力だからこそ、余計に憧れが募ります。
<超能力>という言葉を聞くと、なんだかわくわくしてきます。手を触れずに物を動かしたり、未来の出来事を見通したり、一瞬で遠く離れた場所に移動したり・・・文字通り、普通の人間の力を超えた能力だからこそ、余計に憧れが募ります。 「宇宙人」と聞くと、どんな存在を思い浮かべるでしょうか。いわゆる「グレイタイプ」と呼ばれる大きな頭と黒い目を持つタイプから、映画『エイリアン』に登場するような化け物じみた姿、地球人そっくりの容姿を持つものなど、色々でしょうね。ちなみに私はというと、子どもの頃に見たアニメの影響で、足がたくさんあるタコ型宇宙人を想像してしまいます。
「宇宙人」と聞くと、どんな存在を思い浮かべるでしょうか。いわゆる「グレイタイプ」と呼ばれる大きな頭と黒い目を持つタイプから、映画『エイリアン』に登場するような化け物じみた姿、地球人そっくりの容姿を持つものなど、色々でしょうね。ちなみに私はというと、子どもの頃に見たアニメの影響で、足がたくさんあるタコ型宇宙人を想像してしまいます。