 本好きとしては大変ありがたいことに、私が住む自治体は複数の図書館を運営してくれています。とはいえ、しょっちゅう行くのは徒歩圏内にある近所の図書館がメイン。行き来に時間がかからない分、本選びに時間をかけられるし、思い付きでふらっと行くことができてとても便利です。
本好きとしては大変ありがたいことに、私が住む自治体は複数の図書館を運営してくれています。とはいえ、しょっちゅう行くのは徒歩圏内にある近所の図書館がメイン。行き来に時間がかからない分、本選びに時間をかけられるし、思い付きでふらっと行くことができてとても便利です。
その一方、時には普段利用する所とは違う図書館に行くのも楽しいものです。図書館によって蔵書が違うため、「あ、これずいぶん前に読んだ本だ!」「そう言えば、これってこの作家さんの著作だったんだな」等々、新鮮な面白さがあります。先日、所用で出かけた場所で普段利用しない図書館に立ち寄ったところ、昔読んで大好きだった本と再会しました。小池真理子さんの『あなたに捧げる犯罪』です。
こんな人におすすめ
日常系イヤミスが好きな人

 創作の世界には、<群像劇>というストーリー手法があります。これは、特定の主人公を設けるのではなく、複数の主要登場人物がそれぞれ別の物語を紡ぎ、最終的に一つの結末に辿り着くスタイルのこと。グランドホテル形式、アンサンブル・キャストなどの呼び方をされることもあるようです。大ヒットを記録したラブコメディ映画『ラブ・アクチュアリー』形式のこと、と言えば、分かりやすいかもしれません。
創作の世界には、<群像劇>というストーリー手法があります。これは、特定の主人公を設けるのではなく、複数の主要登場人物がそれぞれ別の物語を紡ぎ、最終的に一つの結末に辿り着くスタイルのこと。グランドホテル形式、アンサンブル・キャストなどの呼び方をされることもあるようです。大ヒットを記録したラブコメディ映画『ラブ・アクチュアリー』形式のこと、と言えば、分かりやすいかもしれません。 この世には数えきれないほどの主義・傾向がありますが、その中でも<ナルシズム>の認知度の高さは群を抜いていると思います。これはギリシャ神話に登場する美少年・ナルキッソスが、泉に映る自分の姿に恋したエピソードに由来し、自分自身を強く愛する精神状態と指すとのこと。あまりによく知られた用語なので、「あの人ってナルシストだよね」「今の言い方、ナスルシストっぽかったかな」等々、日常会話に登場する機会も多いです。
この世には数えきれないほどの主義・傾向がありますが、その中でも<ナルシズム>の認知度の高さは群を抜いていると思います。これはギリシャ神話に登場する美少年・ナルキッソスが、泉に映る自分の姿に恋したエピソードに由来し、自分自身を強く愛する精神状態と指すとのこと。あまりによく知られた用語なので、「あの人ってナルシストだよね」「今の言い方、ナスルシストっぽかったかな」等々、日常会話に登場する機会も多いです。 「嫁姑の仲よきはもっけの不思議」などという言葉もあるように、嫁と姑というのは多かれ少なかれ揉めるものと思われがちです。赤の他人の同性同士が身内になるという状況のせいでしょうか。もちろん、嫁姑関係が円満にいっている家庭もたくさんあるんでしょうが、小説やドラマの中には、確執を抱えた嫁と姑が大勢登場します。
「嫁姑の仲よきはもっけの不思議」などという言葉もあるように、嫁と姑というのは多かれ少なかれ揉めるものと思われがちです。赤の他人の同性同士が身内になるという状況のせいでしょうか。もちろん、嫁姑関係が円満にいっている家庭もたくさんあるんでしょうが、小説やドラマの中には、確執を抱えた嫁と姑が大勢登場します。 小説では、しばしば<パンドラの箱>という表現が登場します。元ネタは、ギリシア神話に登場する、ゼウスによってすべての悪と災いが詰め込まれた箱(本来は壺ですが)。人類最初の女性・パンドラがこの箱を開けてしまったことで、この世には様々な不幸が蔓延するようになります。このことから、<パンドラの箱>とは<暴いてはならない秘密><知りたくなかった真相>というような意味で使われることが多いですね。
小説では、しばしば<パンドラの箱>という表現が登場します。元ネタは、ギリシア神話に登場する、ゼウスによってすべての悪と災いが詰め込まれた箱(本来は壺ですが)。人類最初の女性・パンドラがこの箱を開けてしまったことで、この世には様々な不幸が蔓延するようになります。このことから、<パンドラの箱>とは<暴いてはならない秘密><知りたくなかった真相>というような意味で使われることが多いですね。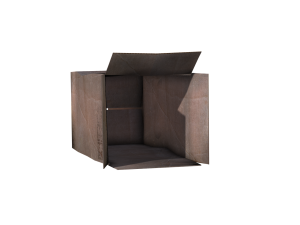 四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。
四月も残りわずかです。この春に引っ越しを経験した人は、そろそろ片づけが一段落した頃合いでしょうか。今年は引っ越そうにも業者が予約できない<引っ越し難民>が続出したんだとか。不自由した方々が一日も早く落ち着き、快適な新生活を送れるよう願ってやみません。 ストーカー。この言葉が日本で一般化したのは、二〇〇〇年前後からだと言われています。特定の相手を狙い、執拗につけ回し、心身に危害を加える。想像しただけで、身の毛がよだつような犯罪行為です。
ストーカー。この言葉が日本で一般化したのは、二〇〇〇年前後からだと言われています。特定の相手を狙い、執拗につけ回し、心身に危害を加える。想像しただけで、身の毛がよだつような犯罪行為です。