 ミステリーやホラーのように<真相究明><問題解決>に重きが置かれる作品の場合、「なぜ主人公は必死に事件に取り組むのか」という動機付けが重要となります。ここをすんなりクリアするための方法の一つは、主人公の職業をマスコミ関係者にすること。何しろ調査・取材することが仕事ですし、犯罪性が高くないと捜査できない警察と違い、まだ物理的な被害が出ていない(判明していない)事件や、何十年も前に起きた未解決事件に対してでも動けます。
ミステリーやホラーのように<真相究明><問題解決>に重きが置かれる作品の場合、「なぜ主人公は必死に事件に取り組むのか」という動機付けが重要となります。ここをすんなりクリアするための方法の一つは、主人公の職業をマスコミ関係者にすること。何しろ調査・取材することが仕事ですし、犯罪性が高くないと捜査できない警察と違い、まだ物理的な被害が出ていない(判明していない)事件や、何十年も前に起きた未解決事件に対してでも動けます。
マスコミ関係者が登場する小説といえば、ぱっと思いつくのは鈴木光司さんの『リング』。雑誌記者である主人公は、その調査能力を使い、呪いのビデオの謎を解こうとします。また、最近映画化もされた塩田武士さんの『罪の声』には、三十一年前に起きた未解決事件の真相に迫る新聞記者が出てきます。上記二作品に比べるとノリはやや軽めながら、この小説の主人公もけっこう大変な目に遭っていました。澤村伊智さんの『アウターQ 弱小Webマガジンの事件簿』です。
こんな人におすすめ
街の怪奇事件がテーマの短編集が読みたい人

 SF小説の舞台になりやすい設定として、<違う惑星><異次元>と並んで多いのが<未来社会>です。私個人としては、今からほんの少し先の時代を描いた近未来小説が好きだったりします。何百年、何千年も未来の話だとファンタジーとしか思えませんが、何十年レベルの未来なら「こういうこともありそうだな」と感情移入しやすいです。
SF小説の舞台になりやすい設定として、<違う惑星><異次元>と並んで多いのが<未来社会>です。私個人としては、今からほんの少し先の時代を描いた近未来小説が好きだったりします。何百年、何千年も未来の話だとファンタジーとしか思えませんが、何十年レベルの未来なら「こういうこともありそうだな」と感情移入しやすいです。 ホラー作品は、大きく分けて二つのタイプがあると思います。それは<自業自得>系と<理不尽>系。前者は、恐怖体験をする原因が(善意悪意は問わず)自分自身にあるタイプで、五十嵐貴久さんの『リカ』や今邑彩さんの『赤いべべ着せよ・・・』などがこれに当たります。
ホラー作品は、大きく分けて二つのタイプがあると思います。それは<自業自得>系と<理不尽>系。前者は、恐怖体験をする原因が(善意悪意は問わず)自分自身にあるタイプで、五十嵐貴久さんの『リカ』や今邑彩さんの『赤いべべ着せよ・・・』などがこれに当たります。 <予言>という単語を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、かの有名な<ノストラダムスの大予言>でしょう。<一九九九年七か月、空から恐怖の大王が来るだろう>という一文が<一九九九年に人類は滅びる>と解釈され、一時期、テレビや雑誌もその話題で持ちきりでした。かくいう私も、ハラハラドキドキしながら特集雑誌を買い求めた一人です。
<予言>という単語を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、かの有名な<ノストラダムスの大予言>でしょう。<一九九九年七か月、空から恐怖の大王が来るだろう>という一文が<一九九九年に人類は滅びる>と解釈され、一時期、テレビや雑誌もその話題で持ちきりでした。かくいう私も、ハラハラドキドキしながら特集雑誌を買い求めた一人です。 他のテーマにも言えることですが、<ホラー>の中には色々なジャンルがあります。幽霊や悪魔と戦う正統派のオカルトホラー、現代社会を舞台にしたモダンホラー、古城や洋館などが登場するゴシックホラー、人間の狂気を扱ったサイコホラー、内臓飛び散るスプラッタ、ホラーながら論理的な謎解き要素もあるホラーミステリーetcetc。ホラー大好きな私は何でもOKですが、この辺りは個人で好みが分かれるところでしょう。
他のテーマにも言えることですが、<ホラー>の中には色々なジャンルがあります。幽霊や悪魔と戦う正統派のオカルトホラー、現代社会を舞台にしたモダンホラー、古城や洋館などが登場するゴシックホラー、人間の狂気を扱ったサイコホラー、内臓飛び散るスプラッタ、ホラーながら論理的な謎解き要素もあるホラーミステリーetcetc。ホラー大好きな私は何でもOKですが、この辺りは個人で好みが分かれるところでしょう。 「家」という言葉には、様々なイメージが付きまといます。ほのぼのと温かく、住人を守ってくれるイメージを持つ人もいるでしょう。と同時に、牢屋のように閉鎖的で、人を捕えるイメージだってあると思います。
「家」という言葉には、様々なイメージが付きまといます。ほのぼのと温かく、住人を守ってくれるイメージを持つ人もいるでしょう。と同時に、牢屋のように閉鎖的で、人を捕えるイメージだってあると思います。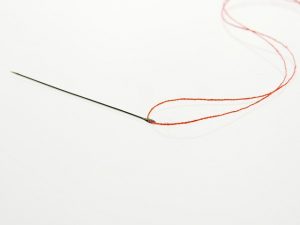 子どもの頃、人形遊びが好きでした。私の子ども時代に主流だったのはタカラトミーから発売された「ジェニーちゃん」。細かなキャラクター設定やお洒落な洋服の数々に夢中になったことを覚えています。
子どもの頃、人形遊びが好きでした。私の子ども時代に主流だったのはタカラトミーから発売された「ジェニーちゃん」。細かなキャラクター設定やお洒落な洋服の数々に夢中になったことを覚えています。 「そんな悪い子はお化けにさらわれちゃうよ」。子どもの頃、そういう脅し文句を耳にした人は少なくないでしょう。「お化け」が「鬼」「幽霊」「人さらい」に変わることはあっても、基本的な構造はどれも同じ。どこからともなく現れ、人間を遠くへ連れ去る怪異の存在は、古今東西たくさん語られています。
「そんな悪い子はお化けにさらわれちゃうよ」。子どもの頃、そういう脅し文句を耳にした人は少なくないでしょう。「お化け」が「鬼」「幽霊」「人さらい」に変わることはあっても、基本的な構造はどれも同じ。どこからともなく現れ、人間を遠くへ連れ去る怪異の存在は、古今東西たくさん語られています。